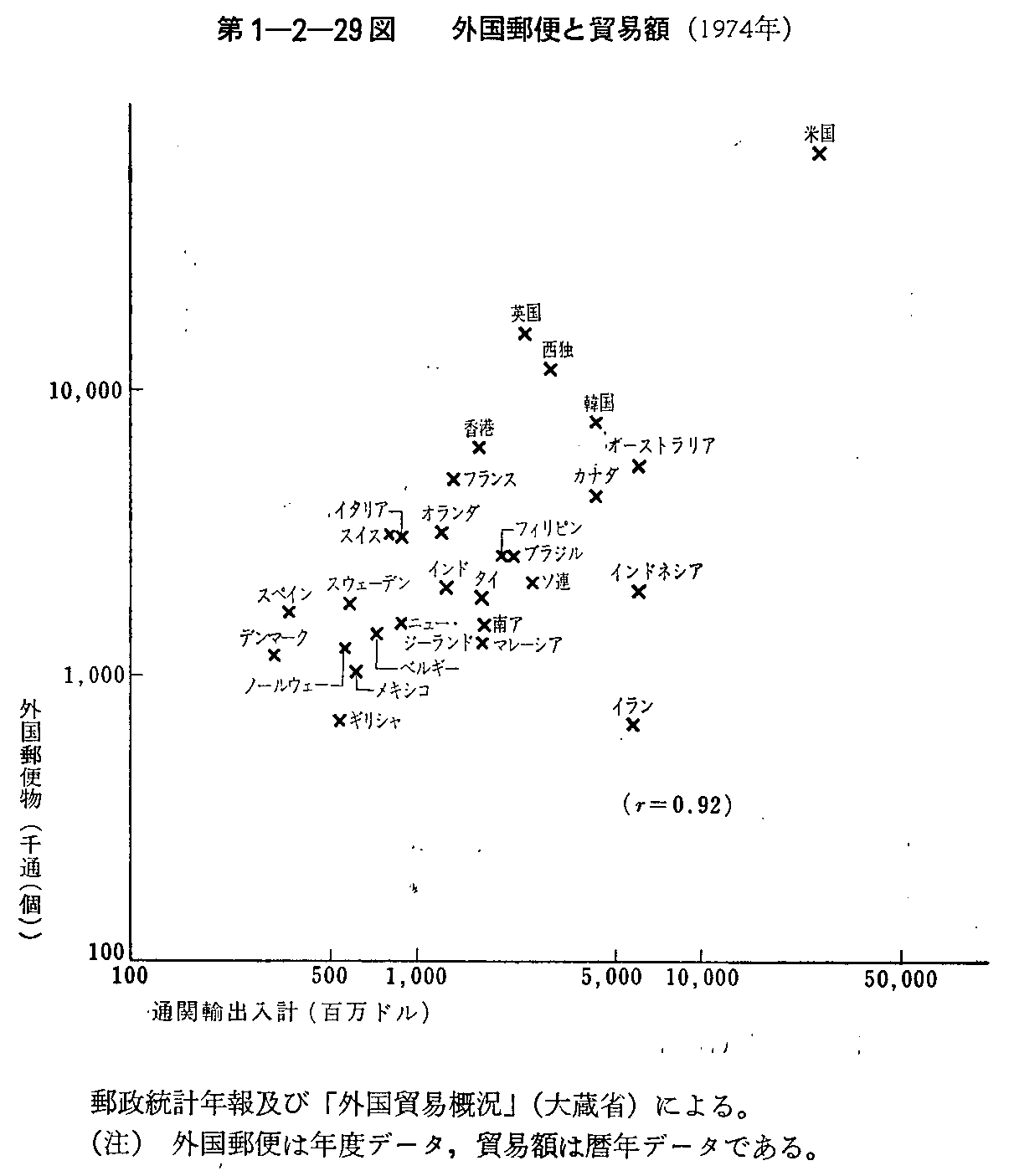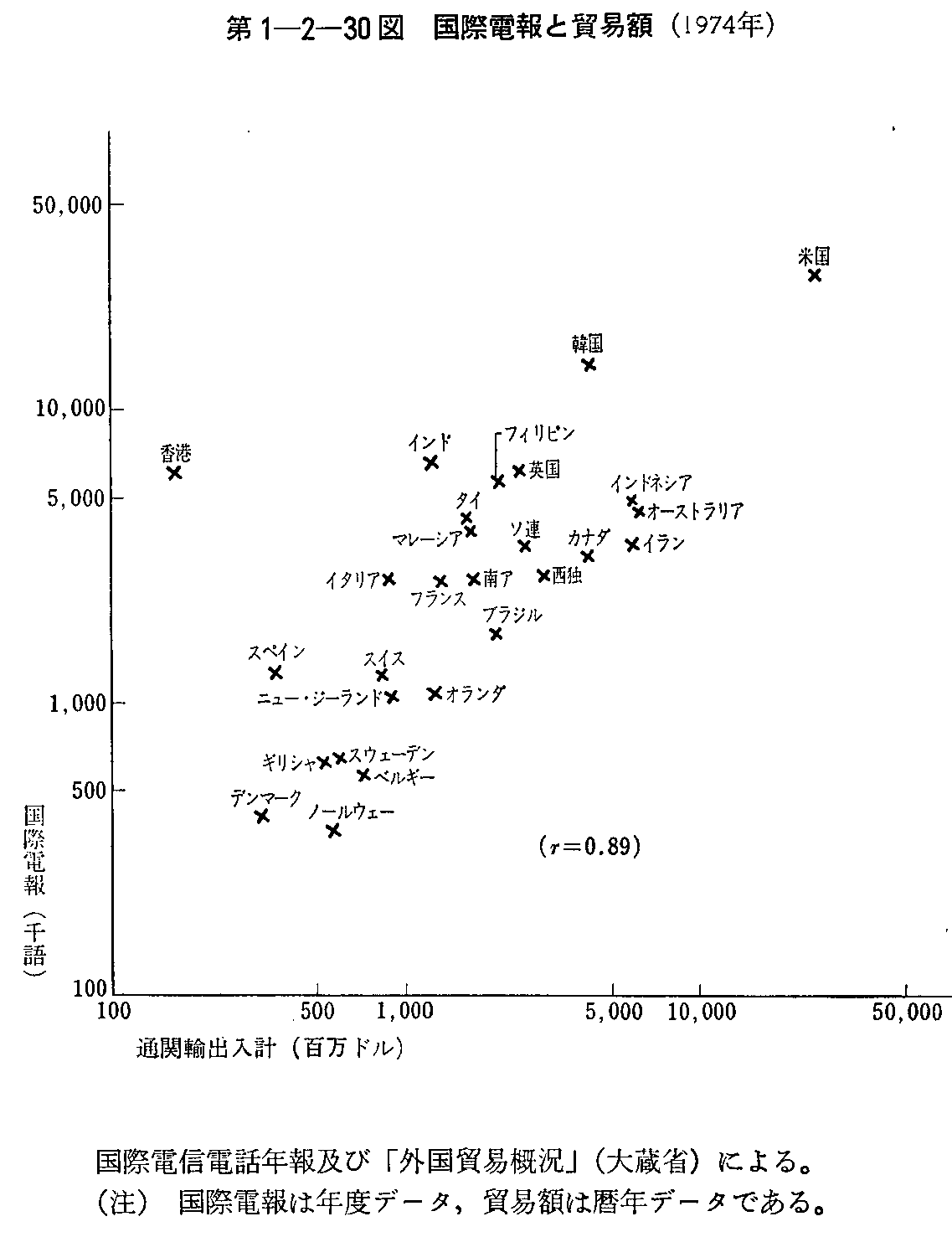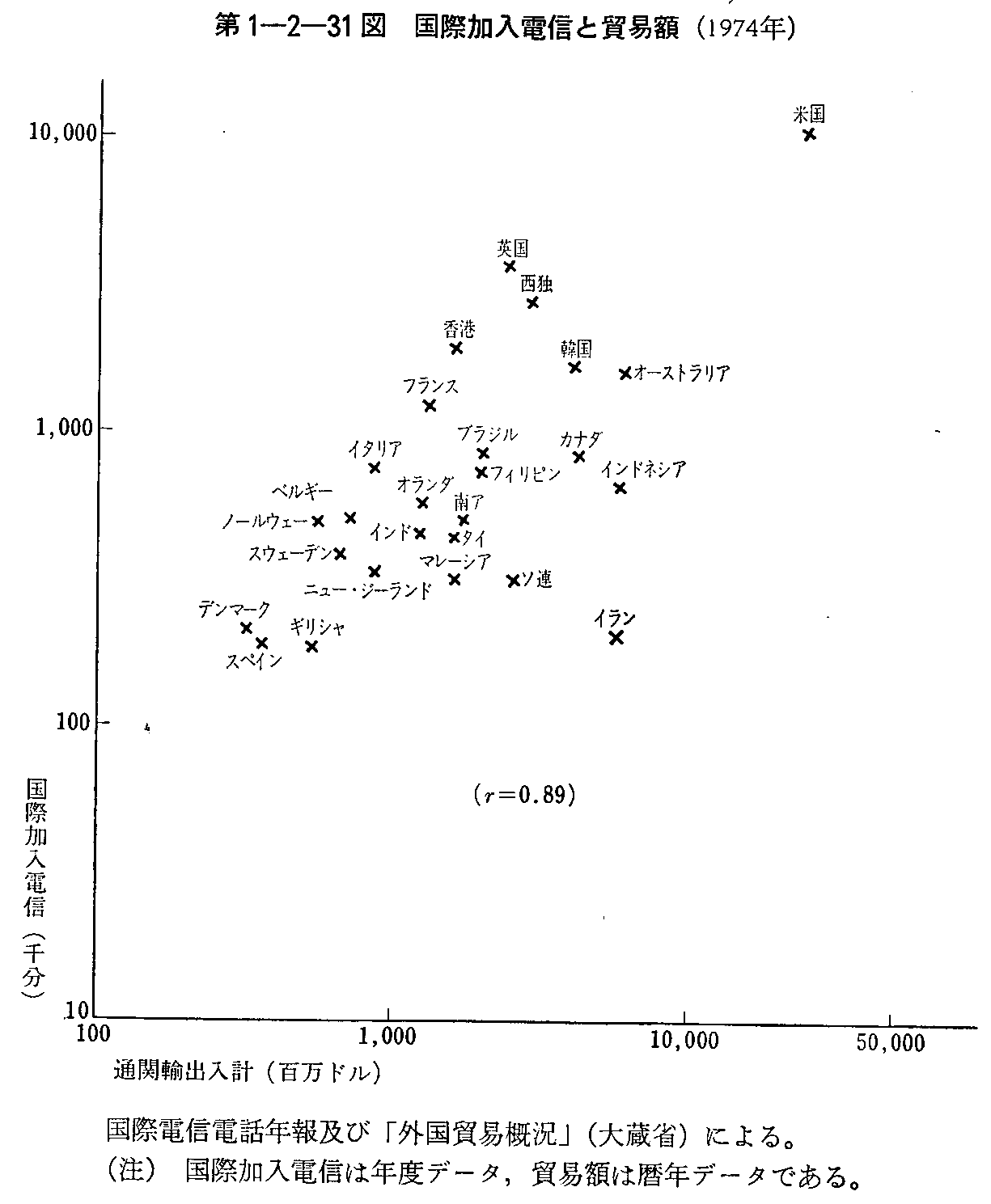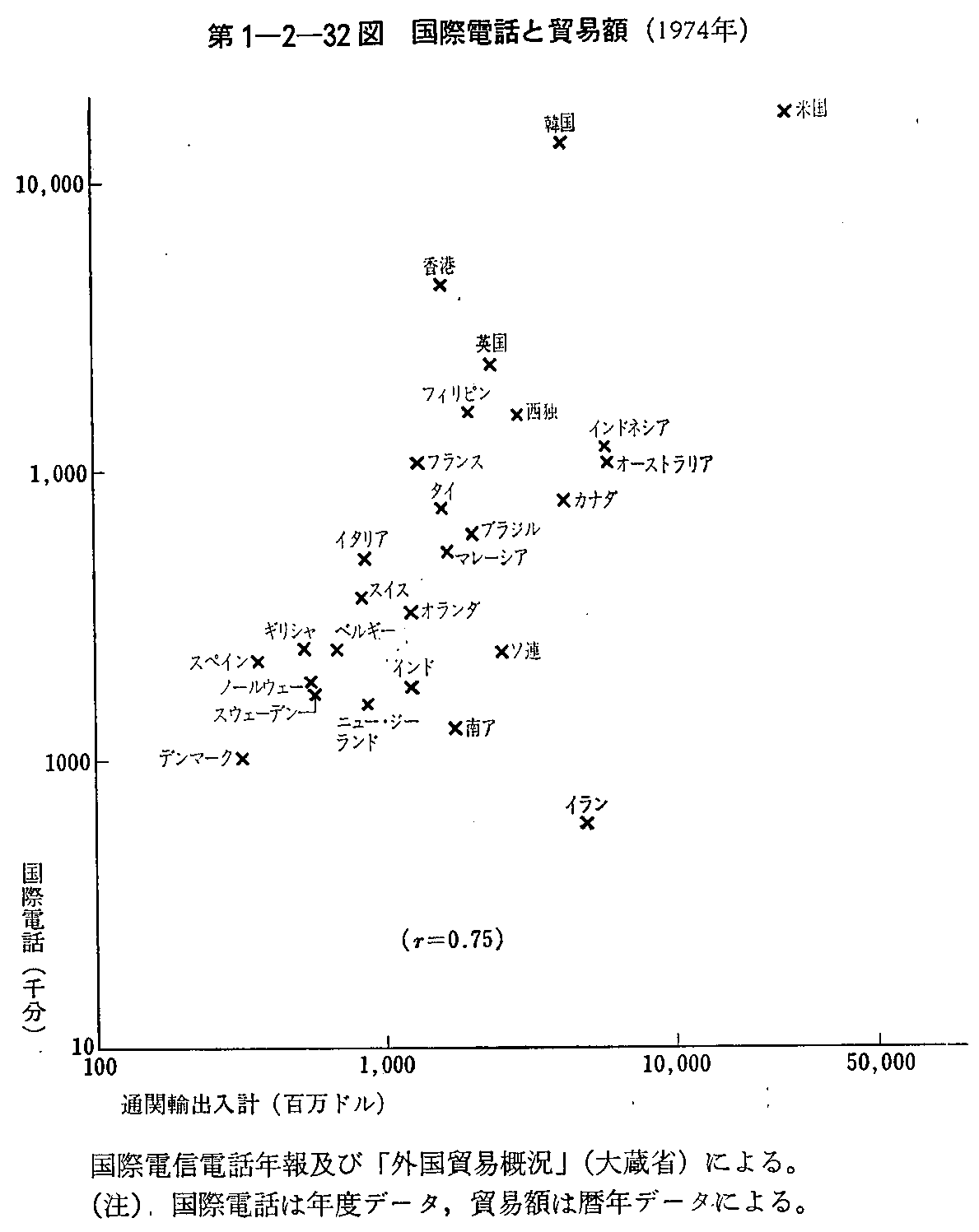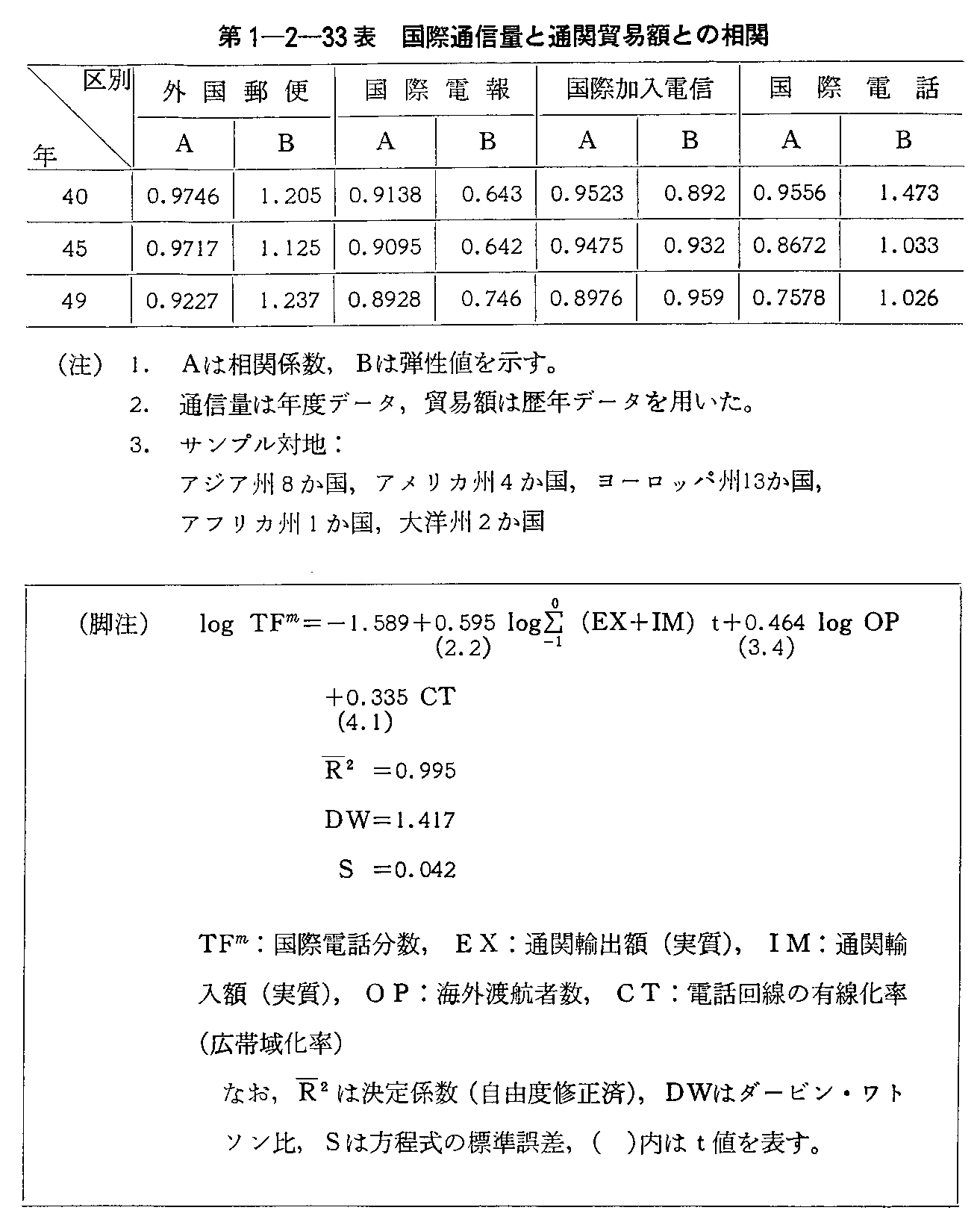第1部 総論
 第1節 昭和50年度の通信の動向
 第2章 通信と日本経済
 第1節 通信事業経営の現状  第2節 通信需要と経済要因
 第1節 通信の諸形態と記録通信  第2節 記録通信の新たな展開と今後の動向
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第4節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 宇宙通信システム  第5節 電磁波有効利用技術  第7節 その他の研究
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 国際通信と貿易の相関関係
以上のように,国際通信は貿易と密接な関係にあることが推察されるが,次に,両者の関係を定量的にとらえてみることとする。第1-2-29図〜第1-2-32図は49年時点での対地別にみた外国郵便,国際電報,国際加入電信及び国際電話の通信量と通関輸出入額との相関を表したものである。こわによると,外国郵便の相関度が最も高く,次いで国際加入電信,国際電報及び国際電話の順となっている。すなわち,記録系の国際通信はすべて国際電話より貿易との相関が高く,国際電気通信については前述の需要構造と符合した結果となっている。なお,これらの相関関係を40年,45年及び49年の3時点について比較すると,各サービスとも最近にいたるほど貿易との相関は低下する傾向にある(第1-2-33表参照)。特に,電話の相関係数は40年,45年に比べ49年は大きく低下しており,電話が貿易以外の目的で利用される度合いが,ますます大きくなってきていることを示している。このことは,貿易1単位当たりの増減が通話量にどの程度影響を与えるかを示す弾性値の推移にも表れているが,更に,貿易に人的交流要因等を加えた回帰分析によっても明らかである(脚注参照)。
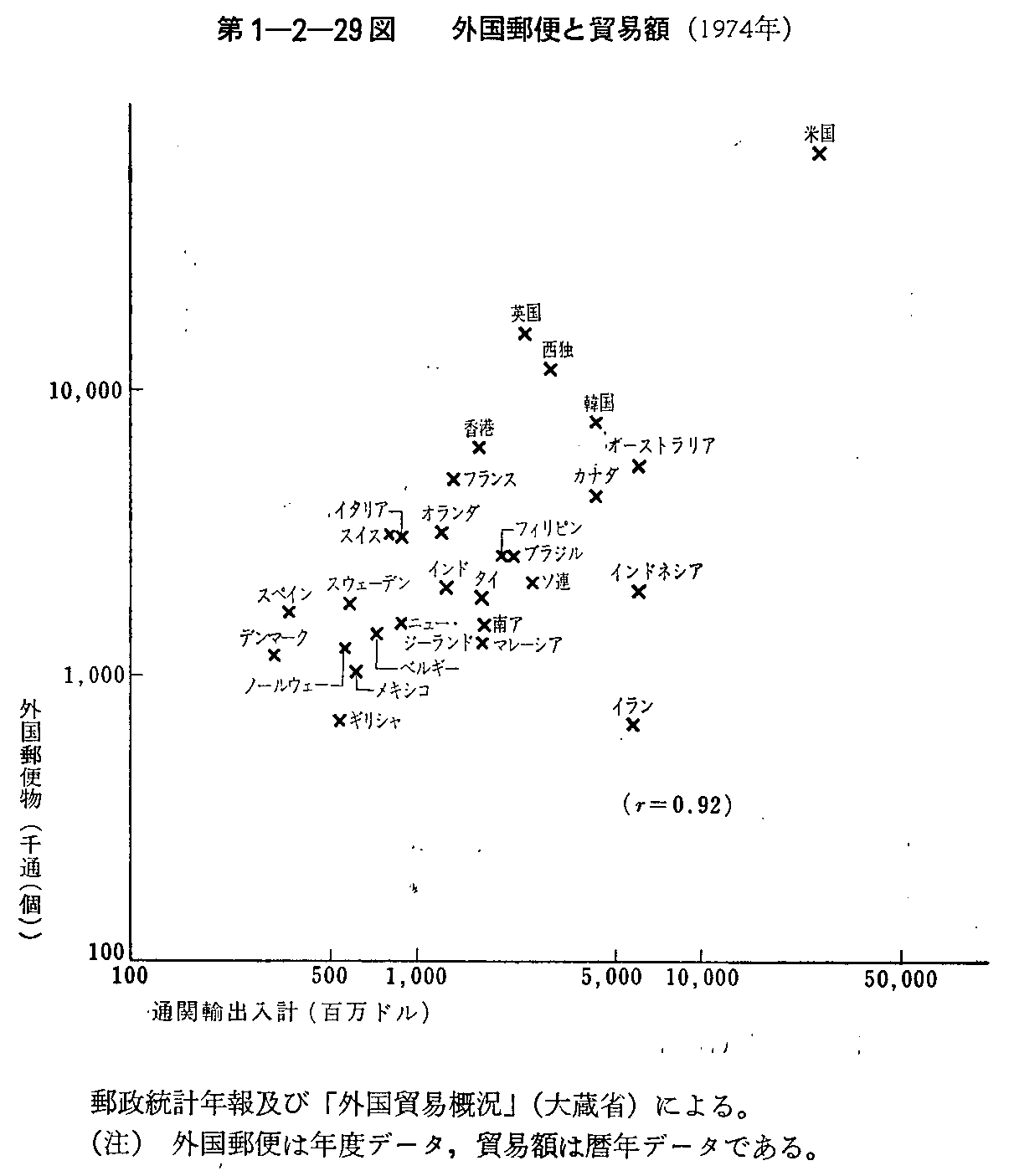
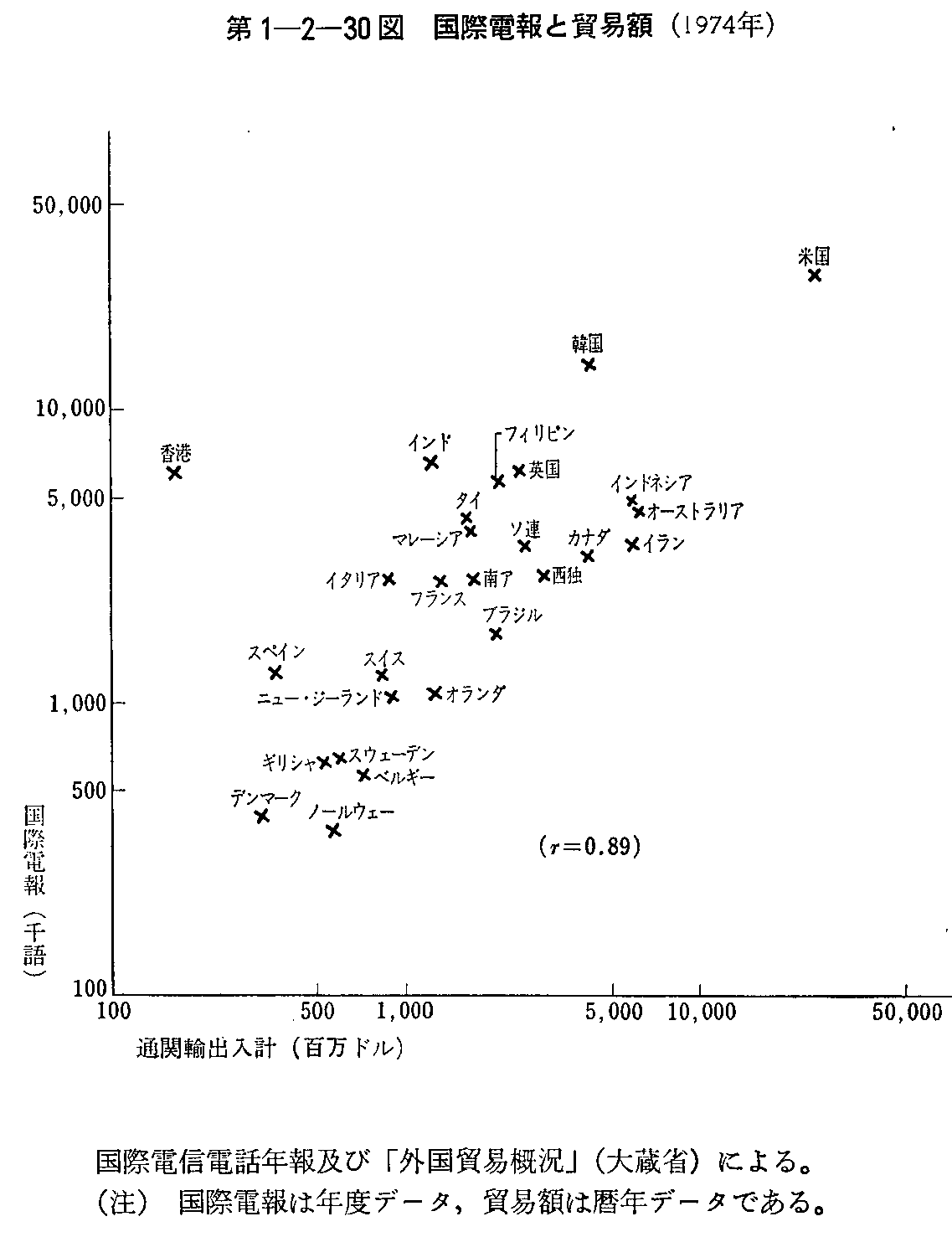
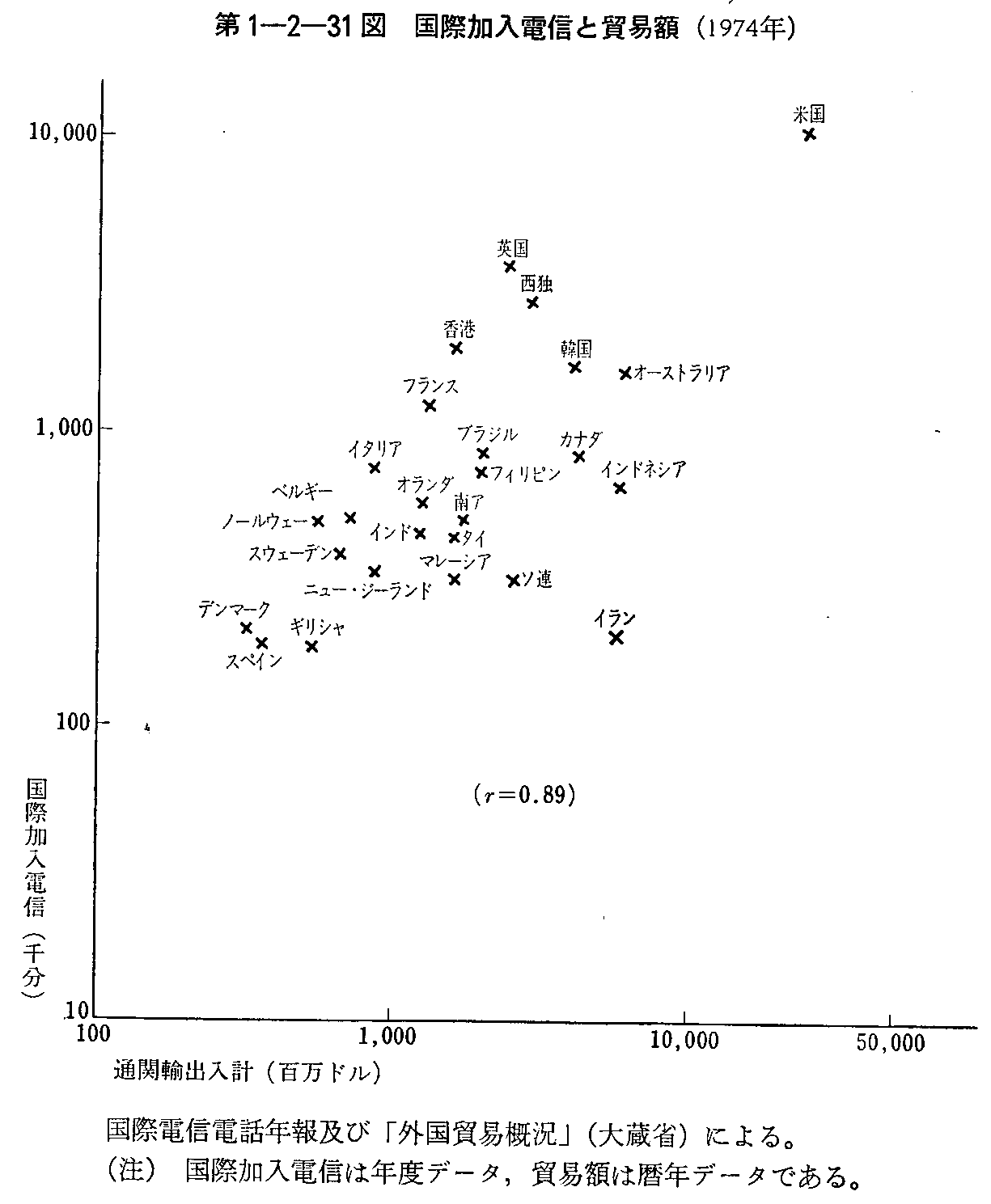
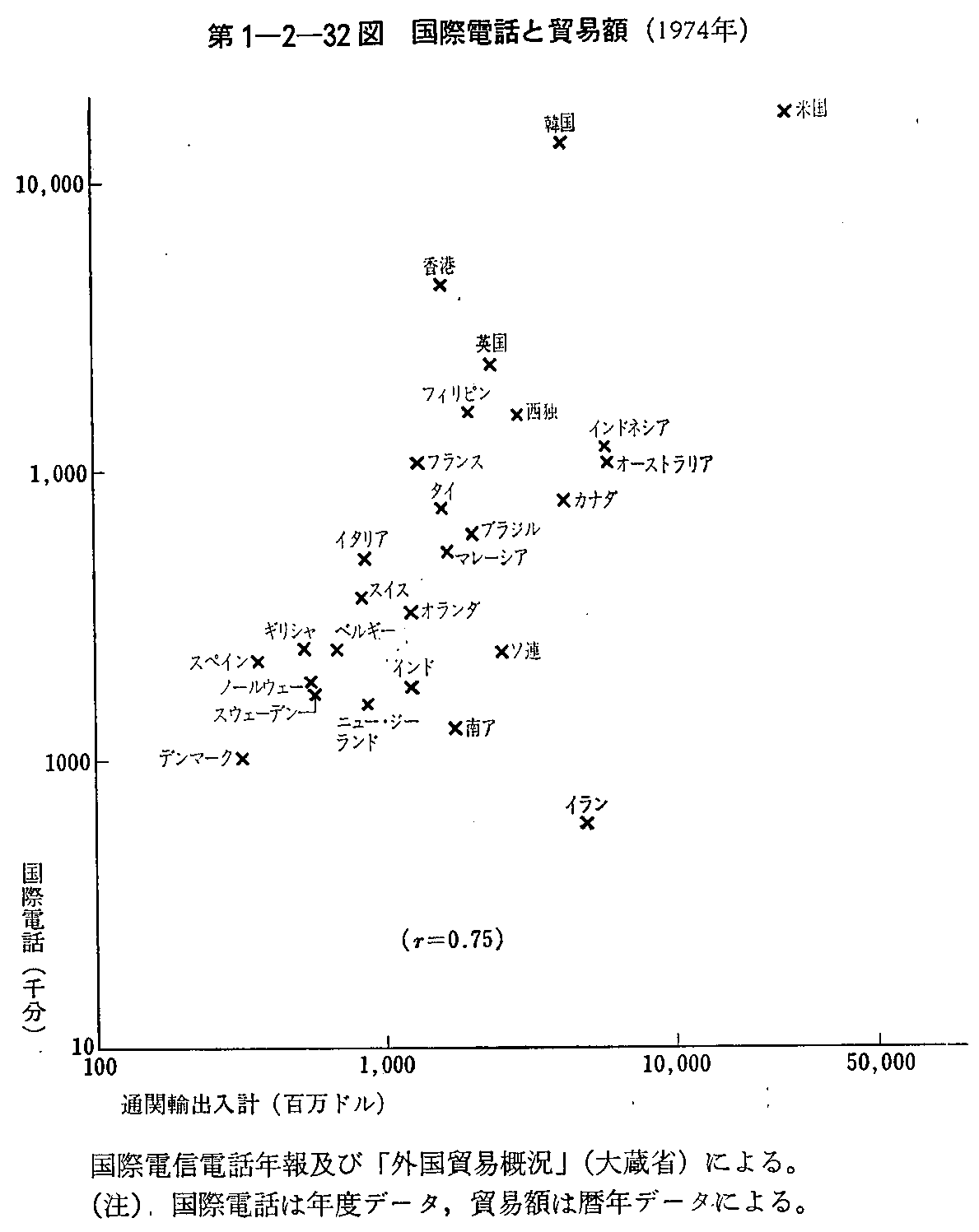
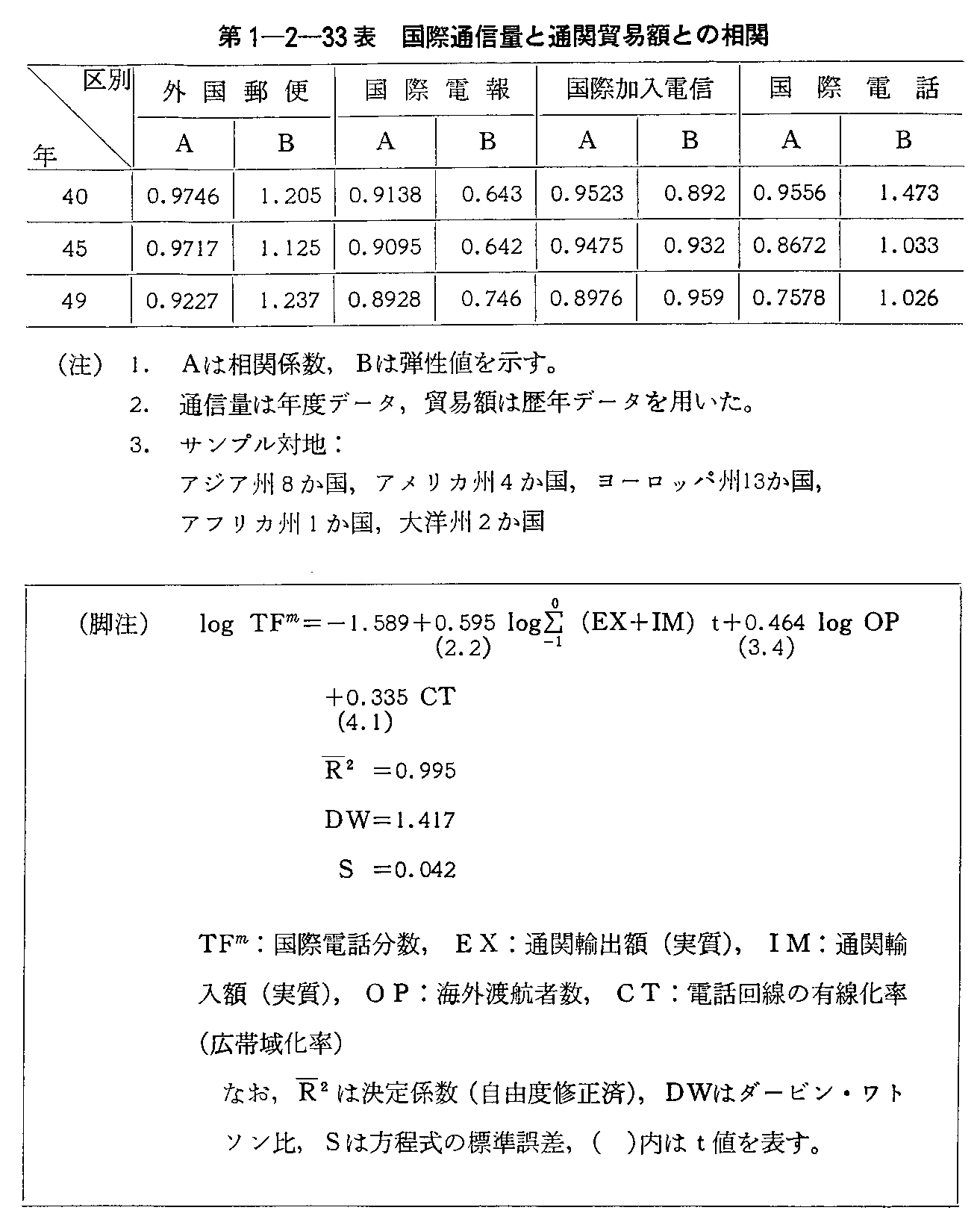
|