|
3 電子郵便の可能性記録通信としては郵便,電報,加入電信,ファクシミリ通信等があるが,郵便は輸送網を利用した通信メディアであり,その他は電気通信を利用した通信メディアである。この2種類の通信メディアは相互に影響し合いながらも基本的には独自の道を歩んできている。ところが,郵便と電気通信とが手を結び,お互いの長所を生かした新しい通信の構想が米国で生まれた。「電気通信による伝送と郵便による配達とを組み合わせたシステム」これが電子郵便(electronic mail)と呼ばれるものである(第1-3-17図参照)。電子郵便の定義は,構想が新しいこともあって,必ずしも確立しているわけではないが,一般的にはこのように解されている。 電子郵便は,欧米において既に実用化ないし試行されており,我が国においても実用化の可能性に関する調査研究が行われている。 (1) 諸外国における電子郵便 電子郵便は,米国,カナダ両国で既に実用化されており,ヨーロッパ諸国では,英国,フランス,スウェーデンの各国が近年相次いで試行を開始している。米国,カナダ両国で実施しているものはテレタイプを利用した系統のものであり,ヨーロッパの3か国で試行しているものはファクシミリを利用した系統のものである。なお,米国及びカナダは,ファクシミリ系統の電子郵便についても調査研究を進めている。 ア.米 国 1970年1月からウェスタンユニオン電信会社(Western Union Telegraph Company)と米国郵便事業公社(United States Postal Service)の共同で「メールダラム(Mailgram)」という名称の電子郵便を実施している。 WUTは1960年代の半ばから近代化計画を推進し,新しい通信サービスの研究開発を行ってきたが,その過程でWUTの電気通信網とUSPSの全国的な郵便配達網を結合すれば新しい通信サービスを提供することができるという構想を描いた。一方,USPSでも,広大な国土の中を従来の運送機関で郵便輸送を行っていたのではどうしても郵便送達のスピードが遅くなるため,郵便を電気通信で送ることができないかという課題を抱えていた。その結果,ここに両者の合意が成立し,共同実験を経て,メールグラムが誕生したのである。 1970年のサービス開始当初は,12都市からのテレックス発信等に限られていたが,その後,窓口発信,電話発信,コンピュータ発信と受付範囲を広げ,受付地域も全国に拡大していった(配達地域は当初から全国である。)。現在では全国どこからどこへでも発信でき,原則として午後7時までに受信局へ到着したメールグラムは,翌日中には郵便物として受取人へ配達される仕組みになっている。 1970年の利用通数は36万通であったが,1974年には約2千万通に達した(第1-3-18図参照)。 メールグラムの特性としては, [1] 全米に配達されること [2] 翌日配達が確保されていること [3] 受取人に電報と同程度の注意を喚起するものであること [4] 各種の発信方法があって利用が簡便であること [5] (電報に比べ)低廉なこと [6] 同文の大量のメッセージの作成及び発信が容易なことが 指摘されている。 イ.カ ナ ダ 1972年10月からカナダ郵政省とCanadian Overseas Telecommunication社(国内電信サービスを提供している民間会社)との共同で「テレポスト(Telepost)」という電子郵便サービスを実施している。 このテレポストサービスは,既存のテレックス網に郵便局の配達機能を結び付け,テレックス加入者が非加入者にメッセージを送信できるようにしたものであり,初期のメールグラムに似たサービスである。配達は翌日配達と速達扱いの当日配達とがある。 ウ.ヨーロッパの電子郵便 英国では郵便電気通信公社が1974年10月から「ポストファックス(PostFax)」と呼ばれるファクシミリ系の電子郵便を試行している。メッセージをポストファックス取扱局の窓口へ差し出すと一般の電話回線網を経由してあて先に最も近い取扱局まで送信された上,配達又は窓口交付によって当日中に受取人へ手渡される。また,ファクシミリ装置の所有者はその装置を使用してポストファックスの送受信を行うことができる。 サービス開始の理由としては,ファクシミリ装置を持たない中小規模の会社や組織が公衆サービスとしてファクシミリを利用したいという需要があったことが上げられるが,そのほか,企業内のファクシミリ網を持つ大企業が自己の設備を活用してファクシミリ装置を持たない顧客や仕入先との情報交換をするためにポストファックスを利用するようになることもねらっているといわれている。 フランスでは郵便電気通信省が1974年10月から「テレコピー(T〓l〓copie)」という電子郵便を試行している。英国の場合と同様,電話回線網を利用してメッセージを送り,受信局では窓口交付又は配達によって受取人へ届ける仕組みになっている。配達の場合は翌々日配達となる。 サービス開始の目的は,電話回線の有効な利用を図り,収入を増大させることなどに置かれている。 スウェーデンにおいても,郵政庁と電気通信庁の共同事業として1973年6月から「テレレター(Teleletter)」という電子郵便を試行している。窓口で受け付けたメッセージは既存の電話回線網で受信局へ送り,当日中に速達便で配達される。 サービス開始の目的としては,より送達速度の速い特別な郵便サービスに対する要望があると同時に,郵政庁としても「迅速な通信」という面で積極的な施策を取る必要があると認めたことなどがあげられている。 試行の目的は三者三様であるが,いずれも電話回線網を利用したファクシミリ系のサービスであり,その仕組みはファクシミリ電報と類似の形態ともいえよう。3か国とも試行後の歴史が浅く,サービスエリアも主要都市に限られているため,利用通数は少ない現状であるが,それぞれの目的に応じて今後どのような歩みをたどるか注目される。 (2) 我が国における調査研究の現状 欧米における電子郵便の実施,特に米国のメールグラムの急成長は我が国においても関心のもたれるところとなった。そのため,郵政省では,通信行政を主管する立場及び郵便事業を経営する立場から,我が国における電子郵便の可能性について50年度から調査研究を行っている。 新しい通信サービスであるため検討を要する点が多岐にわたっているが,検討する上での主要な点は次のとおりである。 まず第一は,電子郵便の将来性についてである。 電子郵便を実施した場合,相当数の需要があるかどうか,その伸びが期待できるかどうかの見通しを得る必要があり,例えば郵便や電報からの代替可能性はどうか,新しい分野の需要があるかどうかを分析することは重要な課題となっている。 第二は,ファクシミリ通信との関係についてである。 ファクシミリは今後とも普及していくものとして予想されており,一般家庭向け簡易形ファクシミリの研究も進められているが,電子郵便とファクシミリはどのように競合するかなどの分析は重要なことであろう。 第三は技術上の諸問題についてである。 電子郵便システムは,テレタイプ又はファクシミリの端末装置,メッセージの交換装置(例えばコンピュータ・センタ)及びこれらの端末装置と交換装置を結ぶ通信回線が基本構成要素となるが,今日いずれの分野においても技術開発が著しい。したがって,検討内容は技術的に可能か否かというよりもむしろ,効率的,経済的,かつ信頼性の高いシステムについて考察する点にあり,技術的可能性の問題もこうした要請を充足させ得るかどうかにかかっているといえよう。 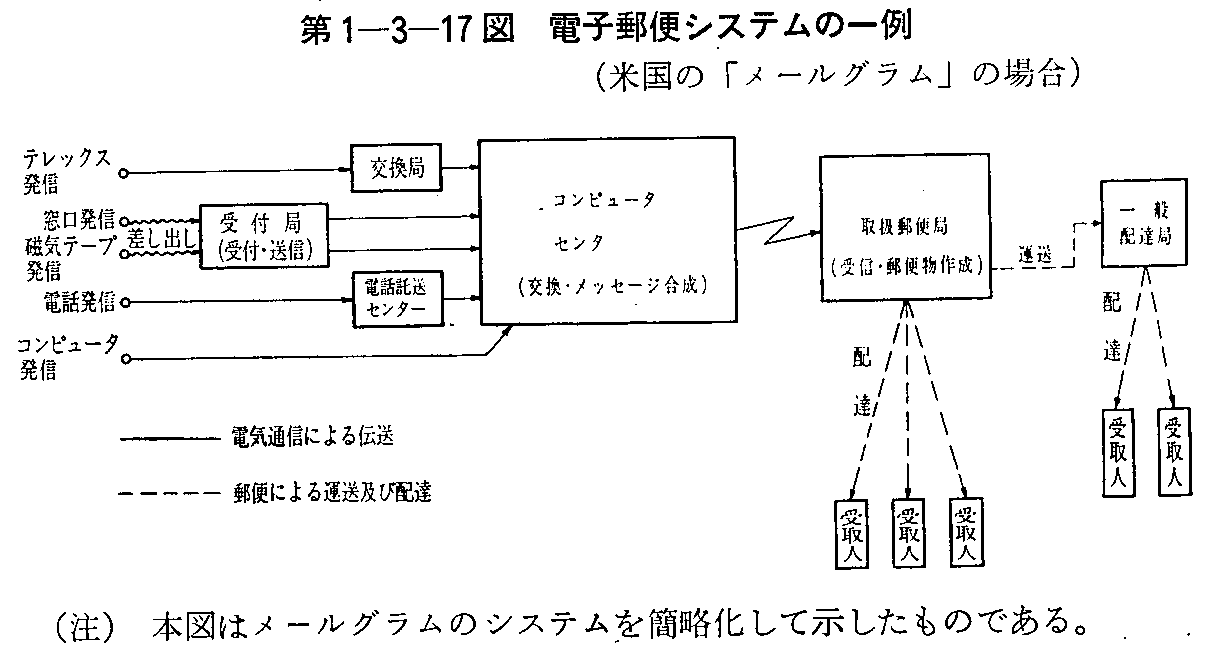 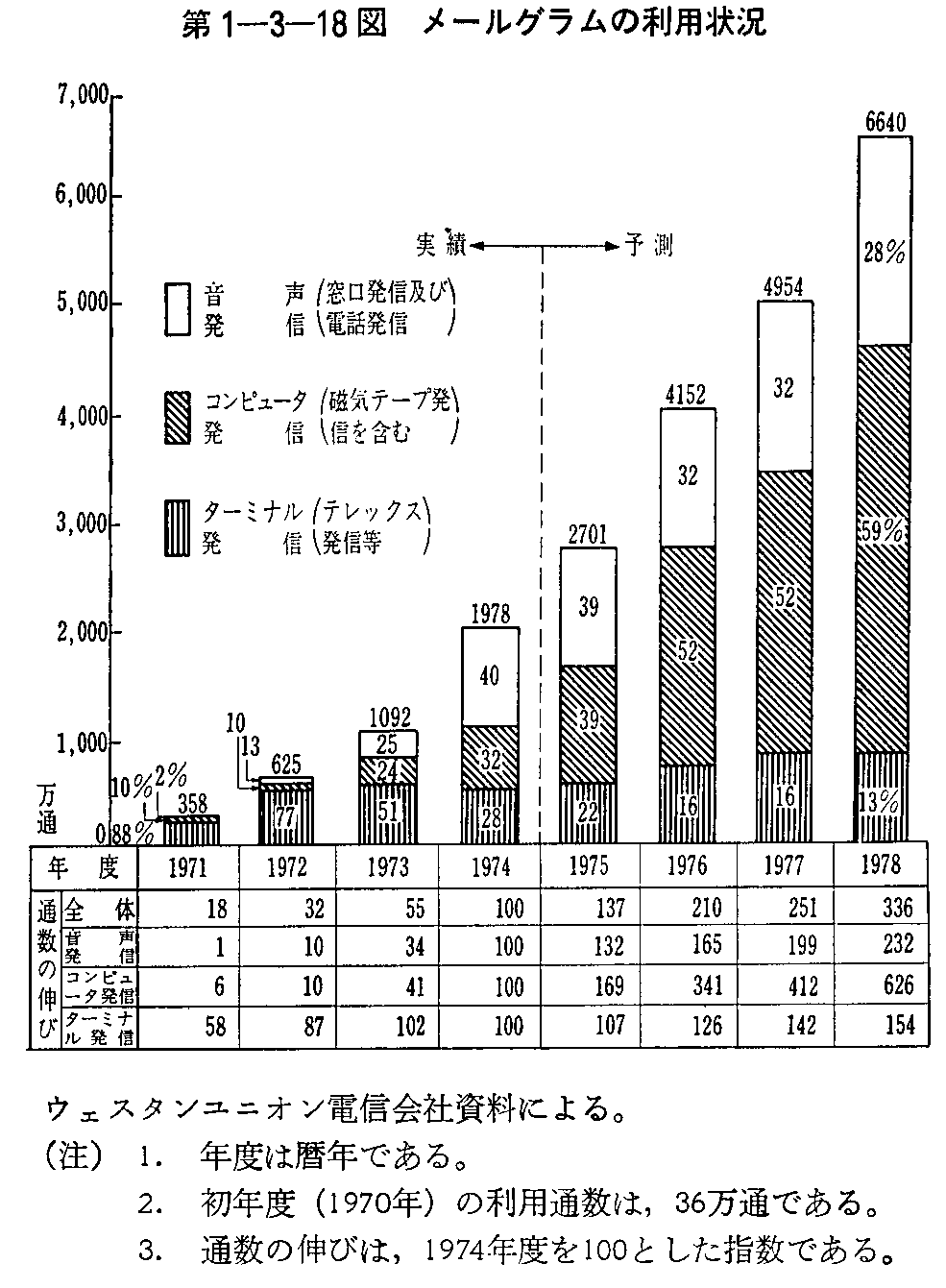 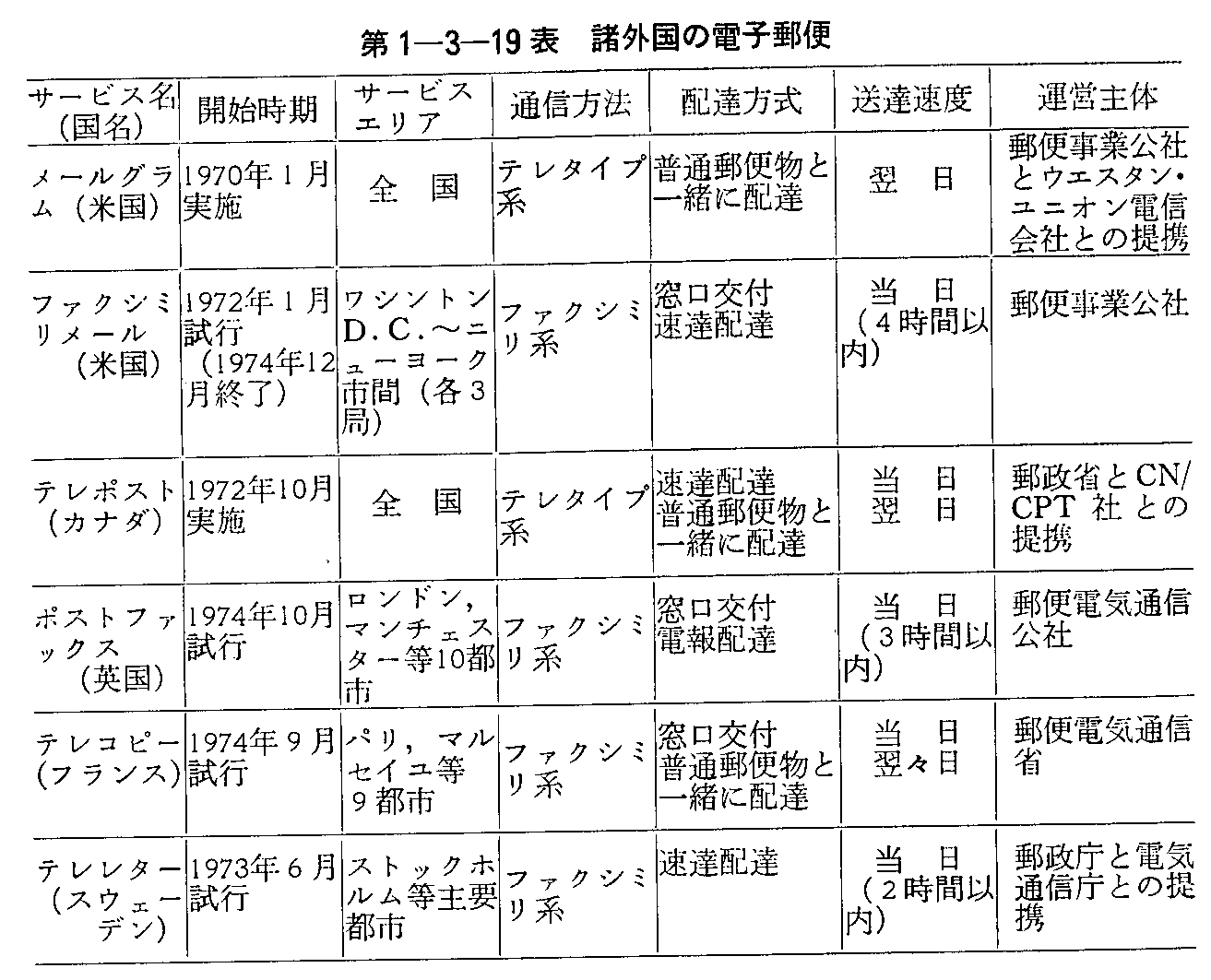
|