 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第2章 通信新時代の構築
第1節 社会経済の発展と通信
1 基幹メディアの普及と国民生活への定着
(1)経済計画,国土総合開発計画と通信
戦後,我が国では経済の変遷に即して種々の経済計画,国土総合開発計画が策定されてきたが,これらの計画の中で,通信は広く国民経済的見地から道路,鉄道,港湾等と並んで産業活動の基盤を形成し,また,住宅,公園,上下水道等とともに国民の生活基盤を形成する社会資本として位置付けられ,その整備拡充が図られてきた。
ここでは,これまでに策定された経済計画,国土総合開発計画の中において,通信は社会資本としてどのように位置付けられ,政策目標の達成にどのようなかかわりを持っているかなどについて概観することとする(第1-2-1表参照)。
ア.昭和30年代-経済高度成長期
この時期は,外国からの援助や特需に支えられた状態からの脱却と完全雇用,高い経済成長を目標に,経済自立五ヶ年計画,国民所得倍増計画等が策定される一方,都市の過大化の防止と地域格差の縮小に配慮しながら,地域間の均衡ある発展を図ることを目標に全国総合開発計画が策定された。
これらの計画の中で,通信については,「電話を中心とする近代的な通信施設の急速な拡充は,国民経済および産業の近代化のための重要な前提である」(国民所得倍増計画),「今後経済規模の拡大に伴って需要が増加することを考慮すると,交通通信施設の整備を一層強化する必要がある」(中期経済計画),「電話の自動化,通信の即時化を強力に推進する」(全国総合開発計画)等とされている。このうち郵便については,経済成長に伴って増加する郵便物に応じた人員,設備,資材を措置する。経営合理化を図るとされ,電気通信については,戦争により打撃を受けた施設を復旧・整備するとともにひっ迫した電話の需給関係を改善する。設備投資促進のため自己資本を拡充するとされている。
30年代においては,おりからの神武景気,岩戸景気等による経済成長により電話需要が大きく伸びる一方,多年にわたる投資不足も重なり電話の需給関係は極度にひっ迫していた。このため,電電公社では“すぐつく電話”,“すぐつながる電話”を二大目標に,設備投資資金を確保するため電信電話債券制度を設け,今後の電話需要に対応できるよう電話局舎の建設,設備の近代化,基幹回線の大容量化等を中心に行い,39年度末までに約1兆5千億円を投資した。これにより電話加入数は30年当時約220万であったものが39年度末には630万まで伸びるとともに,39年1月には東京-大阪間の自動即時化を実施するに至った。
なお,28年に設定した1度数当たりの通話料金7円は,その後の技術革新,電話需要の増加によるスケールメリット等により,51年に10円に改定するまで23年間据え置かれた。
イ.昭和40年代-経済社会発展期
この時期は,経済成長を維持しつつ,社会資本の整備,社会保障の充実等経済の発展と調和のとれた社会の形成を目標に経済社会発展計画,経済社会基本計画等が策定される一方,自然の恒久的な保護・保存,開発可能性の全国土への拡大・均衡化等の課題の調和による人間のための豊かな環境の創造を目標に新全国総合開発計画が策定された。
これらの計画の中で,通信については,「経済の発展と国民生活の向上に伴い・・・・・・情報の適確迅速な交換も必要になってくる」(経済社会発展計画),「国土利用の再構成をはかるため,その基礎的条件となる全国通信網を整備する」(経済社会基本計画),「新しい情報化社会を迎えて,全国的な通信網,交通体系の合理的整備によって,全国土をおおう新ネットワークを計画的に形成する」(新全国総合開発計画)等とされている。このうち郵便については,作業を機械化するため郵便物の規格化を図る。機械設備を導入するとされ,電気通信については任意の地点間で常時,即時に情報伝達ができるような電話ネットワークを整備する。データ通信,画像通信を拡充,開発し,通信の高度化を図る。住宅用電話を中心に一層の電話の普及を図るとされている。
40年代においては,郵便は,設備の近代化を図り増大する郵便物を効率的に処理するため,43年に郵便番号制度を取り入れ,郵便番号自動読取区分機を開発・導入したのをはじめ各種郵便処理機械を導入した。
電話は需要の増大,新しい技術の進展等を背景に住宅用電話を中心に架設を進めた結果,49年度末には住宅用電話比率約60%,加入電話総数約3千万,ダイヤル自動化率99%と,電話はいよいよ国民生活に身近な通信手段となった。さらに,社会経済の発展とともに,通話以外の電気通信サービスの高度化ニーズも顕著になったため,46年に公衆電話網を一般に開放し,ファクシミリ通信を行えるようにしたほか,データ通信サービスとして,全国銀行データ通信システムや地域気象観測システム(AMeDAS)等のサービスが開始されるなど電気通信は経済活動の効率化,国民生活の利便性の向上等に大きく寄与するようになった。
このような電気通信設備建設のため,40年代では30年代の5倍強に当たる7兆6千万円が投資された。
ウ.昭和50年代-新しい安定成長期
この時期は,内外経済環境の変化に対応しつつ安定成長路線への定着を図り,技術革新の進展等に伴う産業構造の高度化等経済社会の新たな展開に備えることを目標に,新経済社会7カ年計画,1980年代経済社会の展望と指針等が策定される一方,人間と自然との調和のとれた安定感のある健康で文化的な人間居住の総合的環境の計画的整備を目標に,第三次全国総合開発計画が策定された。
これらの計画の中で,通信については,「情報,通信分野での技術革新の進展及びトータルな情報通信システムの形成が高度情報社会へ向けての変化を生むことになろう」(1980年代経済社会の展望と指針),「定住構想を達成するためには通信体系のネットワーク形成が不可欠であり,情報の持つ重要性を認識しつつ,情報の一層の高度化,大量化に対応してその媒体である通信体系を計画的に整備する必要がある」(第三次全国総合開発計画)とされている。このうち郵便については作業の機械化を推進し,郵便輸送方式の近代化を図るとされ,電気通信については電話の需給均衡を維持する。データ通信,画像通信及び移動通信サービスの施設を一層拡充し,多様な情報ニーズにこたえる。既存通信網のディジタル化,統合化を順次進め高度な情報通信システムを形成するとされている。50年代においては,郵便は利用者ニーズにこたえ郵便物のスピードアップを図るため自動車輸送主体の新しい郵便輸送システムを導入した。電気通信については,50年代に入ってからも積極的な設備投資を行い,その額は58年度までの9年間に40年代の約2倍に当たる14兆6千億円を投資し,30年代以降の累計は23兆7千億円となった。こうして,53年度末までには全国的レベルによる積滞解消,ダイヤル自動化が完了し,国民の基本的な通信手段としての電話を整備した。以後電話は国民生活の必需品として量的拡大から質的充実を目指し,通話機能以外にもニーズに沿った多種多様な機能を備えた電話機を開発・導入していくこととなる。通話サービス以外でも,電話網利用に比べて通信料が安く多彩なサービス機能を備えたファクシミリ通信網,種々のデータ通信システムの効率的な結合を可能にするVAN(付加価値通信網)が導入され,さらに,双方向で随時,任意に画像情報を検索できるキャプテンが59年11月から商用化されるに至っている。
このように,50年代は基幹メディアに代わって多様かつ高度な新しいメディアが次々と登場してきた時期といえ,この傾向は今後とも一層強まるものと予想される。このような状況において,これらのメディアをいかに利用者のニーズに合致させ,国民の間に普及させていくかが今後の大きな課題となっている。
(2)基幹メディアの整備拡充と国民生活への定着
今日,我が国の郵便,電話,放送といった基幹メディアは,企業,個人等の情報ニーズの増大を背景に,相次ぐ技術革新や通信事業者の経営努力の結果全国に普及し,経済活動の効率化,国民生活の利便性の向上等に大きな役割を果たしてきた。第1-2-2図は,100人当たりの郵便利用通数,電話加入数及びNHK放送受信契約数についてその推移をみたものであるが,近年においてはいずれもその成長が鈍化してきており,このことは,これらの基幹メディアがほぼ成熟の域に達したことなどによるものと考えられる。
ア.郵 便
現物性,記録性,大量性,経済性等の面で優れた特性を持つ郵便は,国民の日常生活に必要不可欠な基本的通信手段として,社会的,経済的に重要な役割を果たしている。
30年度に戦前の水準(昭和9〜11年度平均)の48億通に回復した郵便物数は,その後,経済変動,料金値上げ等の影響を受けたものの,着実に増加して,42年度には100億通を突破,58年度においては162億通と過去最高を記録している。
郵政省では増加する郵便物の正確,安全,迅速な送達を確保するため,これまでも,郵便物の規格化,郵便番号制の導入,郵便番号自動読取区分機の開発配備,機械化集中処理局の建設,航空機搭載対象郵便物の拡大,あるいは集配作業の機動化等,一連の近代化施策を実施し,作業の効率化及び送達速度の安定化,迅速化を図ってきた。
しかしながら,この間の物数の動向をみた場合,30年代では平均7%,40年代では同4%,50年代に入ってからは2%程度と,経済の安定成長への移行等もあって,増加基調にあるものの次第にその伸びは低下してきている。
このような状況を踏まえ,今後とも郵便の健全な経営を維持していくためには,高度化・多様化した利用者のニーズにマッチした良質なサービスを提供し,徹底した事業運営の効率化を図ることが必要である。このため,郵政省では,59年2月に郵便輸送システムを改善し,全種別郵便物の県内翌日配達等大幅なスピードアップを図り,同8月には,業務用郵便等のスピード志向に更にこたえるためビジネス郵便制度の拡充改善,同10月には,電気通信手段を活用した電子郵便実験サービスの全国実施等積極的な改善措置を講じている。
イ.電 話
第二次大戦によって壊滅的な打撃を受けた電気通信施設の復興を図り,我が国経済の立ち直りに寄与するとともに国民の強い電気通信に対するニーズにこたえるため,27年に政府運営の長所と私企業の長所を取り入れた公共企業体として電電公社が設立された。
電電公社では,発足以来今日まで数次にわたる電信電話拡充計画を実行し,「電話の積滞解消とダイヤル自動即時化」,いわゆる”すぐつく電話”,”すぐつながる電話”の二大目標を実現した。
すぐつく電話を目指して,第一次5か年計画をはじめ,第二次,第三次と拡充計画を積み重ねたが,おりからの好景気に伴い電話の需要は目覚ましく申込積滞数は増大する一方となり,第三次の最終年度(42年度)には140万加入の新規電話架設を行ったがその年の積滞数は242万加入となるなど需給改善には程遠い状況であった(第1-2-3図参照)。拡充計画を更に進めた結果,積滞数も45年度末の291万加入をピークにそれ以降は急速に減少し,第五次の最終年度(52年度)末には15万9千加入となり積滞解消の目標をほぼ実現するに至った。
すぐつながる電話を目指して,第二次まで大都市中心に市外通話の即時化を進めてきたが,第三次以降はこれを全国に拡大することとし,この結果,第三次の最終年度(42年度)末には市外通話の即時化率は96%,市外ダイヤル化率は84%まで向上した。第四次,第五次とも引き続きすぐつながる電話の実現に努め,54年3月14日,東京都利島,沖縄県南大東島,北大東島における自動化を最後に全国のダイヤル自動化が完了し今日に至っている。
第1-2-4図は事務用電話と住宅用電話の普及状況をみたものである。
我が国の電話は長い間企業を中心に普及してきたが,近年における所得水準の向上,生活の快適性・利便性志向等により住宅用電話は爆発的に普及し,47年度に事務用電話と住宅用電話の構成比が逆転して以来その差は更に拡大する傾向にある。また,人口100人当たりの加入電話の普及状況をみると,30年度末で2.4加入であったものが30年代後半以降飛躍的に伸び,58年度末には35.8加入に至っている。
このように電話は国民生活に不可欠なメディアとして定着しているが,近年はこれまでのようにただ単に通話ができればよいという状態から,より便利かつ高度な機能を備えることが求められており,これに対してはプッシュホン,ホームテレホン,ビジネスホン,シルバーホン,盲人用ダイヤル盤,カード公衆電話等のサービスを提供している。
我が国経済社会は今後成熟化,高齢化等へと進むにつれて電気通信サービスに対する国民のニーズも多様化することが予想され,電話についてもこのような二ーズに柔軟かつ的確に対応していくことが必要である。
ウ.放 送
我が国の放送は,25年,いわゆる電波3法(電波法,放送法,電波監理委員会設置法)が制定されたことにより,公共放送と民間放送の二系列が併存する今日の放送体制が確立された。
中波放送については,早くから代表的な音声メディアとして国民の間に普及してきた。この放送は一部にはなお難聴の問題もあるが,近年の技術の進展による受信機の小型化,低廉化,モータリゼーションの進展等によるほか,利用者の二ーズに合わせた放送を行うことにより幅広く根強い人気を保ち今日に至っている。
FM放送については,音質の良い放送をステレオで聞くことができることから,国民の期待も大きく,郵政省では43年以降全国で聴取することができるようにその普及を図ってきた。NHKのFM放送については,49年度末までに全国で聴取できるようになった。県域放送を原則とする民間のFM放送については,59年9月末現在で34都道府県について放送が実施できるように周波数の割当てを行い,既に11の都道府県で放送が実施されており,他の県についても順次放送が実施されることになっている。また,周波数の割当てが行われていない13県についても,できる限り早期に放送が実施できるよう所要の検討を進めることとしている。
テレビジョン放送は,28年に東京で放送が開始された。郵政省ではテレビジョン放送を全国に普及させるため,VHFチャンネルのみが利用可能であった30年代には,東京,大阪等の大都市を中心にNHKのほか複数の民間放送が併設できるよう措置した。また,UHFチャンネルの利用が可能となった40年代初頭からは,NHKのほかに全国で2チャンネル以上の民間放送が視聴できるよう措置してきた。さらに,民間放送の全国2チャンネル化がほぼ達成された43年からは,各地域の状況を考慮しながら,順次3チャンネル以上の多局化を進めてきており,その結果,現在では全国30都道府県で3チャンネル以上の民間放送が視聴できるようになっている。
一方,多局化と並行して,テレビジョン放送の難視聴解消等を図るため,中継局に対し周波数の割当てなどを行ってきている。
また,60年度の開校に向けて現在種々の準備を進めている放送大学についても,授業実施予定地域で放送が実施できるように,57年に周波数の割当てを行っている。
この結果,中波,FM,テレビジョン放送等の放送局数は,放送関係の実用化試験局等を含めNHK9,838局,民間放送125社9,834局になった。
NHKは,33年度から置局の拡充,放送番組の充実等を内容とする第1次5か年計画,37年度から総合・教育テレビジョンの全国放送網の早期達成等を内容とする第2次5か年計画を策定し,第2次計画の終了した42年度末には総合・教育とも力バレージは95.5%に達した。置局はその後も難視聴地域の解消を目指して続けており,58年度末現在,辺地における難視聴世帯数は42万世帯にまで減少した。
テレビジョン放送は即時性・娯楽性を持つ上に,このような施策とあいまって今日では国民生活に深く浸透している。テレビジョンの普及過程をNHKの受信契約数でみると,テレビジョンはスタート直後の30年頃は大都市中心で契約数もラジオと比較にならなかったが,その後の我が国経済の急速な発展と技術革新による受像機の低廉化,34年の皇太子御成婚,39年の東京オリンピック等社会的なビッグイベントが受像機購入に決定的なインパクトを与えるとともに,35年のカラー放送実施とあいまって,36年度末で1千万件,42年度末で2千万件,57年度末で3千万件を超え58年度末には3,080万件に達した。
第1-2-5表は35年から55年までの20年間の国民の1日の生活行動別平均時間量の推移をみたものであるが,ラジオ,テレビジョンに接する時間は55年には4時間2分と余暇時間全体の60%を占めている。また,テレビジョン視聴時間は35年当時1時間1分であったものが55年には3時間25分となり,他の生活行動時間が比較的安定した推移を示しているのに比べて際立った増加を示しており,生活時間の中で大きなウェイトを占めていることがわかる。
このように,放送は国民に対する基幹的な情報提供手段として社会的に大きな影響を有するとともに国民生活に必要不可欠なものとなっている。このような状況の下にあっては,国民の放送サービスに対する多様かつ高度なニーズにこたえるため,近年の技術革新の成果を活用し,新たな放送サービスの開発・導入を図っていくことが必要である。
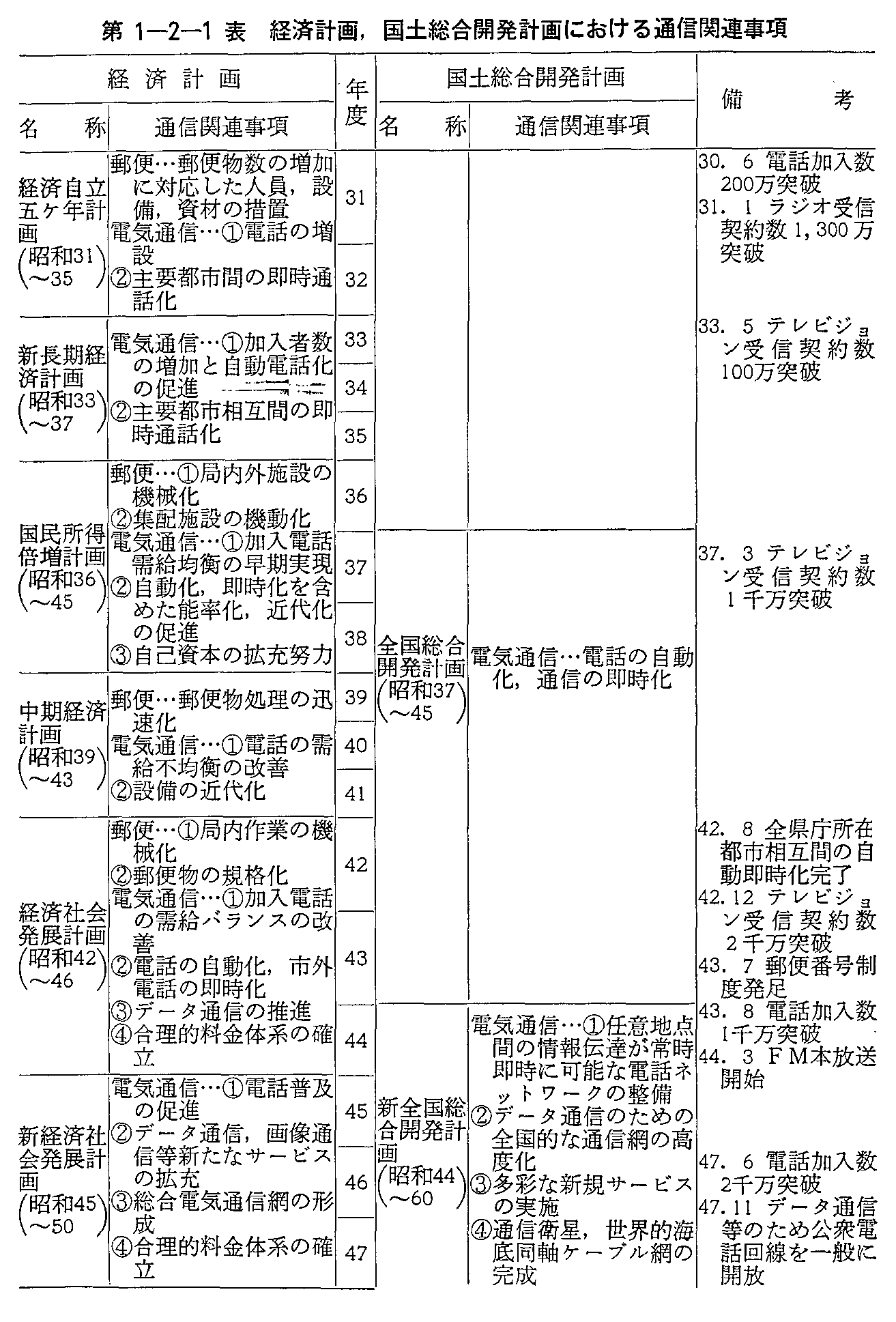
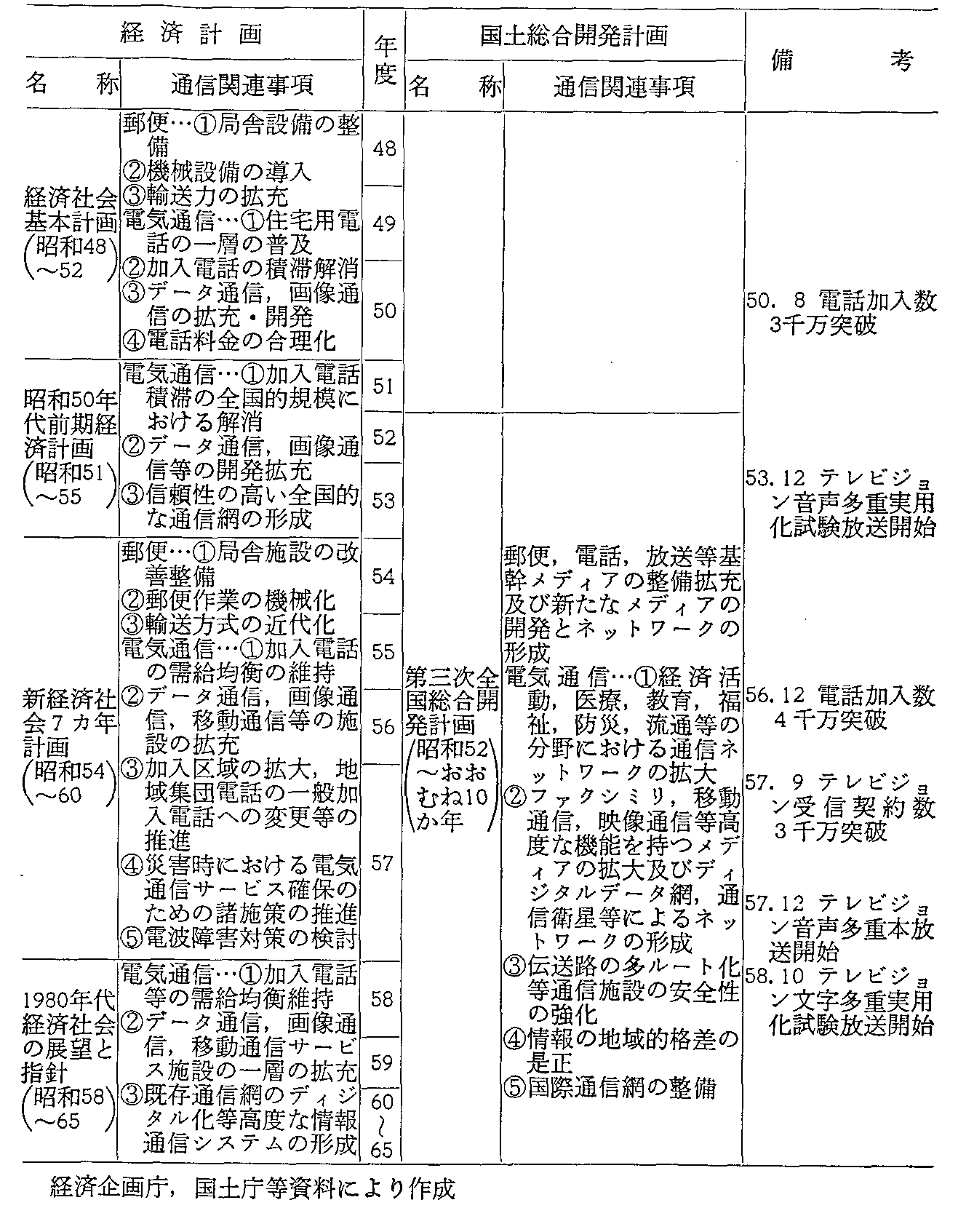
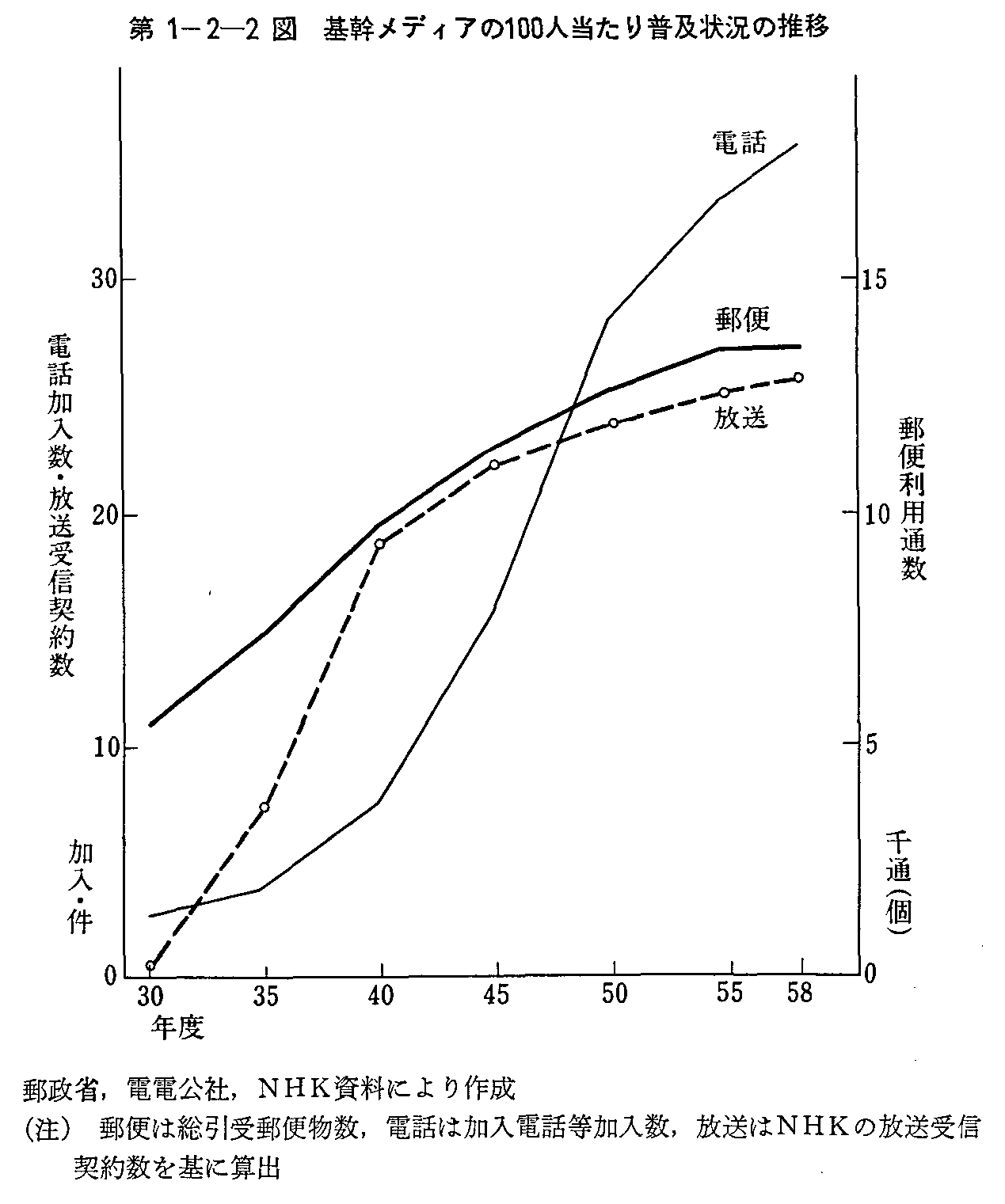
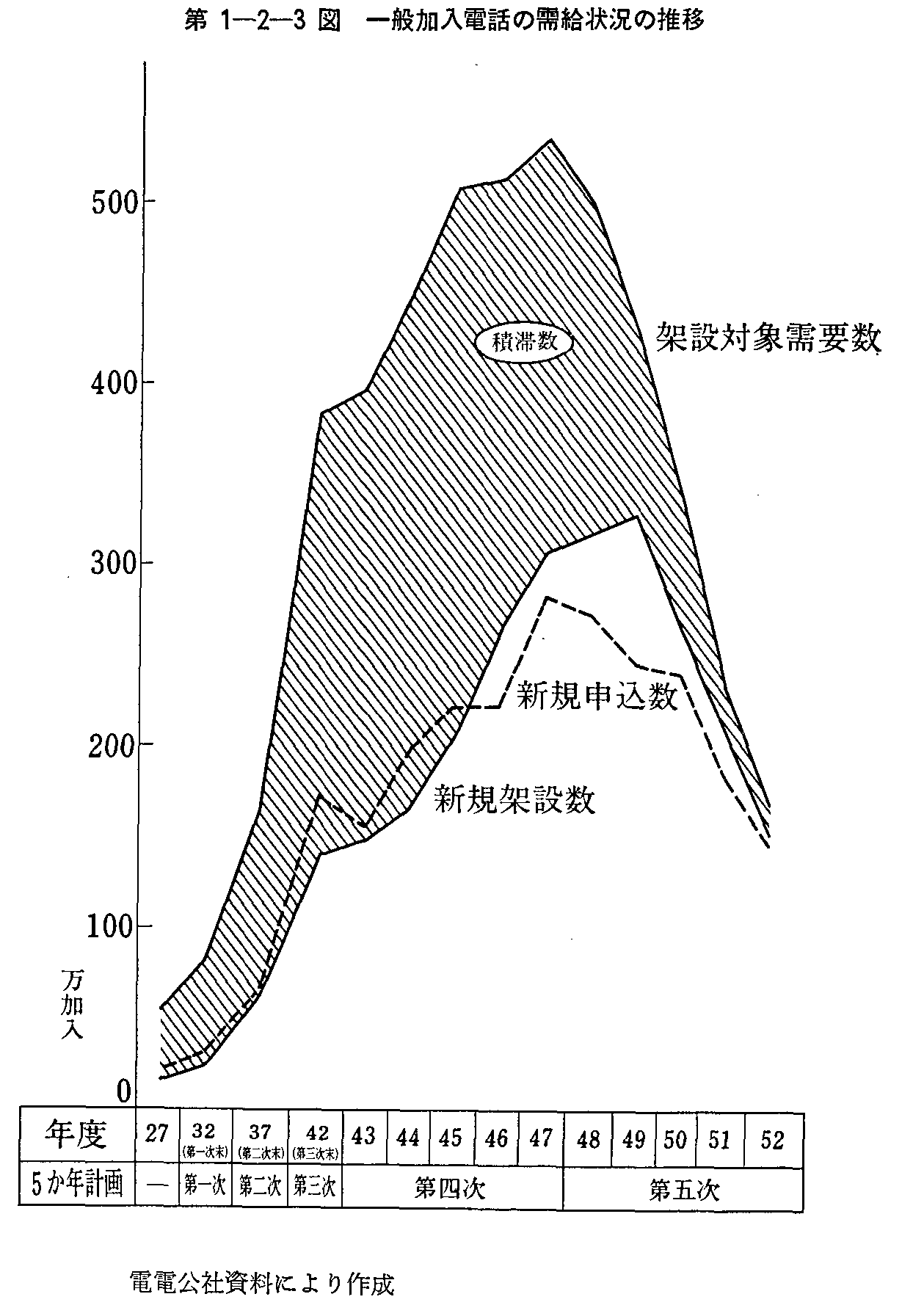
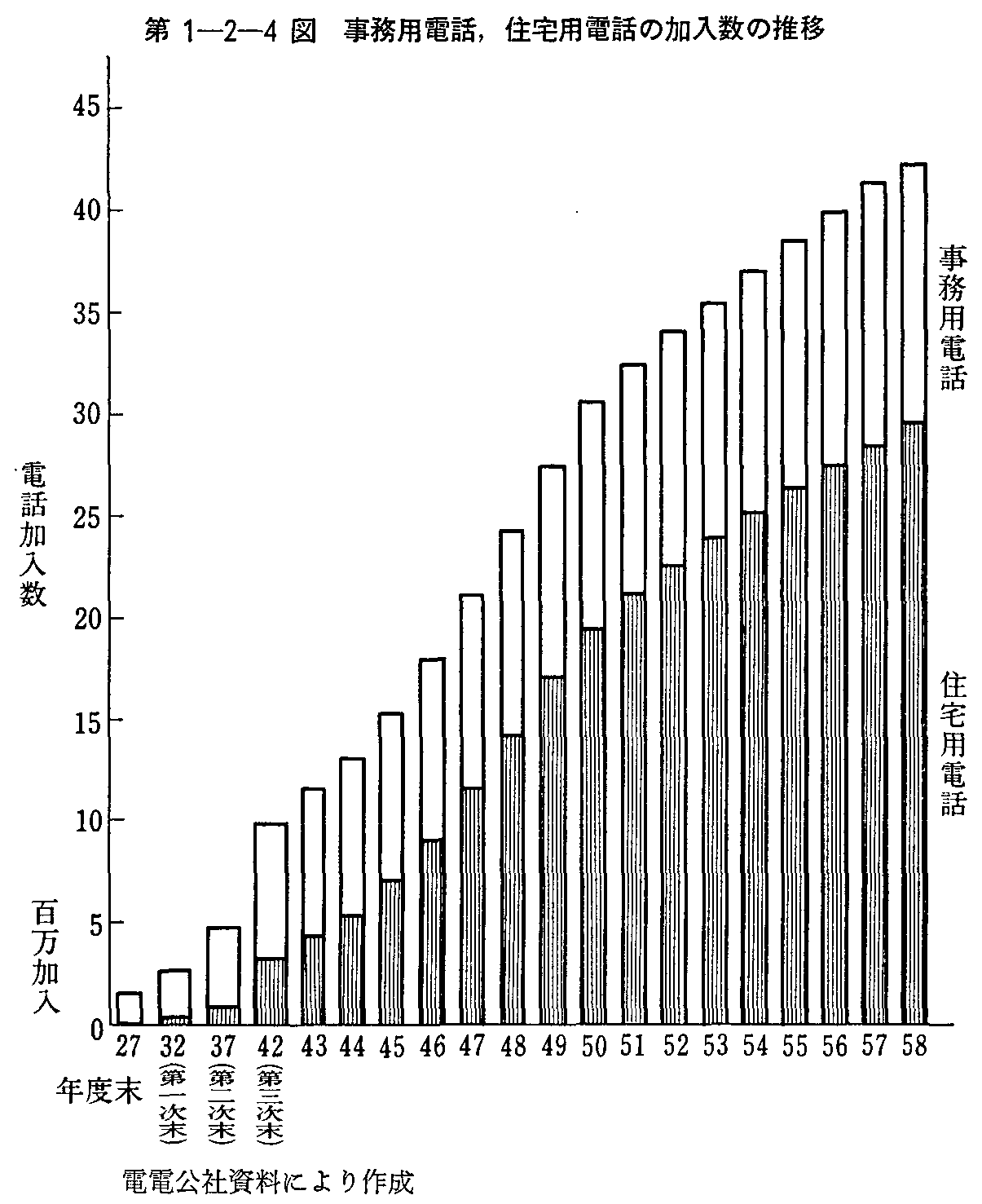
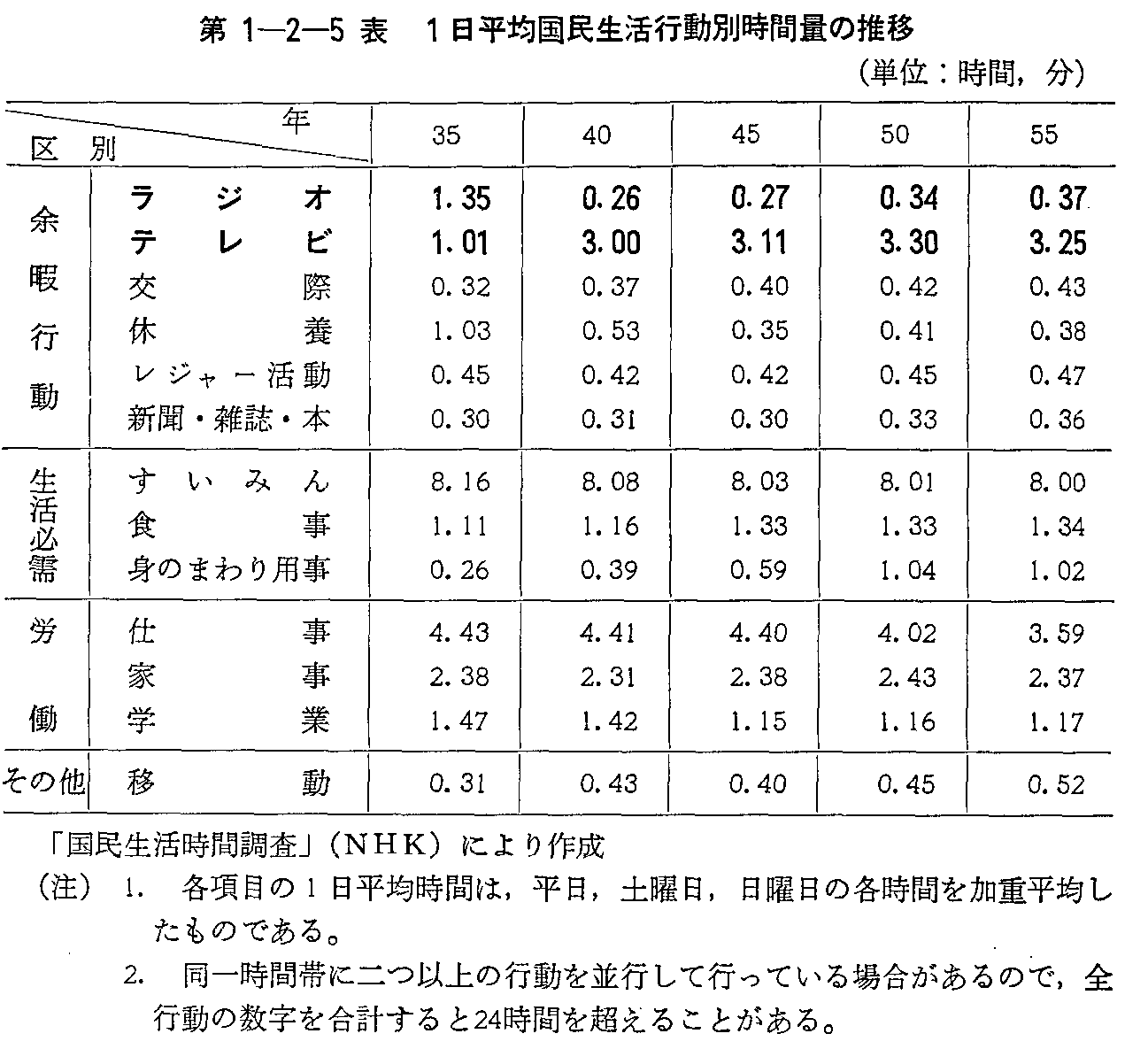
|