 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 情報化の進展と技術革新
郵便,電話,放送といった基幹的な通信メディアは国民生活に深く浸透し,ほぼ成熟段階に達しているが,他方では新しい通信メディアが登場するなど,通信の分野では大きな変化が生じている。ここでは,この背景として,情報化の進展と通信関連技術の急速な発展について概観することとする。
(1)情報化の進展
社会経済の発展や成熟化の中で,国民の意識・価値観が多様化してくるにつれて,あるいは,産業・行政等の分野で資源・エネルギー等の限られた経営資源を効率的に利用する必要性の高まりなどを理由として,社会経済のあらゆる分野で情報に対するニーズが高度化・多様化するとともに,情報の価値や情報への依存度が高まってきている。
ア.産業の情報化
産業の分野において,各企業が生産部門だけでなく事務・管理部門をも含めて業務の合理化・省力化を図るため,あるいは,高度化・多様化する消費者二-ズに対応した商品開発体制を確立するためなどの理由により,情報化についての積極的な取組みがみられる。
企業では生産部門,販売・流通部門あるいは事務・管理部門において,作業・業務等の効率化を図るため,コンピュータ,ワード・プロセッサ,ファクシミリ等の情報処理機器,事務機器等の導入を進めている。また情報を迅速に伝達し処理するため,通信に対するニーズも高度化・多様化しつつ増大しており,このため.各種情報関係機器をシステム化するとともに各部門を結ぶ情報通信のネットワーク化を進めている。
近年では,販売情報を的確に把握し市場開発や商品企画を早期に行い,また,受発注業務の効率化等を図るため,企業内利用を超えて製造業・小売業・運送業等の関連企業間を結ぶ,生産・流通・販売ラインのネットワーク化が進められている。
金融機関では,早くからコンピュータやデータ通信システム等の導入を進めてきたが,近年では,取引先とのネットワークを構築し,残高照会,自動振替等の事務作業の効率化のみならず,情報提供等の付加サービスの提供並びに資金移動取引が行えるエレクトロニック・バンキング化が進んでいる。
産業の分野では,金融業,製造業,運送業等業界を結ぶネットワークや,ホームバンキング,ホームショッピングのような企業と家庭を結ぶネットワークが形成されていき,今後,情報化が一層進展していくものと予想される。
イ.社会の情報化
社会の分野においては,社会の多様な二ーズにこたえ国民福祉の向上に資するため,行政,医療,教育等多くの分野で情報化が進展している。
特に,行政の分野では,住民サービスの向上や住民の安全を確保する観点から,行政情報システム,防災用通信システム,公害監視システム等のデータ通信システムが導入されている。
また,医療の分野では,国民の健康維持に資するため救急医療情報システム,へき地医療情報システム,腎移植情報システム等のデータ通信システムが導入されている。このうち救急医療情報システムは,病院・診療所等の医療機関及び血液センタ等に端末装置を設置し,急病・交通事故あるいは緊急災害等の場合に備えて,診療の可否,空ベッドの有無,手術の可否,血液血清の有無等,救急医療に必要な情報を常時把握するシステムであり(第1-2-6図参照),51年度に神奈川県に導入されたのをはじめ,58年度末現在21府県に導入されている(第1-2-7表参照)。
ウ.家庭の情報化
家庭の分野では,生活の合理化,余暇・生活の充実といったニーズによって情報化が進んでいる。このニーズは,核家族化の進展や女性の社会進出あるいは余暇時間の増大の中で,より強まると考えられる。このため,電話,テレビジョン受像機等の普及に続いて,ホームショッピング,ホームバンキング,ホームセキュリティ等の新しいサービスについても次第に普及し,情報化が更に進展するものと考えられる。
今後,新しいサービスを普及させ,家庭における情報化を進展させるためには,端末機器の購入価格,利用料金の低廉化を図っていくとともに,情報内容・サービス内容を充実させていくことが重要である。また,その利用に当たっても,法制度上の問題(関連法令との調整の必要性)の解決等を図っていく必要がある。
なお,公衆通信網,CATV,放送電波等の通信メディアについて,電話,テレビジョン受像機等の情報通信機器を家庭内で自由に接続できる家庭内情報通信路(ホームバス)の標準化等の検討を進めているが,このホームバスの設備は家庭における情報化の進展に有効な手段となるものと考えられる(第1-2-8図参照)。
(2)通信関連技術の発展
近年,通信関連技術の発展には著しいものがある。第1-2-9表は,通信関連技術の発展についてその変遷をみたものであり,通信ネットワークについてはディジタル技術,その構成要素については光ファイバケーブル,衛星通信,ディジタル交換機等の新しい技術が出現してきている。
通信ネットワークの進展に寄与した技術の基礎となるのは,LSIに代表される素子技術である。コンピュータや通信機器の小型軽量化のみならず,高速化・大容量化・低価格化・高信頼化に大きく貢献するとともに,従来のアナログ技術に代わってディジタル技術を経済的に実現する原動力となった。
ディジタル技術を通信ネットワークに適用する場合の利点は,[1]機器の小型化,低コスト化が期待できる,[2]交換機と伝送路の一体化によりシステム全体の経済化が図れる,[3]雑音や減衰歪の距離による累加がなくなり,通信品質の向上が図れる,[4]冗長度の抑圧,蓄積交換による情報の処理・加工が容易となり,多彩なサービスの提供やサービスの高度化が可能となる,[5]音声,データ,画像等の各種情報を総合的に扱うサービス総合ディジタル網(ISDN)への発展が期待できることである。通信ネットワークを構成する要素の技術についてみると,まず光ファイバケーブル伝送技術は,伝送媒体である光ファイバが有する細径・軽量等の物理的特徴と低損失,広帯域,無誘導,無漏話等の優れた伝送特性を持っている(第1-2-10図参照)。現在,電話換算で5,760チャンネルの回線容量をもつ方式が実用に供されているほか,さらに4倍の容量をもつ方式の開発も進められている。このため,従来の平衡対ケーブルや同軸ケーブルを用いた伝送技術では経済性及び伝送特性の点から発展が妨げられてきた多くの広帯域伝送サービスも,今後発展が可能となる。58年2月及び8月に打ち上げられた実用通信衛星CS-2a,2bにより,我が国も衛星通信の実用化時代を迎えた。衛星通信技術は,従来の地上の伝送技術(同軸ケーブル,マイクロ波)に比して,自然災害に対する高信頼性,サービスエリアの広域性,回線作成の迅速性,回線運用の柔軟性等数々の特長を有しており,その特長を生かした利用形態は広範囲にわたる。CS-2の回線容量は電話換算で約4千チャンネルであるため,衛星の大型化と搭載機器の軽量化・高度化を通して全体のコストダウンと回線容量の大容量化に向けて開発が進められている。ディジタル交換技術は,ディジタル伝送技術と一体となってネットワーク全体の経済化及び通話品質の向上に寄与し,また効率よく回線を使用できる特長を有する。さらに,高速非電話サービスの提供あるいは電話と非電話サービスの同時提供のようなサービス面での利便向上も可能である。
端末機器については,その基本機能である入出力機能,通信機能,データ処理機能が高度化してきており,ソフトウェアによるインテリジェント化が進展している(第1-2-11表参照)。
また,通信ネットワークのディジタル化に伴って,ディジタルデータ交換網,ファクシミリ通信網等のように,ネットワークそのものも通信処理機能等を有し,各種端末機器相互間の接続が可能になってきている(第1-2-12図参照)。
通信関連技術は今後更に発展していくものと予想され,通信メディアの高度化・多様化が一層進展していくものと考えられる。
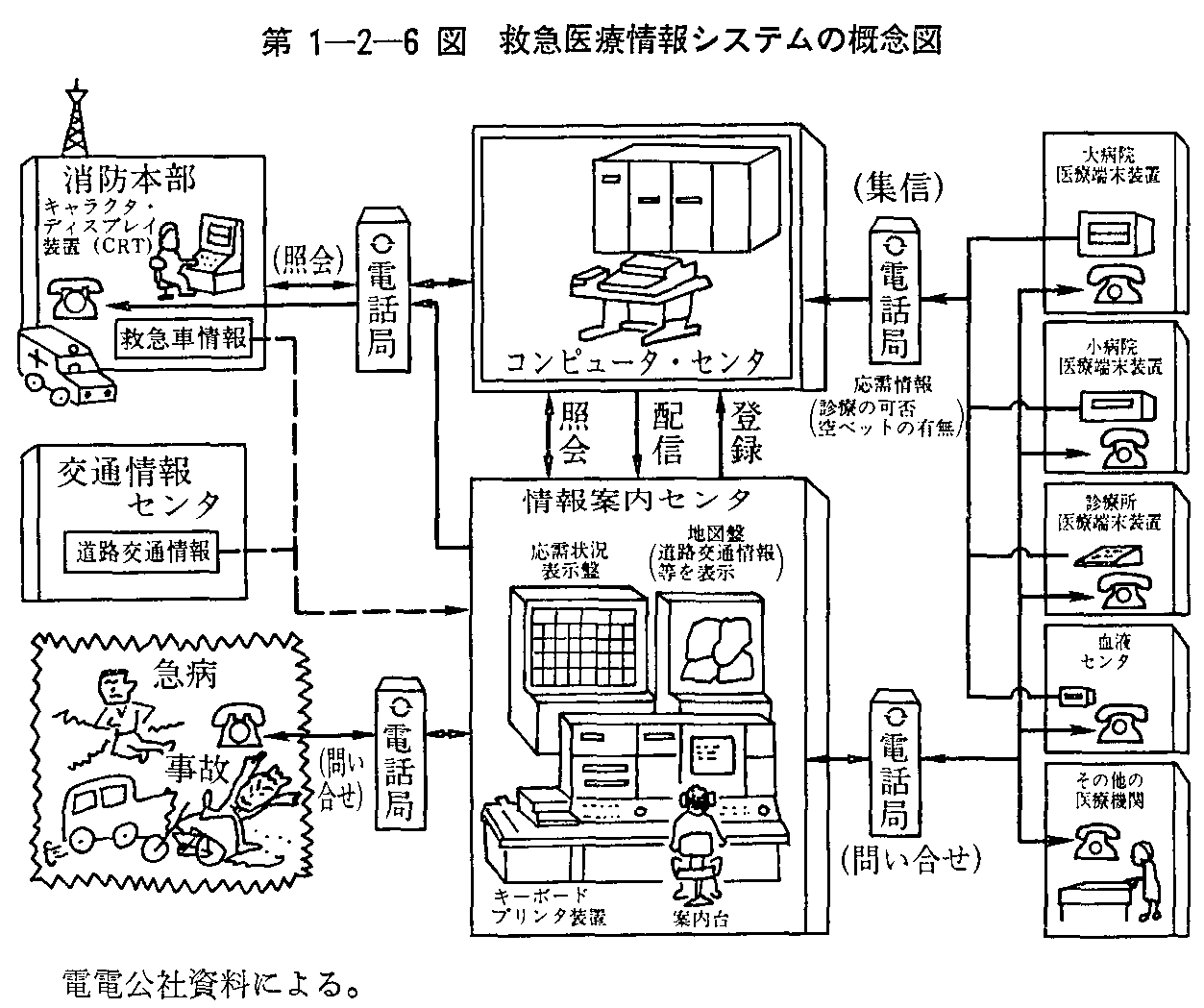
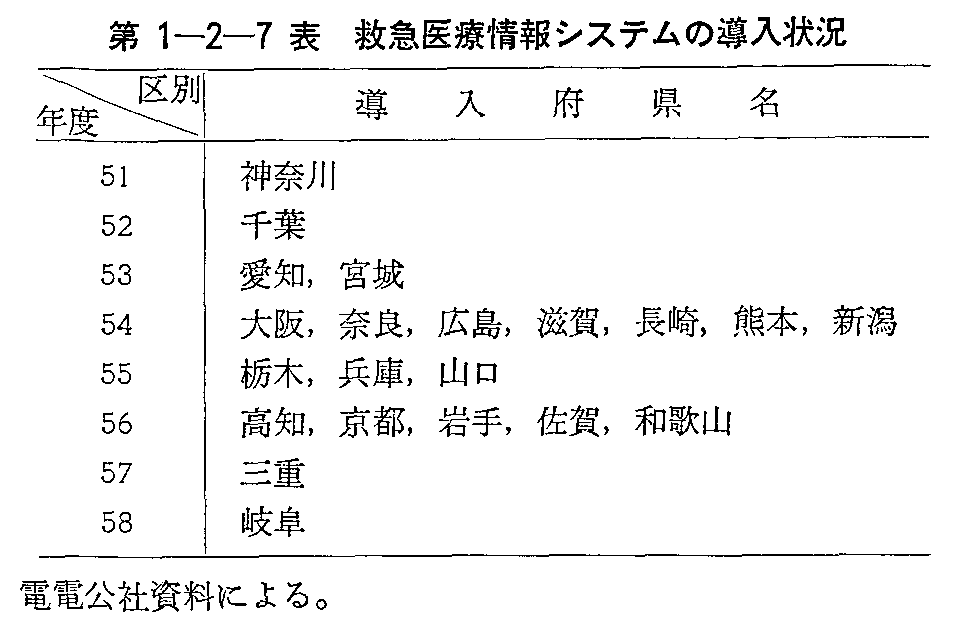
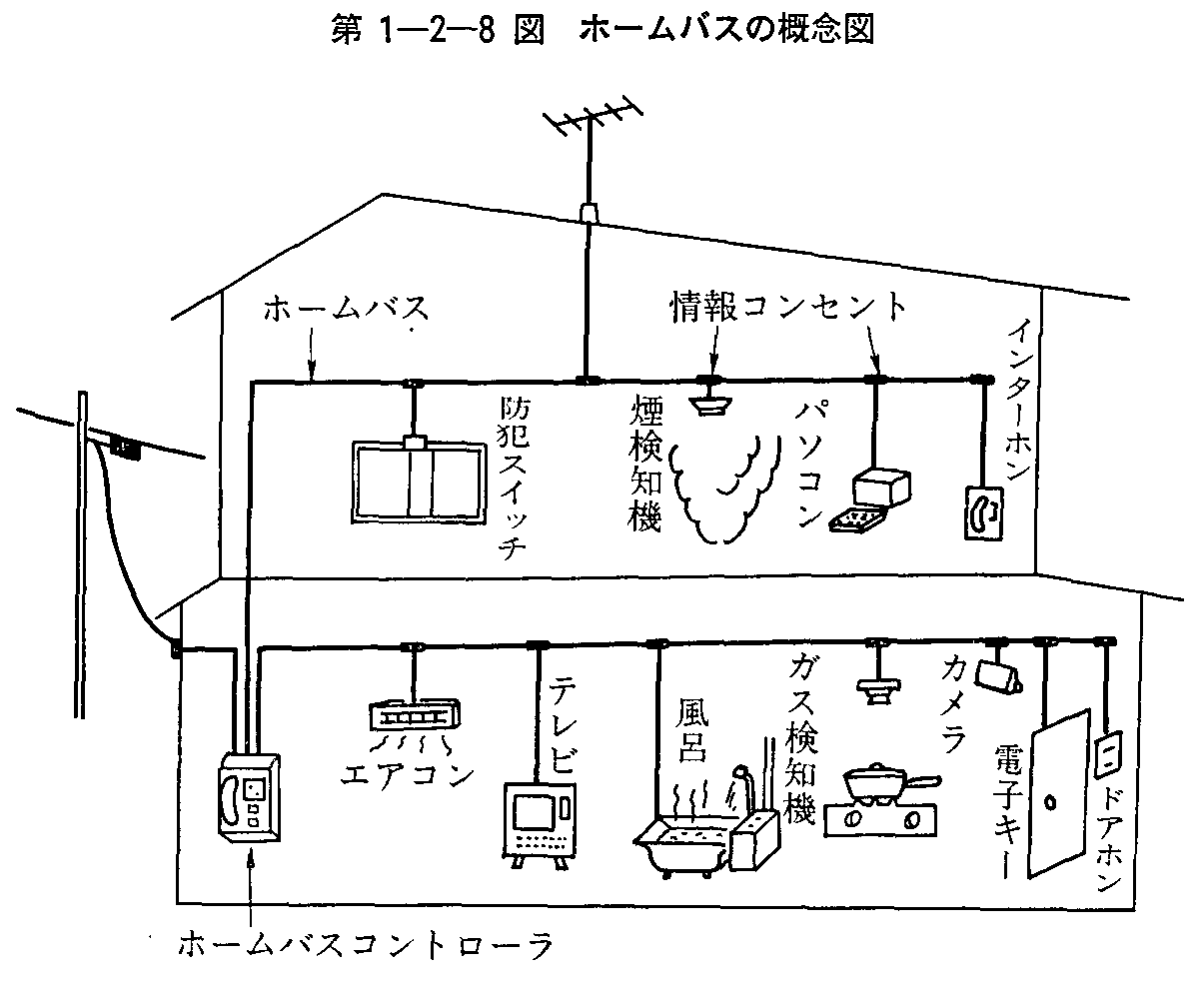
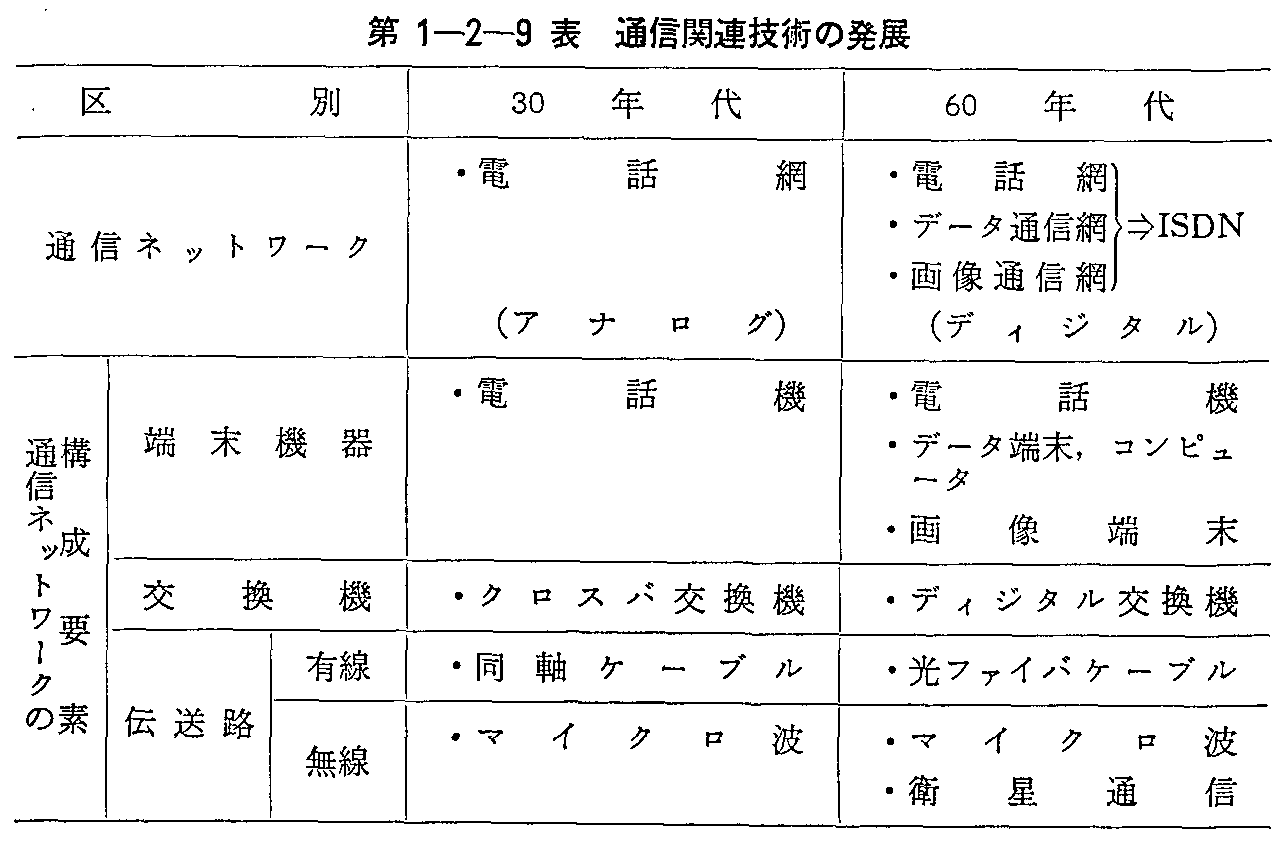
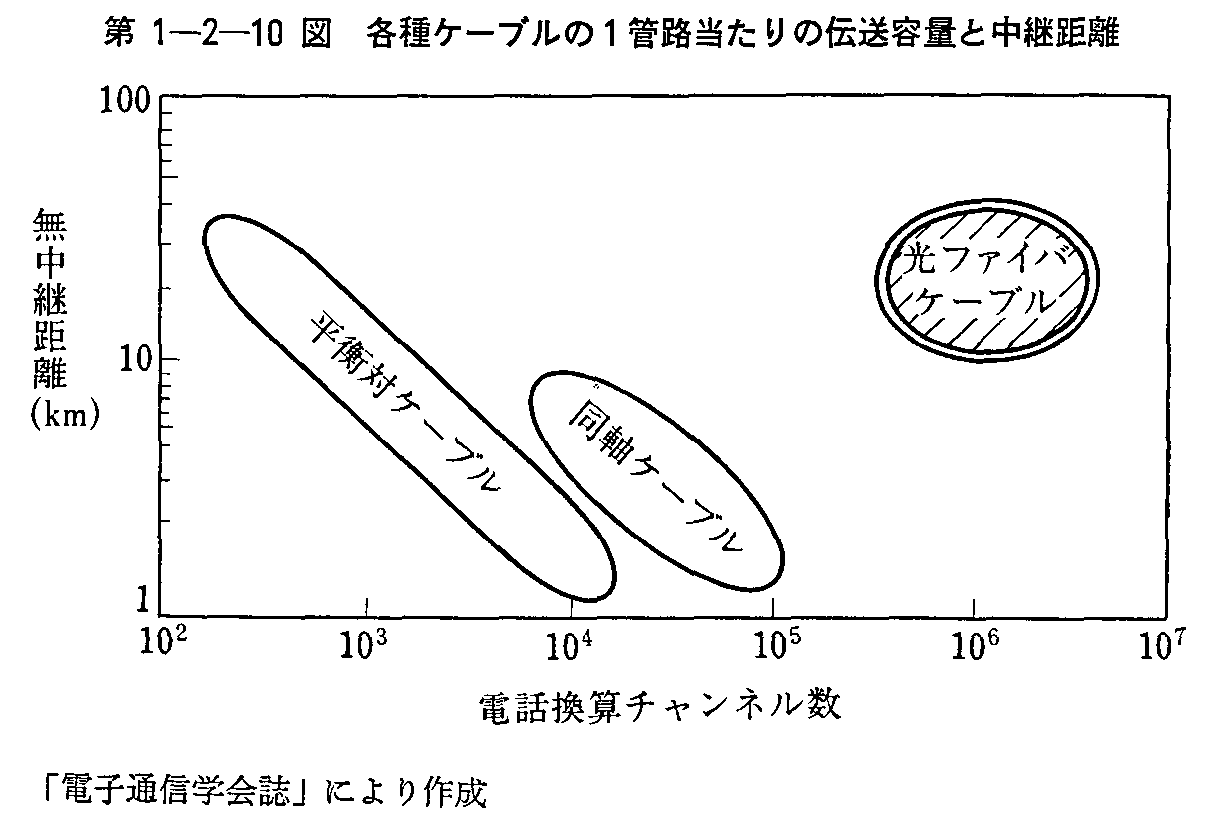
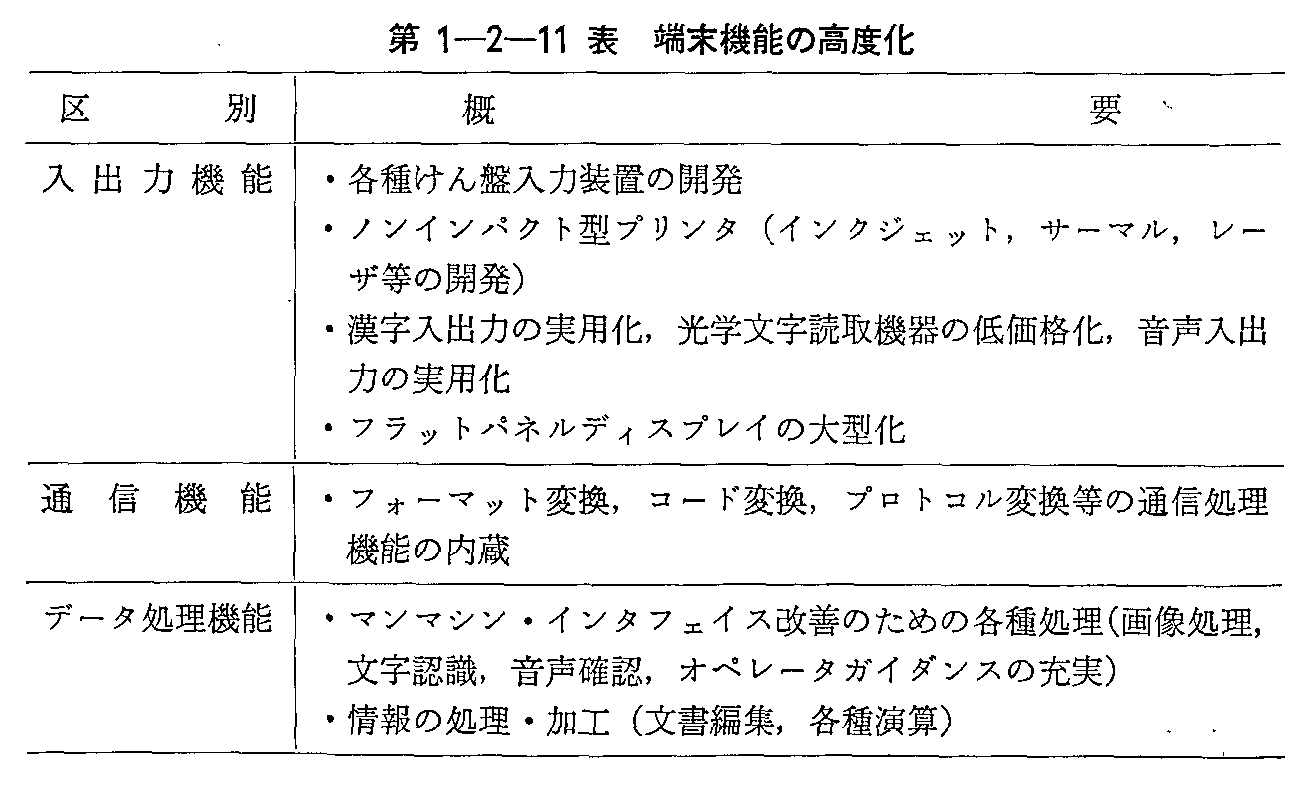
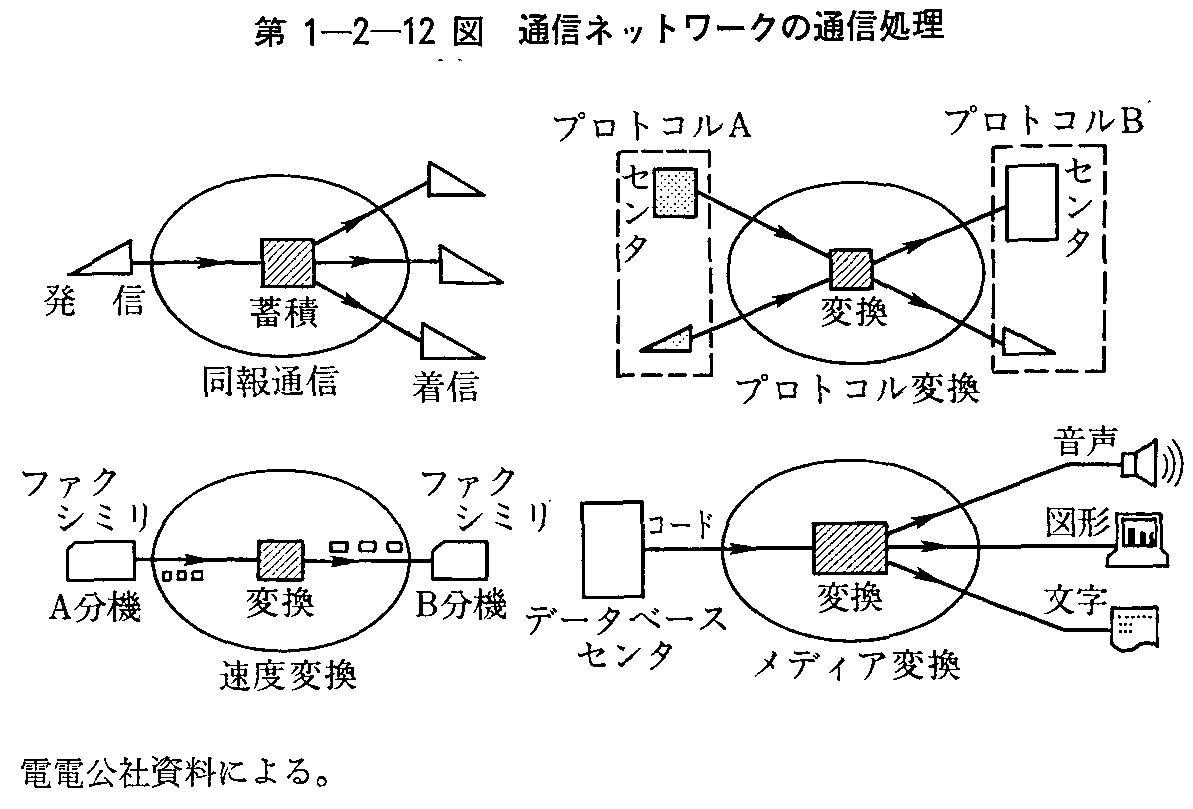
|