 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
3 国際電気通信連合(ITU)
(1) 概 要
ITU(加盟国159か国)は,国際連合の専門機関の一つで,電気通信の分野において広い国際的責任を有する政府間国際機関であり,1865年に万国電信連合として発足した。連合の組織は第2―8―2図のとおりである。
我が国は,1879年にこれに加盟して以来100年余,連合の活動に積極的に参加し,国際協力の実現に貢献してきたが,特に1959年以降は,連合の管理理事会の理事国及び国際周波数登録委員会(IFRB)の委員選出国として連合の運営面においても主要な役割を果たしている。また,連合の本部職員として我が国から5名(1984年3月末現在,IFRB委員を含む。)が派遣されている。
なお,1982年,ケニアのナイロビで採択された新条約は,1984年1月から発効しているが,我が国も批准書を寄託し効力が生じた。
(2) 管理理事会
管理理事会は,全権委員会議によって委任された権限の範囲内で,全権委員会議の代理者として行動し,条約,業務規則,全権委員会議及び連合の他の会議・会合の決定の実施を容易にするための措置を採ることを任務としている。
第38回管理理事会は,1983年5月2日から20日までの19日間,スイスのジュネーヴにおいて開催され,連合の会議・会合計画,連合の予算,人事関係,技術協力等の案件について審議した。1983年度最終予算については,8,594万6千スイス・フランが,また,1984年度予算については,9,363万9千スイス・フランが承認された。
(3) 技術協力
電気通信の分野において,開発途上国に対する技術協力を促進し,提供することは,条約上ITUの目的の一つに掲げられており,電気通信設備や電気通信網の建設及び改善のために実施される技術協力活動は,ITU活動の中で重要な役割を果たしている。
ITUの技術協力活動は,現在その大部分を外部資金に依存している。ITUは,国連開発計画(UNDP)の実施機関の一つとなっており,1982年には,ITUの開発途上国に対する援助総額3,185万9千ドルの82%に相当する電気通信関連プロジェクト(167件)がUNDPから割り当てられた。実施を委託されたプロジェクトは,おおむね[1]アフリカ,アジア,中南米等の各地域における電気通信網の開発の推進,[2]開発途上国における電気通信の管理業務の強化,[3]電気通信関係の人材の育成の3分野に分類することができ,これに対し,専門家の派遣,機材の供与等が行われた。
一方,UNDPによらない技術協力活動としては,国際諮問委員会による技術協力,連合の予算を伴わないテクニカル・アシスタンス・イン・カインドのほかに,近時新たに導入された連合の通常予算による技術協力がある。これは,経費的にはわずかのものである(1982年ITUの通常予算全体の4.1%相当)が,地域事務所の開設,短期専門家の派遣,訓練標準化活動,後発開発途上国への特別援助等極めて広範な活動が展開されている。
また,1982年のナイロビ全権委員会議において,ITUの技術協力に関する運営の在り方が全般的に見直され,技術協力の促進に関する18の決議が採択された。この中には,[1]締約国の主管庁,事業体及びメーカ等からの自発的拠出に基づいて行われる技術協力プログラムである「技術協力のための特別任意プログラム」の創設,[2]電気通信分野の南北格差の是正,均衡のとれた電気通信網の世界的発展を実現するための効率的方法の検討を主たる任務とする「電気通信の世界的発展のための独立国際委員会」(通称メイトランド委員会)の設立等が含まれている。
(4) 国際無線通信諮問委員会(CCIR)
CCIRは,無線通信に関する技術及び運用の問題について研究し,意見を表明することを任務とするITUの常設機関であり,総会及び総会が設ける研究委員会によって運営される。
研究委員会は,現在,全部で13あって(第2―8―3表参照),それぞれの担当分野が決められており,電波天文,電波伝搬等の基礎的な研究から,地上通信,宇宙通信,放送等の実際的な業務に関するものまで広範囲にわたっている。
各研究委員会の審議は,総会から総会までの間に開催される中間会議及び最終会議において行われ,報告書が作成される。
これらの研究の成果として,総会で採択された文書は,勧告等のかたちで発表され,無線通信システムの設計及び実施のための世界的な技術指針となるほか,各種の無線通信主管庁会議の審議の技術的資料として使用されることとなっている。
1983年度における主な会議は,次のとおりであった。
ア.研究委員会中間会議(A1ブロック)
この会議は,1983年8月29日から9月30日まで,スイスのジュネーヴにおいて開催された。このブロックでは,第6(電離媒質内伝搬),第10(放送業務(音声)),第11(放送業務(テレビジョン)),CMTT(音声及びテレビジョンプログラムの長距離伝送)の各研究委員会について行われ,1984年に開催される「放送業務に分配された短波帯の計画作成のための世界無線通信主管庁会議(WARC-HFBC)」に対する報告書を作成した。
また,[1]高精細度テレビジョンの標準化,[2]ディジタルテレビジョンの標準化,[3]テレテキスト,[4]スタジオ用ディジタル音声,[5]ディジタルレコーディング,[6]放送衛星業務用テレビジョンの標準方式についても審議を行い,新しい勧告案を作成した。
イ.研究委員会中間会議(A2ブロック)
この会議は,1983年11月2日から12月7日まで,スイスのジュネーヴにおいて開催された。このブロックでは,第1(スペクトラムの有効利用,監視),第2(宇宙研究及び電波天文業務),第5(非電離媒質内伝搬),第7(標準周波数及び報時信号)の各研究委員会について,[1]宇宙業務のスプリアス発射の許容値,[2]無線スペクトラムの占有度の自動監視,[3]静止衛星からの不要発射による電波天文業務への干渉,[4]放送業務用VHF・UHF帯電波の伝搬特性,[5]移動業務におけるディジタル信号の伝搬特性,[6]衛星による世界的時刻供給等に関し各国から提出された寄与文書262件(我が国からは29件)について審議を行った。
(5) 国際電信電話諮問委員会(CCITT)
CCITTは,無線通信に関する技術及び運用の問題を除く電気通信業務の技術,運用及び料金の問題について研究し,意見を表明することを任務とするITUの常設機関の一つであり,CCIRと同様の方法で運営されている。
CCITTにおける研究活動の中心的役割を担う研究委員会(SG)は全部で15あり,その他,開発途上国向けハンドブックの作成にあたる特別自主作業部会(GAS),電気通信網の在り方を研究する世界及び各地域プラン委員会等がある(第2-8-4表参照)。1981年〜1984年研究会期の活動成果は,各SGごとに勧告案,報告書として取りまとめられ,1984年秋にスペインで開催される第8回総会の場で,SGの再編成,来会期研究課題のリストの作成と並んで審議,承認される。
総会で承認されたCCITT勧告は,電気通信技術の標準化,業務の国際的運用上欠くことのできない指針となる。
今日,研究委員会の活動領域は,電話の伝送・交換という伝統的な研究分野からファクシミリ,テレテックス,ビデオテックス等のテレマティーク・サービス,ISDN(サービス総合ディジタル網)に関する先端技術分野,高級プログラミング言語等の新しい研究分野に至るまで極めて広範囲なものとなっている。
1983年度ジュネーヴで開催された主な会議として,1983年4月のSGII中間会合において,電話網の運用,管理,トラヒック理論の研究が行われ,同年12月のSGI第3回全体会合では,欧米を中心に普及拡大の要請の高いテレテックスとテレックス間の相互通信,ファクシミリ蓄積サービス等の新しい国際間通信サービスの運用方法の勧告化が検討された。
また,技術面では,SG<10><8>第3回全体会合が同年6月に開催され,ISDNの網構成,サービス概念の整理が行われ,翌1984年3月のSGVIII最終会合においては,G4ファクシミリ,テレテックス端末の技術的特性の研究に大きな進展がみられた。
さらに,1983年7月11日から15日まで,郵政省招請のもとに「ビデオテックス国際標準化東京会合」が開催され,世界の約20か国で開発実用化が進められているビデオテックスの方式(画像情報の符号体系等に関する通信規約)を国際的に標準化するための勧告の具体化について,CCITTの専門家の間で話合いが行われ,日本のキャプテン,欧州のCEPT及び北米のNAPLPSの3方式を共に国際標準とすることで基本的合意が得られた。
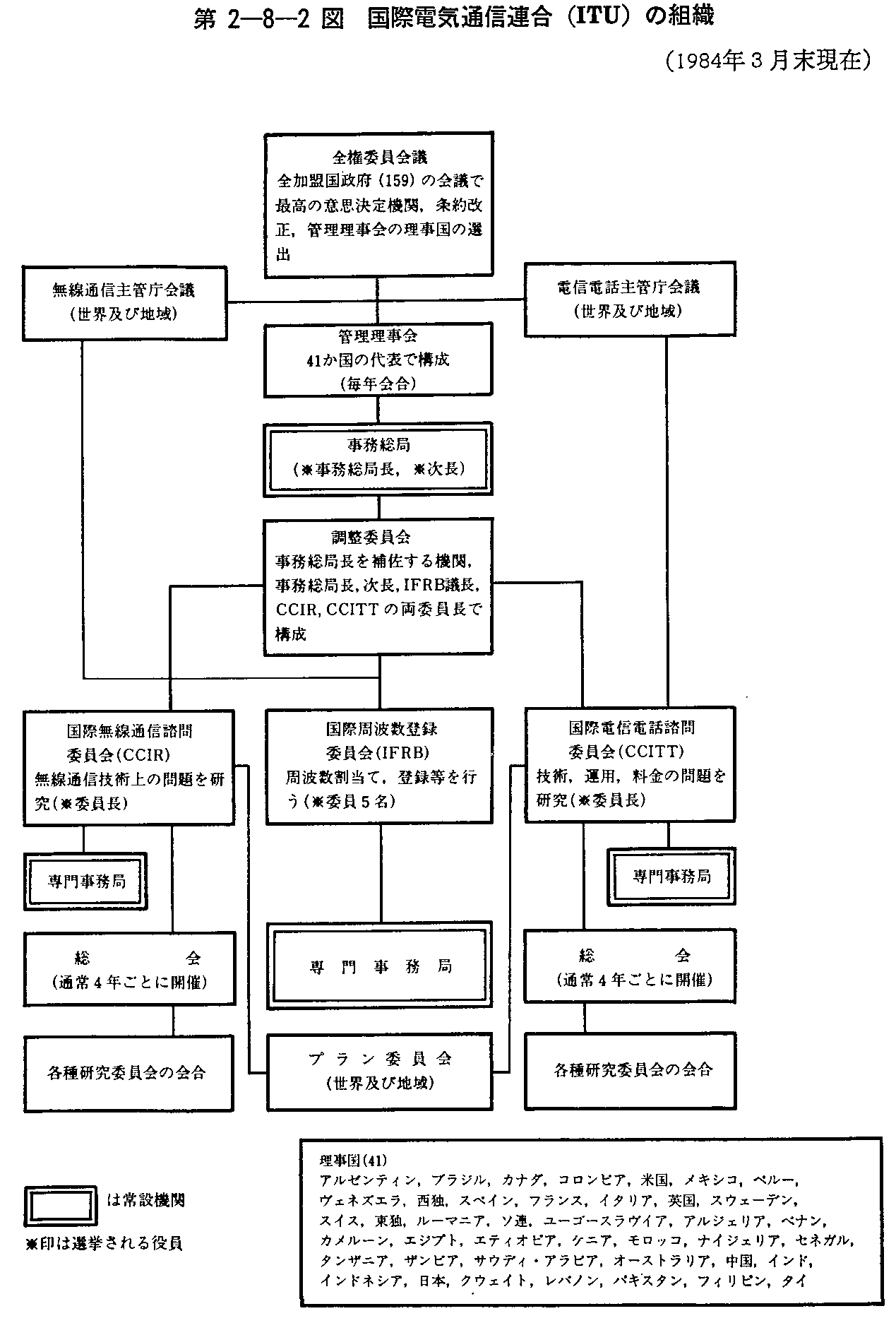
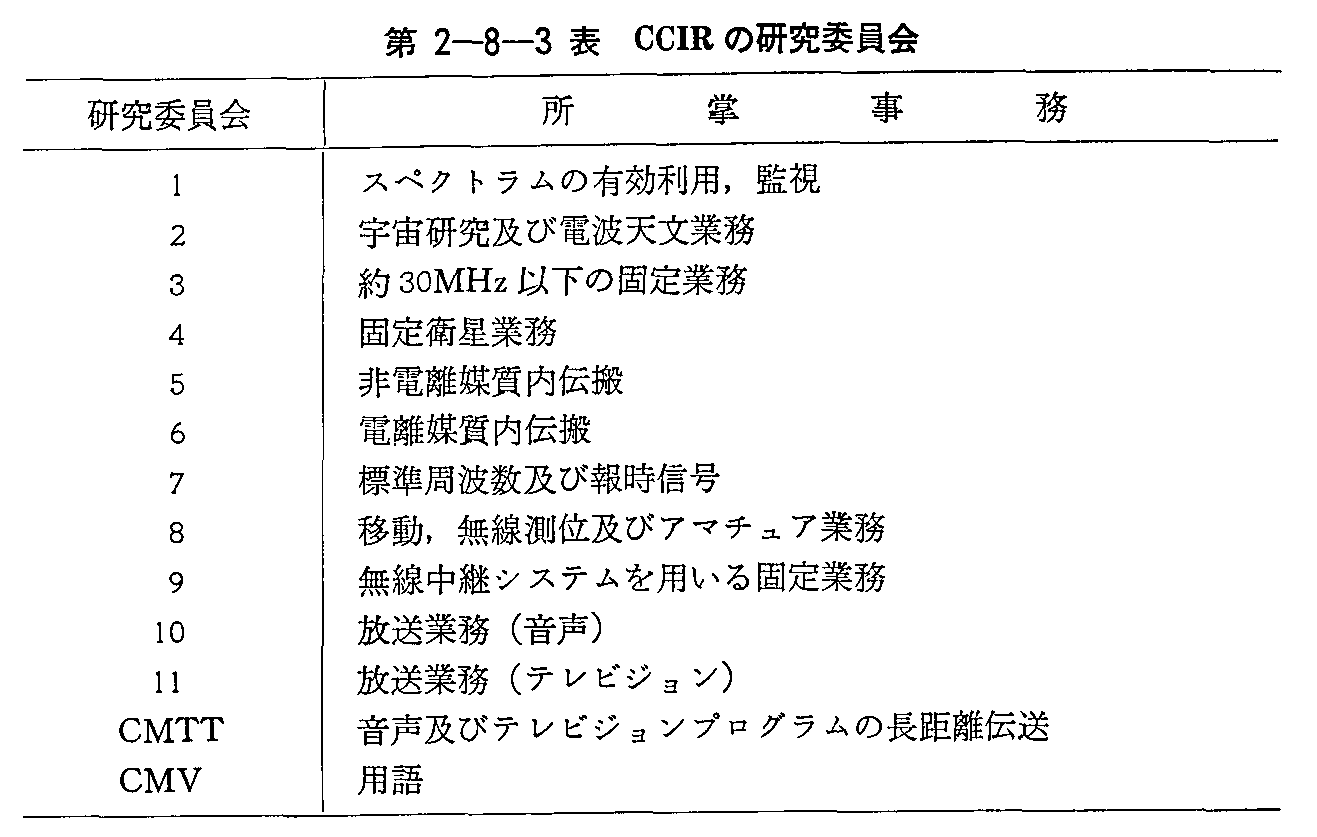
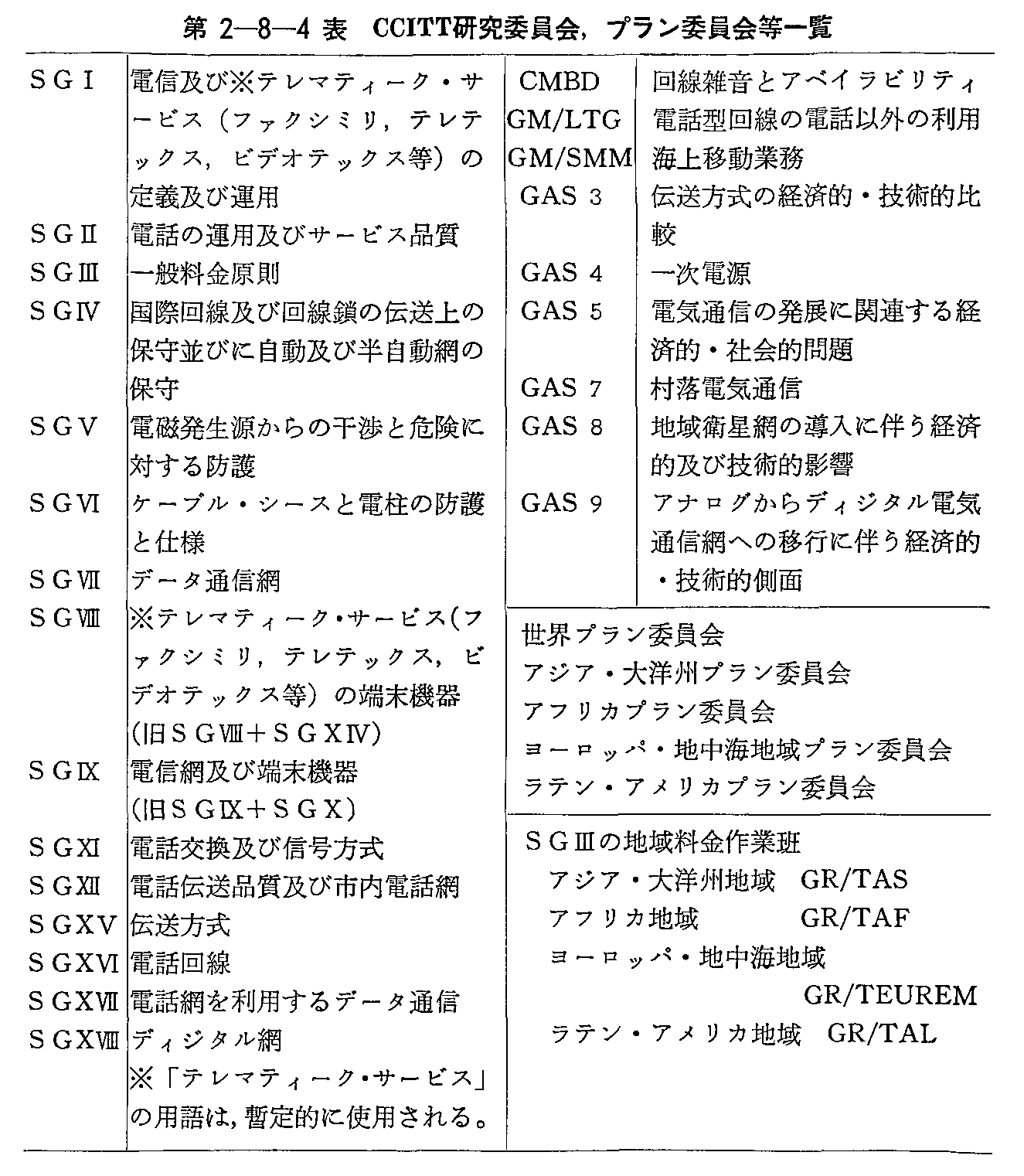
|