 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 多元的構造への展開
(1)多元的構造への要請と競争原理の導入
ア.多元的構造への要請
これまで,電気通信事業では,戦争によって荒廃した電気通信設備を速やかに復興し,一日も早く,加入電話の積滞を解消するとともに全国自動即時化を実現することが,最も重要な課題であり,国民・利用者の希求するところでもあった。このため,電電公社は,6次にわたる長期拡充計画を策定し,鋭意電気通信ネットワークの整備拡充に努め,この二大目標の達成を実現した。
今日,我が国は,情報化の著しい進展の中で,高度情報社会への転換期を迎えようとしている。電気通信は,あらゆる人が必要な情報を容易に入手し,利用し,伝え合うことができる多層的なトータルネットワークの構築を通じて,豊かな国民生活の実現,産業経済の活性化及び地域社会の自立的発展を達成するため,社会先導的な役割を果たすことが期待されている。
また,近年,電気通信技術の著しい発展に伴い,新しい通信メディアが次々と実用化されるとともに,インタフェイス技術の進歩により複数の電気通信ネットワークの併存が可能となっている。電気通信に対するニーズは,加入電話の需要が充足されるにつれて次第に高度化・多様化してきている。今や,多彩なサービスを利用者が幅広く選択できるようにすることが,利用者の利益を増進するものと考えられるに至っている。
このような技術の進展,ニーズの多様化等電気通信をめぐる諸情勢の変化の中で,利用者利益を確保し,また,電気通信に対する社会の期待にこたえていくためには,サービスの提供主体を多元化して,利用者二ーズに応じた多彩なサービスを各事業者が創意と工夫をもって提供できるようにするとともに,電気通信事業分野に競争原理を導入し,電気通信事業の一層の活性化,効率化を促し,事業を一層発展させていく必要がある。電気通信事業を長い歴史をもつ独占体制から転換し,これに代わる競争原理を導入した新しい時代を構築していくことが,高度情報社会の形成に向けて我が国の発展を図るために必要不可欠なものとなっている。
イ.競争原理の導入
電気通信事業分野に競争原理を導入し,国民・利用者の利益の増進に資するためには,新規参入を単に制度的に可能とするだけでは不十分であり,競争原理が十分機能する事業環境を整備していくことが必要である。
このため,まず,新規参入が実質的に実現するための施策が必要である。既存事業者が享有している優遇措置(土地利用特権や周波数の優先的利用)を新規参入事業者にも及ぼすことや,既存事業体が保有する経営・技術情報を適切な条件のもとに開示するなど電気通信事業者相互間のイコール・フッティングを確保する必要がある。
また,そのほかに,有効かつ公正な競争条件を確保するため,次のような点について十分配意する必要がある。
第1に,電気通信ネットワークの相互接続の確保であり,新規参入事業者のネットワークが既存事業者のネットワークに適正な条件の下で接続できるようにする必要がある。
第2に,内部相互補助の抑制であり,既存事業体がその市場支配力を背景に競争制限的な内部相互補助を行うことのないようにしていく必要がある。
第3に,既存事業体の業務範囲の見直しである。電気通信サービスには,電信電話やデータ通信,端末機器提供サービスまで多種多様なものが含まれており,競争の進展度合等を考慮した上で業務分離を行うことも,公正な競争を確保する上で有効な手段であると考えられる。
第4に,適正な料金政策である。料金問題はこれまでにも遠近格差の是正等利用者の立場からの指摘がなされているが,新たに,有効な競争を確保する見地からも,技術の発展動向を踏まえた料金政策の在り方について検討する必要がある。
(2)諸外国の動き
我が国においては,高度化・多様化する情報ニーズと技術開発の進展により,衛星通信,衛星放送,キャプテンシステム,VAN等の様々な新しいメディアが登場するに伴い,電気通信事業分野に競争原理を導入しようとする動きなどがみられ,大きな変革の時代を迎えようとしている。
こうした電気通信の自由化の動きは,諸外国の中で,特に,米国と英国において顕著になってきている。
ア.米 国
米国では,1934年に通信法が制定され,規制機関として連邦通信委員会(FCC)が設立された。公衆の利益の確保と保護を目的とするFCCは,当初,その目的達成手段として,いわゆる規制下の独占政策をとっていたが,その後,競争を可能とする需要の増大と技術開発の進展,並びにこれらを背景とした電気通信事業分野への新規参入意欲の高まりを受けて,端末機器分野における自由化,回線分野における新規参入の許可といった競争導入・促進政策を展開し始めた(第1-2-39表参照)。
アメリカ電信電話会社(AT&T)が独占的なシェアを占めていた電話サービス分野に競争原理が導入される契機となった,1969年のマイクロウェーブ・コミュニケーションズ社(MCI)にかかる裁定において,
FCCは,競争を導入すべきと判断した理由として以下の点を挙げている。[1]特殊通信事業者の参入により,増大かつ変容する需要を最も満足させるような,幅広い選択と柔軟性を利用者に与えることができる。[2]通信サービスに対する多様な需要が生じており,そのすべてを効率的,経済的かつ迅速に満たすには巨大な資本が必要であり,AT&Tのみではその責任を遂行するのは困難であり,新規参入によりその責任が分散でき,現在又は将来の需要に応ずることができる。[3]競争導入により,合理的料金で適切かつ効率的サービスを提供するための有効な調整が図られる。
このような政策の下,MCI等の特殊通信事業者,USテレホン社等の再販売通信事業者,サテライト・ビジネス・システムズ社(SBS)等の衛星通信事業者らの参入が相次ぎ,利用者はどの会社の長距離通信網に加入するか自由に選択できる状況となった。しかし,AT&T以外の会社を利用する場合,余分に11ケタのダイヤルを要するなど各社の競争は平等な条件下におかれたものではなかった。こうした中で,AT&Tに対し反トラスト訴訟を起こしていた司法省とAT&Tの間に,1982年,和解が成立し,新しい同意審決が発効した。この同意審決により,[1]AT&Tは,データ処理・通信及び宅内機器販売分野への参入の道を開いた一方で,[2]AT&Tは,22のベル系電話運用会社(BOCs)を分離し,[3]新たに独立して市内通話サービスを提供することとなったBOCsは,1986年9月までに,市内アクセスを望むすべての長距離通信事業者に同一の条件(料金,形態,品質等)で,BOCsの回線を利用させることとなった。
1984年1月,AT&Tは,22のBOCsを分離し,長距離及び国際通信を提供するAT&Tコミュニケーションズと,通信・情報機器の研究開発,製造販売を行うAT&Tテクノロジーズに組織を再編成した。今後,長距離分野では,接続条件等の同一化が進むにつれ,先に述べたような利用者の不便が解消され,また市内分野では,過渡的現象としての値上げ等はあるものの,独立採算制によることとなった各社の合理化・効率化といった経営努力が進められ,利用者の利益は増大して行くものと考えられている。
イ.英 国
英国の電気通信は,1969年以来,英国郵便・電気通信公社(BPO)によって独占的に運営されてきたが,保守党政権の電気通信自由化政策により,BPOの郵便事業と電気通信事業の分離,端末機器の自由化等を内容とする英国電気通信公社(BT)法が成立し,自由化への第1段階を迎えた(第1-2-40表参照)。
1981年7月に成立したBT法では,従来と同様にBTに対して電気通信システム運営の独占権が与えられているが,電気通信システムの運営等の免許は,BTのほか新たに産業大臣も付与することができ,これらが付与する免許に基づく運営はBTの独占権の侵害とはならないとなっており,実質的にはBT以外の通信事業者の参入が可能となった。
これにより,1982年2月,BTと競合する独自の電気通信網の設置,運用を申請していたマーキュリー(発足当初,ケーブル・アンド・ワイヤレス社(C&W),ブリティッシュ・ペトロリアム社(BP),バークレイ銀行によるコンソーシアム(共同企業体)であったが,1984年5月,8月と続けてバークレイ銀行,BPが撤退した。)に免許が付与され,また,1982年10月から,付加価値通信事業者に一般免許が付与された。こうした電気通信分野の自由化に対応して,BTは料金体系の見直し,ディジタル通信サービスの拡充等に努めている。
また,経済,産業の活性化を図るため,広範囲な分野にわたって国営企業の民営化に取り組んでいる保守党政権は,電気通信分野においても,電気通信自由化の第2段階ともいえるBTの民営化を目指し,1982年7月,産業大臣は,英国議会において「英国の電気通信の将来」という声明でBT民営化の方針を発表した。この声明の中では,より安定した料金,よりよい効率,より高品質なサービスというものは消費者の選択と市場における試練を通じて達成し得るものであるという,BT民営化に当たっての考え方を明らかにしている。
その後,1984年4月に新たな電気通信秩序の形成を主目的とした1984年電気通信法が制定された。同法では,BTの独占権を廃止し,規制機関として電気通信庁(OFTEL)長官を設置し,電気通信システムを運営するものは,大臣又は長官が交付する免許を受けなければならなくなり,BTは電気通信システム運営者の一つとして位置付けられることになった。
また,この法案が審議されていた1983年11月の下院通信委員会において,政府は今後7年間,新たな公衆電気通信事業者をマーキーリー以外認めることはないとの方針を明らかにした。これは,新たな電気通信網の建設には巨額な投資とこれらの投資から収益を得るまでにはかなり長い期間が必要とされ,ケーブルの敷設あるいは無線周波数の割当てに関し,諸制約があるためとしている。
なお,BTの承継会社である英国電気通信会社(British Telecommunicationsplc)へのBTの権利債務の譲渡に関する規定は,1984年8月6日に施行された。
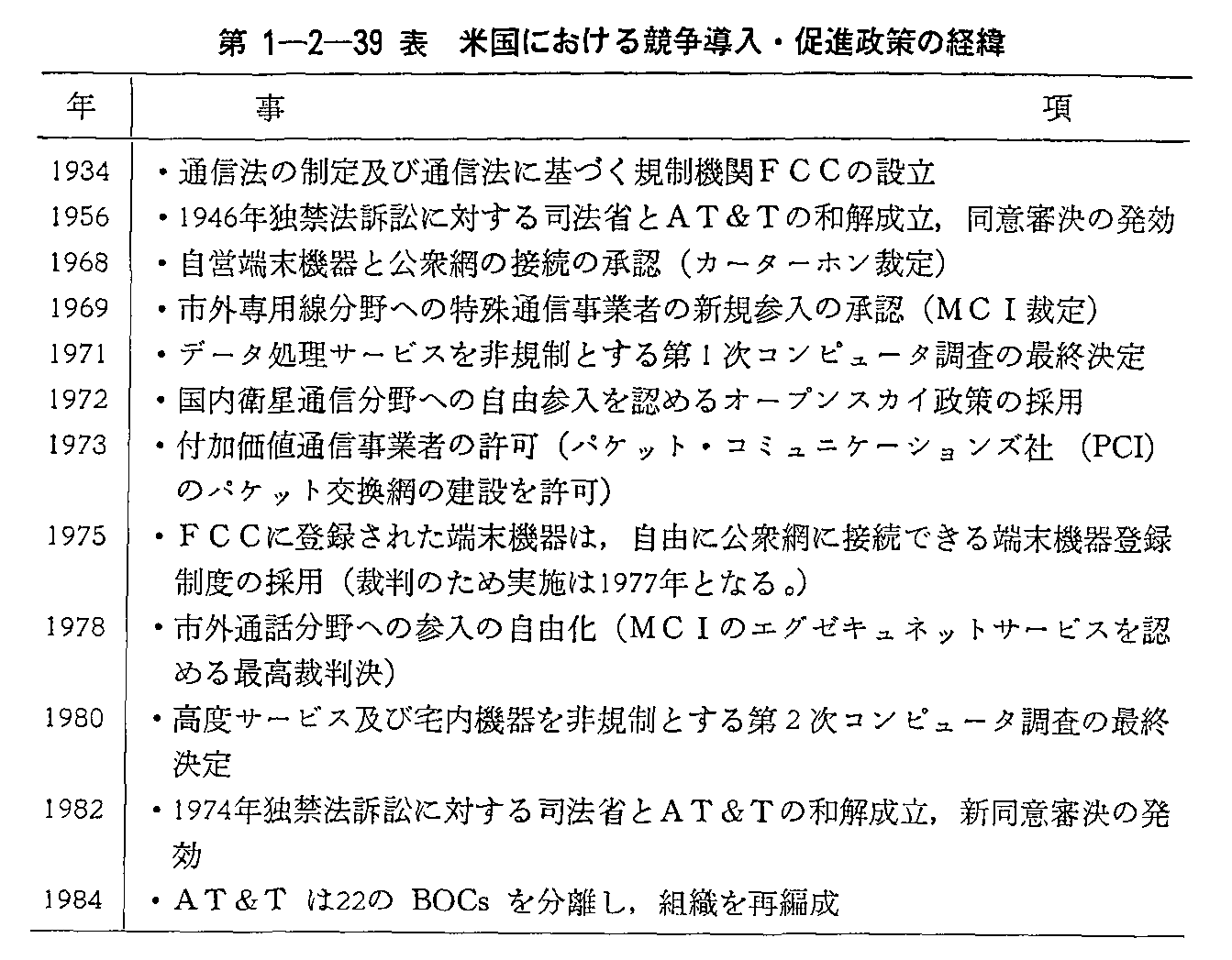
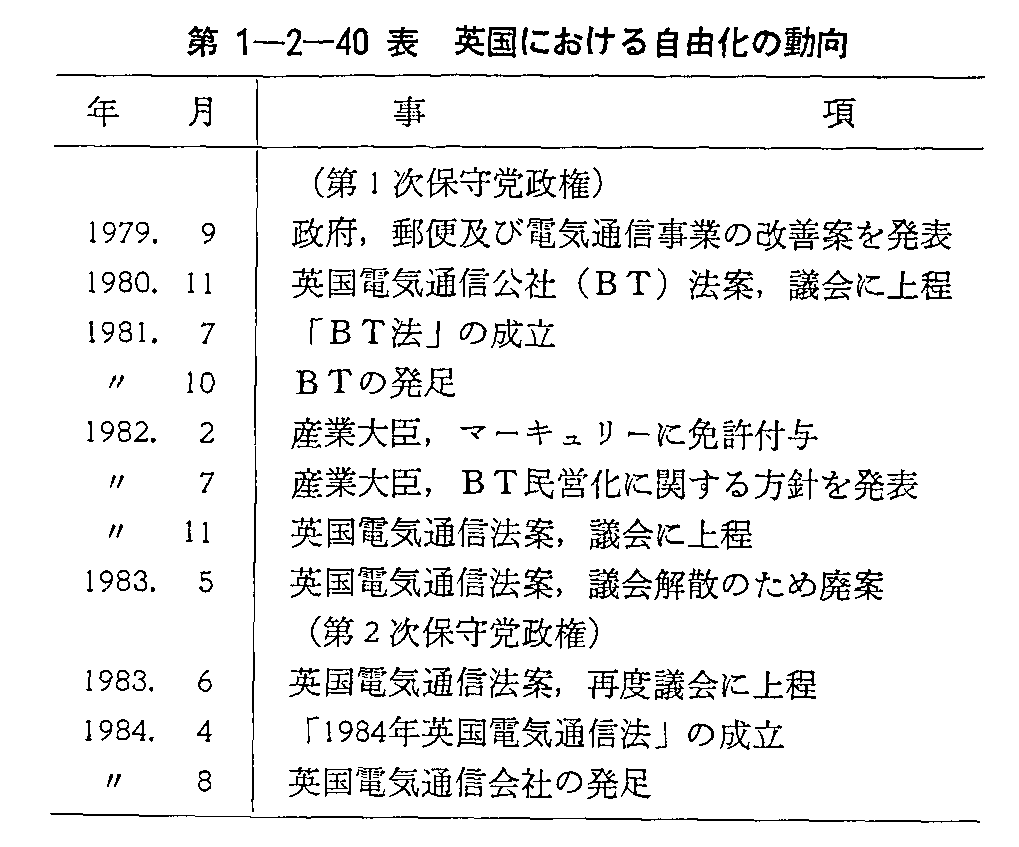
|