 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 多様化する画像通信
(1)ファクシミリ通信
ア.ファクシミリ通信の概要
ファクシミリ通信は,任意の文字,図形,写真等を,簡易な操作でそのまま伝送できる記録通信であり,漢字を使用する我が国の国民生活に適したメディアとして,広く国民生活に普及するとともに,その利用分野は非常に広範囲となっている。
我が国のファクシミリ通信は,46年の公衆電気通信法の改正により,電話網が音声以外にも使用できることとなったため,47年以降,電話網利用ファクシミリを中心に普及発展してきた。ファクシミリの設置個数は,58年度末現在,電話網を利用したものだけでも48万7千個となっている。
イ.ファクシミリ通信の現状と動向
電話網を利用したファクシミリの設置個数の推移を機種別にみると,第1-2-18図のとおりであり,主力機がG1機(低速機)からG2機(中速機),G2機からG3機(高速機)へと移行していることがわかる。
また,利用層の業種別にみたファクシミリの設置個数の推移は,第1-2-19図のとおりであり,47年の調査では,全体の12.8%を占めるにすぎなかった金融・製造業・商社が,57年には53.1%と過半数を占めるに至っている。
ファクシミリ通信が,このように急速に普及発展した背景としては,ファクシミリの持つ記録性,正確性,迅速性等の優れた特性のほかに,次のことが挙げられる。
まず第1に技術開発がある。近年の目覚ましい技術開発により,機器の低廉化,インテリジェント化が急速に進展した。今後も,後に述べるファクシミリ通信網サービスにおいて,網が提供し得る機能では自らのニーズを満足させられない利用者の存在を背景に,機器のインテリジェント化は一層進められることとなろう。
第2に,通信方式の標準化がある。同一企業内での利用にとどまらず,企業間,不特定多数間におけるファクシミリ通信の必要性が増大し,異機種ファクシミリ相互間の通信を可能とするため,通信方式の標準化が進められてきた。国際的には,国際電信電話諮問委員会(CCITT)において,G1機は1968年,G2機は1976年,G3機は1980年に,それぞれ標準方式についての勧告が採択されており,また,国内においても,郵政省が中心となり,国際標準化動向を考慮しながら,国内の標準通信方式をとりまとめ,推奨通信方式として告示している。
第3に,新たにファクシミリ専用のファクシミリ通信網サービスが提供されたことがある。56年9月に開始された同サービスは,[1]長距離伝送路にディジタル伝送方式を採用し,[2]さらに蓄積交換方式を用いることにより,長距離通信のコストダウン,通信料の遠近格差の是正,ページ単位課金,発信者電話番号等の自動記載,再呼,不達通知,短縮ダイヤル,無鳴動着信等の多彩なサービスの提供を可能にし,利用者の便益を向上させた。
なお,58年度末現在,同サービスは,東京,大阪等21都市において提供され,利用者は9,551加入となっている。また,同時に販売が開始されたミニファクスは機能を簡易化し,低廉・小型軽量・操作容易な端末として,個人事務所・商店等の新たな需要層を開拓しており,58年度末現在,電話網利用のファクシミリ設置個数の14.0%を占めている。
ウ.ファクシミリ通信の新たな展開
ファクシミリが,広く国民生活の各領域に普及するにつれ,ファクシミリの持つ有用性に対する認識は更に身近なものとなってきている。しかし,同時にその認識は,従来のファクシミリに対するニーズをより高度化・多様化するものでもある。具体的には,[1]一層の高速化,[2]低廉化,[3]通信相手の拡大,[4]中間調,カラーを含めた画質の向上,[5]付加機能の拡充,[6]他のメディア,端末との複合化等である。
こうした中,制度・技術の両面から,これらのニーズの充足を図るべく種々の方策が展開されている。その一つに,先に述べたファクシミリ通信網サービスを更に充実させた新ファクシミリ通信網サービスの開始がある。59年7月末開始の同サービスは,親展通信,ファクシミリボックス等の蓄積交換サービス機能,コンピュータとの通信を可能にするセンタ・エンド型通信サービス機能が付加されたほか,A4判伝送も可能となり,利便性が一層向上した。
また,現在,数秒でA4判が送れる高速機でディジタル網を利用したG4機の標準化,ファクシミリ機能とテレテックス機能を合わせ持ったミクストモードの標準化について検討が進められている。
これらにより,コンピュータやテレテックスとの接続が望めるなど,多様な利用が可能となり,ファクシミリ通信の適用領域が拡大し,ファクシミリ通信はオフィスオートメーションの中核の一つとして,今後ますます重要な役割を果たすこととなろう。
(2)ビデオテックス
ビデオテックスは,最新の電気通信技術,画像処理技術等を活用し,広く普及したテレビジョン受像機と電話回線を用いて,会話形式により情報センタに蓄積された文字図形情報の検索を行うほか,その双方向性を利用して銀行,百貨店,旅行会社等と接続して残高照会,商品・切符の注文・予約等利用者の個別ニーズにこたえ,受け手主導で情報を得ることができる新しい情報通信メディアである。
諸外国におけるビデオテックスの開発は近年大きく進展し,アジア,オセアニア等においても関心が持たれ,商用ないし実験の段階にある。世界に先駆けてその開発に乗り出した英国では,プレステルの名称で1979年から商用サービスが開始され,その後,フランスのテレテル,西独のビルトシルムテキスト,カナダのテリドン等が商用化されている。
ア.実験の概要
我が国においては,郵政省と電電公社が共同し,情報提供者,メーカ等の協力を得てキャプテンシステム(CAPTAIN:Character And Pattern Telephone Access Information Network System)の名称で,54年12月から56年3月まで東京23区内における1千のモニタを対象に第1期実験を行った。56年8月からは第2期実験として,モニタ数2千,蓄積画面数20万とそれぞれ第1期の倍とし,情報検索機能の充実,表示機能の向上を図ったほか,特定の利用者グループに特定の情報提供を可能とするクロ-ズド・ユーザ・グループ・サービス,利用者から商品の注文・予約を可能とするオーダ・エントリ・サービス等の機能拡充を行いながら実施してきたが,59年7月,第1期から通算して5年に及ぶ実験を終了した。
イ.商用サービスの概要
キャプテンは,これまでの実験による成果を踏まえ,59年11月から商用化されており,そのシステムの基本構成は第1-2-20図のとおりである。
商用サービスの当初の提供地域は,東京23区と周辺の主要都市及び京阪神地域であるが,需要動向等を考慮しつつ,順次拡大する予定である。また,利用の際の通信料は全国均一の3分30円となっている。
商用化に当たり新たに構築されたネットワーク「ビデオテックス通信網」は,通信処理装置,多重化装置及び電話網から構成され,多分野にわたる情報センタをこれに接続することにより,多様なサービスの利用が可能となった。
また,商用化に当たっては,表示方法に「新キャプテン方式」が導入され,これにより,実験時のドットパターン表示はもちろんのこと,幾何学図形表示やモザイク図形表示,さらに簡易動画表示,メロディ表現も可能となり,効果的な情報提供が行えるようになった。同方式と実験方式との比較は,第1-2-21表のとおりである。
このような商用サービスの開始を前に,59年2月,提供される膨大な情報の整理・体系化や利用案内簿の発行等,本サービスの普及促進のための組織としてキャプテンサービス株式会社が,情報提供者,メーカ,電電公社等関係者の出資により設立された。なお,59年8月現在,金融,商業,出版,印刷等の業界から,400を超える企業等が情報提供の申込みを行っている。
ウ.ビデオテックスの今後の課題
家庭からビジネス分野まで幅広い利用層を対象とするメディアであるビデオテックス(キャプテン)は,国民生活の充実,社会活動の効率化等に大きな効用をもたらすものとして,我が国はもとより諸外国においてもその普及発展が期待されているが,そのためには,端末機器・利用料の低廉化とともに,ビデオテックスの特性を生かすことのできる地域の個別情報や専門的な情報を中心に,利用者のニーズに即した情報の質量にわたる充実が望まれる。
(3)CATV
ア.CATVの概要
CATV(有線テレビジョン放送)は,当初においては,主としてテレビジョン放送の難視聴を解消するために,放送波を地域の共同アンテナで受信して有線で各家庭に分配するシステムとして発生したため,Community Antenna Televisionの略称とされていた。しかし,最近では,各家庭への分配に使われる伝送路の伝送能力を生かし,自主放送や各種の情報サービスの提供等を行うシステムとしても利用されるようになったためCable Televisionという,より広い概念の略称と考えられるようになっている。
我が国では,30年に初めての施設が群馬県内に建設されたが,この施設をはじめ,初期のCATVは,主として辺地におけるテレビジョン放送の難視聴解消のための施設として普及した。その後,都市において高層ビル及び高速道路,新幹線等の高架建造物によるテレビジョン放送の受信障害が多発するようになったため,その有効な解消手段として都市部でのCATV施設の普及が進み,今日では,これら都市難視聴解消を目的としたものが,施設数,契約者数とも,辺地における施設を上回るようになった。
さらに最近では,大規模・多チャンネル・多目的のいわゆる「都市型CATV」施設設置の動きが各地でみられるなど新たな展開をみせている。このようにCATVは古くて新しいメディアであるといえる。
イ.CATVの現状と動向
58年度末現在,CATV施設数は3万6,162,受信契約者数は393万で5年前と比較すると,施設数は1.6倍,受信契約者数は1.7倍に増加している。しかし,1施設当たりの平均受信契約者数は109で,CATV先進国ともいえる米国の規模(58年1月1日現在,平均加入世帯数は約4,500)と比べ極めて小規模であり,また全施設の99.1%が難視聴解消を目的としているなど,CATVの現状は,従来と比べ,あまり変化していない.(第1-2-22表参照)。
ただ,自主放送を行う施設についてみると,施設数は58年度末現在180と全体の0.3%にすぎないものの,施設数,受信契約者数ともこのところ着実に増加しており,しかも1施設当たりの平均受信契約者数は次第に増加して,58年度末には約2千となっている(第1-2-23図参照)。近年は,自主放送を行う施設の設置許可申請が多数出されるようになり,今後一層,自主放送を行う施設は増加するものと考えられる。
また,第1-2-24表は,58年度末までに許可を受けた引込端子数2万以上の施設を規模の大きい順に並べたものであるが,57年度末以前に許可を受けた(c),(d),(e)が,いずれも難視聴解消を主目的とした施設であるのに比べ,58年度に許可を受けた(a),(b),(f)は,いずれも主目的が自主放送でチャンネル数も多い。こうした「都市型CATV」といわれる新しい型の施設を設置する動きは各地にみられ,今後の動向が注目されている。
ウ.CATVの新たな発展に向けて
CATVは,地域密着性,多チャンネル性等のほか,双方向性をも兼ね備えるメディアとして,現在その発展が各方面から期待されている。
すでに既存CATV施設においても,衛星放送の同時再送信や,CATV施設間を電気通信回線で接続しての文字情報による二ュース放送等が実施されているほか,劇場映画の放送等によるペイサービス(有料テレビジョン放送サービス)や,防犯・防災サービス等についても早期実現に向けて検討が進められているなど,CATVの新たな活用が進展している。
また,CATVの高度利用を目的として,筑波研究学園都市において「高度総合情報通信システム」の開発調査を行っており,60年度には運用実験を開始する予定である。このシステムは,実用モデルとして,筑波研究学園都市の約3万世帯を対象に,最新の電気通信技術と多摩CCIS実験の成果を生かし,難視聴解消のため建設された有線テレビジョン放送施設に双方向機能を付加し,地域で求められる多様なサービスを提供しようとするものである。
こうした状況を踏まえ,郵政省は,CATV施設の活性化と発展を図るため58年5月,原則としてCATV施設のセンタ・端末間における双方向サービスを認めることとし,さらに,11月には,CATV事業者の接続,番組伝送用として,無線回線(23.48〜23.6GHz帯)の利用を認めた。
今後,CATVが,地域社会に密着した高度で多様かつ経済的な情報通信システムとして機能していくためには,次のような方策が望まれる。第1には,施設の大規模化を図り,そのスケールメリットを各種サービスと有効に組み合わせることにより事業の採算を図っていくことである。第2には,CATV番組の配給機構の組織化等,番組ソフト流通の円滑化・活発化を図ることである。さらに,第3には,CATV施設の建設資金に対する政策金融の活用等により,資金調達の一層の円滑化を図ることである。こうした各課題の解決により,CATVは新たなメディアとして一層の発展が期待できるであろう。
(4)文字多重放送
ア.文字多重放送の概要
文字多重放送は,テレビジョン放送電波のすき間を利用して,通常のテレビジョン放送と同時に文字や図形で構成された多種類の情報を送るシステムである。いつでも好きな時に文字図形情報をブラウン管上に呼び出せる点でキャプテンシステムと類似しているが,キャプテンシステムが電話とテレビジョン受像機を使って,利用者に個別に情報を提供するのに対し,文字多重放送はテレビジョン電波を使って,不特定多数に向かって放送するという違いがある。また,文字多重放送は,情報の供給量ではキャプテンシステムに劣るが,情報の速報性ではキャプテンシステムより優れている。
文字多重放送は,メッセージを安価に伝送でき,また,伝送された文字図形情報をハードコピーとして紙にプリントもできるなど,放送としての速報性に随時性,記録性等が加味された新しいメディアであるといえる。
国際的にはテレテキスト(TELETEXT)と呼ばれており,51年に本放送を開始した英国をはじめ,現在各国でコード方式と呼ばれる伝送方式により本放送又は実験放送が行われているが,我が国の場合は,漢字を用いるという特殊性やこれに対応した誤り訂正方式が存在しなかったことから,漢字伝送に適したパターン方式と呼ばれる伝送方式によって開発が進められてきた。
イ.文字多重放送の現状
我が国では,56年3月,電波技術審議会から漢字表示に適したパターン方式と呼ばれる伝送方式の技術基準が答申され,これを受けた郵政省では,文字多重放送の実用化に向けて放送法等の改正(57年12月施行)を行うとともに,文字多重放送についてパターン方式による送信の標準方式を定めた。
これを受けて,NHKは58年10月,東京と大阪で,主として聴力障害者を対象とした番組編成によって実用化試験放送を開始した。
放送開始後6か月間の状況は第1-2-25表のとおりで,これらの放送は総合テレビジョン放送に重畳して放送された。標準的な1週間の延べ放送時間は650時間で,このうち,独立番組は647時間,字幕番組(主番組のセリフや音楽,効果音等を主番組の補完として放送するもの)は3時間であった。
受信機の出荷台数は58年末で約2,600台にすぎないが,NHKが58年11月,この受信機を持つ聴力障害者関係の112施設に対して行ったアンケートでは,ニュース85%,天気予報80%という高い利用状況が示され,また,ほぼ全員から文字多重放送は聴力障害者にとって役に立つメディアであると評価された。
ウ.今後の開発動向
現在,文字多重放送に採用されているパターン方式は,コード方式に比べ,きめ細かい画面を伝送できる反面,伝送効率が悪く,速度がかなり遅いという欠点がある。我が国での開発開始当時には,コード方式での伝送は技術的,コスト的に不可能と考えられていたが,最近では技術の急速な進歩によって,家庭用受像機に漢字の文字発生器を導入して,コード方式で伝送することも可能となってきた。
こうした情勢から,電波技術審議会においても,55年度からコード方式について審議が進められ,58年3月には,方式の基本パラメータについて一部答申が行われた。
ここで定められた方式は,ヨーロッパで採用されているような文字やモザイク図形をコード化するという方式に加え,文字発生器にない外字や精細な図形はパターン方式と同じように画素に分解して伝送するものであり,キャプテンシステムで使用される符号化方式との整合を図るなど,コード方式とパターン方式の長所を併せたハイブリッド方式ともいえるものである。近い将来,このハイブリッド方式の技術基準が確立されれば,伝送速度はパターン方式に比べ5〜10倍となり,サービスできる情報量が大幅に増加するとともに,簡単な音楽を付加音として伝送することも可能となる。多様化しつつある利用者二ーズに対応するためには,多様な番組提供が必要であり,そのためにもハイブリッド方式の技術基準の確立が待たれている。
(5)電子郵便
ア.電子郵便実験サービスの拡大
現在,実験サービス中の電子郵便は,ファクシミリ通信の技術を郵便に取り入れることにより,送達速度を大幅に向上させた新しい郵便サービス(以下「ファクシミリ型電子郵便」という。)である。このサービスは56年7月から東京,名古屋,大阪の3都市間で開始し,その後,福岡,札幌へサービス地域を拡大し5都市14の郵便局でサービスを提供してきた。
この間利用者からは,サービス地域の拡大,引受郵便局の追加等の要望が寄せられてきたことから,これらの要望にこたえるとともに,実験の一層の充実を図るため,59年10月から全国の県庁所在地等の主要郵便局に端末機を設置し,引受,配達を含めサービスの全国拡大を行ったところである。
拡大後のサービスのシステム構成は,第1-2-26図に示すとおりで,郵便局の窓口で引き受けた通信文等をファクシミリにより送信し,受信局では,これを電子郵便専用の封筒に納めた上で速達郵便物の例により受取人へ送達するものである。
イ.電子郵便の利用状況
58年度の電子郵便の利用通数は,約6万4千通でありその内容は慶祝・弔慰と各種挨拶,図面,グラフ,数表類等の緊急通信に利用されるなどファクシミリ型電子郵便の特徴を生かしたものとなっている。
利用者の反応としては,送達時間が速い,慶祝用に便利,イラスト等が自由に送れる,などが評価される一方,取扱郵便局の拡大,カラー送受信等の要望が寄せられている。
ウ.今後の電子郵便
今後の電子郵便については,現在実験サービス中のファクシミリ型電子郵便の拡充及び新しい電子郵便サービスの導入について検討しているところである。
その第1は,コンピュータ郵便の導入である。コンピュータ郵便とは,利用者からあて先リストと通信文を収録した磁気テープの提供を受け,これをもとに郵便局のコンピュータ等により郵便物を作成して配達するシステムである。同様のサービスは,現在,英国(EP:Electronic Post)及びスウェーデン(EPS:Electronic Post Service)で実施されており,米国でも利用者から磁気テープ持込みでなくオンライン入力という方法であるが,同様のサービス(E-COM:Electronic Computer Originated Mail)が提供されている。
第2は,国際間電子郵便サービスの開始である。
国際電子郵便の取扱いについては,米国による国際電子郵便サービスの提唱を契機として,欧米諸国間にファクシミリ型の国際電子郵便サービス「インテルポスト」が開始されており,そのサービスのネットワークは徐々に拡大されてきている。
我が国においても,国際郵便の即日又は翌日配達を目指して,米国,英国,韓国等7か国との間で59年度中に国際電子郵便の実験サービスを開始する予定で所要の準備を進めている。今日,電気通信技術は著しく進展しており,利用者のスピード志向も高まっている。こうした中で,電子郵便は,電気通信技術を取り入れたスピーディな郵便サービスとして,利用者のニーズに十分こたえるものと考えられる。
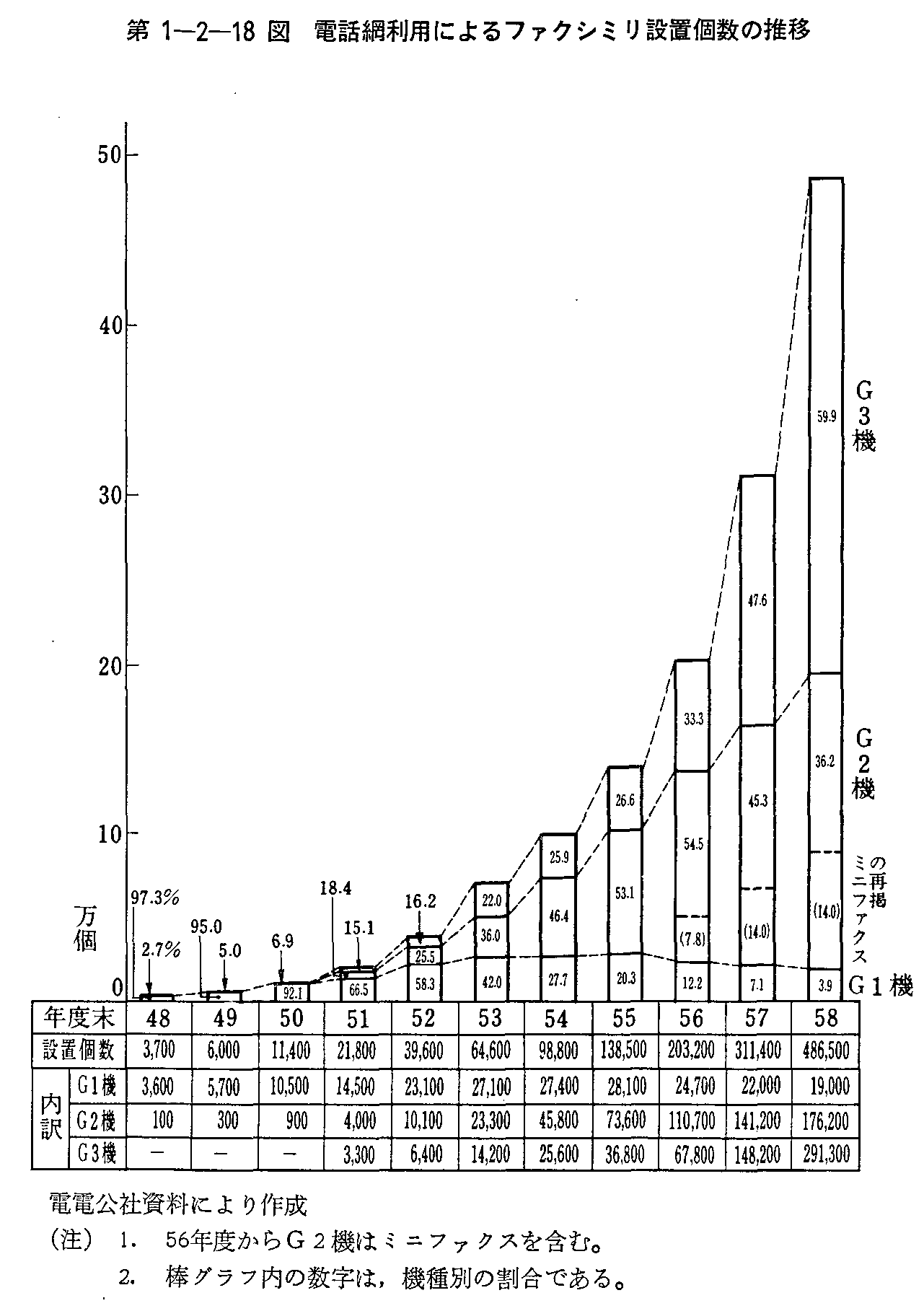
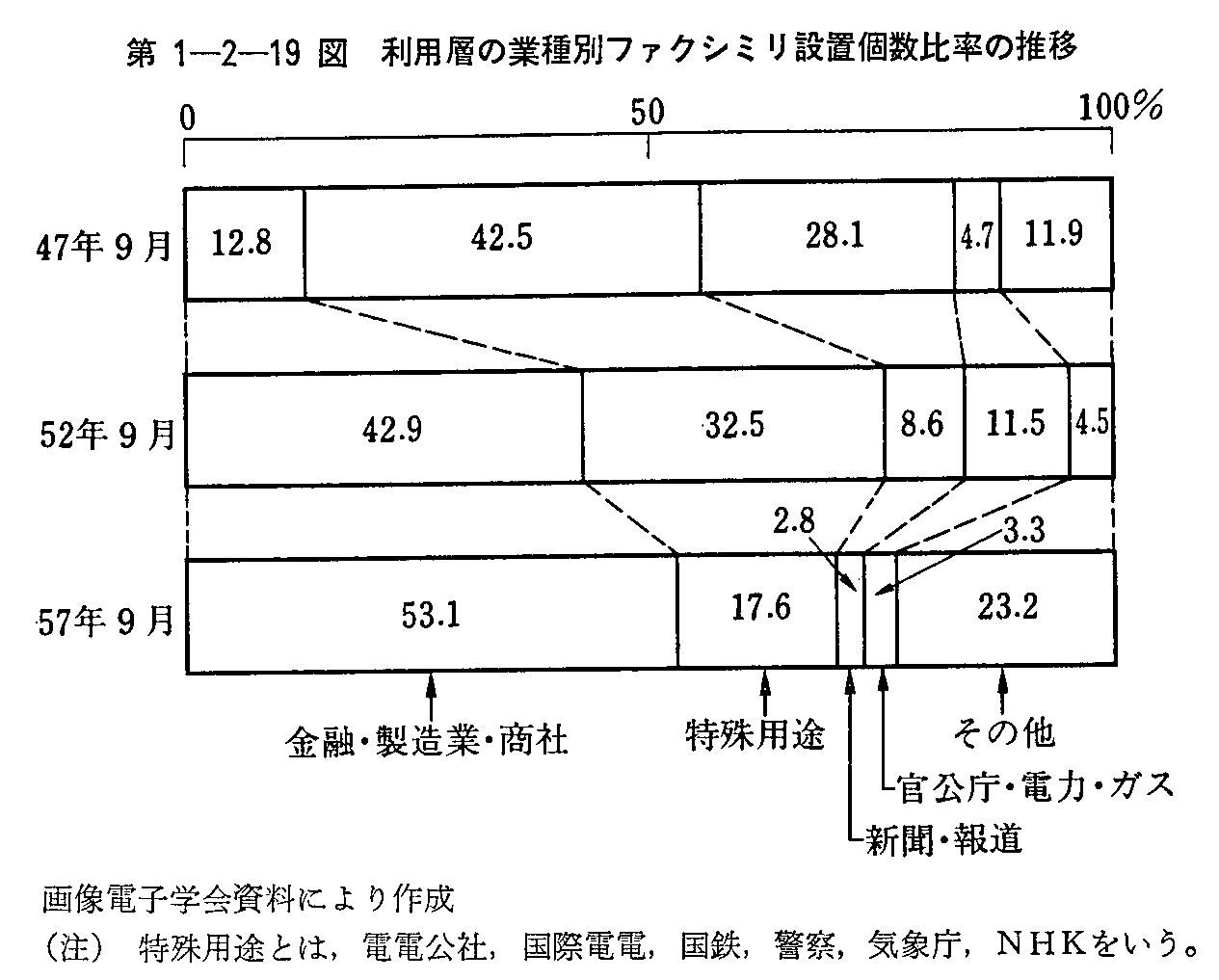
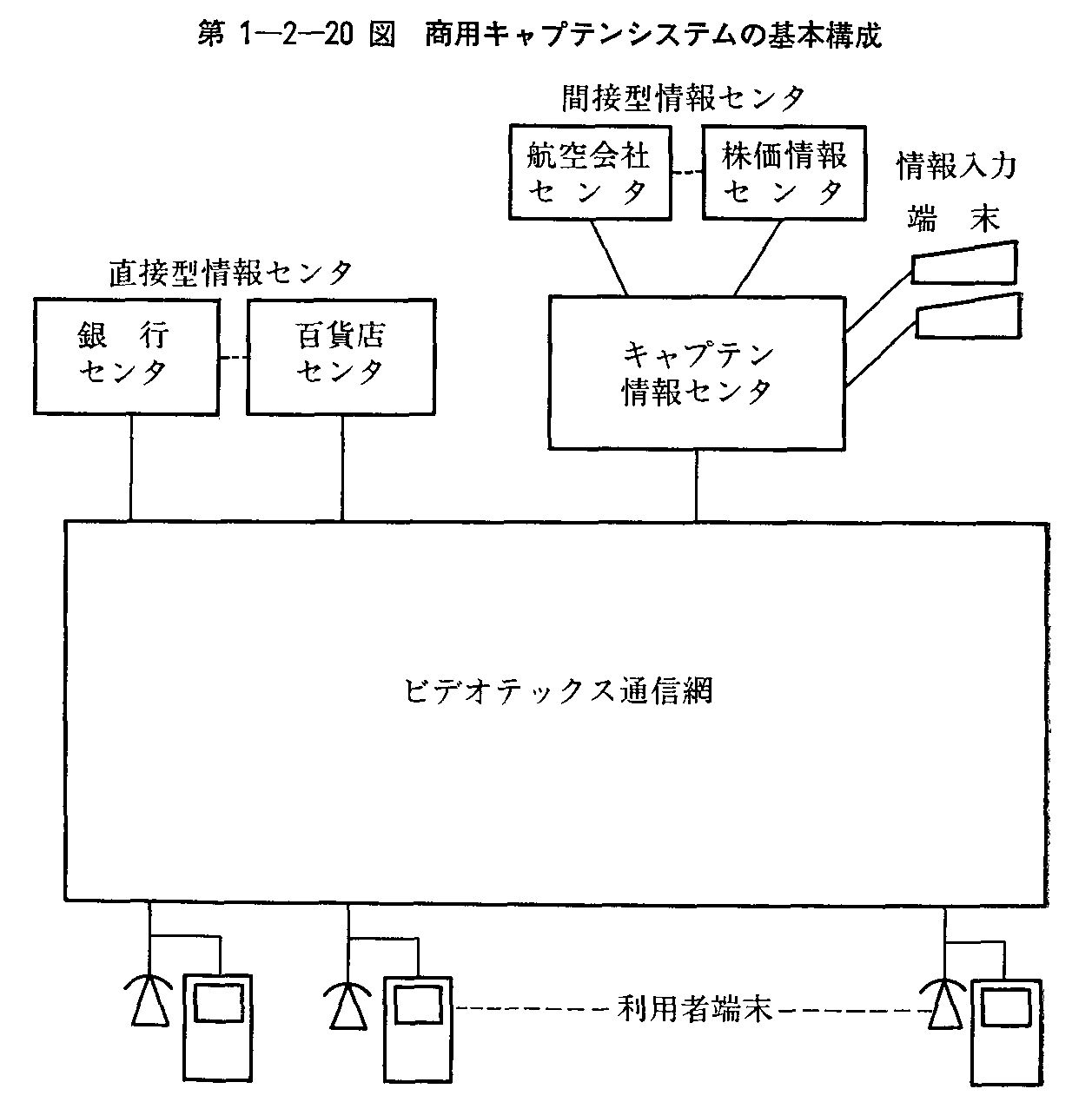
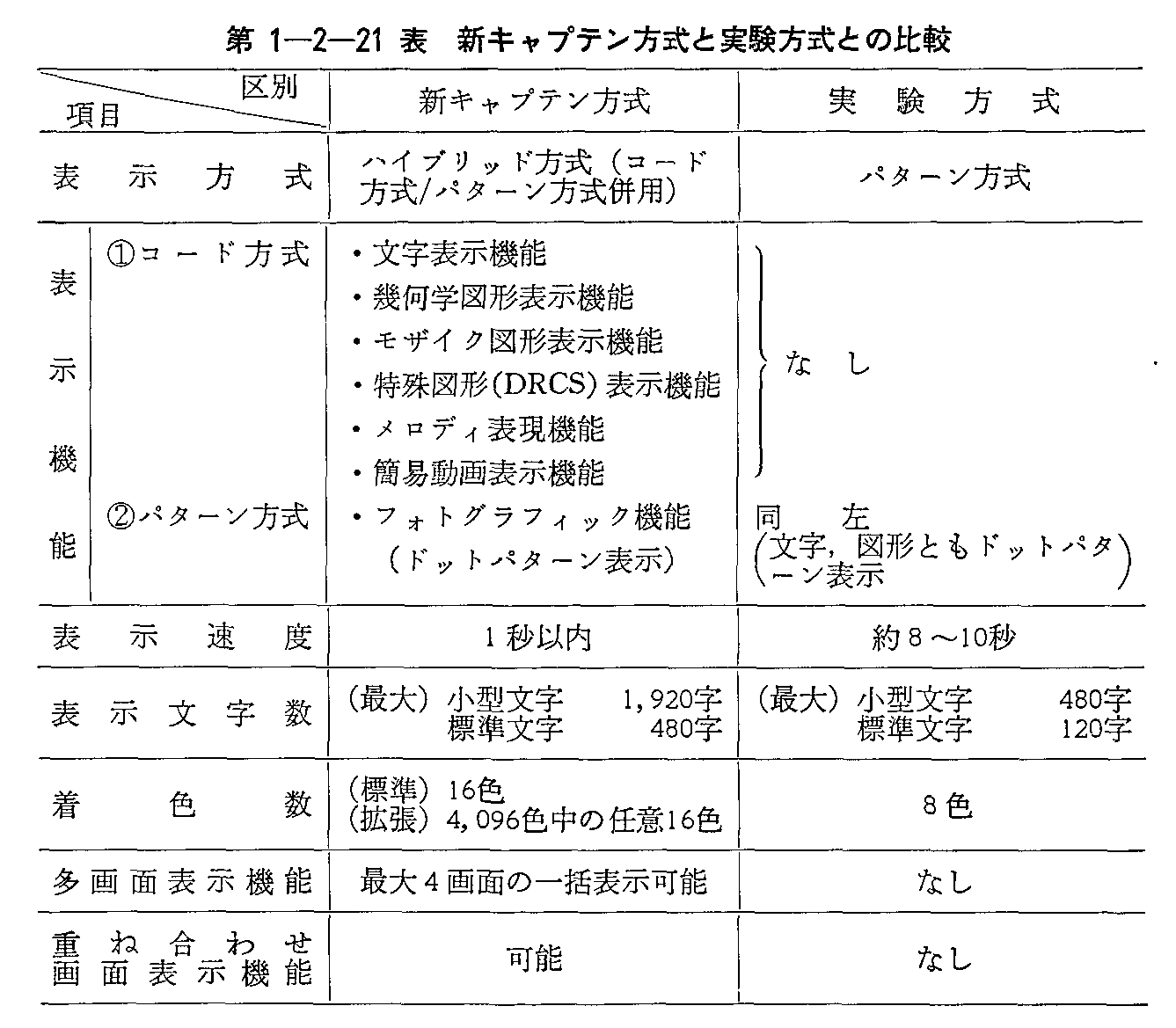
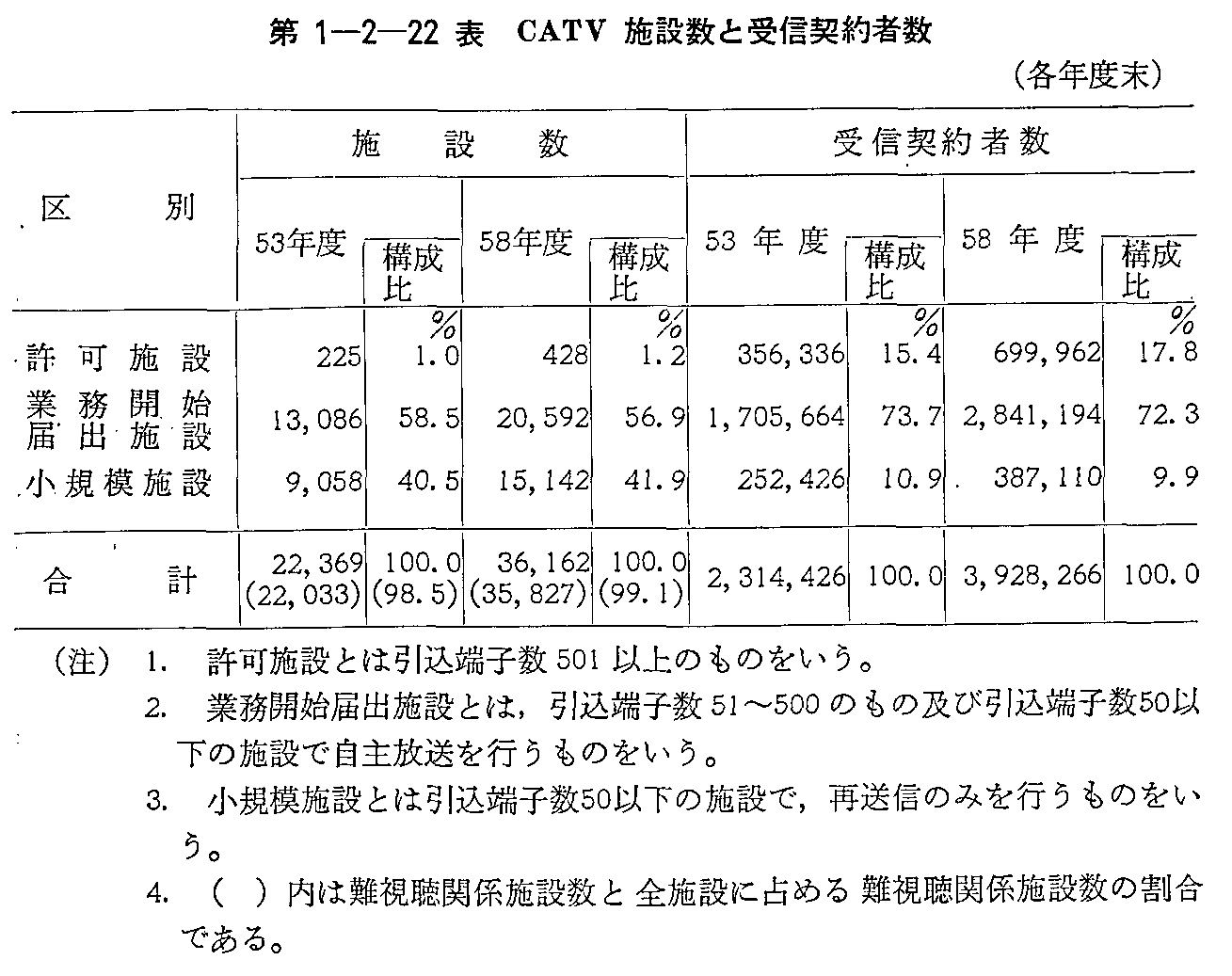
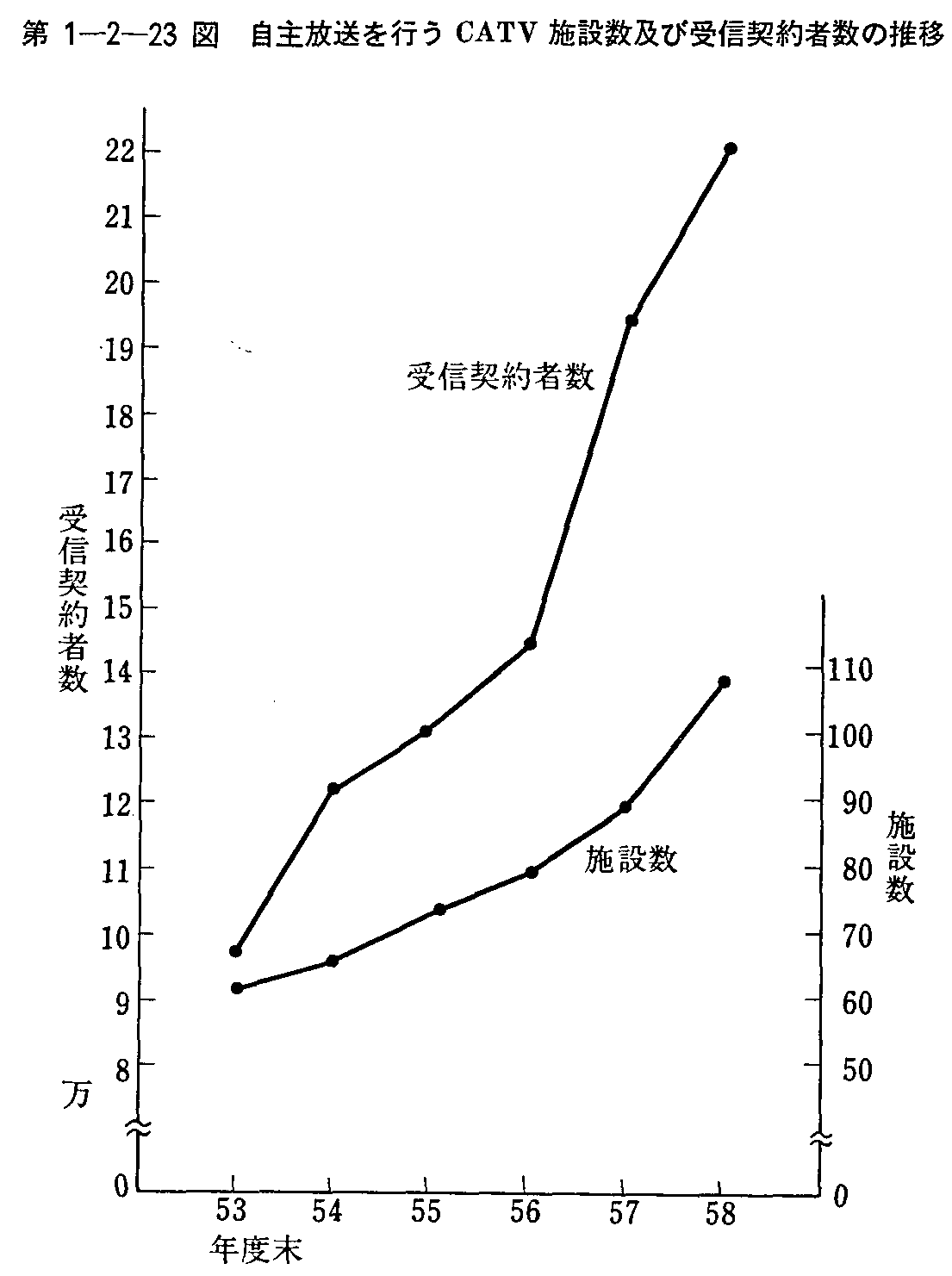
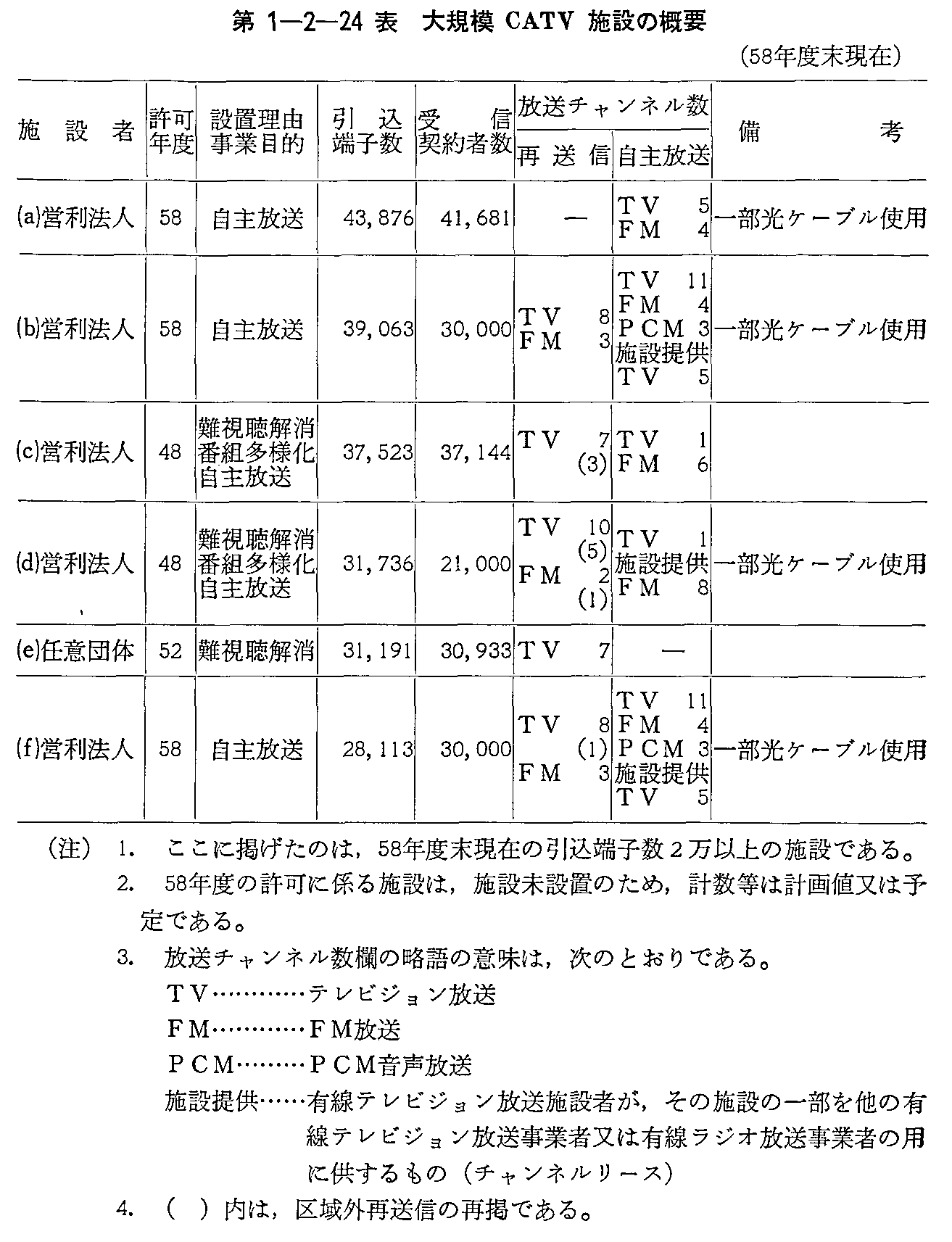
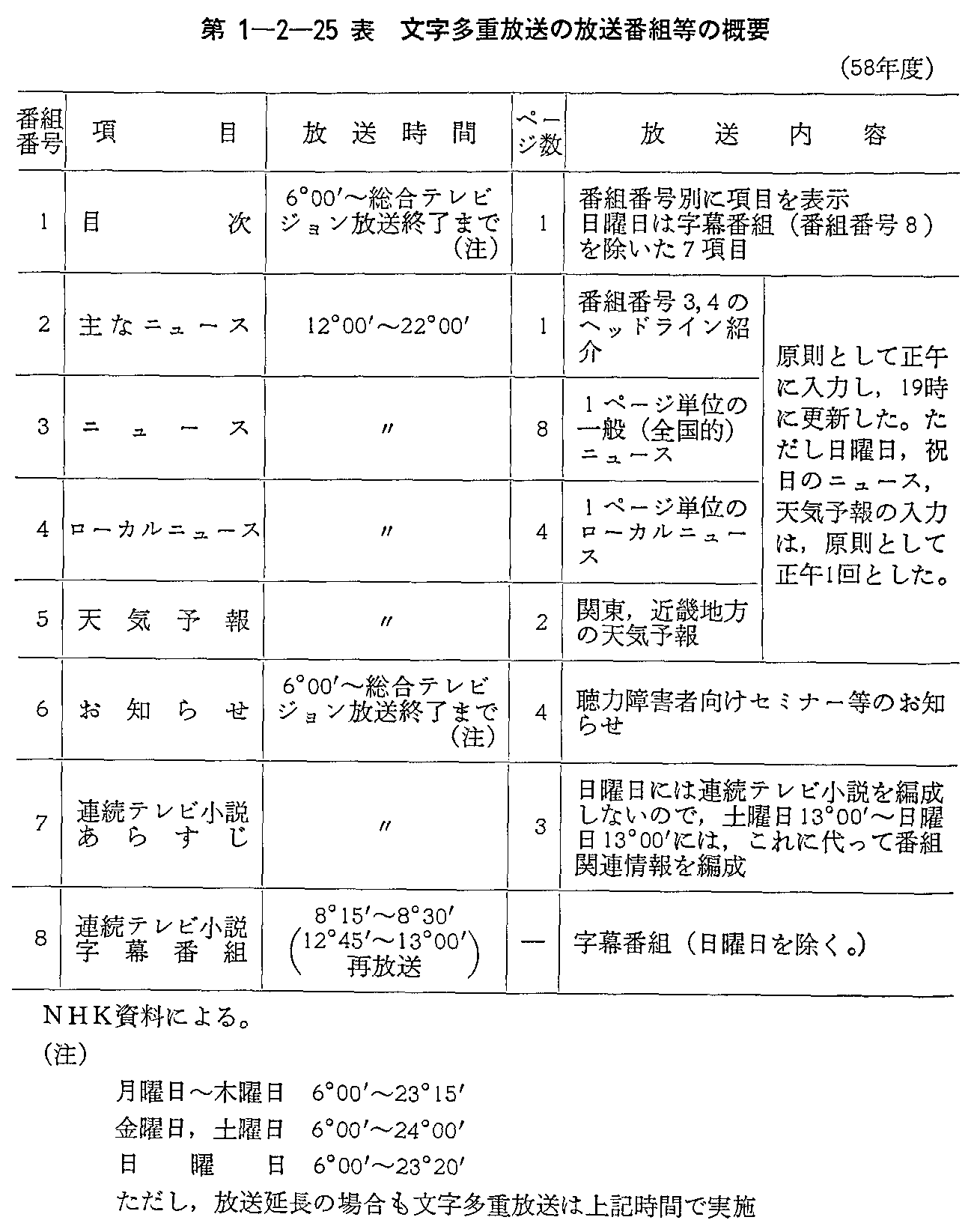
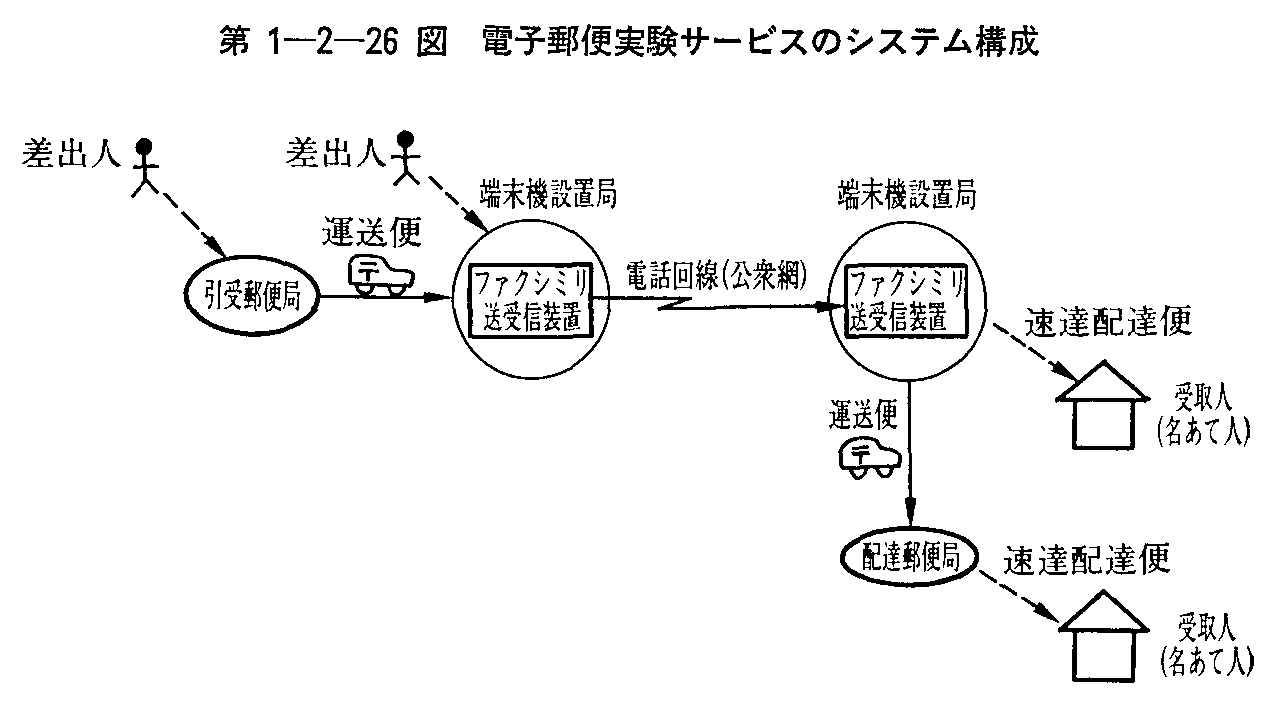
|