 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
3 総合的な基盤整備の推進
高度化・多様化する利用者ニーズに対応し,産業経済の活性化と豊かな国民生活の実現に向けて,通信がその重要な役割を果たしていくためには,競争原理を導入していく必要のあることは既に述べたとおりであるが,それとともに高度情報社会形成の基盤となる多層的なトータルネットワークの構築や技術開発等を総合的に推進していく必要がある。
(1)多層的なトータルネットワークの構築
ア.新たなネットワークの構築
現在,我が国では,電話網をはじめ,加入電信網,データ通信網等,各種通信網が個別に構成されている。しかし,最近では,ディジタル技術や光ファイバ通信技術等の発達により,種々の電気通信網を一つのネットワークに統合することが可能となり,統合された電気通信網を基礎として,種々のサービスを提供するサービス総合ディジタル網(ISDN:Integrated ServicesDigital Network)を構築することが当面の重要課題であると考えられるようになった。現在,国際電気通信連合(ITU)の国際電信電話諮問委員会(CCITT)を中心に国際的な検討が進められている。
我が国では,この流れの一環として,電電公社により高度情報通信システム(INS:Information Network System)構想(第1-2-41図参照)が進められており,59年9月,東京の三鷹・武蔵野地区において実験が開始された。この実験で提供されるサービスの概要は,第1-2-42表に示すとおりである。
電気通信網の統合は,通信網の提供者にとっては設備共用による経済性の向上等のメリットがあるとともに,サービス利用者にとっては,各種の通信サービスを同一の通信網から容易に得られるというメリットがある。
さらに,今日では,DDX網やファクシミリ通信網にみられるように,電気通信網は,単に通信に係る電気信号を忠実に伝送するだけでなく,各種の蓄積交換・処理の機能も包含できるようになった。
今後は,端末機器のインテリジェント化,サービス複合化の動向とあいまって,提供サービスの高度化・多様化が期待される。
イ.テレトピア構想
情報通信システムは,高度情報社会の重要なインフラストラクチャーであり,産業振興,地域振興等の多元的観点から,その整備・普及を図っていく必要がある。ことに,人間中心の豊かな社会を実現するためには,活力ある安全で快適な地域社会に向けて,それぞれの地域が自立的発展を図っていく必要があり,こうした地域振興の観点から,各地域社会でも情報通信システムへの認識が高まりつつある。
高度情報社会に向けての新しいインフラストラクチャーの整備に当たっては,全国レベルのネットワークの整備とともに,これと有機的に結びつく地域に密着した情報通信システムの整備も重視される必要があり,また地域特性を踏まえたニューメディアの普及促進も重要となる。
郵政省が,58年8月に提唱したテレトピア構想(正式名称は未来型コミュニケーションモデル都市構想)は,こうした背景を踏まえ,国民的視野に立って,望ましいニューメディア普及の方向を見出す必要性から生まれてきたものである。テレトピア(Teletopia)とは,テレコミュニケーション(Tele-communication=電気通信)とユートピア(Utopia=理想郷)の二つの言葉を合わせた,この構想の一般名称である。
テレトピア構想では,全国レベルのネットワーク形成に加えて,新たに未来型コミュニケーションモデル都市(以下「モデル都市」という。)に様々なニューメディアを導入し,全国的普及の拠点とするとともに,その実用的運用を通じて地域社会に及ぼす効果や影響,問題点の把握等を行うこととしている。そのイメージは第1-2-43図のとおりであり,究極的には,21世紀に向けた,我が国全体の高度情報社会への変革に資することを目的としている。
国民ニーズの高度化・多様化及び地域の抱える問題の多様性を考えると,今後,各地域社会の目標とすべぎ発展の方向は様々であるため,モデル都市のイメージについても多くのタイプが考えられるが(第1-2-44表参照),これらは,あくまでも各地域が自らの地域社会発展の一助として,どのようなニューメディアを導入していくかを検討する際の参考に資するものであり,基本的には,地域の主体的な企画,創造性に基づくユニークな都市づくりが行われることが望まれている。郵政省では,今後,モデル都市の指定を希望する地方公共団体からの基本計画の提出を受け,59年度末までにモデル都市の指定(全国10地域程度)を行い,関係行政機関と連携しつつ,テレトピア構想の推進を図ることとしている。
(2)技術開発の推進効率的かつ信頼度の高い多層的なトータルネットワークを構築するためには,その前提となる技術開発を推進する必要がある。特に,標準化の推進,安全性・信頼性対策の確立,研究開発の推進が重要である。
ア.標準化の推進
現在,通信ネットワークを構成している端末機器は,電話機をはじめ,コンビュータ,データ端末,ファクシミリ等多岐にわたっているが,第1-2-45表のように相互に接続可能な端末機器は,データ通信を除けば同一種類の端末相互に限定されている。
今後は,インテリジェント化・複合化した各種端末機器が,ネットワークに接続されること,通信処理機能等の処理機能を有する機器がネットワークに接続されること,複数の電気通信事業体間での網間接続が行われることなどにより,その接続形態はますます多様化するものと考えられる。
このような状況の中で,異なる端末機器・各種システム相互間の円滑な通信の確保,相互接続のための変換機能の開発等資源の効率的な利用を実現するため,通信インタフェイス,通信手順及び通信品質の標準化が必要となる。
標準化の対象としては,
[1] ネットワークと端末機器との接続基準
[2] ネットワークに通信処理装置やデータ処理装置等のシステムを接続する場合の接続基準
[3] 端末機器及び各種システム相互間の通信規約
[4] 異なるネットワーク間を接続するための接続基準
[5] ネットワーク自体の品質基準等が挙げられる。標準化を推進するに当たっては,通信サービスの提供の確実性が保証されること,通信の秘密が確保されること,ネットワークや端末の発展を促進するものであること,より良い通信品質が確保されること,緊急災害時や過疎地及び福祉用の通信サービス提供に資すること,といった条件を考慮する必要がある。
また,標準化については,今後も国が中立的な立場から,利用者,電気通信事業者,製造業者等各界の意見を十分反映し,かつ国際的協調にも配意しながら標準化の推進を行う必要がある。特に,ISO,CCITT等の国際標準策定の場において,一層の貢献を行う必要がある。
イ.安全性・信頼性対策の確立
多層的なトータルネットワークは,社会・経済の活性化を促進し,豊かな国民生活を実現すると同時に,反面,依存度増大に伴い,自然災害,システム障害等によるシステムの機能停止がネットワーク全体に影響を及ぼし,社会・経済活動に多大の支障をもたらす恐れがある。さらに,個人情報の蓄積の増大に伴い,個人のプライバシーを脅かす可能性も予想される。したがって,その効用を享受するためには,このようなぜい弱性を克服する必要があり,安全性・信頼性の確保に向けて最大限の配慮を行う必要がある。安全性・信頼性対策を考慮する場合,障害等の発生原因がシステムの外部にあるか内部にあるか,また人為的な原因による場合は故意によるものかよらないものかといった要因で発生原因を分類し,それぞれに対する効果的な対応手段を講じることが必要である。
その対策としては,第1-2-46表のとおりハードウェア・ソフトウェア等技術的なもの,プライバシー・データ保護等に関する法制度面での対策等国・地方公共団体等を中心に進める制度的なもの,及び,障害発生時の損害を補填する保険によるもの,といった対策に大きく分類することができる。制度的対策としては,安全性・信頼性対策を実施するに当たっての過大な負担を防止するとともに,あわせて対策の必要性の認識を深め,その充実を期すために,安全性・信頼性確保のあるべき姿を合理的かつ明確に示した適正な基準の存在が不可欠である。このため,現在データ通信ネットワークの安全性・信頼性を確保する上で採用することが望ましい措置の基準として「データ通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和57年郵政省告示第771号)が制定されている。さらに,個々のデータ通信システムの高度化・ネットワーク化を促進するため,各種データ通信システムの通信方式や安全性・信頼性に関する状況を公開する必要があり,58年2月から実施されている「情報通信ネットワーク登録規程」(昭和57年郵政省告示第904号)は一定のレベルの安全性・信頼性確保措置をとり,標準の通信方式を用いている情報通信ネットワークを登録・閲覧可能としたものである。
ウ.研究開発の推進
電気通信分野の研究開発は,国及び電気通信事業体による先端的基礎的研究開発,並びに,企業性の追求の下に応用技術を主体とする民間の研究開発,さらに,これらが有機的に結合された共同開発体制によって世界のトップレベルに達している。このため通信メディアの高度化・多様化が進展している。
今後,高度情報社会に向けて,新しい通信メディアの円滑な導入と普及促進を図るためには,伝送技術,交換技術や自動翻訳電話のような言語に関する技術等の研究開発が重要となる(第1-2-47表参照)。
電気通信分野は,その技術先端性と成長産業としての重要性から欧米諸国を中心に世界各国とも高度化等諸方策を講じており,今後の研究開発で欧米と対等の地位を確保する上からも,なお一層強力かつ効率的な研究開発の推進が必要である。
このためには,国及び電気通信事業体の研究開発の活性化を進めるとともに,民間の自主的研究開発に期待し,相互の競争体制を確保する一方,基礎的研究部門においては技術力の結集を図り,データベースの構築,研究機関相互間の人材交流等を行う必要がある。
さらに,研究者・技術者等の人材の養成・確保も不可欠である。
また,ネットワーク化の進展に伴って,一定の水準を持った電気通信関連技術者,コンサルタント等への要請が増大するものと考えられるため,電気通信技術に関する資格制度の設置,コンサルタントの育成等を図り,技術者の養成を促進する必要がある。
(3)高度情報社会の形成に向けて
成熟化,国際化,高齢化,情報化等の社会情勢の変化に対応しつつ,来るべき21世紀に向けて,豊かな国民生活や社会・経済の効率化・活性化を実現していくためには,通信メディアそれ自体の高度化・多様化を進めていくとともに,提供する情報内容の充実や多様性の確保といった面にも十分配慮して,通信メディアの発展を図っていくことが極めて重要であると考えられる。
しかしながら,通信メディアの発展は,国民生活においては生活様式の変化や思考パターンに影響を与えるとともに,産業界においても,ネットワークの進展等により異業種間の融合や競合を生じさせ,業界自体の構造を変化させるなど多大な影響を与えるものと予想される。
また,新しいネットワークの構築や高度なデータベースの構築には相当の期間と資金を要するものである。
このような状況の下において,高度情報社会を早期に実現していくためには,それぞれの通信メディアがその特性を生かしながら,関係分野と整合性を保ちつつ,調和ある発展を遂げていくことが必要不可欠なものとなっている。このため,国としても,長期的・総合的な指針を策定し,電気通信分野における競争原理の導入をはじめ,多層的なトータルネットワークの構築や技術開発の推進等,通信メディアの高度化・多様化のための施策を調和のとれた形で推進していくことが必要である。
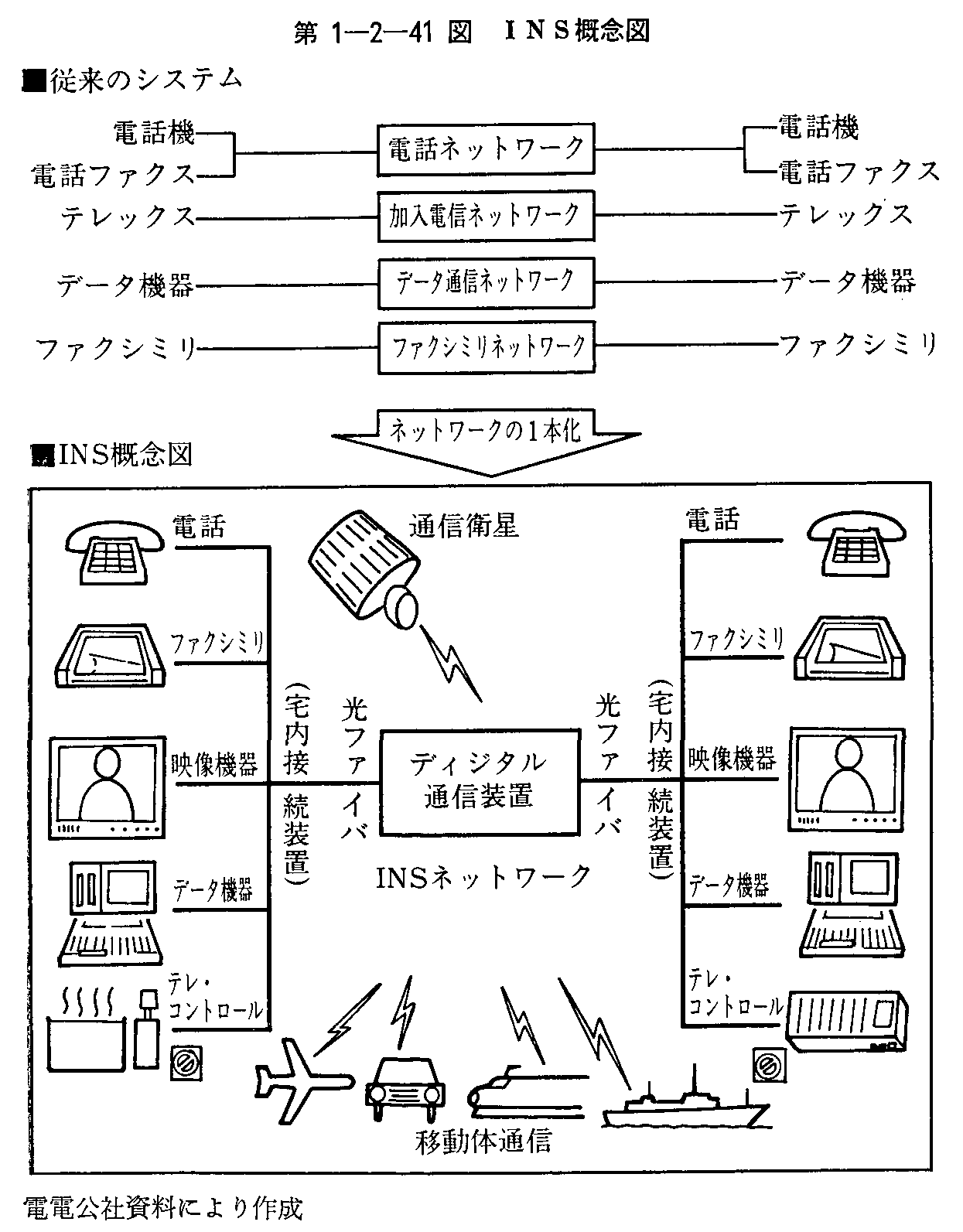
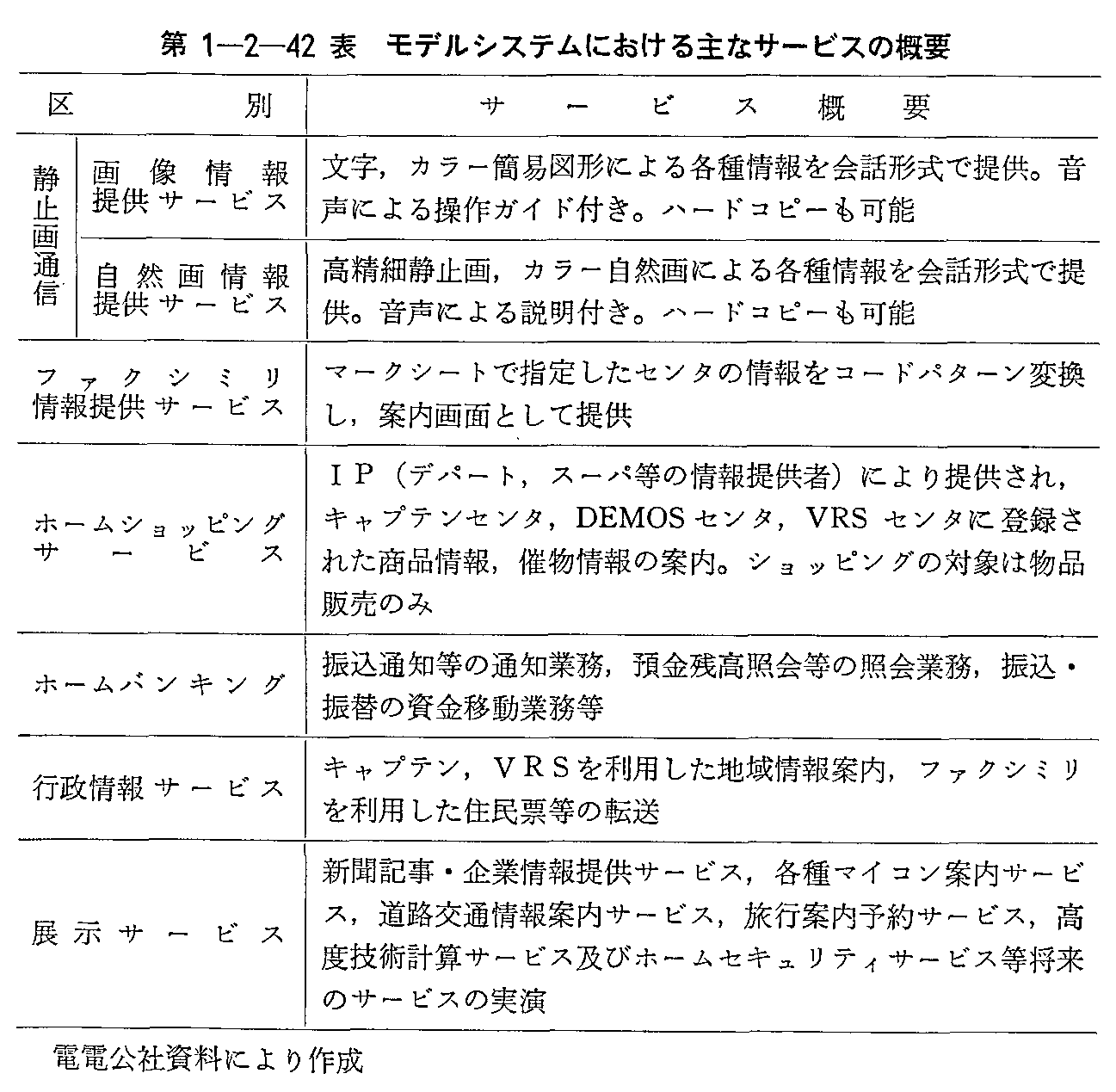
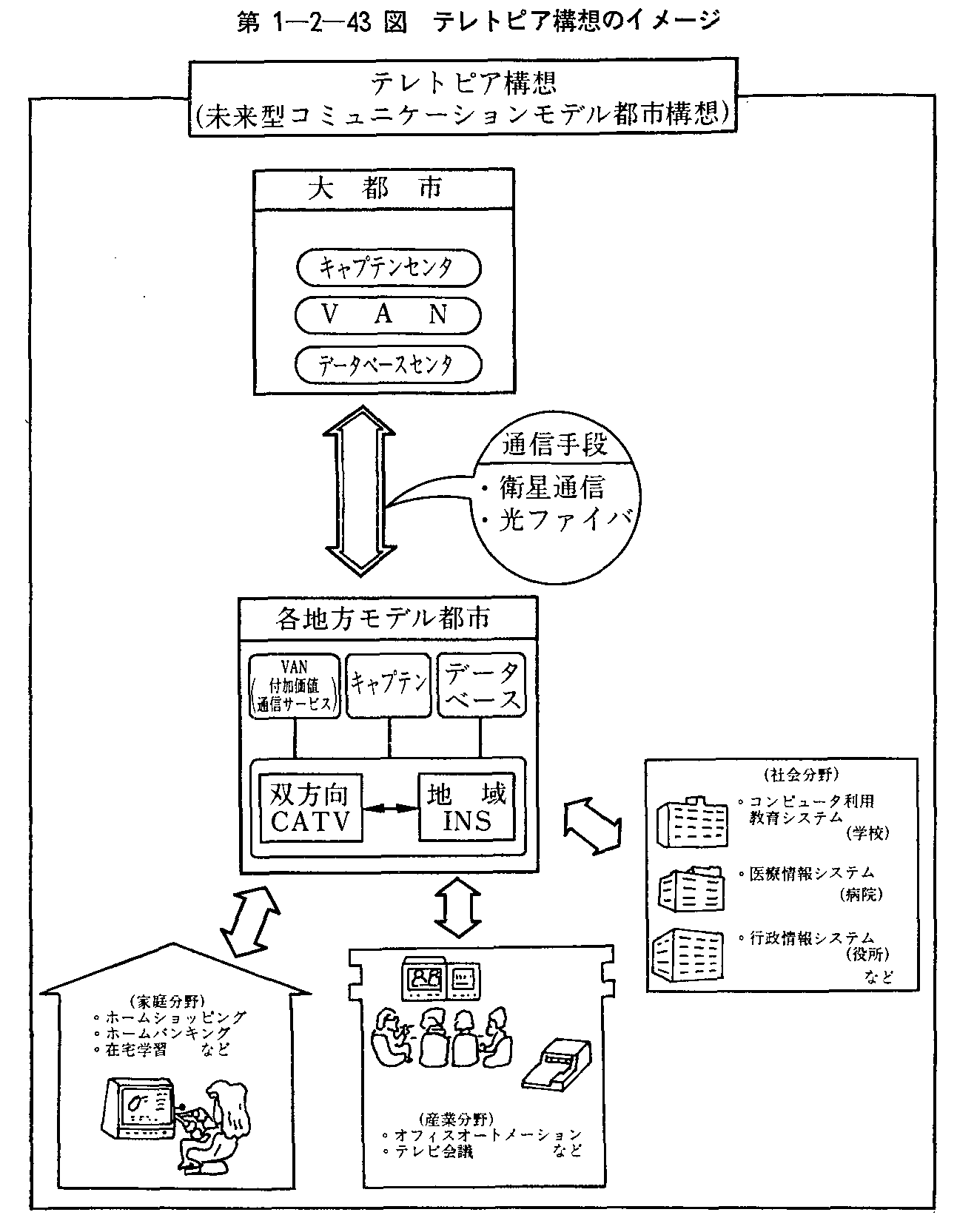
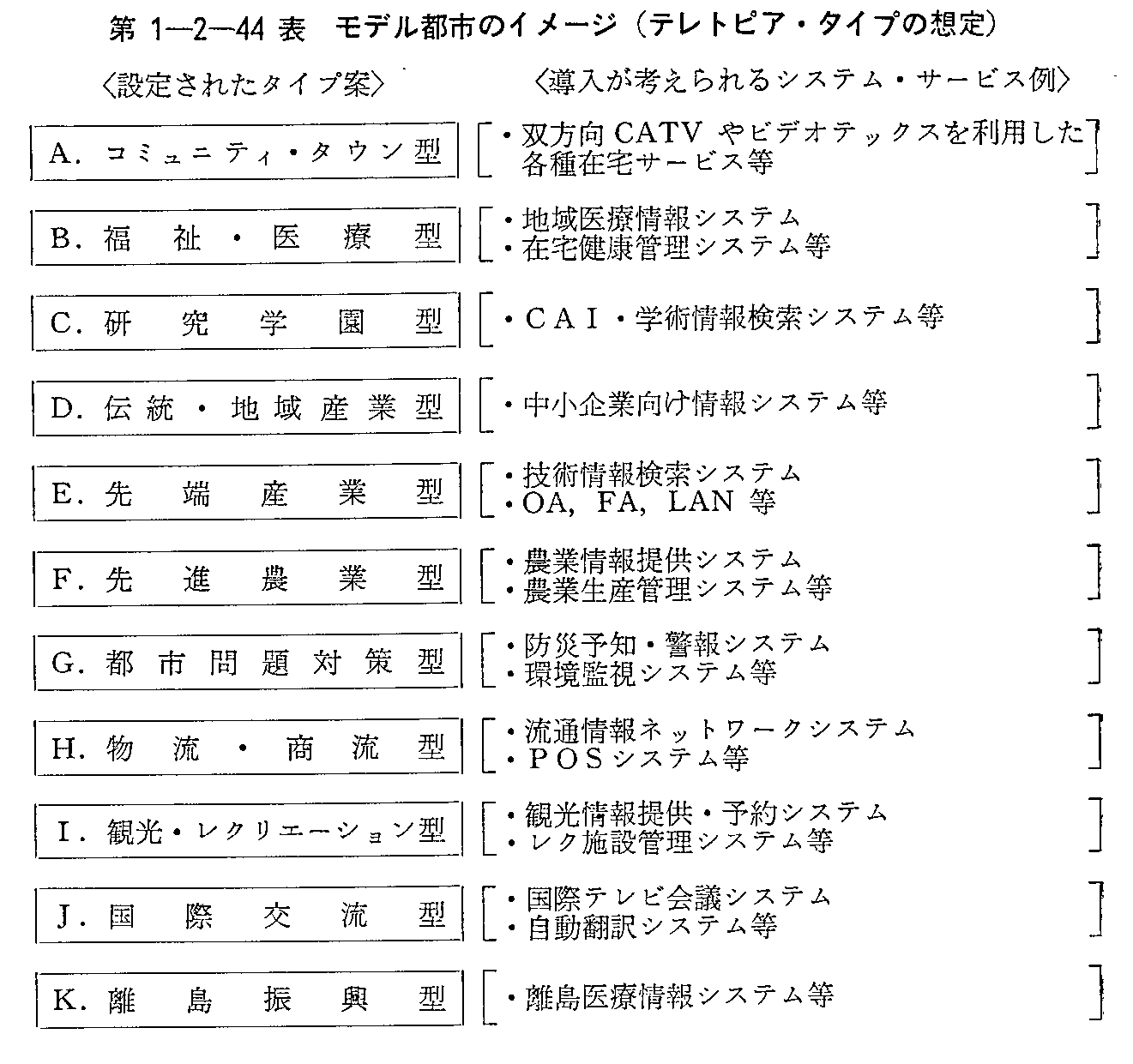
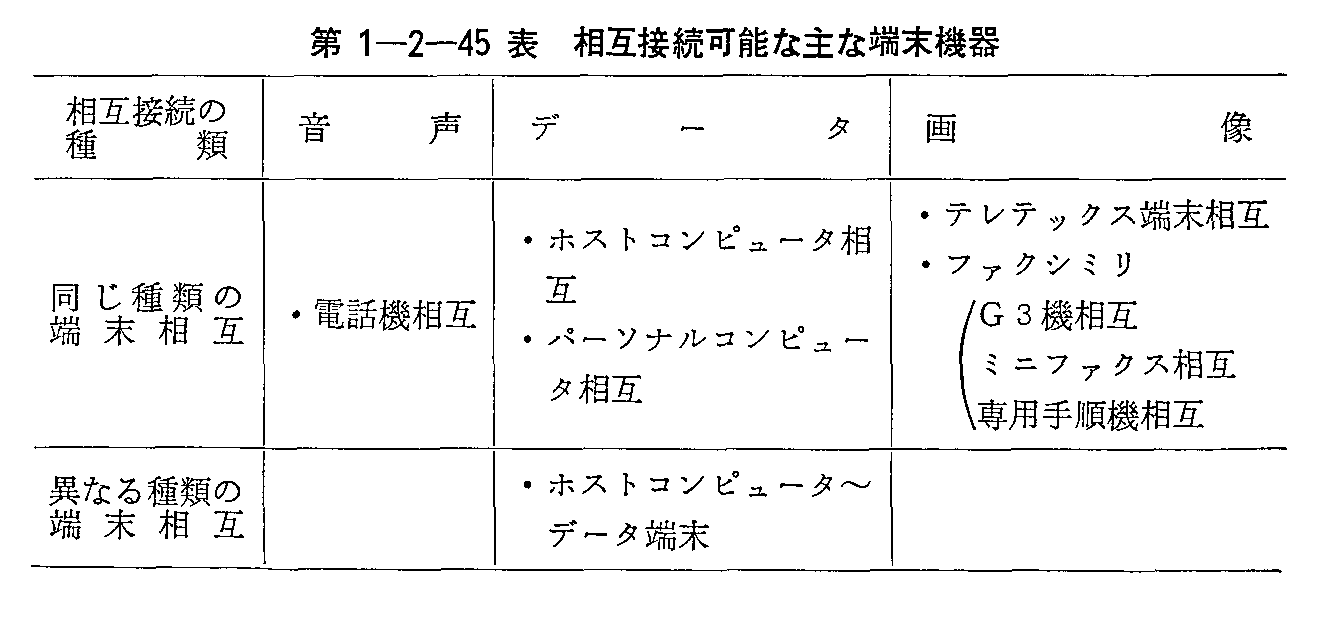
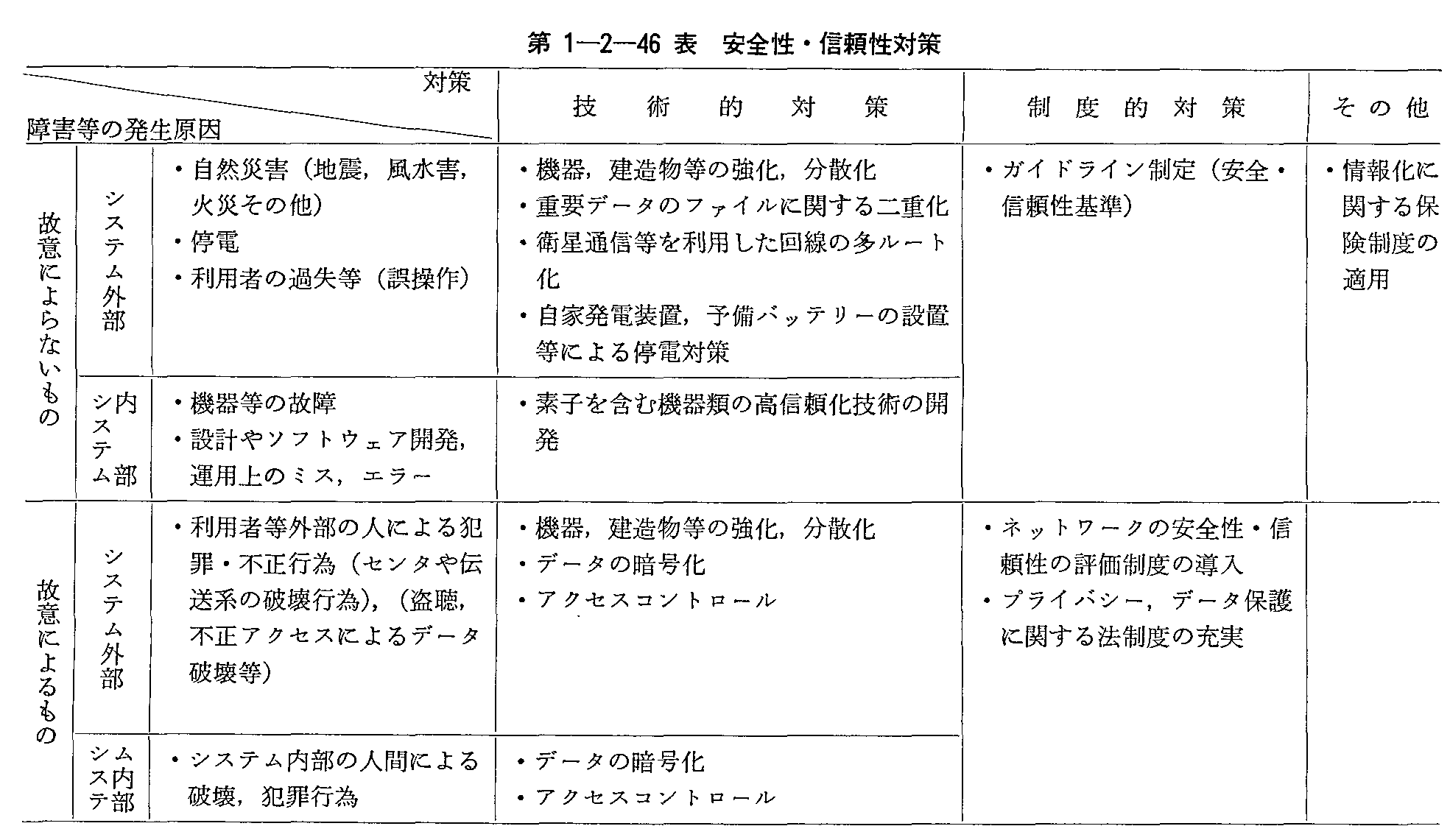
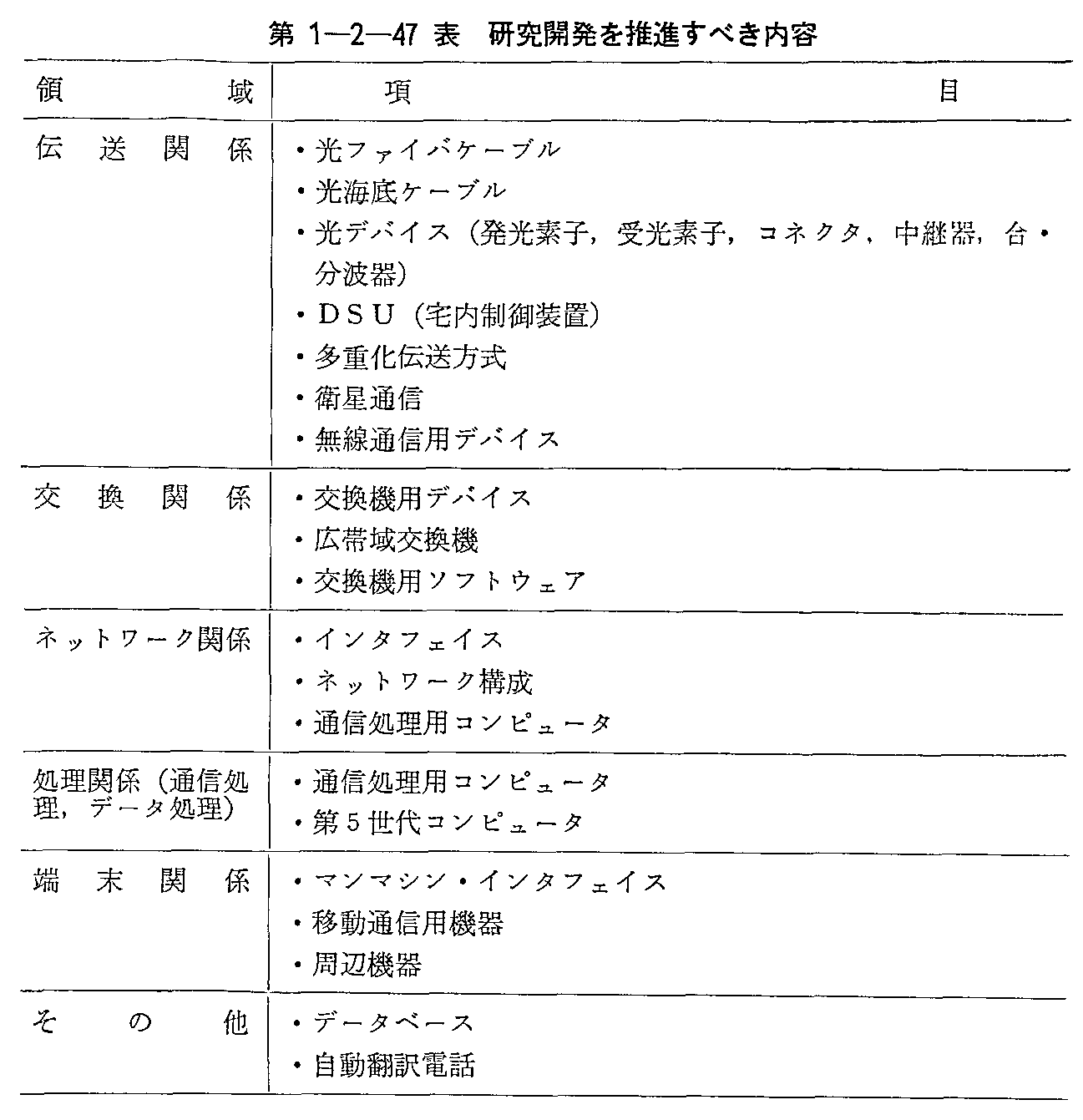
|