 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第3節 国際公衆電気通信の現状
1 国際電気通信サービスの現状
(1) 国際電報
国際電報は,世界中の国又は地域との間で取り扱われており,国際通信サービスのうちで最も古いものである。その通信需要については,かつては国際通信の主役として順調な伸びを示してきたが,近年においては国際加入電信の普及及びファクシミリ通信やデータ通信の発展に伴い,44年度の602万通をピークとして大幅に減少してきている。
我が国に発着する国際電報及び我が国が第三国の立場で中継する国際電報の58年度の取扱数は,215万通で前年度の256万通に対して15.9%の減となっている(第2-2-12図参照)。
このように国際電報は,恒常的にその業務規模が縮小しており,収支状況も悪化してきているが,国際電報が依然として主要な通信手段である地域も多くあることから,今後とも基本的な国際通信手段としての役割を果たしていくものと思われる。
(2) 国際加入電信
国際加入電信は,不在通信が可能なことから時差のある国際通信には特に適しており,国際間の企業活動には欠かせない通信手段となっている。その通信需要については第2-2-13図に示すとおり年々増大しているが,ファクシミリ通信やデータ通信への需要の移行等の要因により,最近は伸びが鈍化する傾向にある。
我が国に発着する国際加入電信及び我が国が第三国の立場で中継する国際加入電信の58年度の取扱数は,4,962万度で前年度の4,568万度に対して8.6%の増となっている。
本サービスは,国際電電の国際加入電信加入者だけでなく,電電公社の加入電信加入者で国際利用登録を行った者も利用することができるが,このほか,国際電電の各営業所に公衆用国際加入電信設備(テレックスブース)があって,一般の利用に供されている。58年度末における国際電電の国際加入電信加入者は8,939加入,電電公社の加入電信加入者で国際利用登録を行った者の数は2万3,598加入であり,これは前年度末に対してそれぞれ547加入,1,190加入の増となっている。
(3)国際電話
国際電話は,我が国経済社会の一層の国際化が進展する中にあって,国際間の基幹的な通信手段となっており,個人利用の増大及び国際電話網利用によるファクシミリ通信あるいはデータ伝送の利用の増大とあいまって,その取扱数は第2-2-14図に示すとおり飛躍的に増大している。
我が国に発着する国際電話及び我が国が第三国の立場で中継する国際電話の58年度の取扱数は,4,974万度で前年度の3,808万度に対して30.6%の増となっている。
我が国で取り扱う国際電話の種類としては,利用者が直接相手国加入者をダイヤルして接続する国際ダイヤル通話と,オペレータを介して接続する番号通話,指名通話等があるが,このうち国際ダイヤル通話については,48年に米国本土等4対地との間で開始されて以来対地拡張が進められ,58年度末には113対地との間で利用可能となっている。
また,国際ダイヤル通話ができる電話機は,従来電電公社の電子交換機(DEX)に収容されている電話機と電電公社のクロスバ交換機に収容されているプッシュホンで国際電電に利用登録を行ったものに限られていたが,59年3月から,東京,大阪等全国主要17都市及び成田(新東京国際空港局)においては,電電公社がクロスバ交換機に付加した発信番号送出機能(ID機能)を利用して,クロスパ交換機収容の回転ダイヤル式電話機からも国際ダイヤル通話を利用できるようになった。
このような国内利用地域の拡大,対地拡張,52年の小刻み課金制(6秒毎に課金)の導入及び57年の料金.改定(番号通話と国際ダイヤル通話に料金格差を設ける。)により,国際ダイヤル通話の利用は大幅に増加しており,58年度末において,国際通話の発信に占める割合は61.9%に達している(第2-2-15表参照)。
なお,国際通話が利用できる電話機は加入電話,国際電電営業窓口及び国際電電委託局(公社局等)に限られていたが,59年3月から一部のカード公衆電話からも国際通話がかけられるようになった。
(4) 国際専用回線
国際専用回線は,特定の地点相互間で多量の通信を行う企業や公共機関等に適したサービスであり,その種類には,テイタイプ通信を行うための電信級回線(12,5b/s,25b/s,50b/s,75b/s,100b/s,200b/s, 1,200b/s)と電話,ファクシミリ,テレプリンタ等を交互又は同時に組み合わせて使用することができる音声級回線がある。
国際専用回線の料金は,国際電話や国際加入電信の従量料金制とは異なり,通信量に関係ない定額料金制(月額)となっていることから,通信量が多いほど割安なものとなる。
58年度末の国際専用回線の利用状況(国際特定通信回線等を含む。)は,回線数で電信級回線575回線,音声級回線299回線となっており,前年度末に対して電信級は30回線の減,音声級は62回線の増となっている(第2-2-16図参照)。
(5) 国際テレビジョン伝送
国際テレビジョン伝送は,通信衛星を経由してテレビジョン画像を伝送するサービスでNHK及び民間放送各社が利用しており,世界の主要な出来事がテレビジョンを通して放映されている。
本サービスは,通信衛星の出現によって初めて商用に供されたもので,伝送の種類には,スポーツ番組や首相の各国歴訪等のニュースを臨時に伝送する随時伝送,毎日一定の時間帯に時事ニュース等を伝送する定時伝送及び59年4月からサービスを開始した,一定の期間1日24時間フルタイムベースで番組等を伝送する長期サービスがある。
その取扱数は,近年の国際交流の活発化等に伴って,第2-2-17図に示すとおり大幅に増加しており,今後もこの傾向は続くものと思われる。
58年度における取扱数は,送受信合わせて4,607度で前年度の3,593度に対して28.2%の増となっている。
国際テレビジョン伝送の取扱対地は,世界各地に新しい地球局が次々に建設されたことに伴って逐次拡張され,58年度末には84対地となっている。
料金は,随時伝送,定時伝送及び長期サービスに分けて定められており,それぞれ全対地均一料金になっている。
(6) 国際ファクシミリ電報
国際ファクシミリ電報は,47年12月に世界に先.駆けて開始されたサービスで,国際間の伝送に高速のファクシミリ装置を使用して発信紙に記載された文字や図表等をそのまま再現し,その受信記録紙を受取人に送達するサービスであり,国際電報や国際加入電信では送ることができない日本字や手書き文あるいは図表等を送りたいとき手軽に利用できるサービスである。
取扱対地については,従来米国本土等4対地に限られていたが,57年1月以降大幅に対地拡張され,58年度末には21対地との間で取り扱われている。
(7) その他のサービス
データ通信に属さない公衆電気通信サービスであって,国際電電の提供しているサービスとしては,上記以外に次のようなものがある。
海事衛星通信,国際無線電報,国際無線テレックス,国際写真電報,国際航空業務報,国際放送電報,国際無線電話通話,国際航空無線電話通話,国際音声放送伝送,国際デーテル,国際プレス・ブレティンサービス
(8)国際通信料金の改定
国際電電は,これまで数次にわたり国際通信料金の改定を行ってきたが,さらに59年4月1日にも料金改定を行った。
今回の料金改定は,国民生活,経済活動に影響が大きい国際通話,国際専用回線(国際特定通信回線を含む。)を重点とするとともに,国際加入電信,国際テレビジョン伝送等を含め,ほぼ国際通信全般にわたり値下げを行ったものであり,その概要は次のとおりである。
ア.国際通話
アジア,北米,太洋州の近隣地域に重点を置き,160対地を対象に料金値下げを行った。
(ア)番号通話料金制導入49対地の番号通話について3〜8%,また,44
対地の指名通話について1〜8%の値下げ
(イ)国際ダイヤル通話が可能な42対地を対象に2〜8%の値下げ
(ウ)夜間及び日曜に係る割引制度を国際ダイヤル通話が可能な全対地に拡
大するとともに,新たに深夜(23時〜5時)割引を設け,夜間(20時〜 23時,5時〜8時)・日曜(5時〜23時)10%,深夜20%の割引をする
(エ)番号通話料金制未導入39対地を対象に3〜8%の値下げなお,主要対地向け改定料金は,第2-2-18表のとおりである。
イ.国際加入電信
全取扱地域を対象に3〜7%の値下げを行った。主要対地向け改定料金は,第2-2-19表のとおりである。
ウ.国際専用回線
全取扱地域を対象に電信級5〜40%,音声級9〜28%の値下げを行った。主要対地向け改定料金は,第2-2-20表のとおりである。
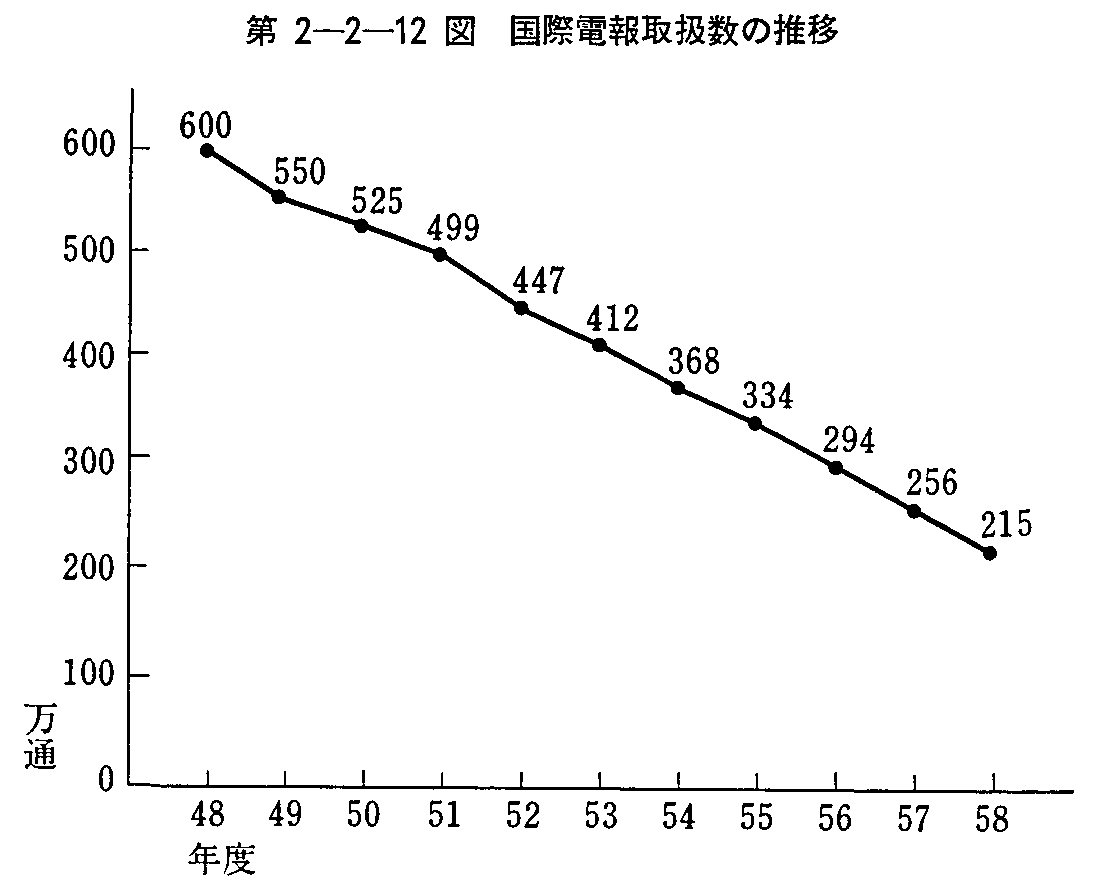
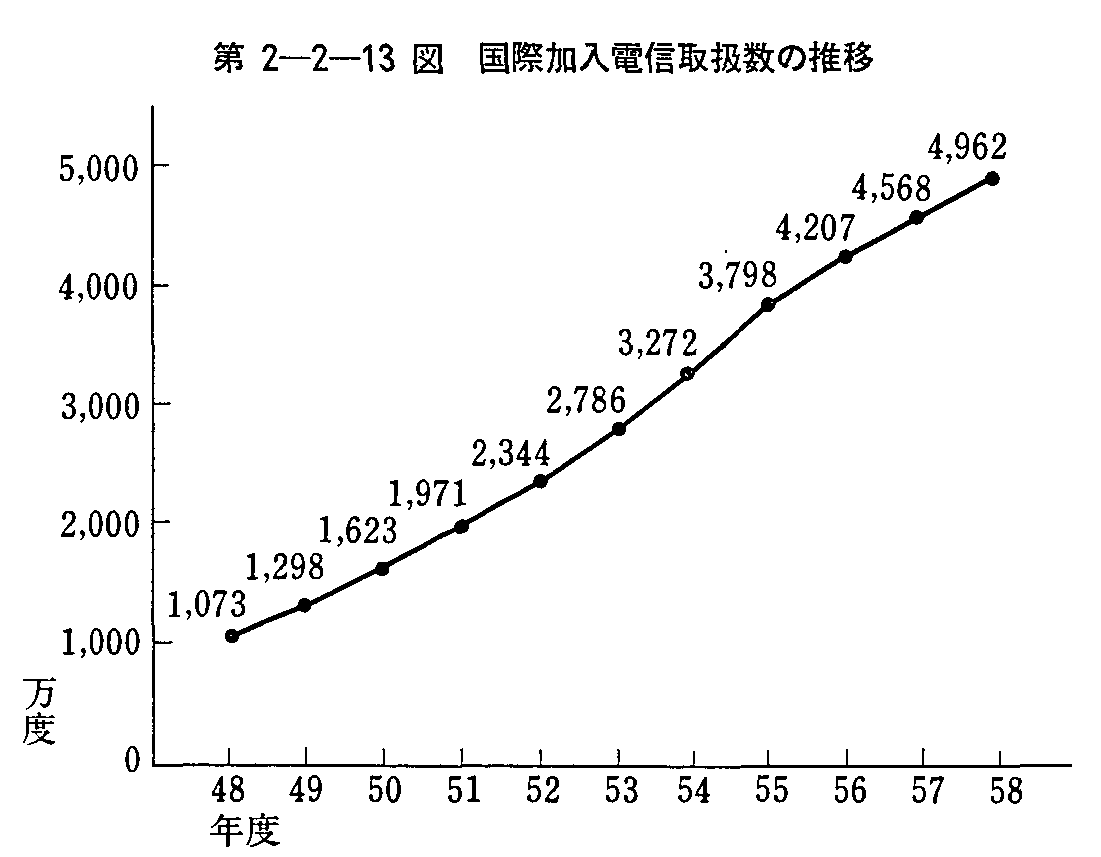
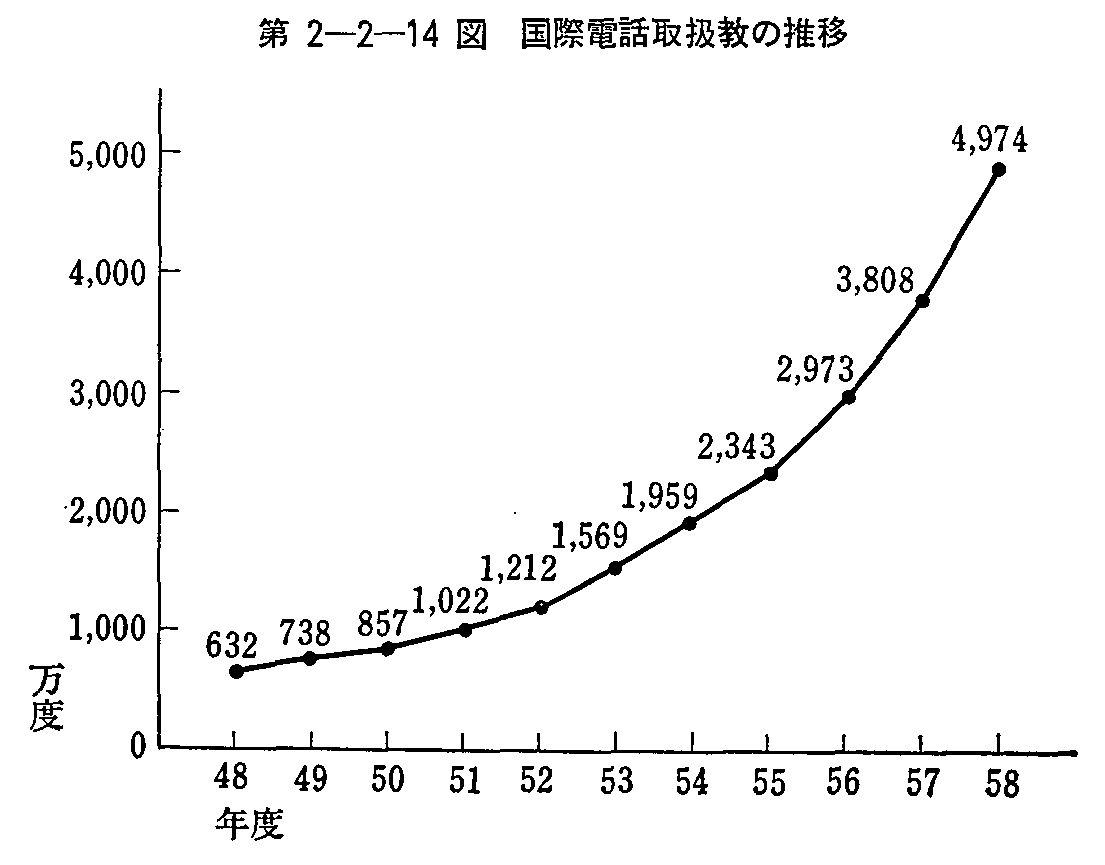
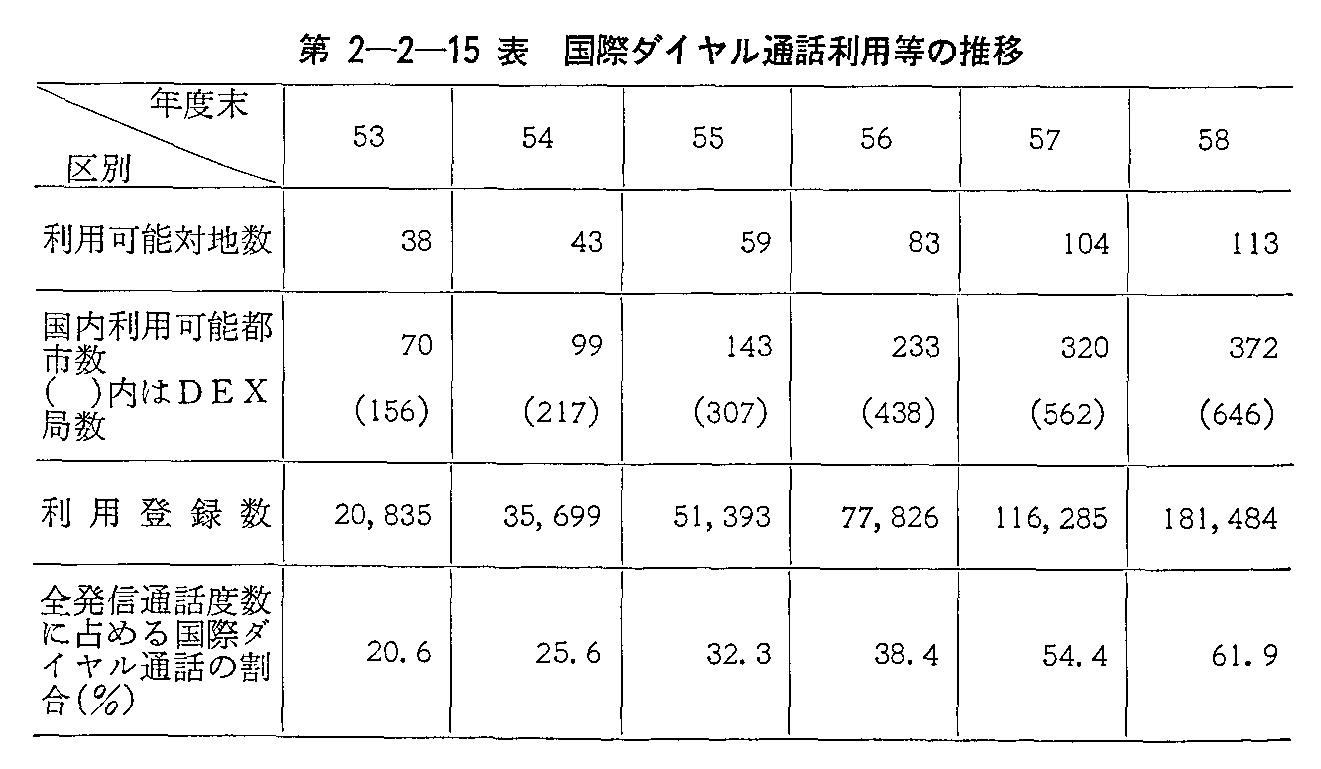
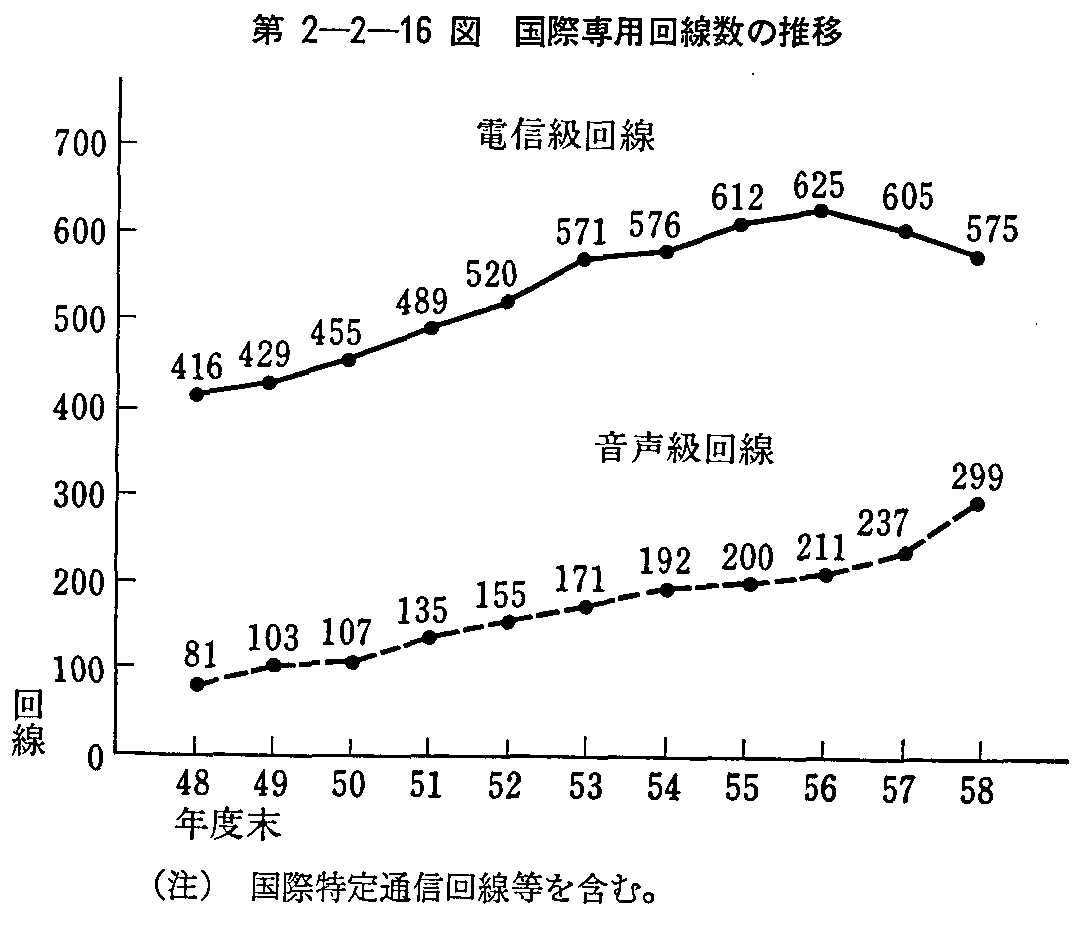
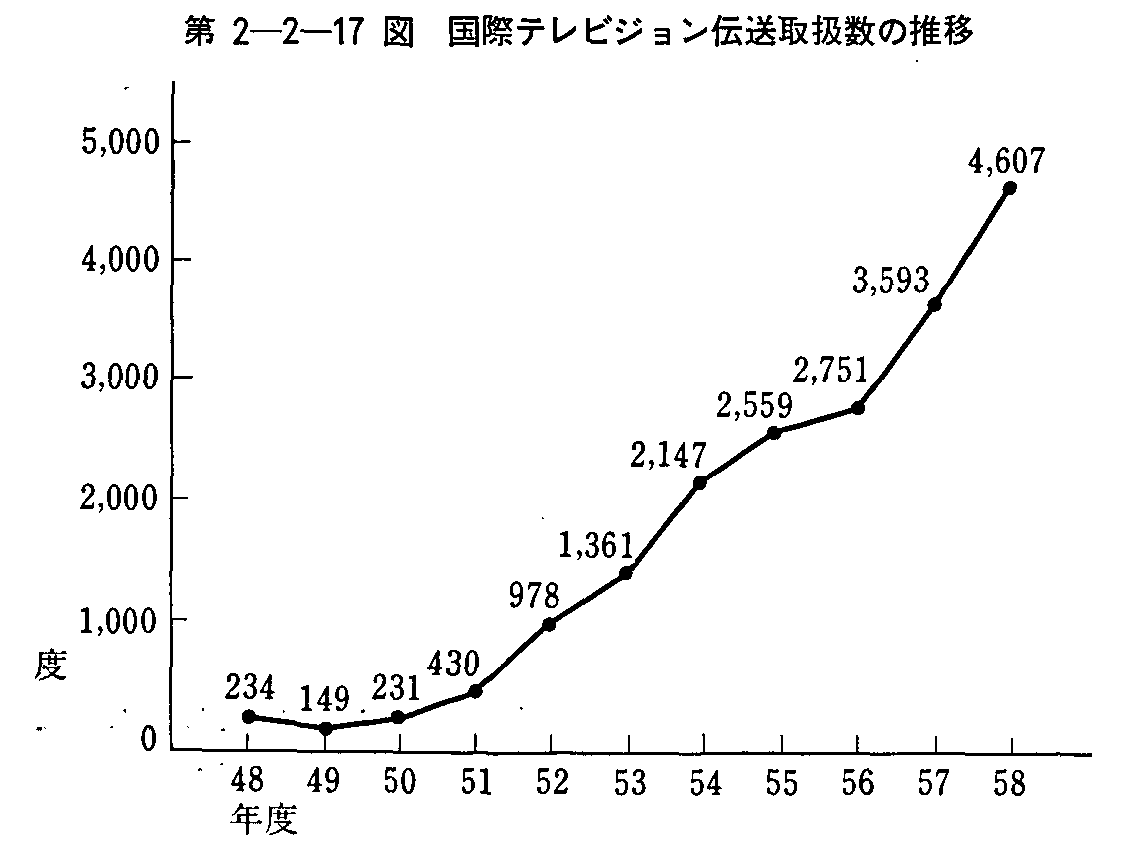
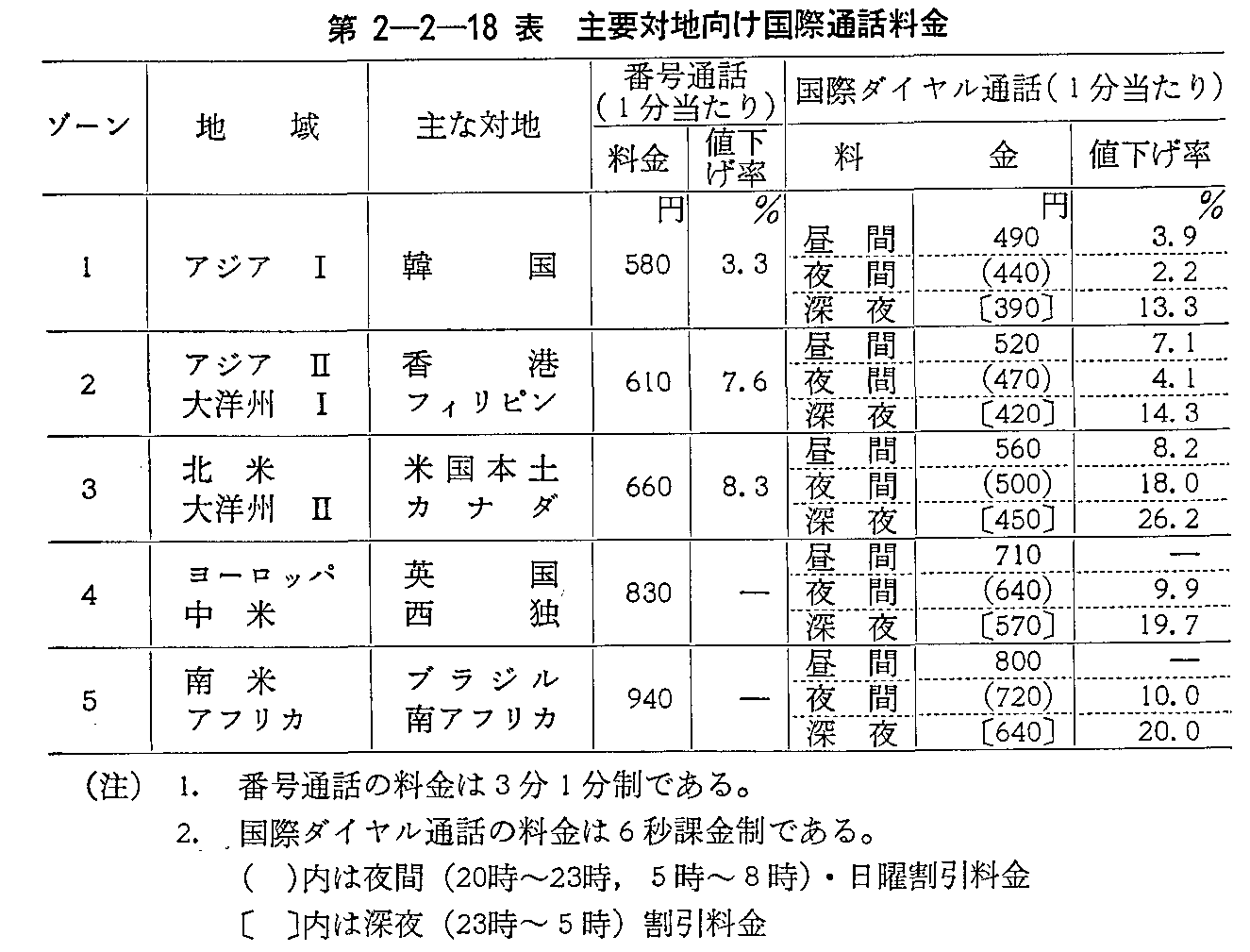
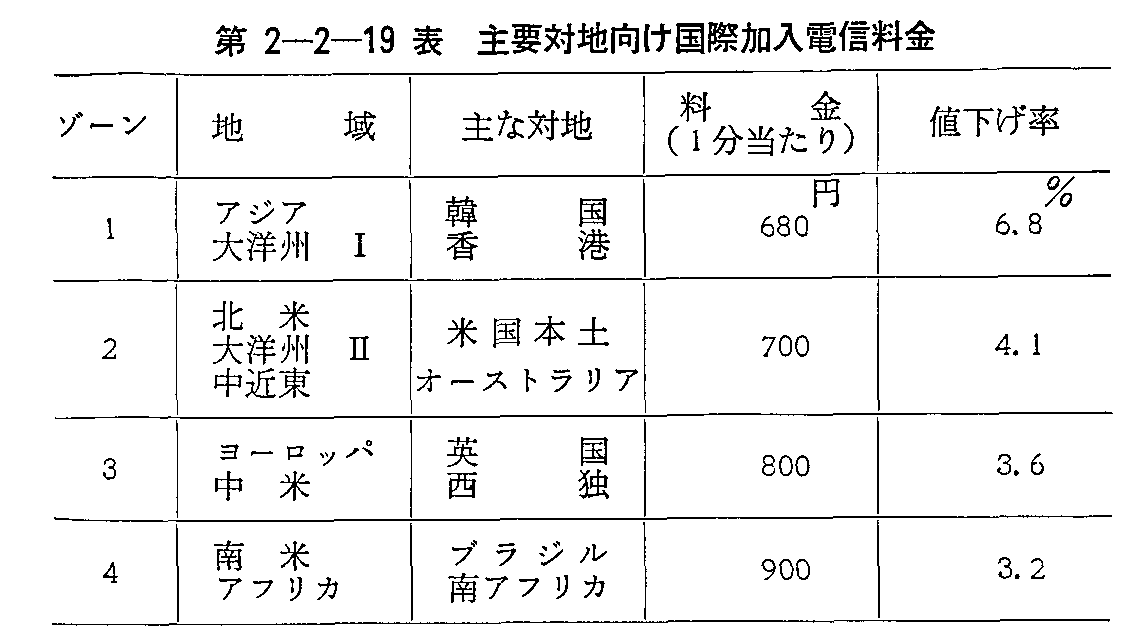
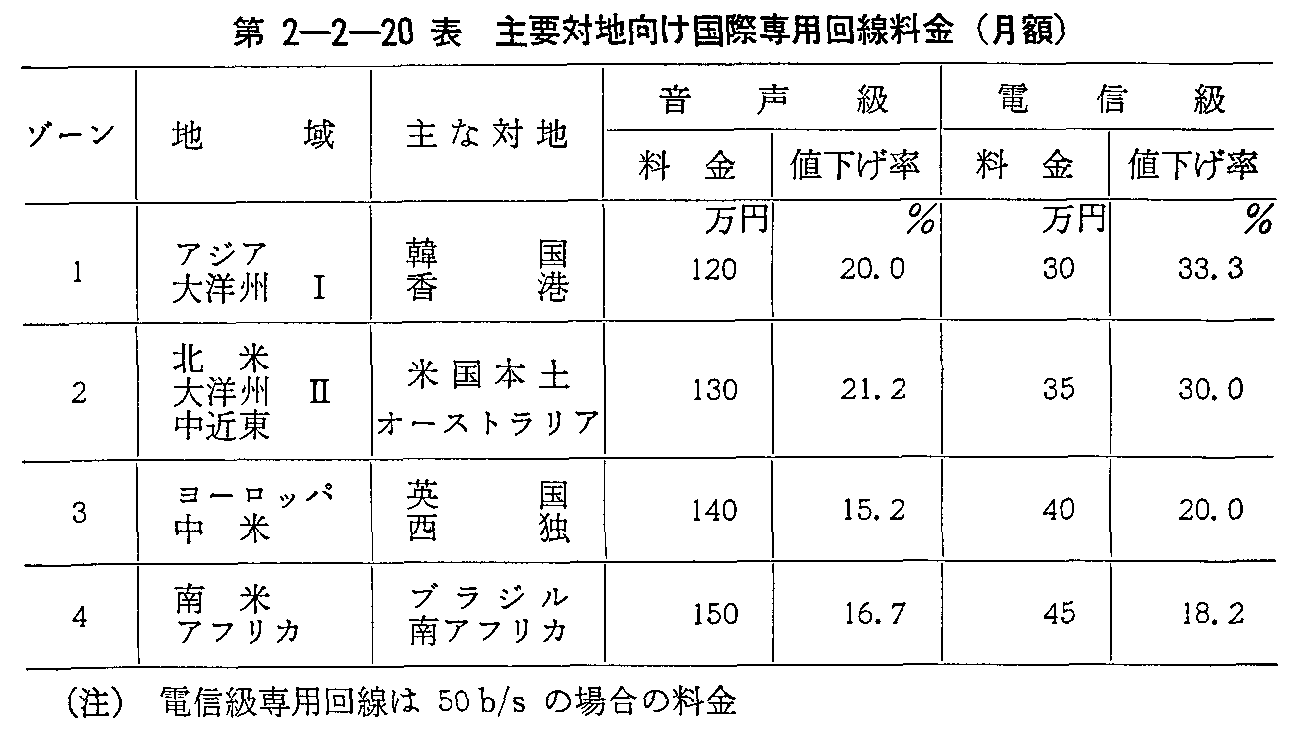
|