 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第3節 通信新時代の構築に向けて
1 高度化・多様化する通信メディア
これまで述べてきたように,情報化の進展と技術革新を背景に,次々と新しい通信メディアの実用化ないしは実用化に向けての研究開発が進められている。このような状況にある現代は,ニューメディア時代とも呼ばれているが,その主な特徴としては,第1に,情報ニーズがますます高度化・多様化し,新しいメディアに対する国民・利用者の二ーズもますます高度で多様なものになっていること,第2に,新しい通信メディアが,従来の郵便,電気通信,放送といった既存メディアの境界領域に登場するというメディアの融合現象がみられること,第3に,通信メディアがネットワークで結ばれ,ますます大規模化していることなどが挙げられる。
(1)多様な情報ニーズ
近年,就業構造の変化,都市化の進展,所得水準の上昇,教育レベルの向上,余暇時間の増大等の様々な社会経済情勢の変化を背景に,人々の意識・価値観が多様化してきている。
第1-2-34表は,テレビ視聴率の変化をみたものであるが,視聴率15.1%以上の高視聴率番組の割合は,52年の2.9%が,58年には1.0%に低下してきており,番組選択が分散し,多様化してきていることがうかがえる。
一方,第1-2-35図は,日常の家庭生活において関心のある情報及び今後得たい情報の種類について調査したものであるが,「一般ニュース」に対する二ーズは相変らず高いものの,生活の質の向上や多様な豊かさを求める今日の傾向を背景に,「健康・医療情報」,「教育・学習」等,マス・メディア主体の情報提供では十分対応しきれない個別的分野での情報ニーズが高まっていくことがわかる。こうしたニーズの動向を考えると,今後各種ニューメディアが実用化されるにつれ,各人が選択的・主体的に情報を入手できるリクエスト型メディア
電気通信系メディア相互間では現在のテレビジョン放送の音声信号のほかに,別の音声信号を重畳して,二か国語放送,ステレオ放送等を可能とする音声多重放送,電話の双方向性に映像を取り入れ,テレビジョン画面を見ながら隔たった地点相互間で会議を進めるテレビ会議等が登場している。
マスコミ系とパーソナル系の間では,電話の双方向性に映像を取り入れ会話形式で映像情報を検索するキャプテン,テレビジョンに双方向機能を取り入れ視聴者応答サービス等を行う双方向CATV等が登場している。
このような融合は今後も一層促進されるものと予想されるが,これらの新しいメディアは,その性質上既存メディアと類似の機能を有しているため,既存メディアとの間あるいは他の新しいメディアとの間で新たな競合が生じつつある。このような状況は利用者のメディア選択の幅を広げ利用者利益の完成し,郵便貯金,郵便為替,郵便振替等の国民生活に密着した金融サービスが,この大規模ネットワークにより提供されている。さらに,金融機関と企業,家庭等外部とを接続するファームバンキング,ホームバンキングについて検討が進められており,既に一部実施されている。
また,販売・流通業界においては,クレジットカードによるショッピングデータの交換を行うCAFISシステム(Credit And Finance Information Switching System:クレジット情報データ通信システム)の導入が進められているほか,消費動向の早期把握による商品戦略の樹立を可能とするためのPOS(Point Of Sales:販売時点情報管理システム)のシステム化やこうしたシステムと代金の支払とを一体化したシステムについて検討されている。
このような企業間ネットワーク化の急速な動きの要因として,安定経済成長下になってデータ通信を企業間の取引活動等に利用することにより,企業活動全体としての一層の合理化・効率化を図る必要性が広く認められてきていることが挙げられる。また,データ通信を将来性の高いビジネスチャンスと考え,データ通信を用いた企業間ネットワークを基盤として,既存のサービスをより充実した形で提供したり,あるいは,従来にない新しいサービスを展開するといった多様な利用方法が着実に検討されるようになってきていることが挙げられる。
一方,企業間ネットワーク化の要因として,異機種コンピュータ間,異種システム間の通信を可能とするインタフェイス技術の進歩が挙げられる。インタフェイス技術の向上により,システム間接続によるデータ通信ネットワークの大規模化及び複数のネットワークの併存が可能となっている。また,57年10月のデータ処理のための回線利用の自由化の中で,いわゆる中小企業VANサービスが制度化されたように,企業間接続をサービスとする電気通信事業に民間企業が参入できるようになったことも,ネットワーク化の機運の高まりに対して一つの契機となったといえるであろう。
このようなデータ通信に対するニーズの増大及び技術の進展等があいまって,データ通信ネットワーク化に対する要請が高まっており,あらゆる業務,業界分野においてネットワーク化の検討,推進が行われていくものと予想される。
また,データ通信システムのネットワーク化の進展と並行して,ファクシミリ通信やビデオテックス等の新しい通信メディアについても,そのネットワークの形成がみられるとともに,CATVについても大規模化,双方向化の動きがあり,これらの通信メディアについてもネットワーク化の進展が予想される。
今後,電気通信ネットワークは,各通信メディアのネットワークの高度化・複合化の様相をみせつつ,多層的なトータルネットワークの形成に向けて発展していくことが期待されている。
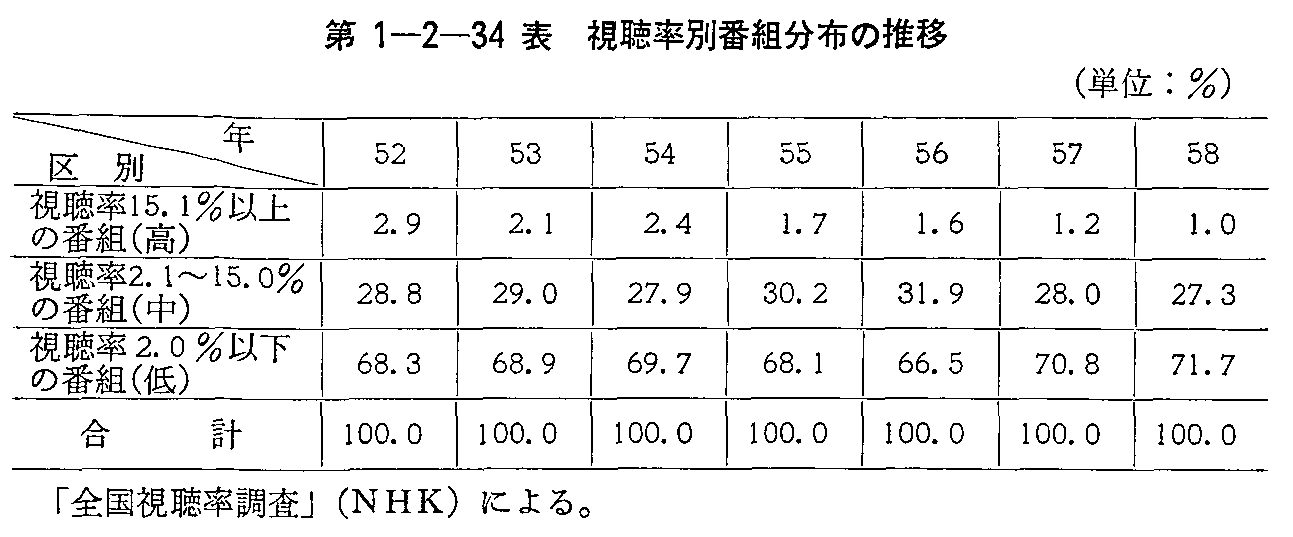
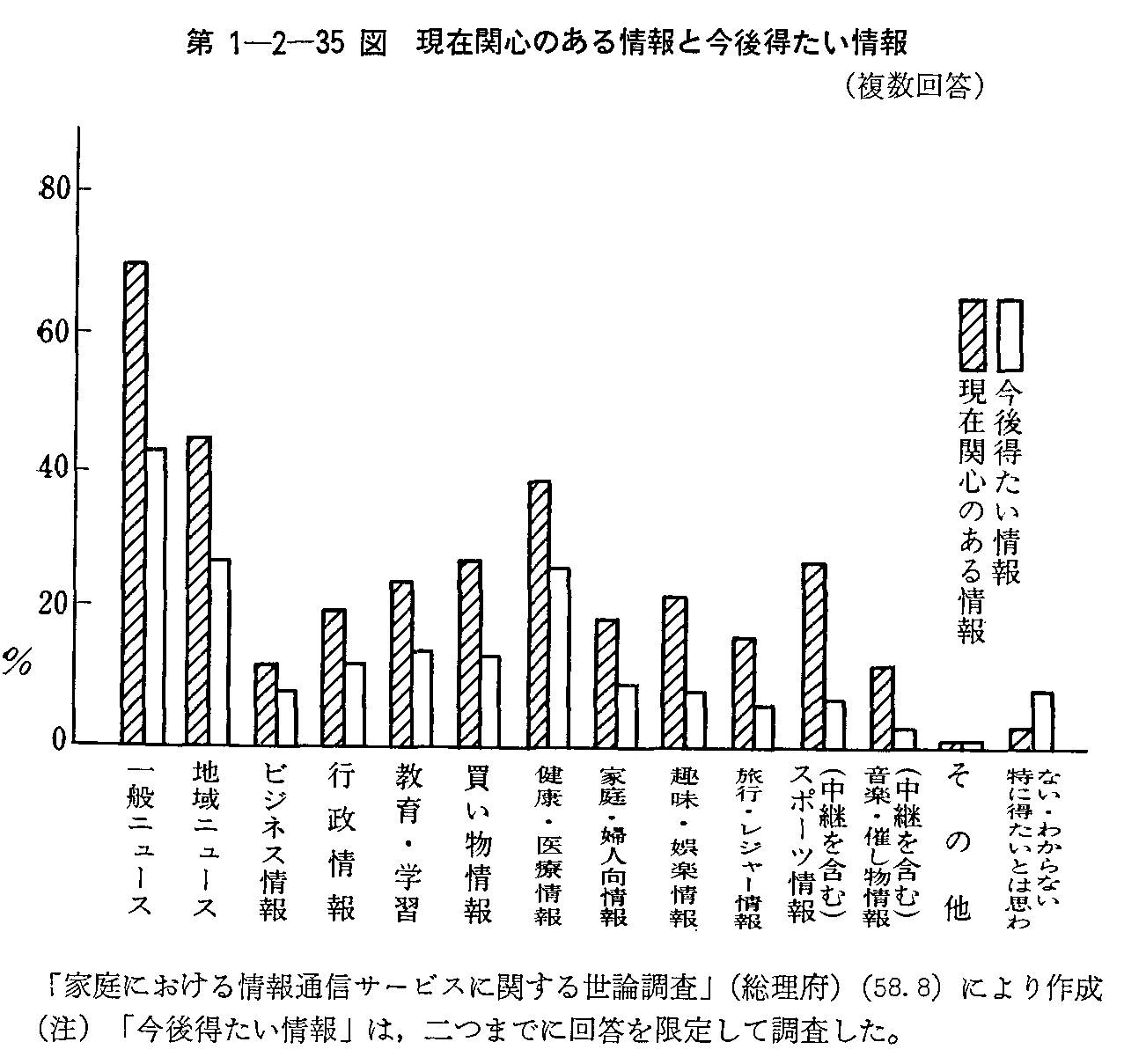
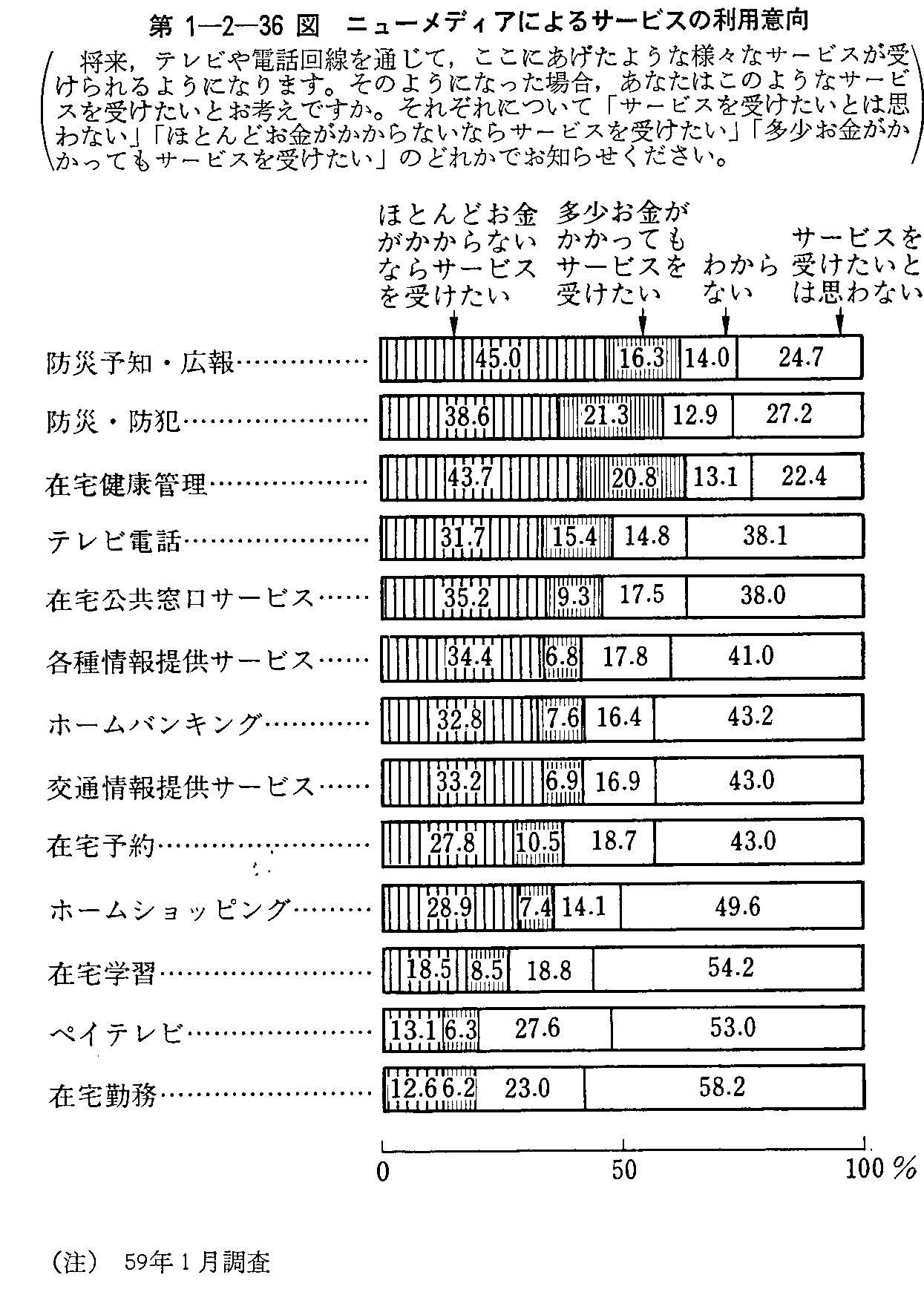
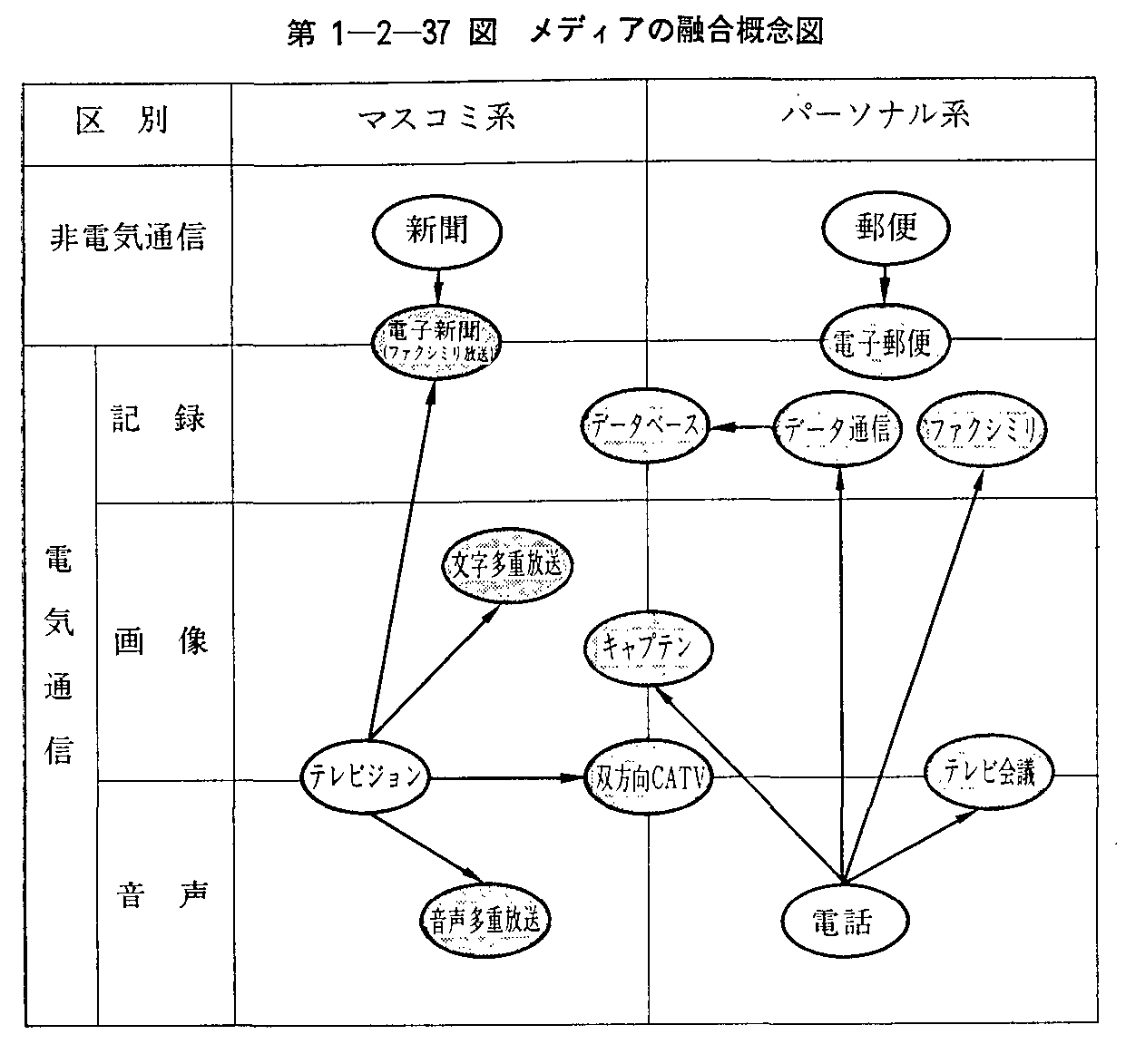
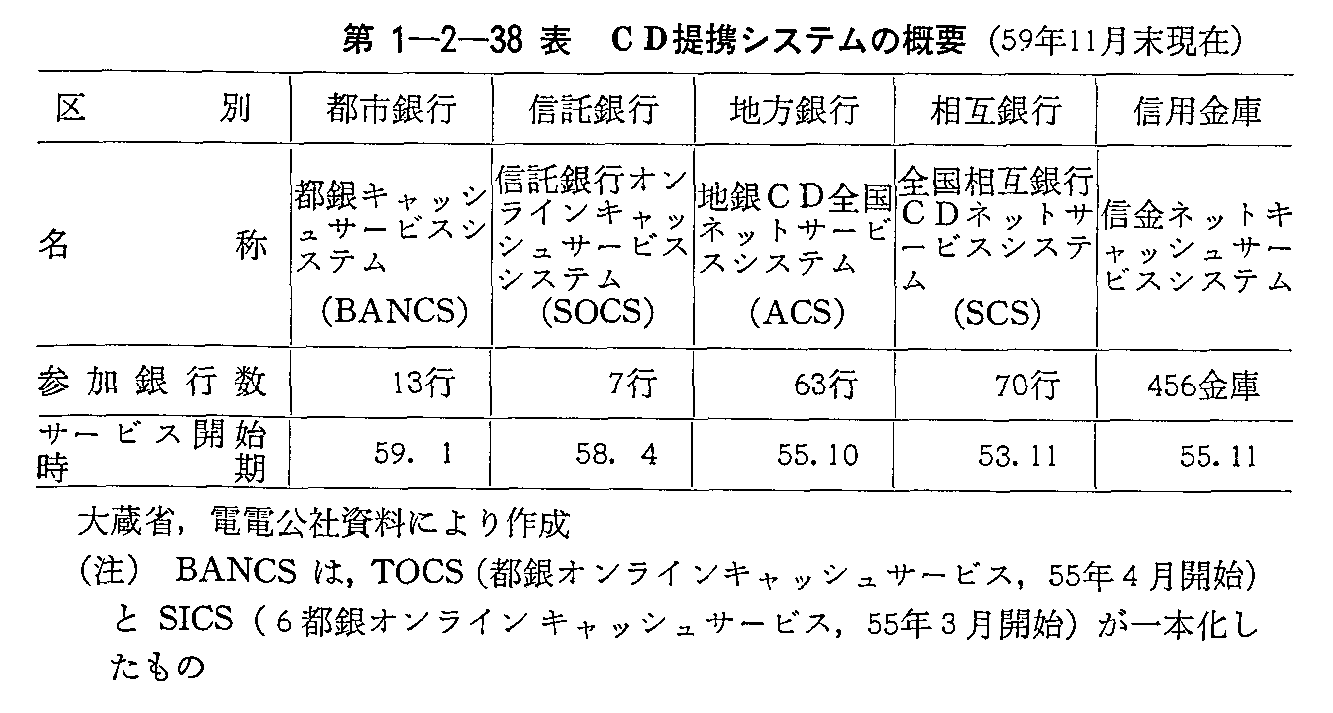
|