 第1部 総論
 第1節 昭和58年度の通信の動向  第2節 情報化の動向
 第2章 通信新時代の構築
 第1節 社会経済の発展と通信  第3節 通信新時代の構築に向けて
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数管理及び無線従事者
 第1節 周波数管理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第5節 有線伝送及び交換技術  第6節 データ通信システム  第7節 画像通信システム  第8節 その他の技術及びシステム
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 通信・放送分野における国際協力の実績
(1) 概 況
国際協力を大別すると,研修員の受入れ,専門家の派遣等を行う技術協力と開発プロジェクトに対して資金を供与する資金協力との二つに分けられる。技術協力は,開発途上国に対し技術を普及させ,またはその国の技術水準を向上させることを目的とする援助のことであり,資金協力と異なり,人を媒体として実施されることから,開発途上国の国づくりのための人づくりに貢献するほか,国民相互の理解を深めるのに役立つという特徴を有する。
この技術協力の形態としては,研修員の受入れ,専門家の派遣,開発調査の実施,海外技術協力センタの設置,運営に対する協力等かあり,これら政府ベースの技術協力は,主として国際協力事業団(JICA)を通じて実施されている。
研修員の受入れは,開発途上国の通信・放送関係技術者等を我が国に受け入れて,我が国の進んだ技術を習得させるもので,58年度においては446名の研修員を受け入れている。
次に,専門家の派遣は,開発途上国へ通信・放送の専門家を派遣して,現地で職員の訓練,通信・放送施設の建設,保守及び運用面の指導,開発計画の企画,助言等を行うもので,58年度においては,186名の専門家を派遣している。
開発調査は,開発途上国の通信・放送関係の開発計画について調査団を編成し,現地作業及び国内作業を行って,その計画の実現に協力するもので,58年度において実施した開発調査は,13件122名の専門家がこれに参加している。
海外技術協力センタは,開発途上国における通信・放送関係の技術者,人材の養成,技術の研究開発等を行うために現地に設置されるもので,我が国は,このセンタに対し,専門家の派遣,機材の供与,相手国のカウンターパートに対する研修実施等を通じて協力を行っている。58年度は,7か国8センタに対し93名の専門家を派遣するとともに,59名のカウンターパートを受け入れている。
次に,資金協力であるが,その主要な形態には有償資金協力(円借款)と無償資金協力がある。58年度においては,3か国6件の電気通信プロジェクトに対し,約252億円の円借款が,1か国1件の放送プロジェクトに対し,約13億円の無償資金協力が約束された。
(2) 技術協力
ア.研修員の受入れ
研修員の受入れ方式には,大別して集団研修と個別研修とがある。集団研修は,開発途上国の多くに共通してニーズの高い分野を選定し,あらかじめ研修コースを設定し,集団的に研修を実施するもので,58年度においては郵政省関係コースで335名を受け入れている。個別研修は,開発途上国から個々に要請される専門分野について研修を行うもので,郵政省関係では,58年度においては111名を受け入れている。個別研修には,単発要請,特定地域あるいは特定国を対象とする特設コースへの参加,カウンターパートの受入れ,UPU,ITU等の国際機関からの要請による受入れが含まれる。研修対象者は,開発途上国の政府機関,公共機関及び民間の通信・放送関係で活躍する技術者,行政官,研究者等で,当該国政府から推薦されたものである。
(ア)郵便,貯金関係
郵便分野における研修員の受入れは,郵政幹部セミナの開催と個別研修員の受入れにより38年度から実施しており,58年度までに合計256名を受け入れている。58年度は,アジア,中近東及びアフリカ地域を対象とする郵政幹部セミナを開催し,地域内に共通する国際郵便業務の問題とその解決策をテーマとして討議を行ったが,このセミナには,16か国から16名が参加した。
APPU職員交換計画では,58年度には13名を受け入れ,58年度までに合計162名となった。
(イ)電気通信関係
電気通信分野における研修員の受入れは,我が国が29年にコロンボプランに加盟するとともに開始され,58年度までに受け入れた研修員の総数は,アジア・大洋州地域で1,504名,中近東・アフリカ地域で936名,中南米地域で981名,UNDP/ITU計画で224名,APT計画で20名,その他262名,計3,927名に達している。
58年度において我が国は,アジア・大洋州地域で107名,中近東・アフリカ地域で86名,中南米地域で69名,ITU,APT等国際機関計画で19名,その他23名,計304名(集団229名,個別75名)の研修員を受け入れている。
電気通信関係の研修は,当初,開発途上国の個々の要請に基づき,個別研修として実施されていたが,37年度に集団研修コースを創設して以来,コースの拡大・強化を進め,58年度においては,第2―8―9表のとおり,15コースを実施した。
また,58年度に個別研修員として受け入れた75名の内訳は,交換機5か国9名,通話品質改善5か国5名,搬送技術3か国5名,衛星通信技術4か国7名,ケーブル関係3か国7名,電気通信事情視察5か国7名,その他6か国12名と,中国から科学技術の現状調査団23名の受入れである。
(ウ)電波・放送関係
電波・放送分野における我が国の研修員の受入れは,58年度までにアジア・大洋州地域で794名,中近東・アフリカ地域で388名,中南米地域で239名,ITU等の国連計画で29名,その他25名,計1,475名に達しており,58年度において,アジア・大洋州地域で63名,中近東・アフリカ地域で26名,中南米地域で24名,計113名(集団90名,個別23名)の研修員を受け入れた。
我が国は,36年度から開発途上国の個々の要請に基づき,研修可能な分野について個別研修員として受け入れていたが,38年度にテレビジョン放送管理,教育テレビジョン番組及びテレビジョン放送技術の3集団研修コースを創設して以来,コースの拡大・強化を進め,58年度においては,第2―8―10表のとおり,7コースの集団研修を実施した。
また,58年度において個別研修員として受け入れた23名の内訳は,テレビ番組4か国9名,テレビスタジオ技術3か国5名,ラジオ・テレビ総合開発計画1か国3名,放送事情視察2か国2名,その他3か国4名となっている。
(エ)第三国研修の実施
第三国研修は,我が国が特定の開発途上国で協力しているプロジェクトや技術訓練センタに,生活環境の類似した近隣諸国から研修員を受け入れて,技術移転を効率的に実施する現地研修方式である。
58年度は,メキシコ,タイ,フィジー,ペルー及びアジア太平洋放送開発研究所(AIBD:Asia Pacific lnstitute for Broadcasting Development,在マレイシア)において電気通信及び放送分野の研修を実施した。
[1] メキシコにおける第三国研修(伝送無線技術コース)〔第8回〕(58.9.26〜12.2)
メキシコ通信運輸省附属電気通信学園において,伝送無線技術,ルーラル電話方式,マイクロ波回線設計,マイクロ波伝搬理論等の知識及び技術を習得させることを目的として実施し,9か国22名が参加した。
[2] タイにおける第三国研修(電気通信技術コース)〔第7回〕(59,1.11〜3.14)
タイ政府と合同で,モンクット王工科大学において,ディジタルファクシミリ,電子テレタイプ及びディジタル交換方式の知識及び技術を習得させることを目的として実施し,8か国16名が参加した。
[3] フィジーにおける第三国研修(電気通信の地域研修コース)〔第1回〕(58,10.31〜12.9)
フィジー通信公共事業省附属電気通信訓練センタにおいて,電話交換,電話線路,無線通信,衛星通信及び保全システムの知識及び技術を習得させることを目的として実施し,11か国21名が参加した。
[4] ペルーにおける第三国研修(ディジタル通信技術コース)〔第1回〕(58,11.28〜12.16)
ペルー運輸通信省附属電気通信訓練センタにおいて,ディジタル通信網,ディジタル交換,ディジタル伝送等の知識及び技術を習得させることを目的として実施し,11か国23名が参加した。
[5] AIBDにおける第三国研修(ENG(Electronic News Gathering)技術の地域研修コース)〔第1回〕(59.2.7〜3.17)
AIBDにおいて,ENG/EFP(Electronic Field Production)機器の保守と運用の知識及び技術を習得させることを目的として実施し,9か国15名が参加した。
(オ)帰国研修員巡回指導
帰国研修員に対するフォローアップ事業の一環として,その所属機関等を訪問して,当該研修コースの効果測定,問題点及びニーズの把握,新技術の紹介等を行うことを目的として,58年度においては,2チームを派遣した(第2―8―11表参照)。
イ.専門家の派遣
専門家の派遣は,開発途上国の郵便・通信・放送関係の主管庁,事業運営体,研究機関,教育訓練機関等へ専門家を派遣し,郵便・通信・放送開発計画の企画・助言,施設の建設,保守,運用面の指導,職員の訓練,第三国研修における講義等を行うことにより開発途上国の人材育成に貢献することを目的としている。
(ア)郵便関係
郵便専門家の派遣は,JICAベースによるものとしては,50年度から開始され,58年度末までにアジア・大洋州地域へ54名,中近東・アフリカ地域へ8名,中南米地域へ8名,国際機関へ1名,計71名の専門家を派遣し,また,APPU職員交換ベースにより163名,UNDP/UPUベースにより25名,UPU基金ベースにより1名,海外経済協力基金(OECF)ベースにより2名派遣しており,合計262名の専門家を派遣した。
58年度の郵便専門家派遣実績については,前年度から継続のものを含めて,第2―8―12表のとおりである。
(イ)電気通信関係
電気通信専門家の派遣は,35年度から開始され,58年度末までにJICAベースによるものとして,アジア・大洋州地域へ388名,中近東・アフリカ地域へ268名,中南米地域へ357名,国際機関等へ36名派遣し,また,UNDP/ITUベースにより262名,ESCAPベースにより2名,APTべースにより6名派遣しており,計1,319名の専門家を派遣した。
これらの電気通信専門家は,主として,電話交換,マイクロウェーブ,通信網計画,電話線路,電話伝送,衛星通信等の分野において,開発途上国の技術者の育成及び電気通信開発プロジェクトの円滑な推進のために協力を行っているが,近年の傾向として電気通信網計画の指導助言を行う政策顧問的な業務も増加しているとともに,電気通信分野の第三国研修の講師としても協力を行っている。
58年度の電気通信専門家派遣実績については,前年度から継続のものを含めて,第2―8―13表のとおりである。
(ウ)電波・放送関係
電波・放送関係の専門家派遣は,電気通信関係と同じく35年度から開始され,既に20年余を経ているが,その間,開発途上国の経済,社会,文化の発展に大きく貢献してきた。
58年度末現在における専門家派遣実績は,JICAベースによりアジア・大洋州地域へ372名,中近東・アフリカ地域へ75名,中南米地域へ88名,国際機関等へ27名派遣し,また,UNDP/ITUベースにより7名,ESCAPベースにより4名,計573名の専門家を派遣した。
これらの専門家は,主として開発途上国の放送事業体及び放送主管庁においてテレビジョン放送制作技術,テレビジョン放送番組制作及び放送局の建設計画・運用及び保守について指導・助言,技術者の育成等を行うものであるが,最近は,計画分野における政策顧問的任務も増加しつつある。さらに,放送分野の第三国研修の講師としても協力を行っている。
58年度の電波・放送専門家派遣実績については,前年度からの継続分を含めて,第2―8―14表のとおりである。
ウ.開発調査
(ア)電気通信関係
電気通信分野の開発調査は,37年度にボリヴィアに対して実施したものが最初であるが,その後次第に増加し,58年度の7件(第2―8―15表参照)を加え,同年度末までに合計106件となっている。
しかしながら,開発途上国においても,幹線網等の電気通信施設の整備は進んできており,最近は案件も頭打ちの傾向にある。今後は,各国ともアナログ網からディジタル網に転換していくことから,ディジタル網の導入を内容とする開発調査が増加してくるものと思われる。また,幹線網の整備をうけて,ルーラル地域の電気通信整備の開発調査も増加してくるであろう。
(イ)電波・放送関係
電波・放送分野の開発調査は,41年度に実施したタイのテレビジョン放送網建設計画が最初であり,58年度の6件(第2―8―16表参照)を加えると,同年度末までに合計47件となっている。
放送分野は,無償資金協力の場合が多く,開発調査においては,無償資金協力に結びつく基本設計調査が多くなっている。58年度においても,スリ・ランカの教育テレビスタジオ増設計画とスーダンの地方ラジオ放送網計画は基本設計調査である。
エ.海外技術協力センタ
58年度においては,前年度から継続して協力を行っているタイ・モンクット王工科大学,パキスタン中央電気通信研究所,ペルー電気通信訓練センタ,日本・シンガポールソフトウェア技術研修センタ,パナマ国営教育テレビ放送計画及びフィリピン電気通信訓練センタの6プロジェクトのうち,タイ・モンクット王工科大学への協力が終了し,タイの自主運営に引き継がれたほかは引き続いて協力を行い,また,シンガポール生産性向上プロジェクト及びインドネシアラジオ・テレビ放送訓練センタに対する協力が新たに開始された。
58年度において,これら8プロジェクトに関し,通信・放送分野以外のものも含め,派遣された調査団は7件35名,専門家は93名,我が国に受け入れたカウンターパートは59名,また,我が国が供与した機材総額は3億8,100万円であった。タイ・モンクット王工科大学及び現在協力中の各センタの概況は第2―8―17表のとおりである。
(3) 資金協力
ア.円 借 款
通信・放送分野における円借款は,36年度にパキスタンの電信電話施設拡張計画に対して供与されたことに始まるが,その後,マイクロウェーブ網建設計画,衛星地上局建設計画,放送網拡充計画等多岐にわたり供与されてきている。
58年度は,6件で合計約252億円の供与が行われた(第2―8―18表参照)。最近は,放送関係のプロジェクトに供与されておらず,いずれも通信関係のプロジェクトである。
通信関係のプロジェクトの円借款要請は,アフリカ地域,中南米地域から数多く出されているが,これらの地域の国は,債務救済(リスケジュール)を実施しているため円供款の供与は困難となっている。
イ.無償資金協力
無償資金協力としては,42年度のシンガポール衛星地上局建設,46年度のタイ〜ラオス間マイクロウェーブ回線建設が始まりであり,その後,次第に供与される件数は増加している。
58年度は第2―8―19表のとおり,ビルマのテレビ放送施設拡充計画(57年度の継続案件)のみであるが,これは一時的に件数が減ったものと考えられる。
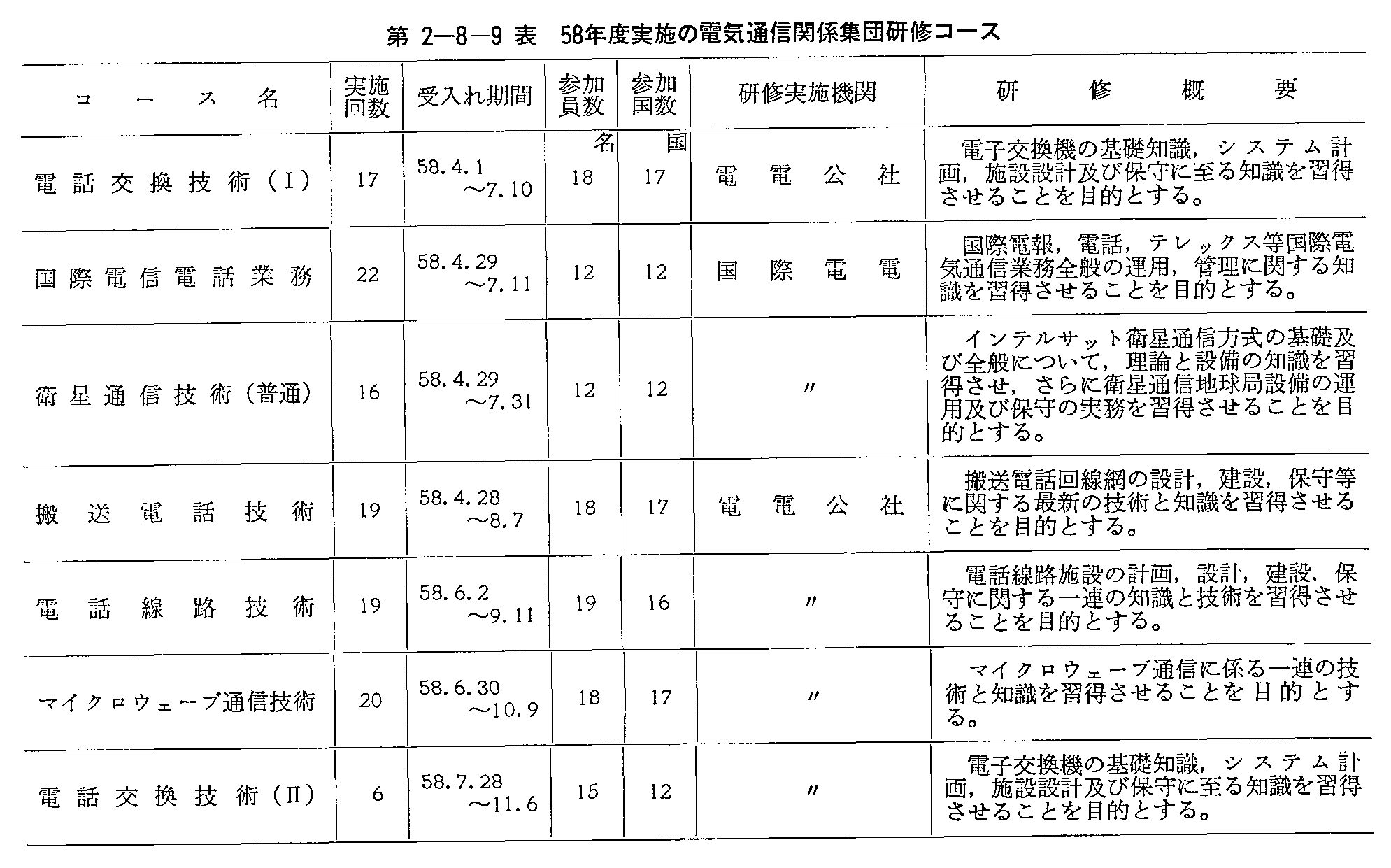
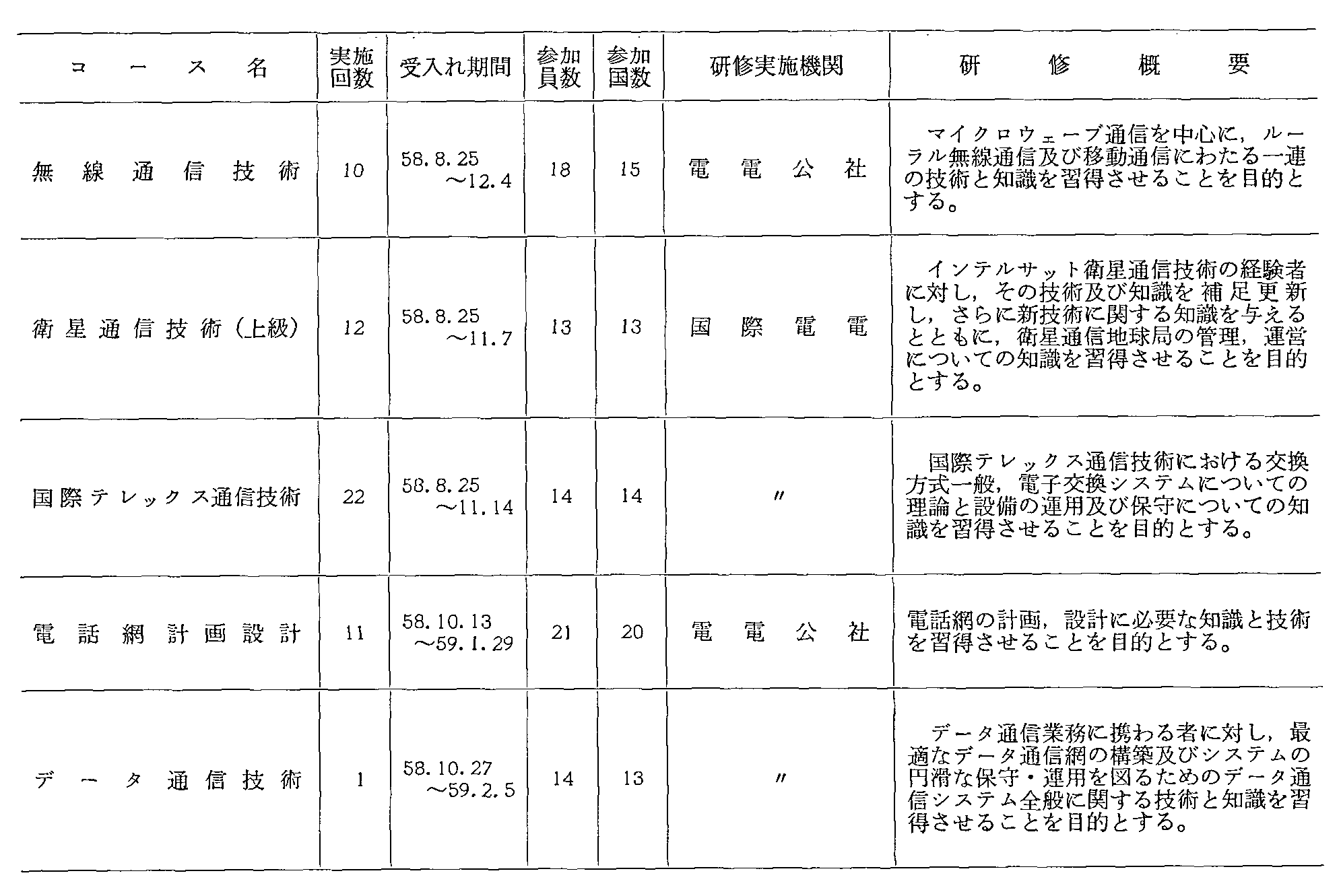
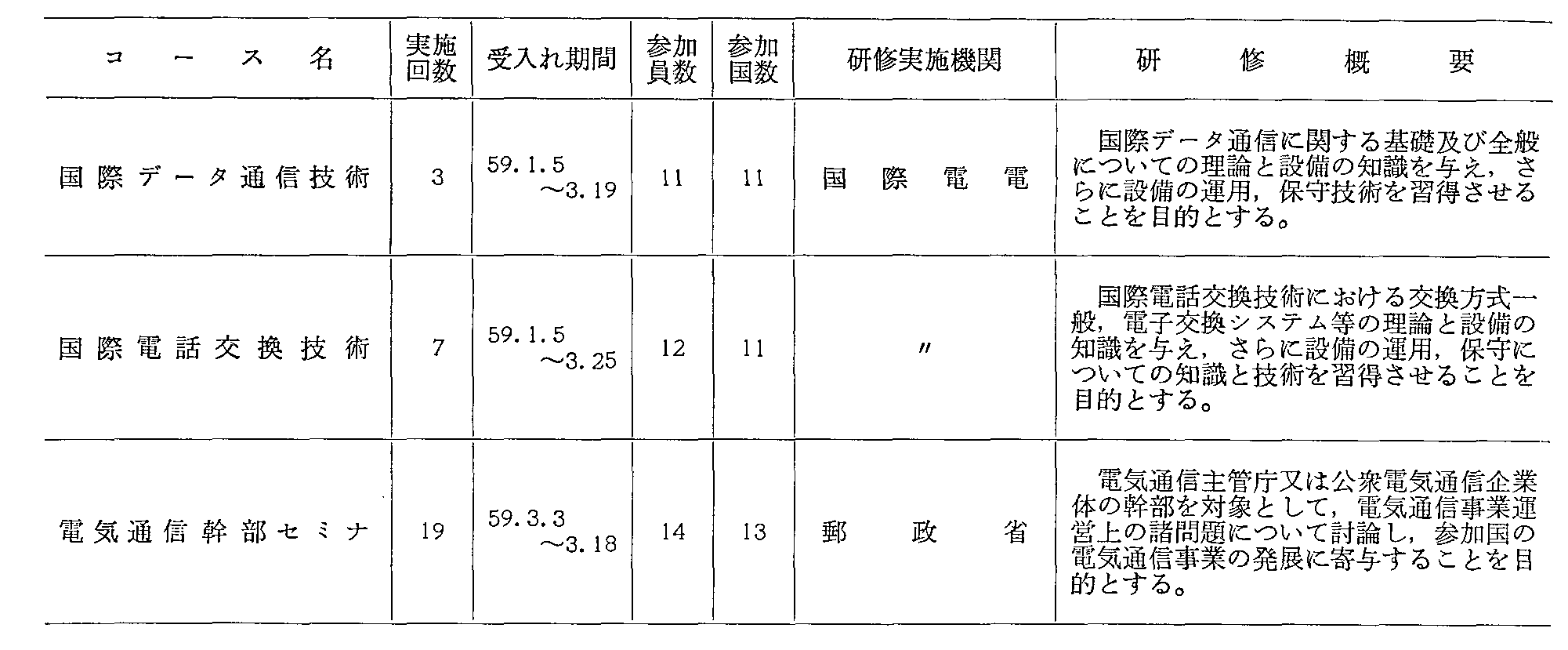
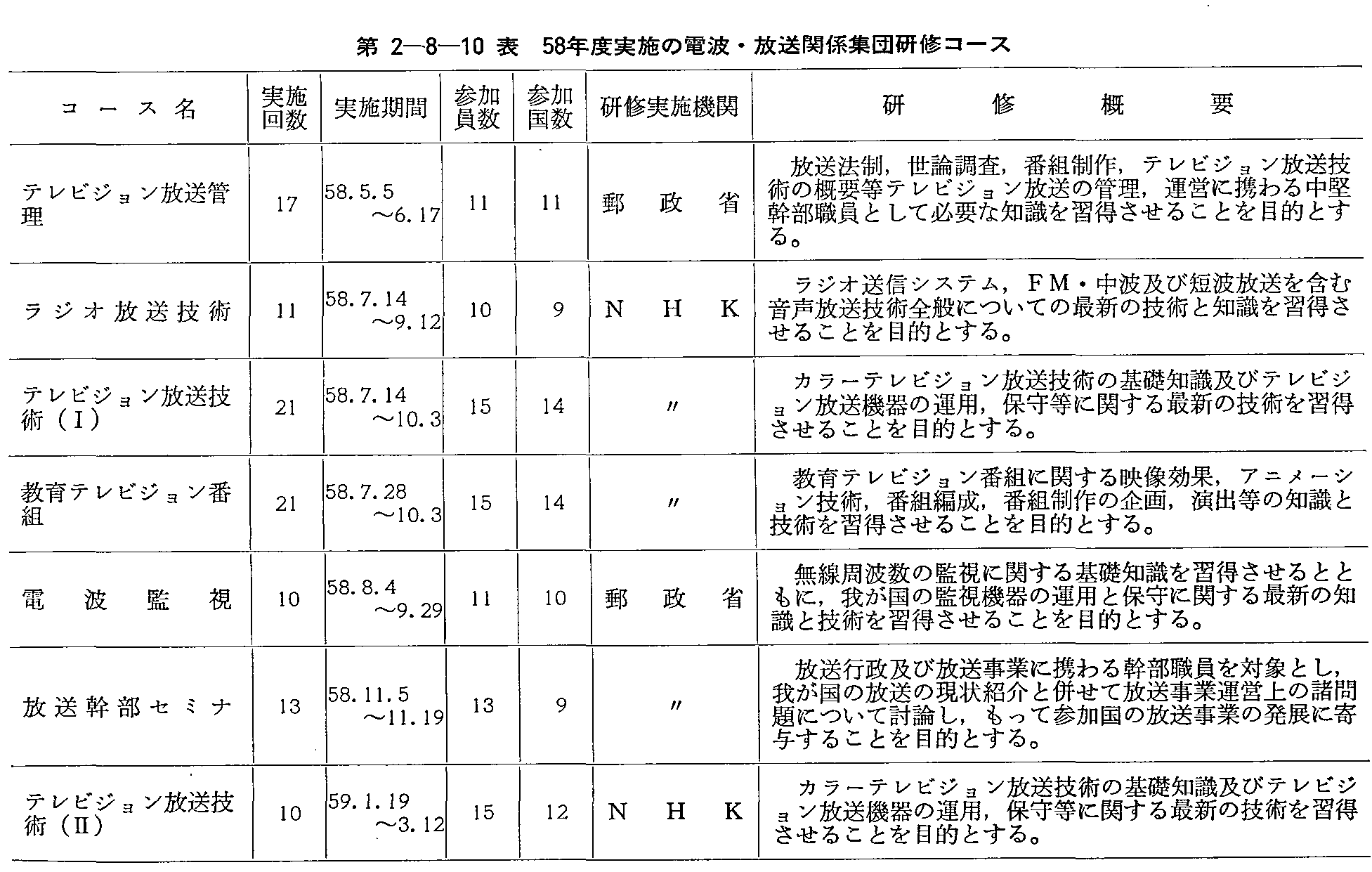
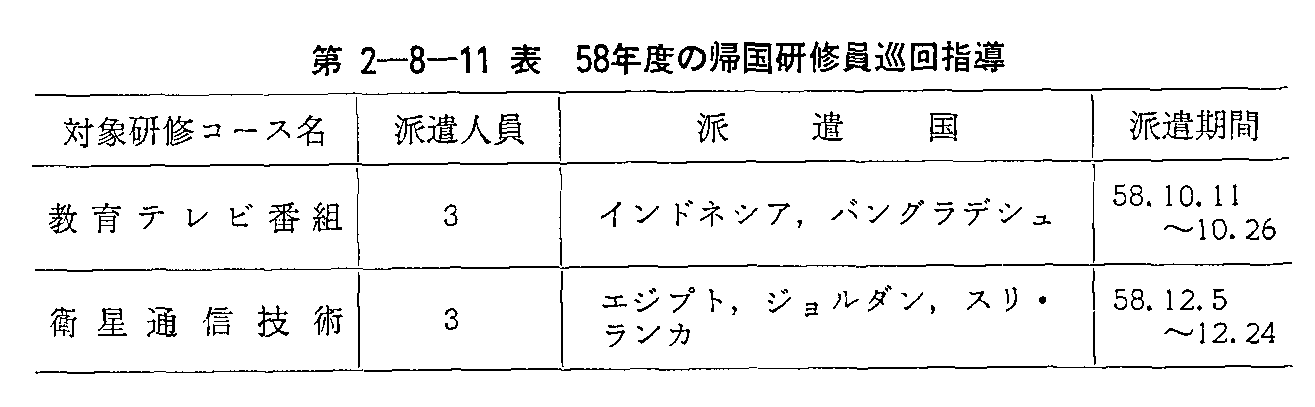
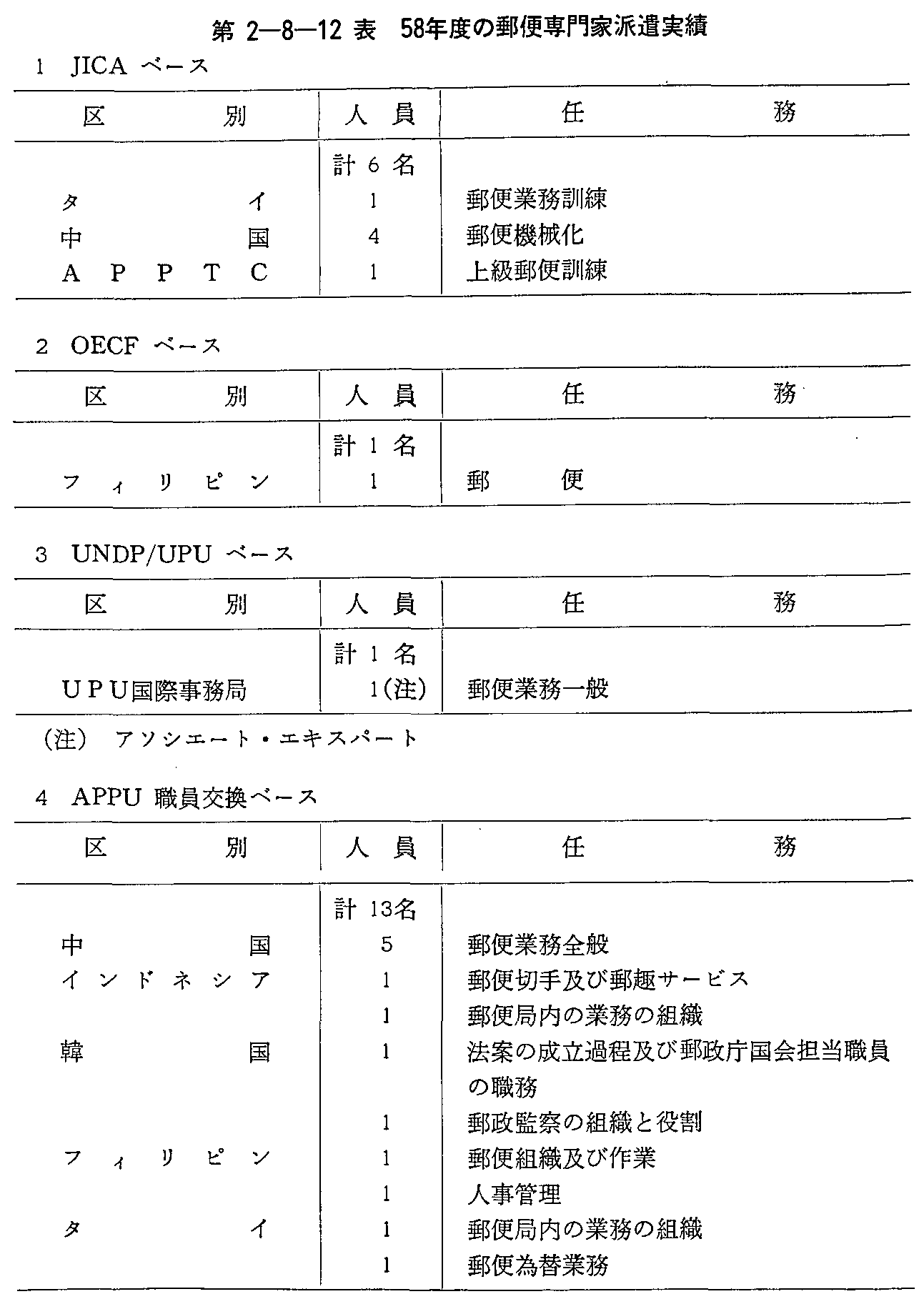
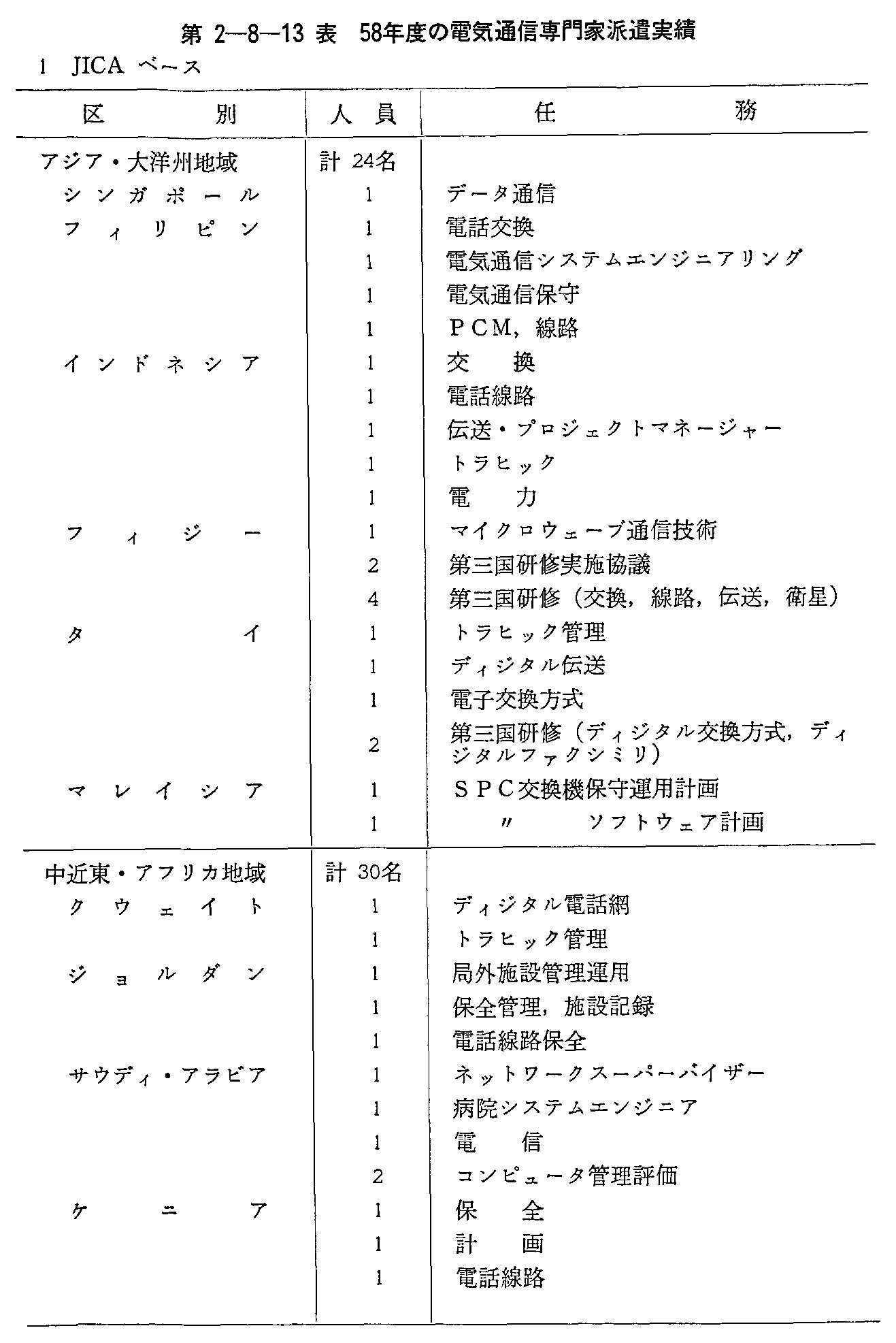
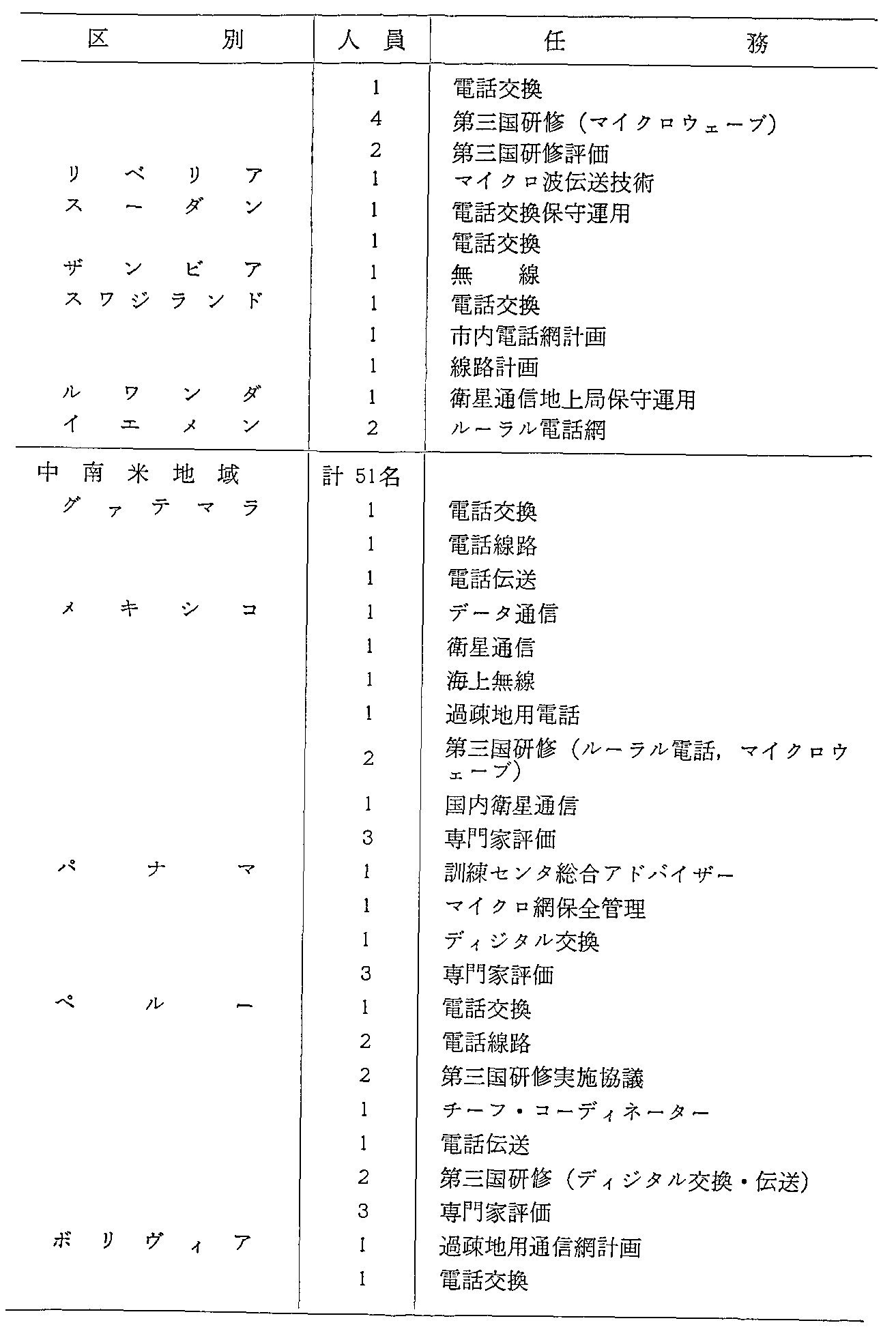
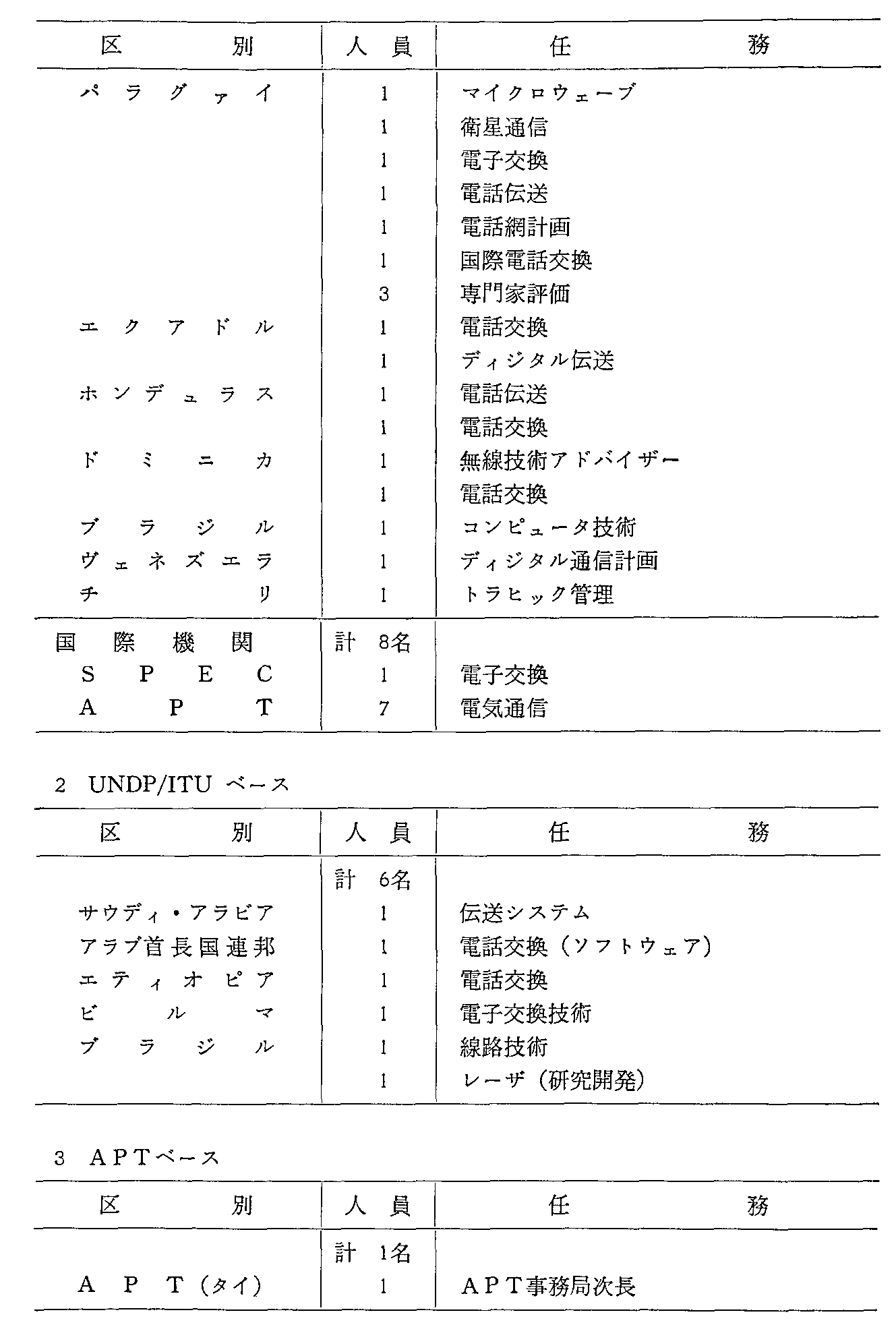
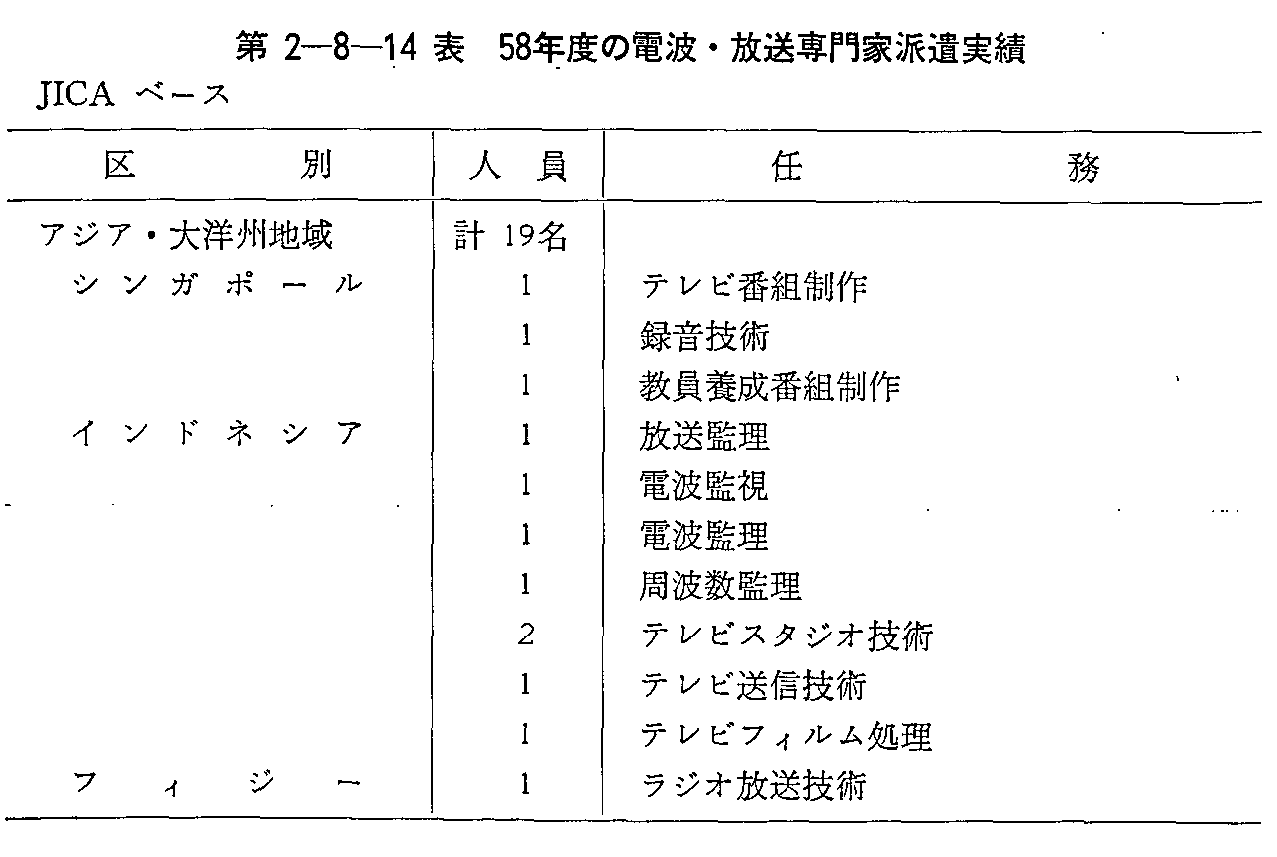
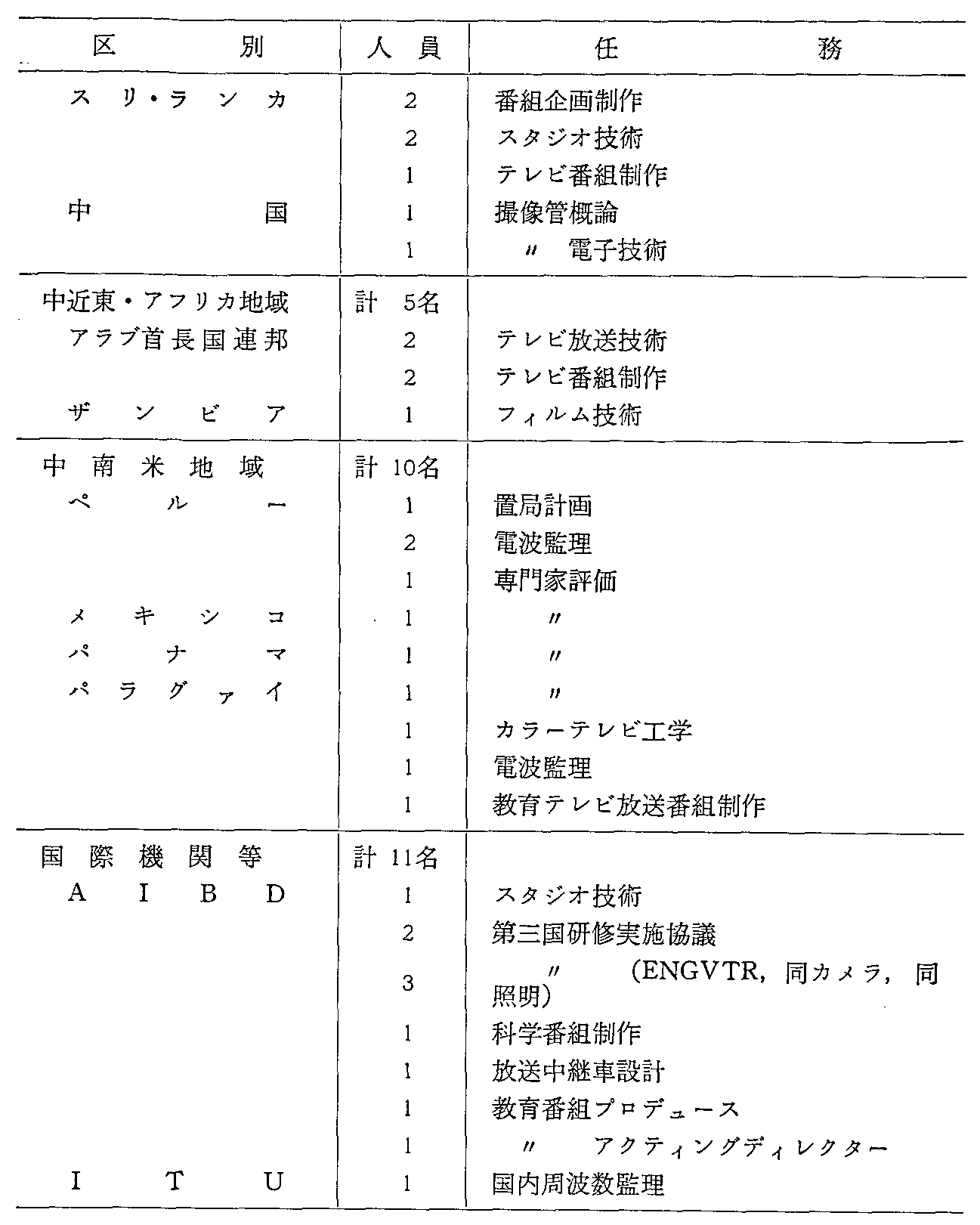
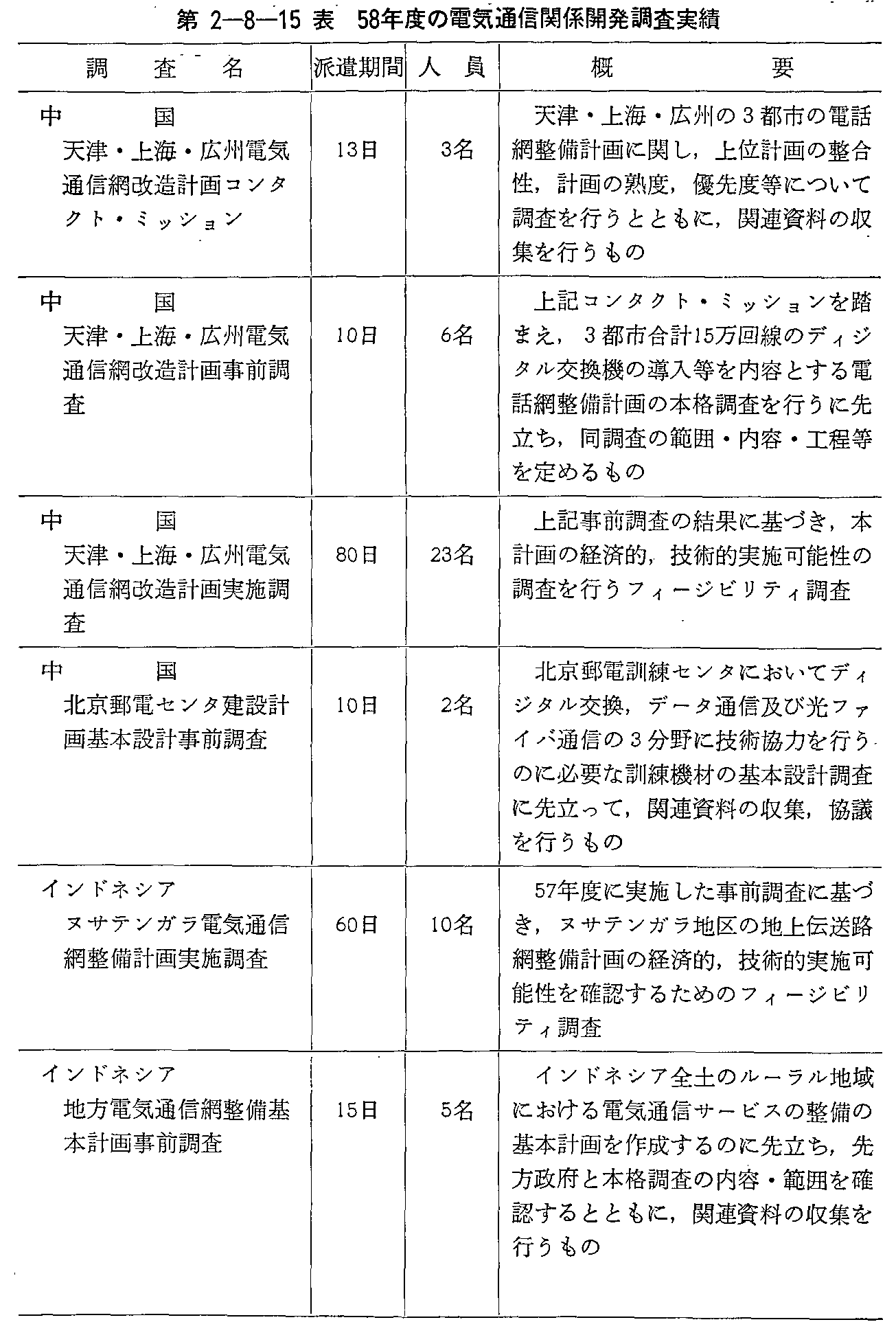
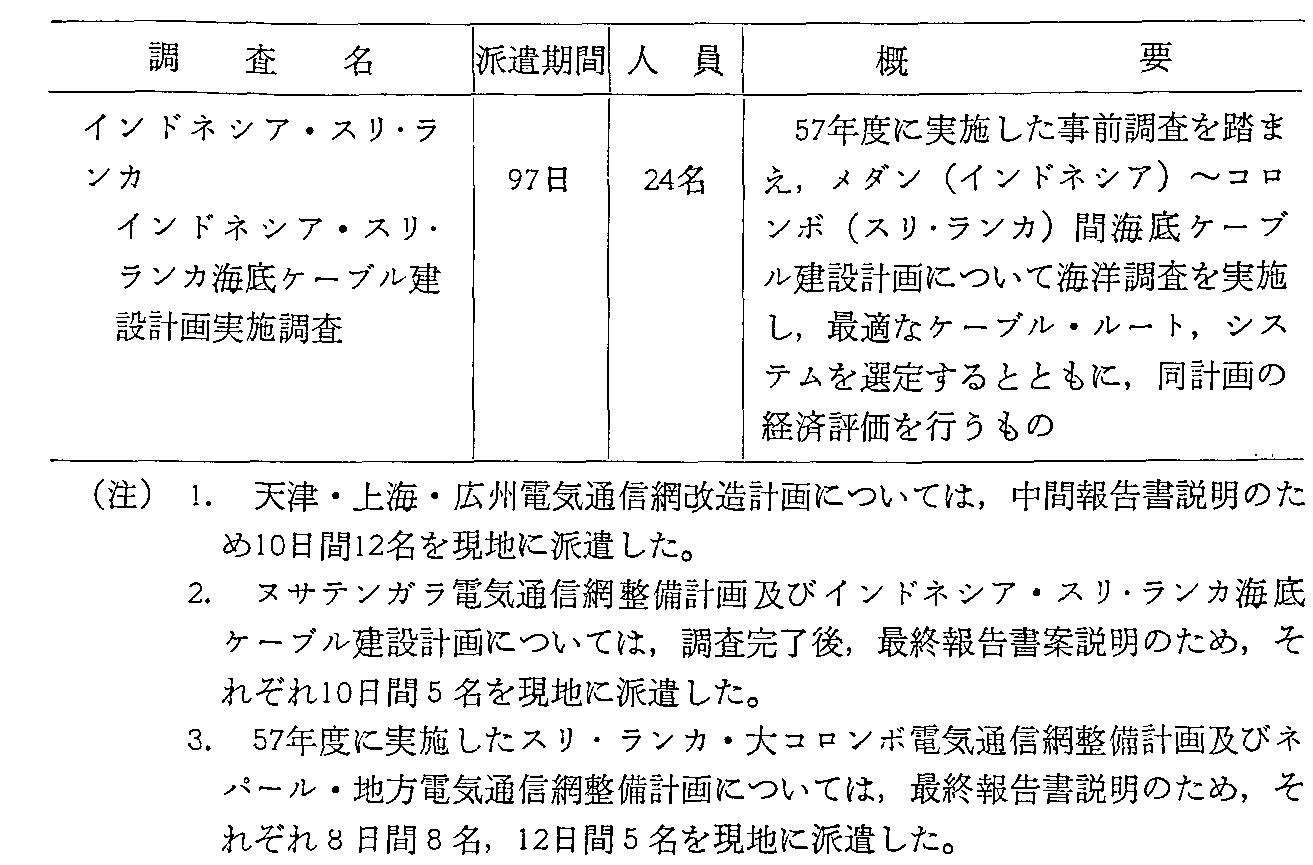
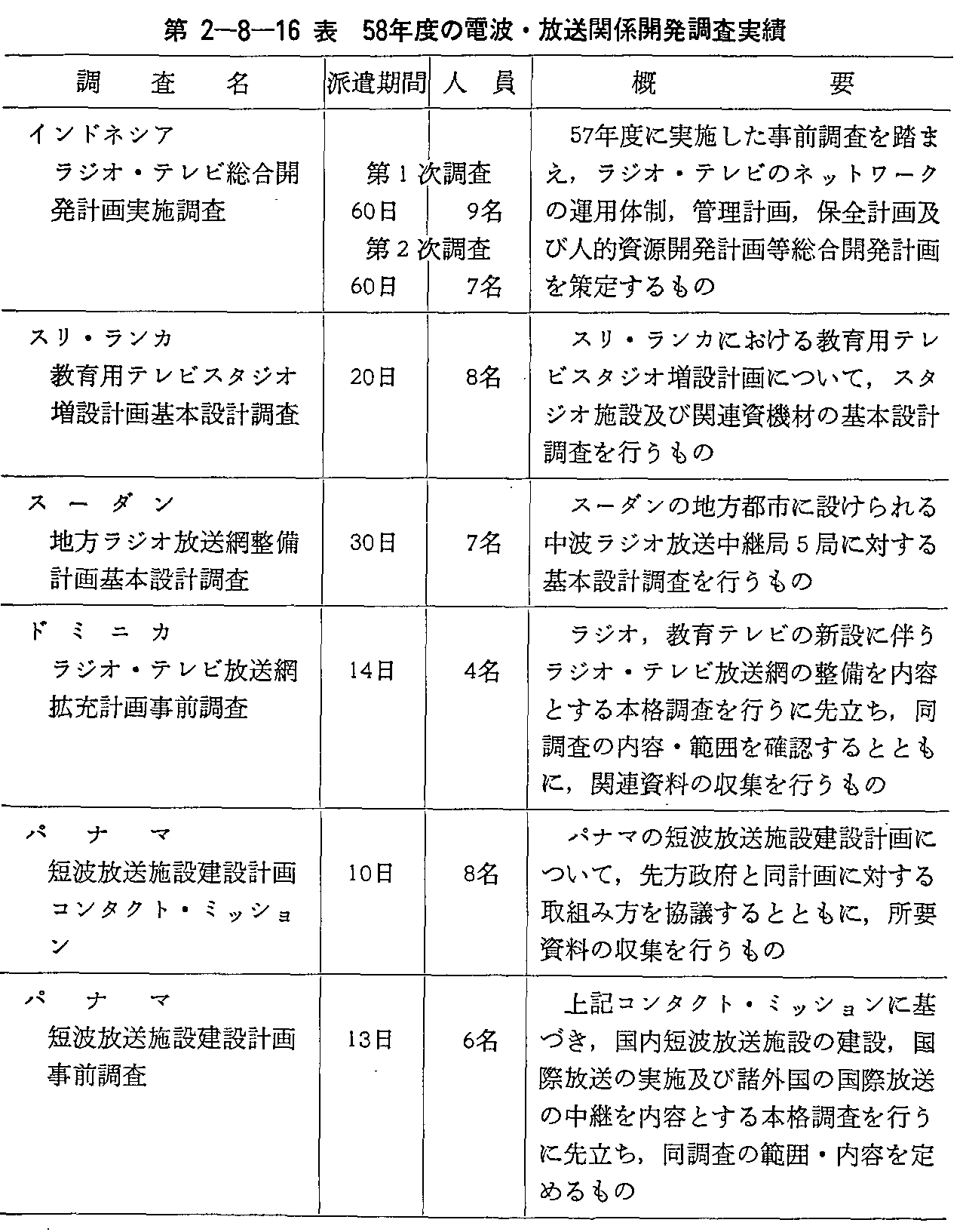
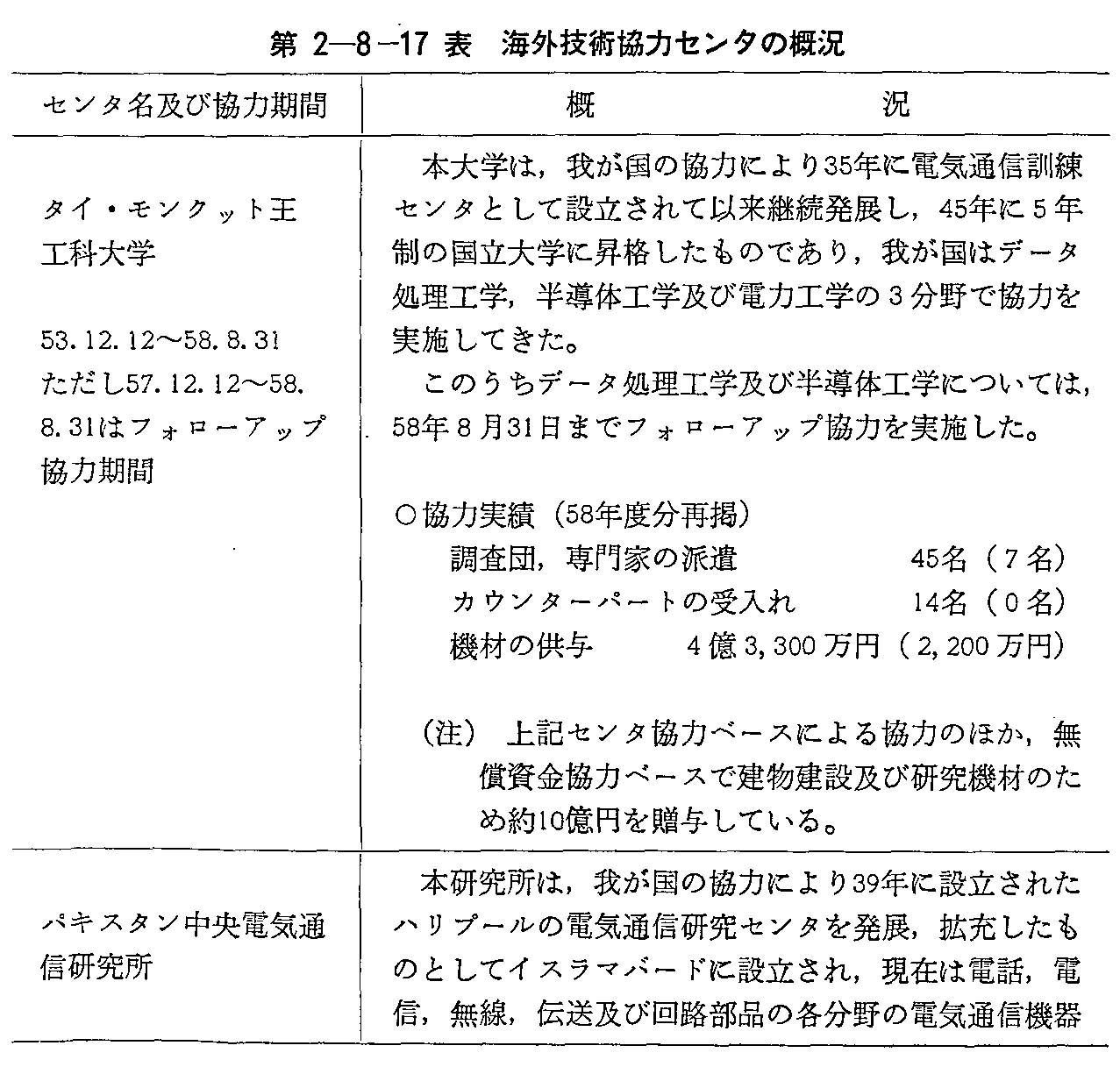
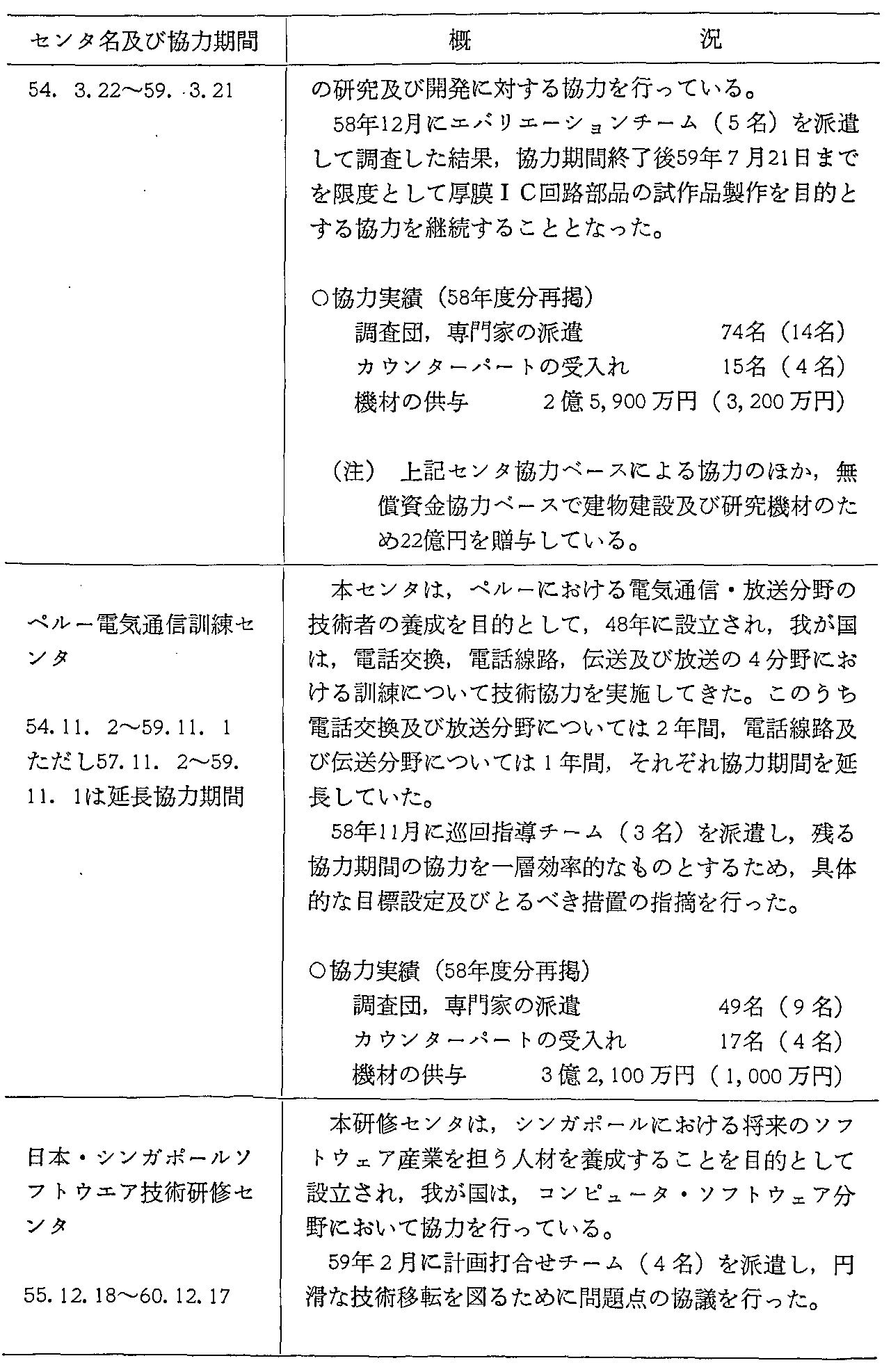
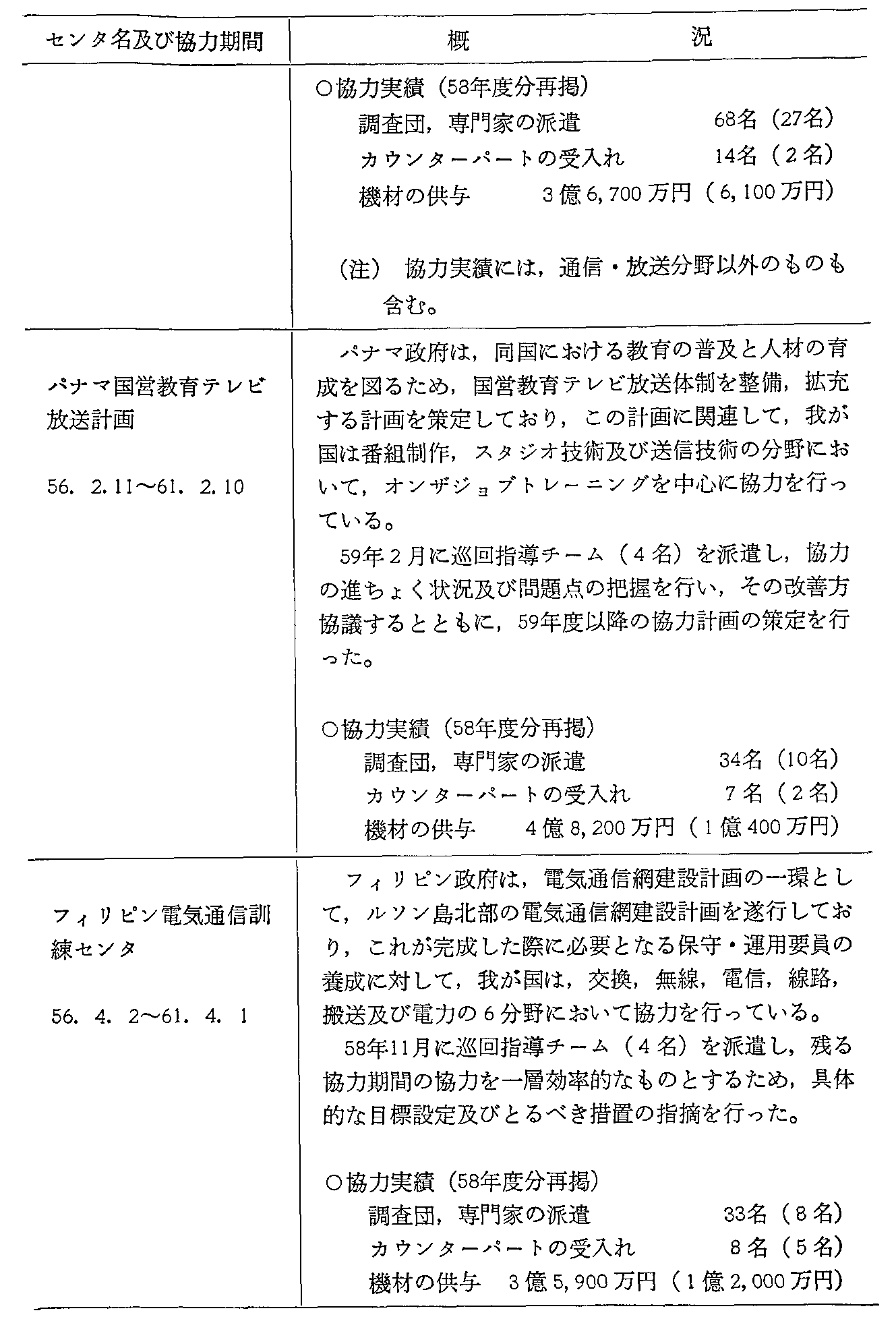
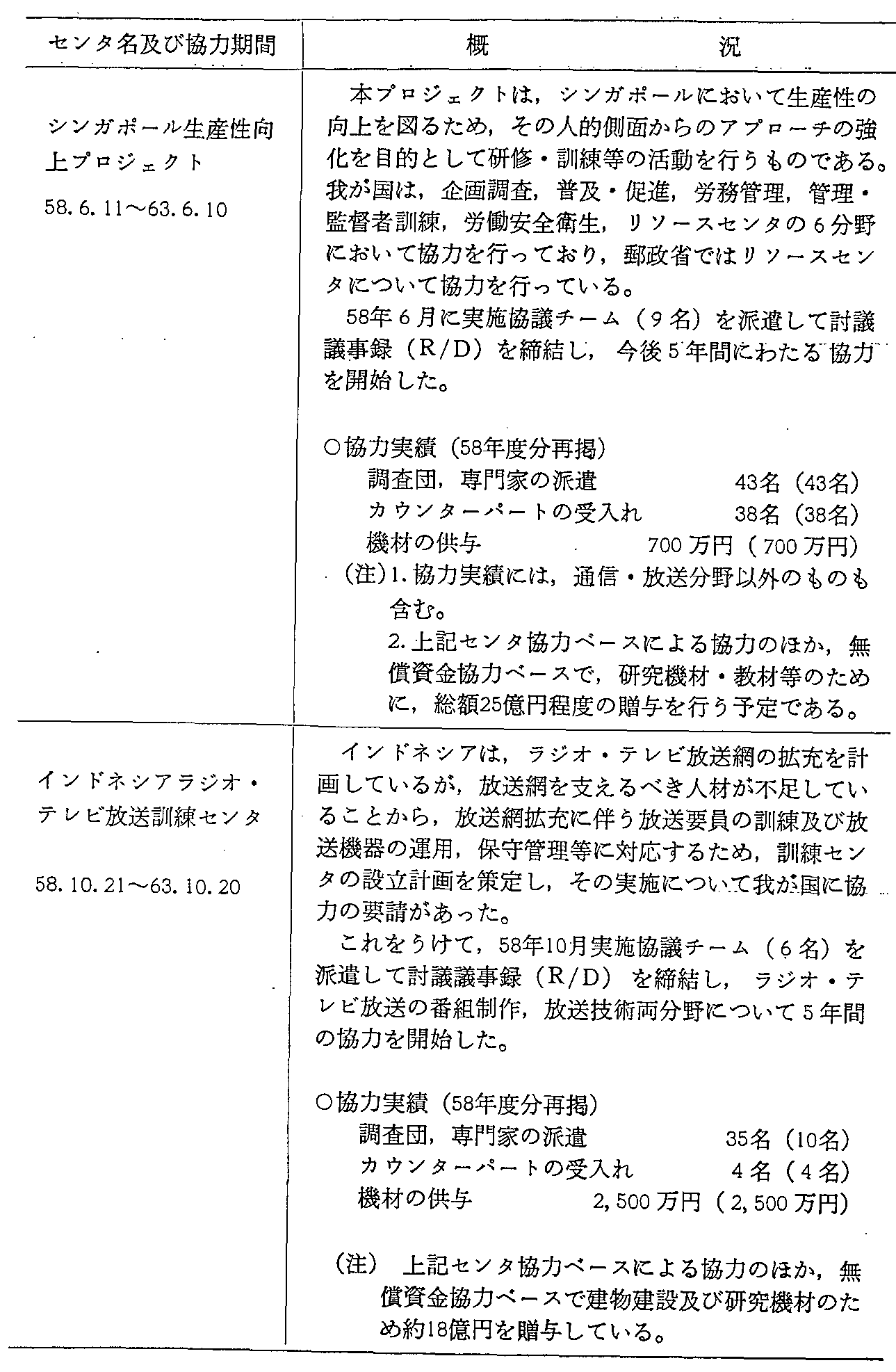
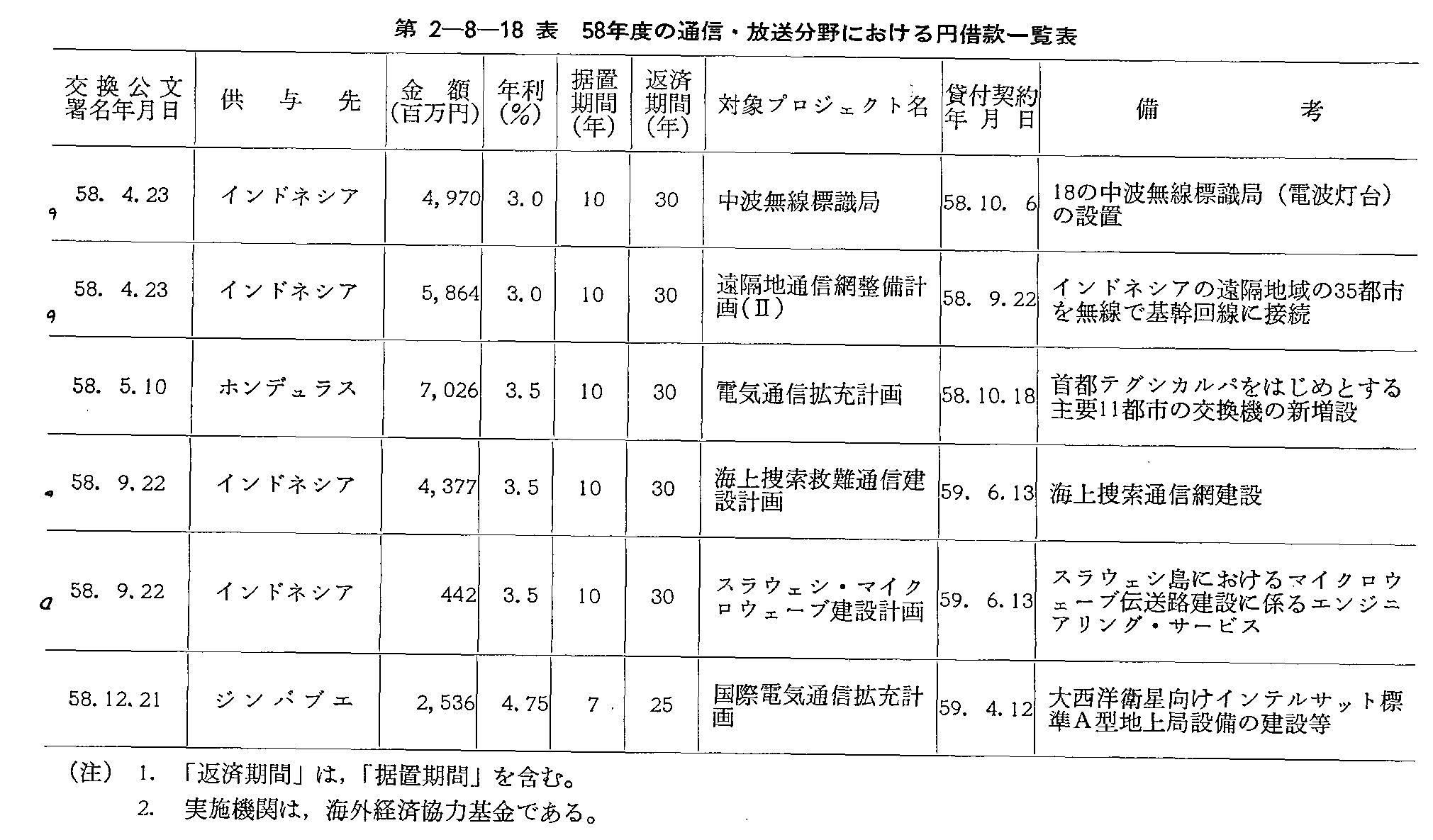
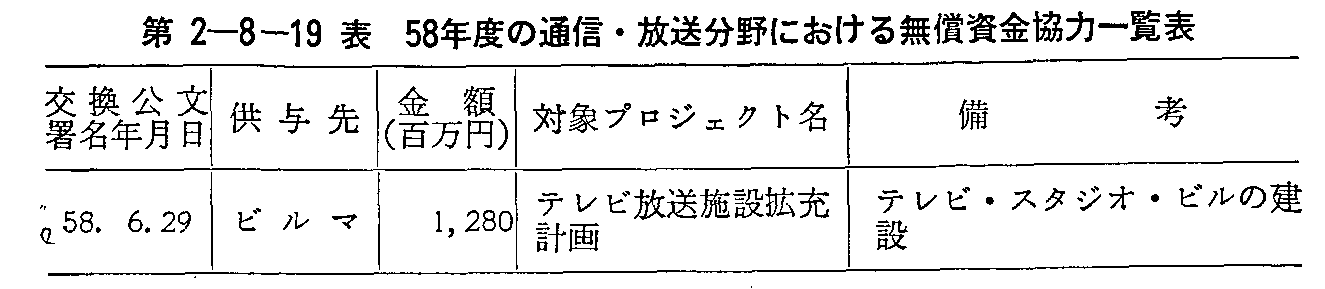
|