 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第1節 昭和49年度の通信の動向
1 通信の動向
(1) 概 況
最近の国内通信の動向は第1-1-1図に示すとおりである。
49年度の内国郵便物数は140億通であり,前年度に対し6.5%増となった。これは,石油危機の影響により前年度実績が特に後半において低かったこと,参議院議員選挙及び統一地方選挙に伴い選挙関連郵便物が増加したこと,年賀郵便物が高い増加率を示したことなどによるものとみられる。これを郵便サービスの生産額からみると,第1-1-3表に示すとおりであり,49年10月1日から小包郵便料金を改定したこともあって,3,793億円と前年度に比べ8.7%の増加となった。
49年度末加入電話加入数(集団電話を除く。)は2,744万に達した。これは,日本電信電話公社(以下「電電公社」という。)関係投資の圧縮の中で電話の架設を優先した結果,328万個の増設があったためである。申し込んでもすぐには付かない積滞電話の数は,新規需要の落ち込みも加わり,48年度末の181万件から49年度末には一挙に99万件に減少し,国民100人当たり普及率も35.6個となった。住宅用電話の加入電話全体に占める構成割合は48年度の57.7%から61.0%へと上昇し,世帯普及率は56.4%に達した。電話総利用回数は伸びているものの,1加入当たりの利用回数は前年度の1日平均4.5回から,49年度には4.0回へと減少してきている。電話サービスの49年度生産額をみると,このような構造的原因に加え,景気の強い影響を受け,1兆6,692億円と対前年度比10.1%の増加にとどまった。47年度,48年度における対前年度比がともに16.5%増であることと比べるとかなりの落ち込みを示した。なお,有線放送電話の生産額は216億円で,対前年度比1.9%の増加であった。
専用サービスは,電話のほか,データ伝送,模写伝送等多様な用途に利用されているが,その利用動向を回線数(A-J規格)でみると,49年度は26万回線と前年度に比べ8.7%増加し,前年度と同様の伸びを示した。この結果,49年度の専用サービスの生産額は446億円で,対前年度比6.2%の増加であった。
電信サービスについてみると,電報の発信通数は,38年度の9,461万通をピークに毎年減少を続けているが,49年度も対前年度比3.9%減の4,268万通であった。国民1人当たりでみるとわずか0.4通しか利用されず,利用内容も慶弔電報が61.5%を占めている。一方,加入電信は着実に伸びており,49年度末加入数は対前年度比8.4%増の7万加入となったが,利用の少ない層への普及を反映して,1加入当たり通信料は月額1万2,700円と前年度より更に下降した。電信サービスの生産額は382億円で,対前年度比2.1%増とほぼ横ばいとなった。
データ通信はここ数年と同様の高い成長を示している。データ通信システム数(私設システムを除く。)は49年度末1,168システムとなり,前年度に比べ57.0%増加した。電子計算機のうちでオンラインシステムに使用されているものが全設置台数に占める割合を示すオンライン化率も年々上昇し,4.9%となった。また,周辺・端末装置はますます多様化,高度化の傾向を強めている。特定通信回線の利用状況でみると3万4千回線と前年度に比べ31.4%の増加となっており,特に高速回線の伸びが目立っている。このような状況の下で公社データ通信サービスの生産額は457億円と前年度に比べ51.8%の増加となった。
テレビジョン放送は国民の間に広く普及しており,日本放送協会(以下「NHK」という。)の受信契約総数は49年度末において対前年度比3.3%増の2,575万件で,世帯普及率は91.7%に達した。このうちカラー契約は2,054万件となり,世帯普及率は73.1%と上昇したが,その契約数の伸びは47年度32.5%,48年度17.3%,49年度12.0%と年々低下しており,カラーテレビ普及の頭打ち傾向は次第に顕著になってきている。民間放送については,前年度大幅な伸びを示した広告費は,49年度の景気停滞の影響を受け,伸び悩みをみせた。この結果,放送サービスの生産額は6,358億円となり,対前年度比10.0%増にとどまった。このうちNHKによるものが1,228億円(5.7%増),民間放送によるものが5,130億円(11.1%増)である。
次に,最近の国際通信の動向は第1-1-2図に示すとおりである。
国際通信需要も内外経済の深刻な不況を反映して,従来の高い伸びから急速に鈍化した。国際電話は,通話度数でみると,48年度は対前年度比で52.5%増と大幅な上昇を示したが,49年度は745万度で対前年度比17.8%増と低い伸びとなった。また,国際電話サービスの生産額をみると,通話時間の漸減傾向も加わり,前年度に比べ10.4%増の318億円とその伸びは低下した。
国際加入電信においてもやや低調で,対前年度比15.8%増の1,243万度となり,また,国際電報は551万通と前年度の実績を下回った。その結果,国際電信サービスの生産額は対前年度比9.7%増の363億円となった。
なお,外国郵便(差立+到着)は,1億9,794万通(個)で対前年度比1.4%の増加とほぼ横ばいであり,地域別にはアメリカ州との間のものが最も多く41.0%を占めている。
(2) 主な動き
ア.低迷した通信事業経営
49年度の日本経済は,戦後初めて実質経済成長率がマイナスになる一方,卸売・消費者物価上昇率が48年度に引き続き2けたを記録したため,景気後退過程で総需要抑制策が実施されるという異常な事態を経験した。
これらの経済情勢の下で,通信事業経営も景気後退に伴い収入が鈍化する一方,人件費をはじめとする諸経費の高騰により支出が増加し,厳しい局面に立たされた。また,物価政策の立場から公共料金の値上げ抑制が行われ,郵便料金,電話料金等は凍結されることとなった。その結果,通信事業の営業損益は次のような悪化の状況を示した。
まず,郵便事業においては,49年度の収支は1,247億円の赤字で,事業経営は財政面において極度に悪化するに至った。
次に,国内公衆電気通信の分野においては,電電公社の事業収支は,1,672億円の赤字で,前年度の259億円の黒字から大幅な赤字に転落した。国際公衆電気通信の分野においても,国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)の営業利益は,前年度に比べ41億円減少し,128億円の黒字にとどまっている。また,NHKについてもその経常事業収支をみると,40億円の赤字となっている。民間放送の営業利益は485億円で,前年度に比べ153億円減少した。
一方,通信機器の受注についても,総需要抑制による官公需の減少,景気後退による民需の減少があり,49年度の通信機器受注総額は5,951億円となり,48年度に比べ3.6%の減となった。
イ.新しい通信サービスの提供
国民生活の高度化,多様化に伴い,通信サービスに対する要望も多様化してきており,このような状況の下で49年度には各種の新しい通信サービスが提供された。その主なものは次のとおりである。
郵便の分野においては,50年2月から英国,ブラジル,香港を,6月からは米国を対象として,国際ビジネス郵便の取扱いを開始した。これは,航空,書留及び別配達(速達扱い)を組み合わせたサービスである。
電気通信の分野においても,50年3月には支店代行電話及び着信転送電話が試行サービスとして開始された。これらは,区域外通話の費用を着信者が負担する形態のサービスで,例えば,支店代行電話の場合,東京の電話から大阪の支店代行電話(東京の電話番号が付与されている。)に区域内通話の料金で通話することが可能となる。発信者の費用負担が軽減されるこのサービスを利用することにより,各企業は顧客サービスの向上,合理化,省力化,営業規模の拡大等を図ることができる。
50年3月にはプッシュホンによる国鉄列車予約サービスが開始された。これにより,東京23区内のプッシュホンから新幹線の座席予約が行えるようになった。
また,防災計画の一環として,49年10月には,災害応急復旧用無線電話,災害応急復旧用移動局電話のサービスが開始された。前者は,災害により加入電話の設備が滅失した際,その代替として使用できるよう災害の復旧,救護に重要な関係を有する国の機関,地方公共団体等にあらかじめ配備される無線電話で,後者は,災害により電話取扱局の設備等が滅失したため加入電話が使用できなくなった際,その代替として使用される電話である。なお,無線電話は830台,移動局電話装置は15装置が49年度中に配備された。
ウ.新しい通信サービスに関する調査
郵政省では,新しい通信サービスを開発するため次の2点について調査を行った。
(ア) 多重放送
多様化する国民の情報需要にこたえるとともに,有限である電波の効率的使用を図るための一方策として,既存のテレビジョン放送や超短波放送(FM放送)の電波に別の情報を重畳して放送を行うこと(多重放送)に関する調査を行うため,多重放送に関する調査研究会議が49年7月に郵政省に設置された。
同会議は多重放送に関する需要動向調査,多重放送の種類とその実用化に関する調査研究及び多重放送実施に伴う放送体制の在り方に関する研究について,51年度を目途に検討を進めているところである。
(イ) 農林漁業地域における多目的総合情報システム
最近,農林漁業地域は,都市近郊部においては都市化,山間部等では過疎化が進んでおり,地域共同体としての性格も大きく変容している。これらの地域における電気通信サービスの現状,問題点及び将来像に関して調査研究するため,48年6月,郵政省に「地域通信調査会」が設置され,49年9月に同調査会から郵政大臣に報告書が提出された。これらを参考として,郵政省では,50年度には有線放送電話設備を利用した静止画伝送システムの開発を進めており,52年度末を総合システム開発の目途としている。
エ.通信関係国際会議の開催
49年度には多くの国際会議が開催されたが,中でも注目すべき会議として以下のものがある。
49年5月22日から7月5日までローザンヌにおいて第17回万国郵便大会議が開催され,条約及び施行規則の改正が行われたが,51年1月1日からこれを国内的に実施するために,外国郵便規則等を改正方検討中である。
49年4月22日から6月8日までジュネーブにおいて国際電気通信連合(ITU)の世界海上無線通信主管庁会議(WMARC1974)が開催された。今回の会議は,1972年のITU管理理事会第二十七会期の決定に従い,短波無線電話海岸局用周波数の区域分配計画の改正等を行うために開催されたものである。会議の冒頭に国際周波数登録委員会(IFRB)委員の選挙が行われたが,我が国からの候補者が,E地域(アジア・大洋州)の委員として当選した。また,短波無線電話海岸局用周波数の区域分配計画においても,我が国は現在の通信を維持し,かつ,将来の通信需要を賄うために必要な相当数の周波数分配を受けることができた。このほか,海上通信分野における無線通信技術の進歩を取り入れるとともに,各種運用方法等を改善し合理化するため,国際電気通信条約附属無線通信規則の関係規定が改正され,51年1月1日から発効することとなった。
49年10月7日から25日までジュネーブにおいてITUの長・中波放送に関する第一地域(欧州・アフリカ)及び第三地域(アジア・大洋州)合同の地域主管庁会議第一会期が開催された。これは,第2章第3節で述べるように,中波放送の国際的な混信が激化している現状にかんがみ,この混信を排除するため必要な技術上,運用上の基準を作成することを目的として開催されたものである。これらの基準は,50年10月に開催される第二会期において再編成が行われる予定の第一,第三地域の長・中波放送用周波数割当計画の基礎となるものである。当会期では中波放送のチャンネル間隔を9kHzにすることなど各種の技術基準が定められたほか,各国の周波数要求の様式等が決定された。
また,ITUの常設機関である国際電信電話諮問委員会(CCITT)及び国際無線通信諮問委員会(CCIR)の合同委員会であるITUアジア・大洋州地域プラン委員会が49年10月23日から30日まで東京において開催された。今会合では域内電気通信の発展に関する一般情報の交換を行うとともに,技術協力問題,料金問題等について検討がなされた。
そのほか,ITU管理理事会第二十九会期(49年6月15日〜7月5日ジュネーブ),CCIR第13回総会(49年7月15日〜26日ジュネーブ),東南アジアケーブル計画に関する日,比,英(香港)の主管庁,通信事業体間の会合(49年8月1日〜2日東京),政府間海事協議機関(IMCO)海上安全委員会海事衛星専門家パネル(49年9月2日〜6日ロンドン),国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会(50年2月10日〜3月7日ニューヨーク)等の会議が開催された。
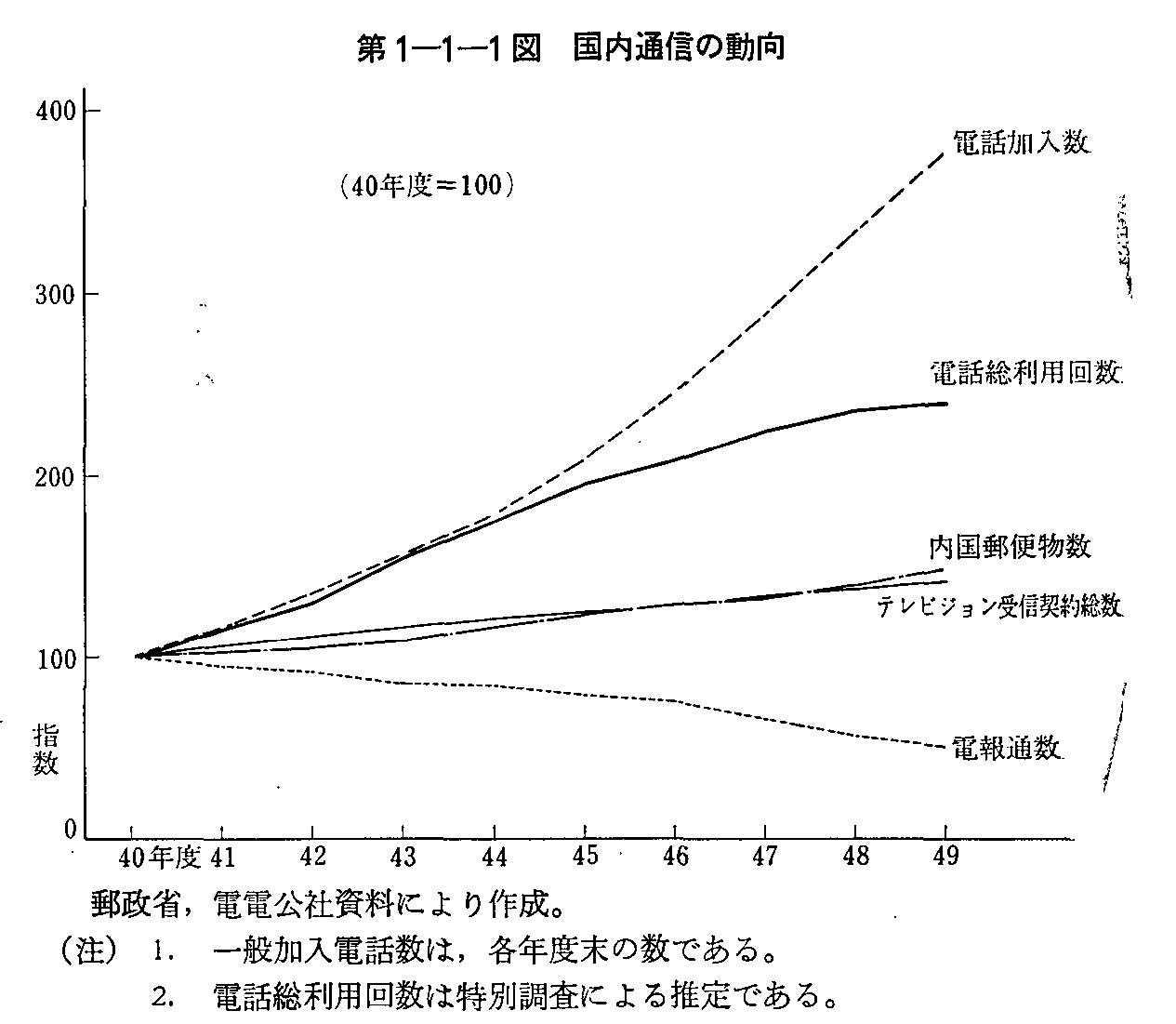
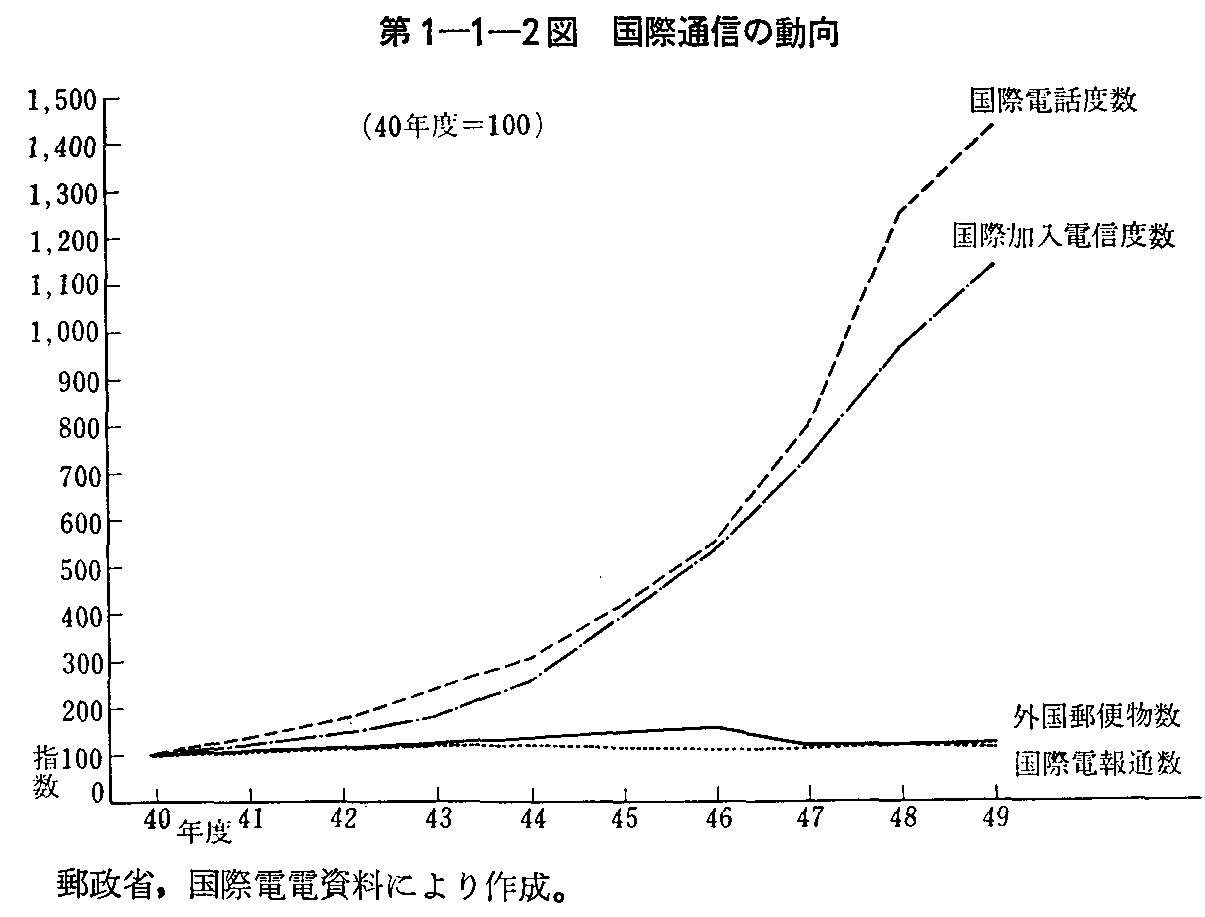
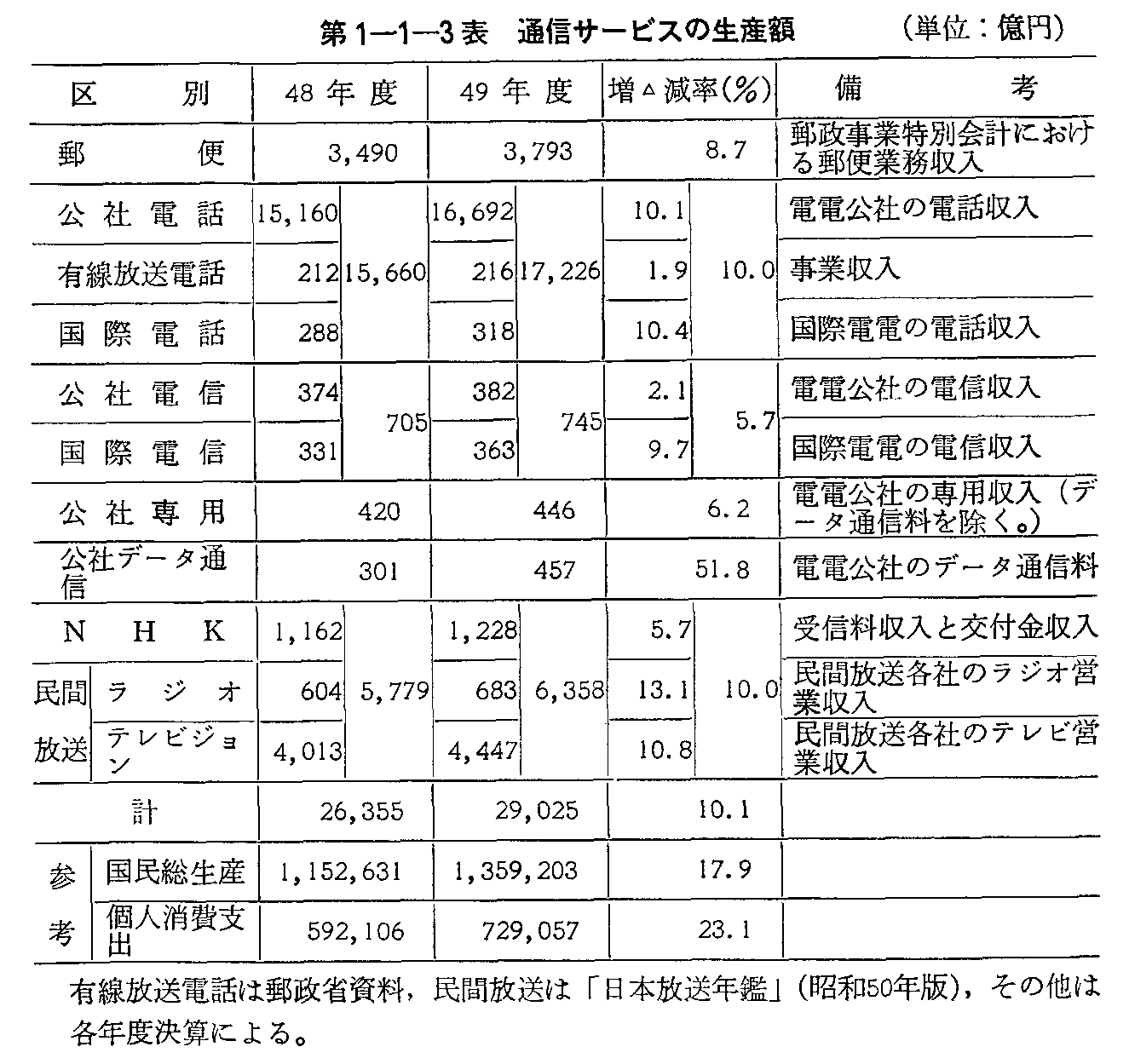
|