 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第2節 国内公衆電気通信の現状
1 電電公社業務
電電公社は,国内公衆電気通信サービスを運営する公共企業体として27年に設立された。49年度末現在,その主な取扱局数は,電報電話局1,403局,電話局167局,電報局(無線電報局を含む。)27局,市外電話局12局となっており,約31万名の職員が従事している。
このほか,電電公社では郵便局,国際電電,日本国有鉄道等へ各種サービスの一部を委託し,あまねくサービスの提供を図るとともに,きめ細かいサービスの提供についても配慮をしている。
(1) 電 報
明治以来100有余年国民一般の緊急通信手段として利用され,経済,文化等の発展に大きな役割を果たしてきた電報は,近年,電話や加入電信,データ通信等多様な近代的通信手段の普及に伴い,その性格が大きく変化してきている。
また一方で,電報事業の収支は,人件費の増大と利用通数の減少により,例年大幅な赤字を続けており,電電公社の事業経営上大きな問題となっている。
ア.施設の状況
電報の取扱いについては電報局,電報電話局をはじめ,電電公社の委託による郵便局その他において,受付,配達等の業務が行われており,49年度末におけるこれら電報取扱局の現状は第2-2-1表のとおりである。
イ.利用の状況
電報通数は,38年度の9,461万通をピークに,その後減少を続けており,49年度には4,628万通と前年度に比べて4%の減少となっている。
国民1人当たりの年間利用通数についてみても,38年度の1.0通に対し49年度は0.4通と相当下回る状況となっている。
一方,最近における利用内容をみると,かつては緊急通信手段であった電報は,その性格が大きく変貌している。すなわち,緊急連絡用の電報は全体の3%程度にすぎず,「ゴケツコンオメデトウ」に代表されるような社交,儀礼のために利用される慶弔用及び企業がその活動に利用する業務用が大部分を占めており,とりわけ慶弔用電報は第2-2-2図のように46年度までは毎年増加を続け,47年度はいったん減少したものの,48年度,49年度と再びわずかながら増加の傾向を示している。
総電報通数中に占める慶弔用電報の割合をみると,39年度17.1%,47年度48.6%,48年度57.3%,49年度61.5%となっており,慶弔用電報の占めるウェイトがますます大きくなってきている。
(2) 加入電信
加入電信は任意の相手方と50b/sの符号伝送が可能な交換網サービスである。31年にサービスが開始されて以来,企業における情報化指向,事務合理化の機運にマッチして,その需要は着実に伸びてきている。
ア.施設の状況
49年度末現在,加入電信加入区域数は830区域,加入数は7万433加入(対前年度比8.4%増)となった(第2-2-3図参照)。
イ.利用の状況
加入電信加入者の業種は,製造,卸・小売,金融・保険,運輸・通信,サービス業等多岐にわたっている。利用内容も,かつては専らメッセージ通信用であったものが,企業の事務合理化の進展につれ,伝票伝送,データ伝送に主役の座を譲り,更に最近では,電子計算機と直結したデータ通信としての利用が逐次増えている。
また,1加入当たり通信料は他の通信手段,特にデータ通信の発展や加入電信の利用の少ない層への普及を反映して若干下降傾向を示しており,10年前の39年度が月額1万9,402円であったのに比較し,49年度は35%減の月額1万2,700円となっている。
(3) 電 話
電話は交換網を通じて任意の相手方との間に音声通信を行うことが可能な典型的なパーソナル電気通信メディアであり,その代表的なものは加入電話及び公衆電話である。
これらは,近年における目覚ましい技術革新による同軸ケーブル方式,マイクロウェーブ方式,新しい自動交換方式等の開発に支えられ,また,経済の発展,生活水準の向上等の要因によって急速に普及し,住宅用電話を例にとれば,20年代までは一種のステータスシンボルと見られたものが,今やナショナルミニマムとしての地歩を占めるまでに至っている。
その普及状況を加入電話を例にとり,実質国民総生産の伸びと比較すれば,第2-2-4図のとおり最近急速な普及を示している。また,電話機数は第2-2-5図のとおり年々増加して,49年度末には3,940万個に達し,その人口100人当たりの普及率は35.6個となるというように(第2-2-6図参照),その充実ぶりをうかがうことができる。
このような電話の普及とともに,企業活動における事務の合理化又は生活水準の向上を反映して,電話の利用方法も,多様な附属装置等を設置することなどによって,高度化,多様化の傾向を深めてきている。
ア.施設の状況
(ア) 加入電話
加入電話等の加入種類別加入数の状況は第2-2-7表のとおりである。49年度末現在一般加入電話数は2,744万となり,集団電話,有線放送電話接続回線等を含めた加入電話等総数は2,887万(対前年度比13%増)となっている。
人口100人当たりの普及率は第2-2-8図のとおりであり,49年度末において26.1加入となり,10年前に比べ約4倍となった。
加入数の推移を事務用,住宅用の利用種別でみると第2-2-9図のとおりで,全体に順調な伸びを示しているものの,最近における生活水準の向上,生活様式の変化等により住宅用電話の増加が目立っており,需要構造が大きく変化してきている。すなわち,49年度は事務用電話48万の増加に対し,住宅用電話は280万増加して新規架設の約8割を占め,これにより年度末における住宅用電話の構成比は61%に達した。
なお,住宅用電話の100世帯当たりの普及率(地域集団電話を含む。)をみると,10年前の39年度末では5.9であったが,44年度末22.9,48年度末49.3と急上昇を描いており,49年度末では56.4に達している。
(イ) 地域団体加入電話
地域団体加入電話は,地域集団電話等の普及に伴い,最近は年々減少し,49年度末施設数は91箇所(組合本電話機数約1万個)で前年度末に比べ24箇所(組合本電話機数約4千個)減少した。
(ウ) 公衆電話
公衆電話には個人等に管理を委託しているいわゆる赤電話(店頭公衆電話),公社直営で電話ボックス等に置かれている青電話(街頭公衆電話),10円硬貨のほか100円硬貨も併用できる遠距離用の100円公衆電話等がある。49年度には赤電話1万6千個,青電話1万7千個,100円公衆電話6千個合わせて3万9千個が増設され,年度末には,総数63万4千個(第2-2-10表参照),人口千人当たり5.7個の普及率となった。
以上のほか,加入電話の一種で公衆電話と同じ機能を持ついわゆるピンク電話は,48年度末51万6千個と47年度末に比べ減少したが(3.9%の減),49年度末では57万4千個と再び増加している。
(エ) 船舶電話
船舶電話とは,入港中あるいは沿岸を航行中の船舶が,電話取扱局の交換によって,船舶と陸上の間又は船舶相互間において通話を行うための無線電話のことをいい,28年港湾内の船舶を対象とする港湾電話として発足した。その後34年には沿岸航行中の船舶にまで対象を広げた沿岸電話が開始され,39年には全国沿岸をサービスエリアとする現在の形態が確立された。以後,サービスの提供範囲は逐次拡大されており,現在の範囲は第2-2-11図のとおりである。
船舶電話の加入数は39年度末約500であったものが,第2-2-12図のように毎年増加を続け,49年度末では約7千加入となっている。これは,サービスエリアが全国に拡大されたこと及び船舶電話が航行の安全確保や運行能率の向上に有用な機器であるという認識が確立されたことによって,需要が非常に高まったためであると考えられる。しかし一方,無線電話であるため,電波の割当ての関係から設置数に大きな制約があり,需要のすべてを満たしきれず毎年積滞を生じている。その数は49年度末には,1,872に上っている。
船舶電話の利用状況は,第2-2-13図に示されているように,電話の通話度数(発信)については毎年増加しており,49年度には811万7千度となっている。また,船舶電話を利用して電報の発受も行うことができるが,船舶発信の電報通数については47年度以来減少傾向を示しており,49年度は16万4千通となっている。
現在,船舶電話による通話は,すべて交換台で手動によって接続する方式がとられているが,サービスの改善,電波の有効利用等の観点から,交換方式の自動化が検討されている。
なお,電電公社は,船舶電話の取付,保守等の業務に関しては,サービスの開始当初から日本船舶通信株式会社に委託している。
(オ) その他の電話サービス
電話サービスとしては,前述のほか,国鉄新幹線列車に設置されている列車公衆電話,110番,119番としてなじまれている警察署,消防署への緊急通報用電話といったものがあり,各々特殊な通話に対する需要にこたえている(第2-2-14表参照)。
更に,事務の効率化,省力化に対する要請や生活様式の変化に伴い,電気通信サービスに対する社会的需要も高度なものとなってきている。一般の電話についても,その電話回線に転換器で接続機器を接続したり,高性能の交換機を利用することによって,新たな使用方法が生まれている。例えば,電話回線にファクシミリ伝送装置を接続して行う画像伝送,プッシュホンによる短縮ダイヤルサービス,電話計算サービス,また,通話中に第三者からの着信があったことを知らせ,その通話を一時保留して第三者と通話することができる通話中着信サービス(キャッチホン)等利用者の要望にあった多様なサービスを提供することができるようになっている。こういった附属装置等の主なものの利用状況は,第2-2-15表のとおりである。
(カ) テレホンサービス
生活水準の向上と住宅用電話の普及に伴い,情報化の進展を示すテレホンサービスが急速に普及してきている。テレホンサービスは,一定の電話番号に電話をかけると,トーキー案内装置等により,あらかじめ録音されているテープが,ニュース,料理法,育児法,経済情報等各種の生活情報を知らせてくれる新しい電話の利用方法で,50年6月末現在,そのサービス件数,回線数は第2-2-16図のとおりである。
イ.利用の状況
前述のような電話の普及状況にもかかわらず,電話利用の伸びは,石油ショック以来の経済情勢を反映して鈍化しつつある。ダイヤル通話の総通話回数についてみると第2-2-17図のとおり,従来,年10%近くの増加を示していたものが,48年度は,対前年度比5.1%増の323億4千6百万回,49年度は,対前年度比1.6%増の328億6千9百万回にとどまっている。
また,利用回数の少ない住宅用電話の比率が年々増加してきた結果,1加入1日当たりの電話利用回数は第2-2-18図のとおり,年々減少する傾向を示している。
一方,1加入当たりの電話料金支払額(月額)は第2-2-19表のとおりで,最近10年間ほぼ横ばい状態であったが,49年度は若干の減少を示している。
ウ.料金制度
電話の料金制度は,そのサービスがガス,水道等他の公益事業と異なり,複雑,多彩となっていることを反映して多様な構造になっている。もっとも代表的な加入電話を例にとってみると,加入時に支払うべき料金と加入後経常的に支払うべき料金とに分かれている。
加入時に支払う料金としては,加入料及び設備料があり,そのほか一定の債券を引き受けることが必要とされている。
また,加入後経常的に支払う料金には,度数料金局に収容されている加入電話の場合,月額で定められている電話使用料(基本料),使用度数に応じて課せられる通話料,附属装置等の使用料としての附加使用料がある。これらのうち通話料については,47年,48年にわたって広域時分制と呼ばれる制度が全国で実施された。これは,従来,度数料金局の最低通話料区域が同一電話加入区域内であったものを単位料金区域(通常数個の電話加入区域を一つのグループとしたもので,全国を567に分けている。)に拡大するとともに,この区域内の通話にも時間に応じて課金する時分制を採用したものである。
この広域時分制は,生活圏・経済圏の広域化と情報化社会の進展に即応し,市外通話料の格差を是正するための一つのステップであり,今後一層合理的な料金体系の確立が必要になってこよう。
なお,通話料金を諸外国と比較すると,第2-2-20表のとおりである。
(4) 専用サービス
公衆電気通信設備の専用(専用サービス)は,特定の者が特定の地域相互間において公衆電気通信設備を排他的に使用するもので,その料金が定額制であることから企業等が大量の通信を行うのに適した通信手段であり,加入電話や加入電信とともに社会,経済の発展に重要な役割を果たしている。
近年,情報化社会の進展につれ,専用サービスに対する国,企業等の需要は順調に増加しているが,数次にわたる電電公社の設備拡充計画の遂行により,大容量伝送方式の開発,その他技術革新の成果を反映した各種規格の専用サービスが提供され,その需要を満たしている。
今後も専用サービスに対する需要は,経済の安定成長下にあっても,質的,量的に増加するものと予想される。
ア.施設の状況
一般専用回線(A〜J規格)は,49年度に約2万回線増え,26万468回線となった。
回線数の経年変化をみると第2-2-21図のとおり年々増加しており,49年度は前年度に比べ9%増加した。
イ.利用状況
現在,専用サービスの制度は,専用回線の特性,用途に応じてA規格からL規格までにシリーズ化され(G,H,K規格は未設),各規格は更に伝送方式及び使用方法により第2-2-22表のとおり細分化されている。
専用サービスの利用状況を規格別回線数でみると,3.4kHzの周波数帯域を使用するD規格は約22万回線で全体の86%を占めている。殊にD-2は,通常の音声伝送が可能なもので電話用として広く利用され,利用数は約21万回線とD規格の93%を占めており,48年度に比べ4%の増となっている。
D-2以外では,データ伝送,模写伝送にも利用できるD-1(帯域使用),データ伝送用のD-5(1,200b/s交流符号伝送)及びD-7(2,400b/s交流符号伝送)の利用は,48年度に比べ,それぞれ13%増,4%減,23%増となっている。
D規格に次いで多く利用されているのはA規格である。A規格は,現在A-1(50b/s直流符号伝送)のみが設定されているが,電信をはじめデータ伝送,遠隔制御等に利用され,その利用回線数は3万6,124回線で前年度に比べ41%増と著しい伸びを示している。
その他のB,C,E,F,I,Jの各規格については,専用サービス全体からみればまだ利用が多いとはいえない。<1>規格及びJ規格は,48kHz又は240kHzという広帯域の周波数帯の伝送が可能で多彩な用途に利用できるものであり,48年11月から一般に開放され,49年度末の回線数は151回線(48年度末119回線)となっている。
なお,L規格は4MHzの周波数帯域の伝送が可能なもので,白黒又はカラー映像信号及び音響信号伝送用としてテレビジョン放送中継に利用されており,NHK及び民間放送各社の49年度末現在の利用状況は,回線延ベキロ4万5,579km,対前年度比0.5%の増加を示している。
(5) その他のサービス
近年,産業,行政,教育等の広範な分野において,従来の電信電話サービスでは十分満たされない電気通信需要が発生しているが,電気通信技術の目覚ましい発展に基づく新システムの開発により,これらの需要に応じて新しいタイプの公衆電気通信サービスが提供されている。
その代表的なものには次のような例がある。
ア.支店代行電話
支店代行電話とは,区域外通話の費用を着信者が負担する新しい形態の着信用電話サービスであり,50年3月に試行的にサービスが開始された。
各企業は,このサービスを利用することにより,顧客サービスの向上,企業の合理化・省力化,営業規模の拡大等を図ることができる。また,各企業は,このサービスを利用することで大都市等に設置された支店,営業所等を廃止又は縮小することができるため,結果として都市集中の緩和を果たす役割が期待される。
イ.着信転送電話
着信転送電話は,構内交換設備又はビル電話にかかってきた通話を必要に応じて転送者の負担で転送するサービスであり,50年3月に試行的にサービスが開始された。各企業は,このサービスを利用することにより顧客サービスの向上を図ることができる。
ウ.高速模写伝送サービス
伝送可能線路距離おおむね35kmの範囲内において,通常12kHzの周波数帯域を用いて専ら模写伝送を行うもので,官庁,銀行等の利用もあるが,大部分は地方自治体の本所・支所間の模写伝送(戸籍謄本等の伝送)に利用されている。
49年度末現在の利用回線数は,1,254回線で48年度末に比べ338回線増加している。
エ.映像伝送サービス
伝送可能線路距離おおむね20kmの範囲内において,通常4MHz以下の周波数帯域を用いて,専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像伝送(放送事業者が行う放送以外の目的のものに限る。)を行うもので,その利用状況は49年度末現在108回線で48年度末に比べ46回線増加している。このうち79回線(73%)は警察の交通管制センターと主要交差点間を結んで,交通管制用として利用されている。また,このほか,官庁,新聞,放送,その他一般の銀行,会社の事務管理用としても用いられている。
なお,カラーの映像伝送は,現在のところホテルに宿泊する外人客を対象として外国語によるニュース,買物案内等を伝送するものが東京都及び大阪市にそれぞれ1回線あるのみである。
オ.高速道路通信サービス
高速道路における自動車事故や非常事態の発生に際し,迅速,的確な措置を採るための非常電話,移動電話のほか,道路管理者の業務管理用電話等を一体的システムとして提供するもので,高速道路網の整備に伴い,ハイウエイ時代に不可欠な通信手段として普及してきた。
49年度末現在,東名高速道路全区間をはじめ,東北縦貫自動車道,中国縦貫自動車道,近畿自動車道,九州縦貫自動車道,東関東自動車道等に利用されている。
カ.ポケットベルサービス
ポケットベルサービスは,加入電話から特定の携帯無線受信機(ポケットベル)の加入者番号をダイヤルすると,無線基地局を経由して自動的に電波が発射され,これを受けたポケットベルの携帯者に「呼出し」を受けていることを知らせるもので,外出している人に連絡するのに最適の無線個別呼出しの手段である。
このサービスは,民間企業が電電公社の委託を受けてポケットベルを調達保有し,これを加入者に貸付け,加入,料金,保守等に関する業務を行っているものである。
我が国では43年7月東京(23区)で開始され,次いで大阪,名古屋と続き,逐次主要地方都市に拡大されている。49年度末におけるサービス提供地域は32地域,加入数は39万5千加人(48年度末24地域,29万加入)である。
加入者の主な業種をみると,販売業の15万加入が最も多く,建設業(7万8千加人),サービス業(6万6千加入),製造業(4万2千加入)が続いている。
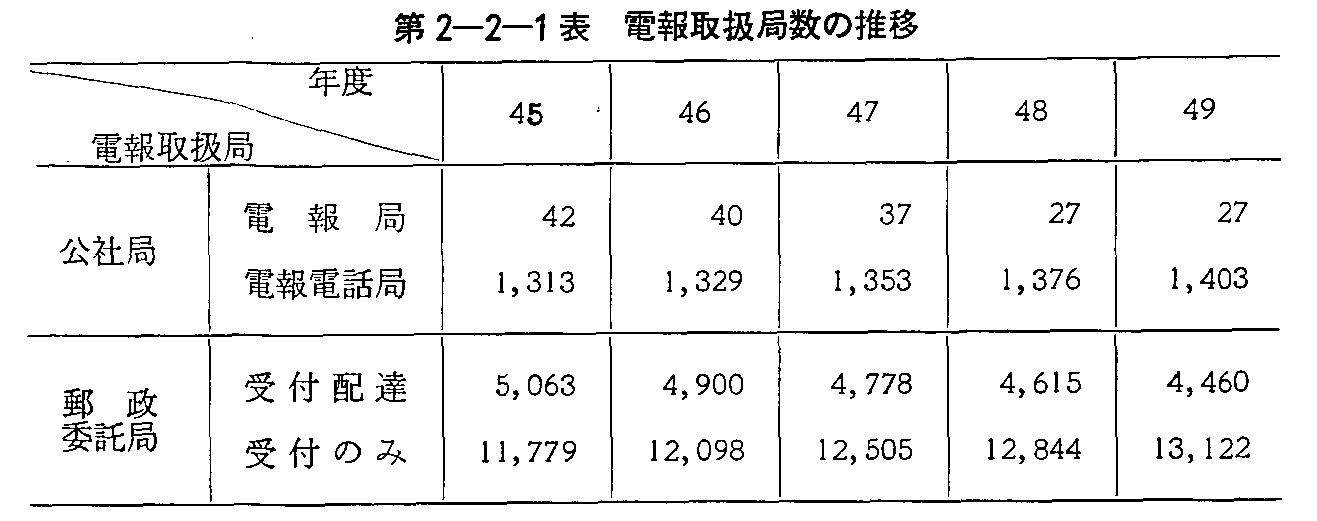
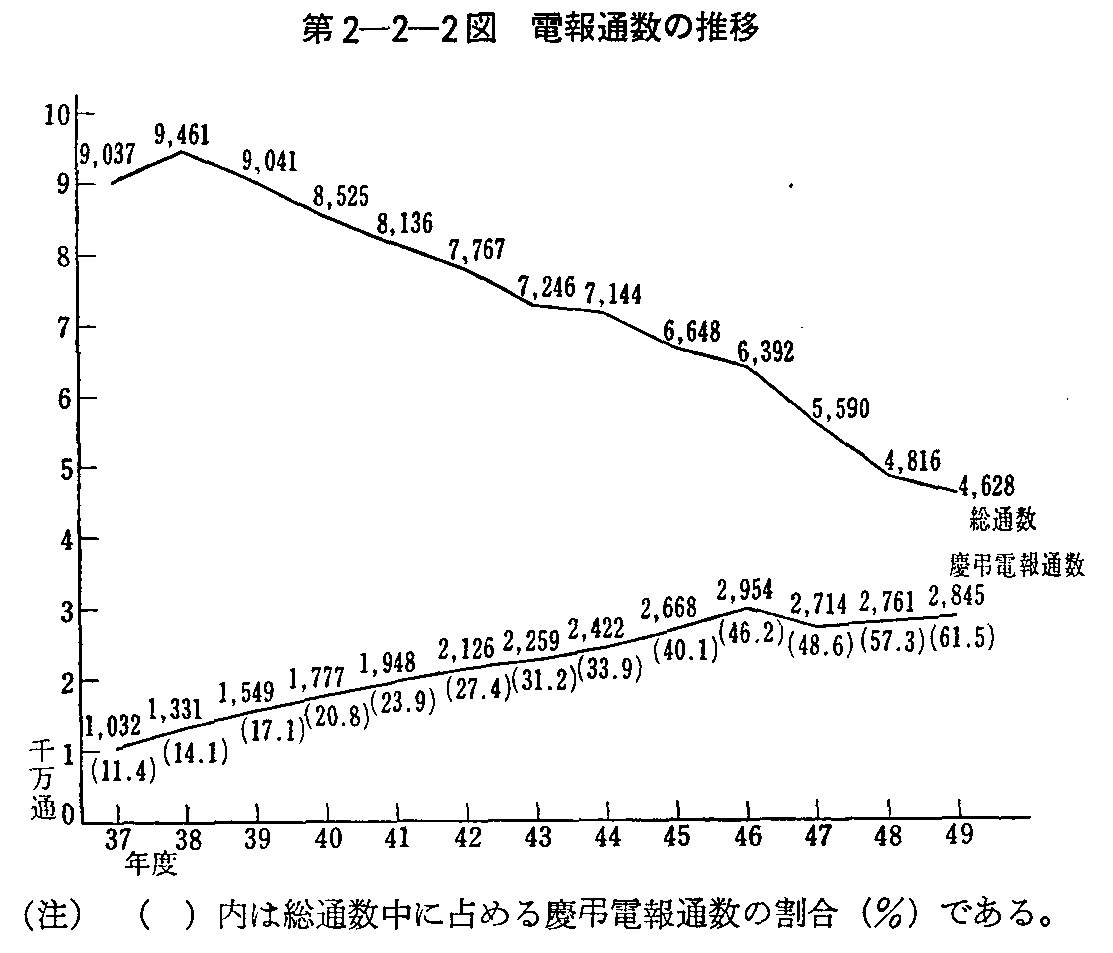
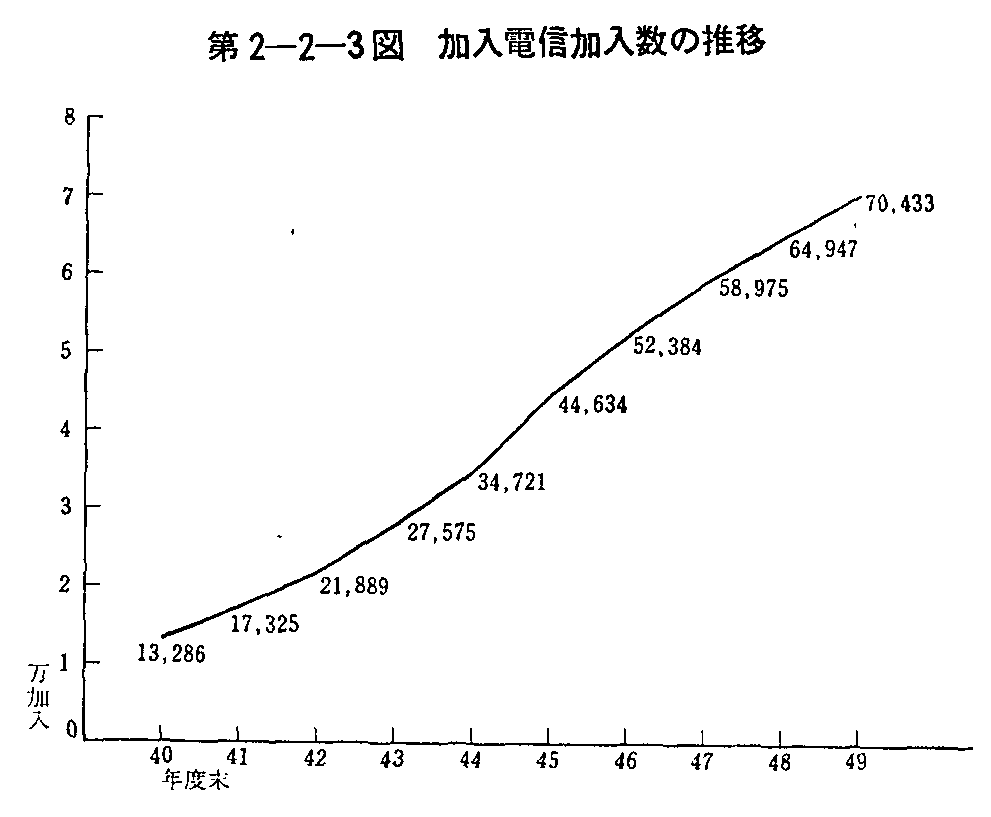
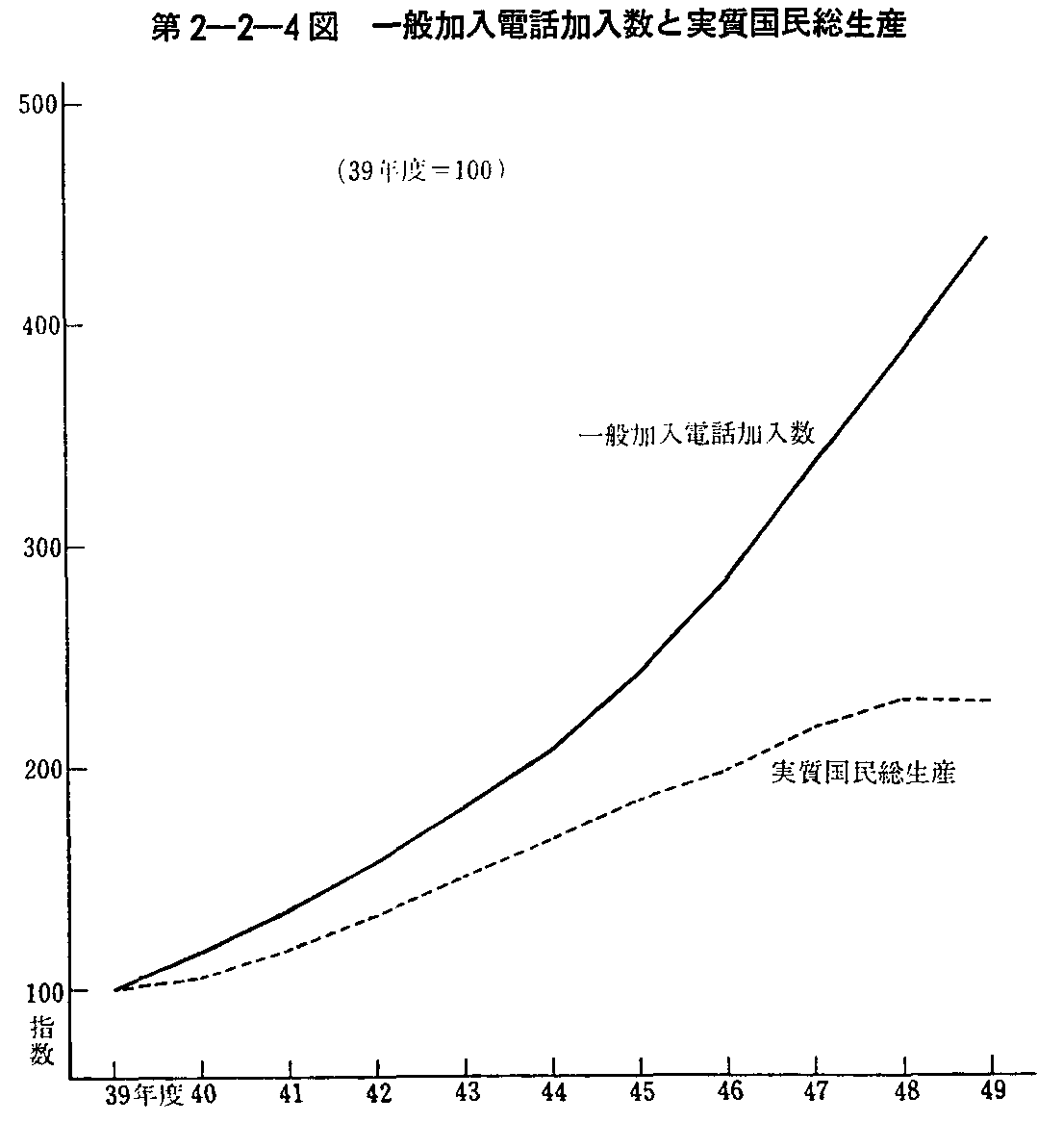
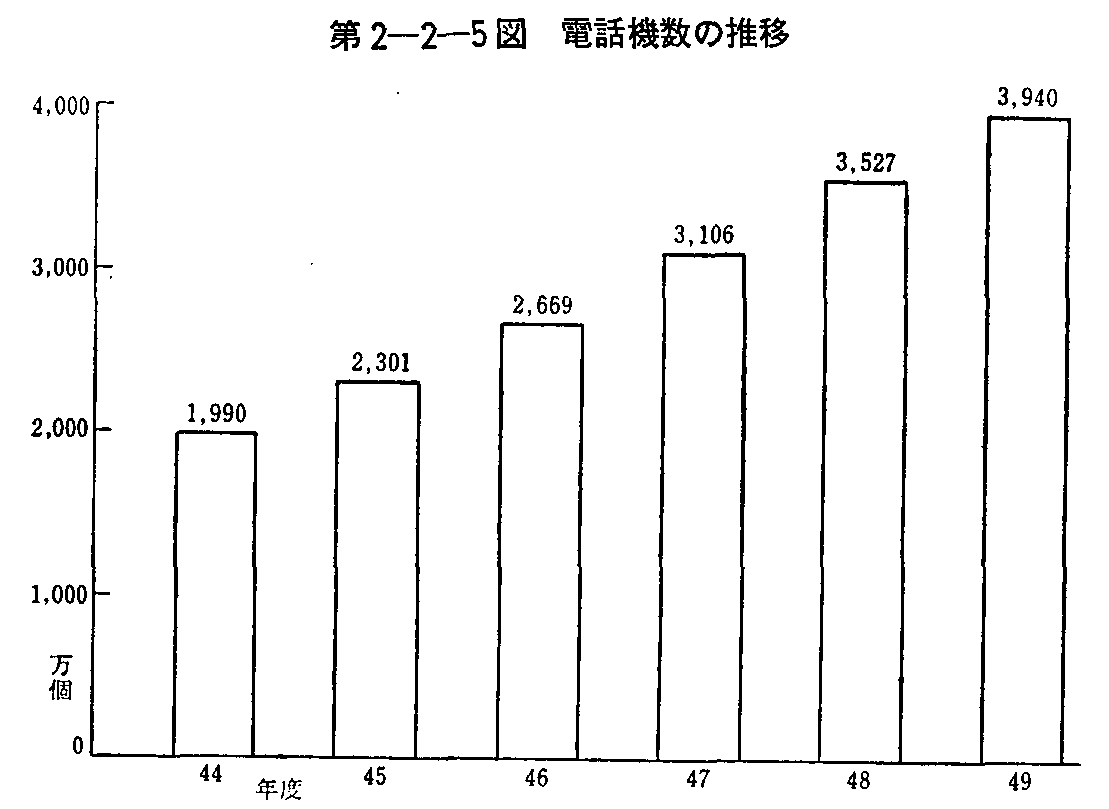
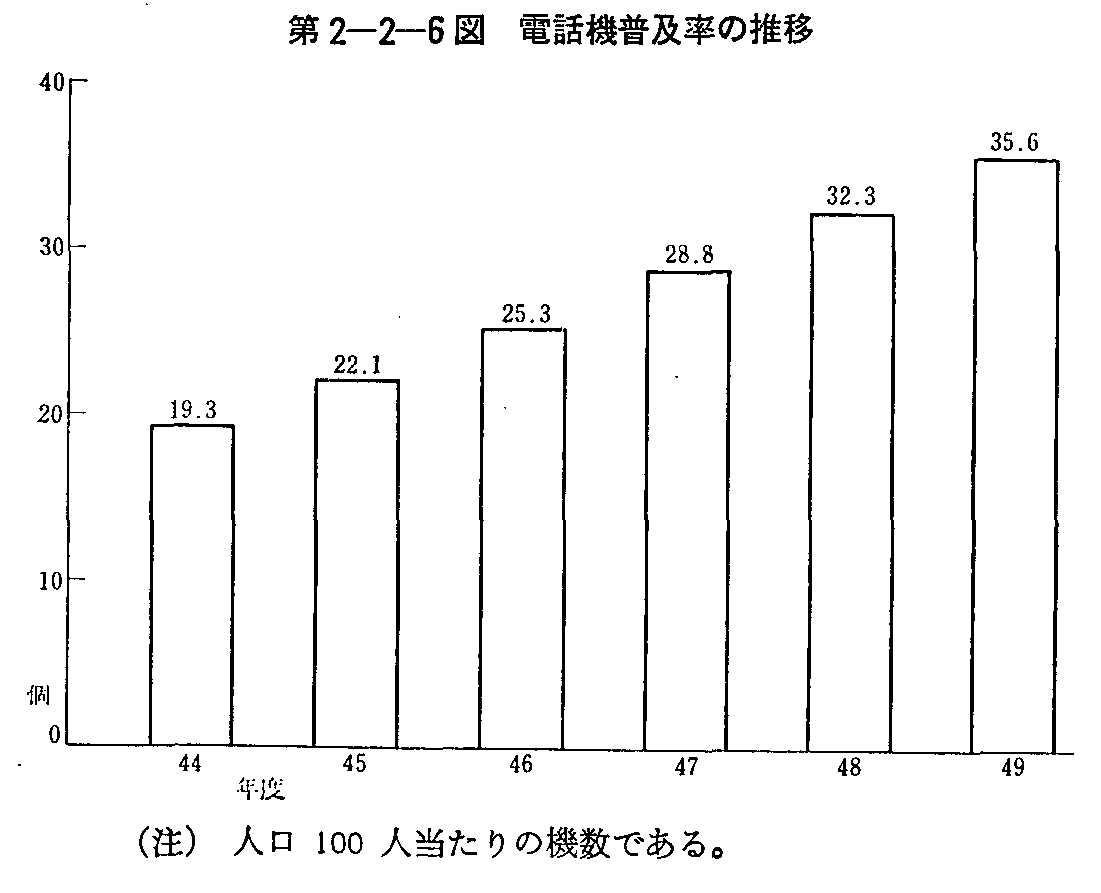
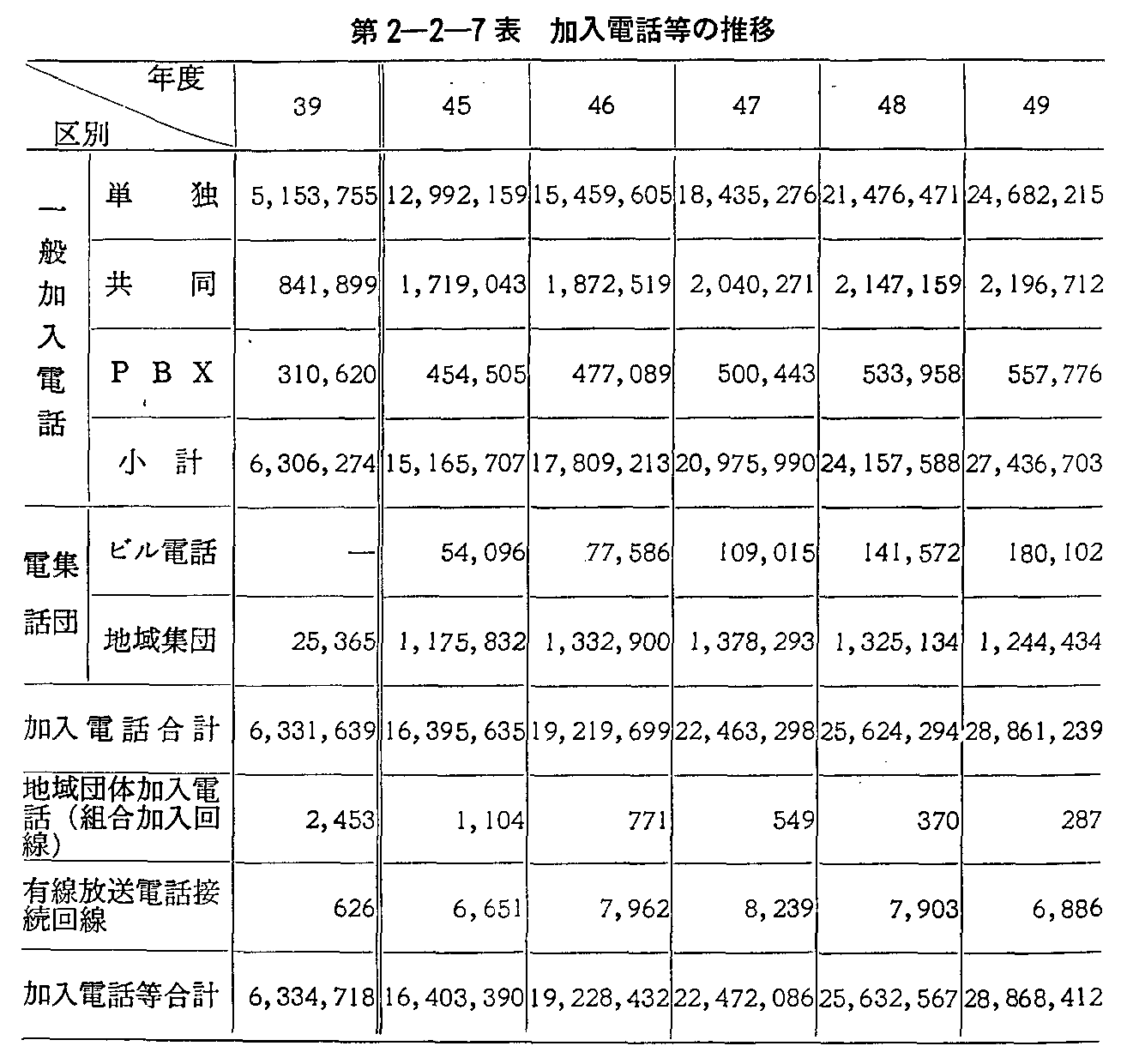
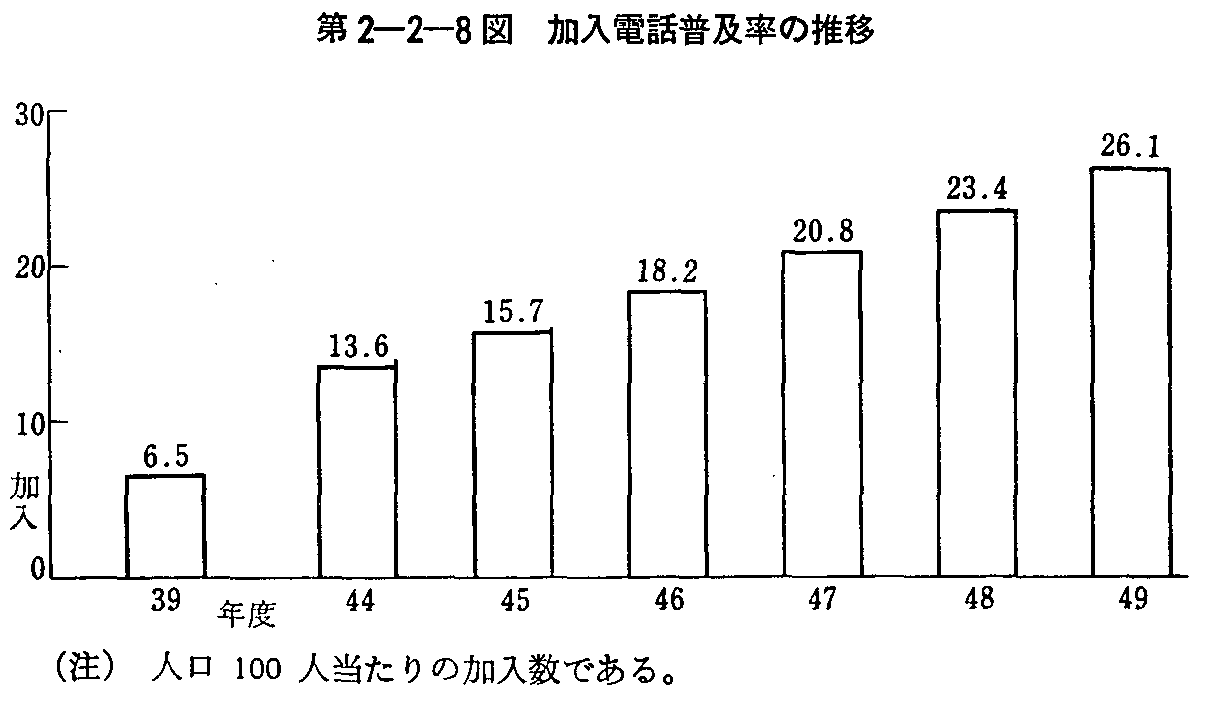
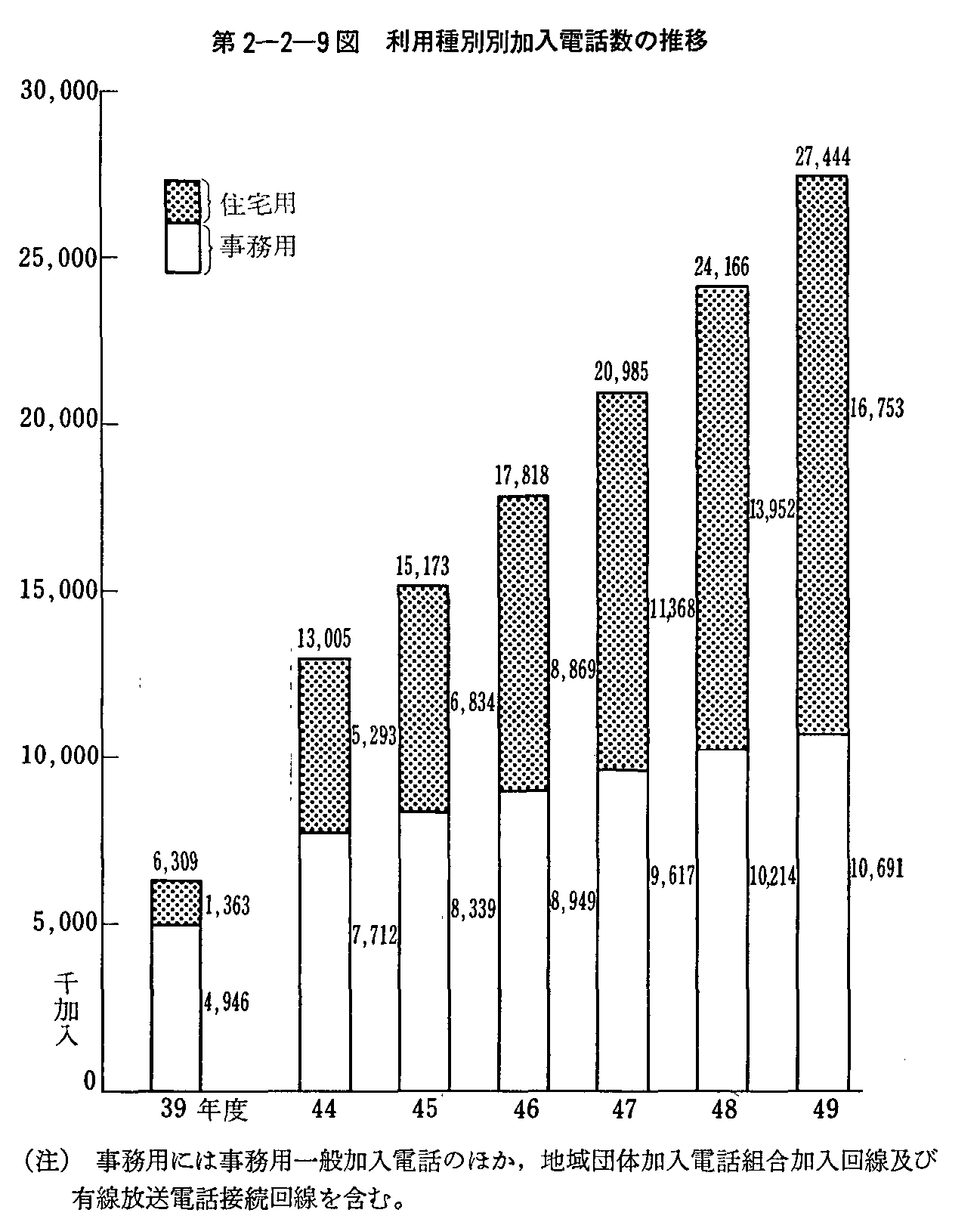
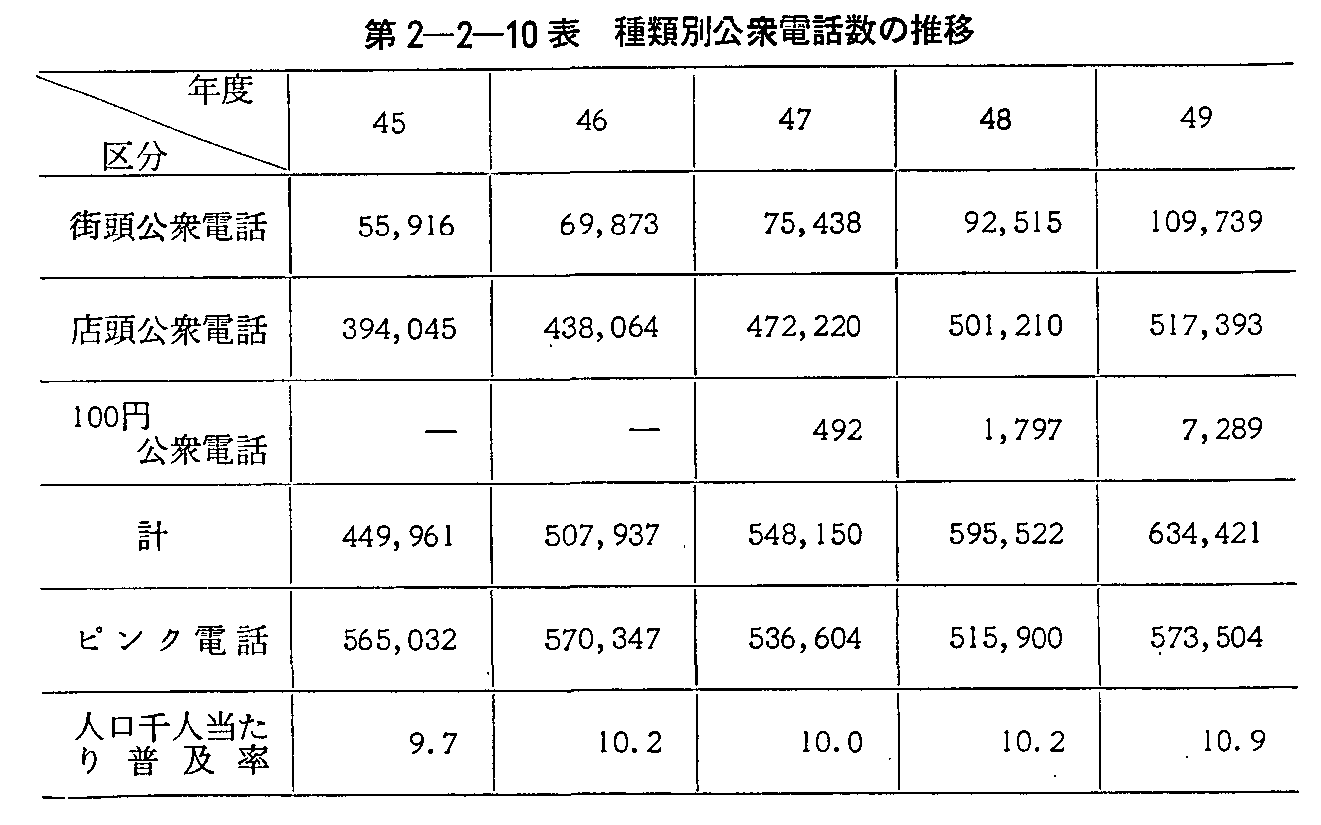
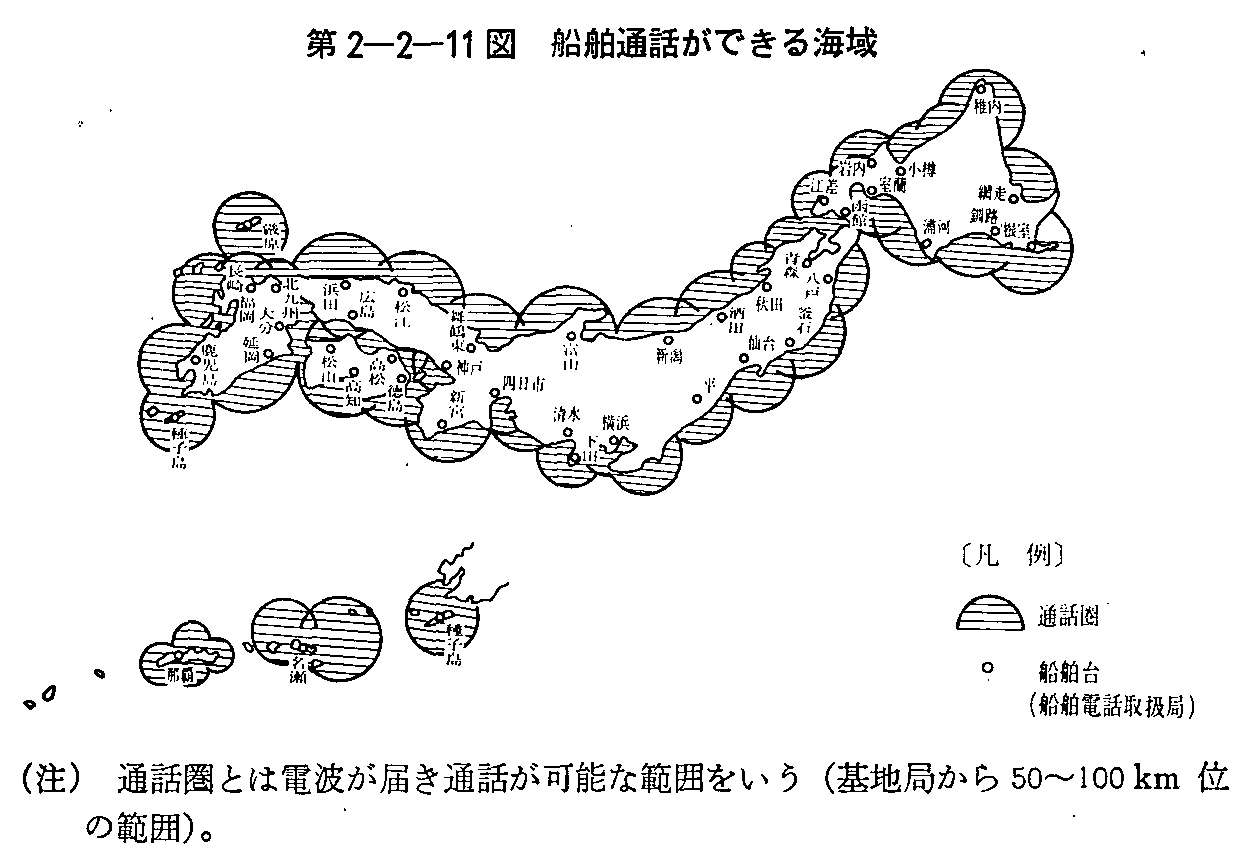
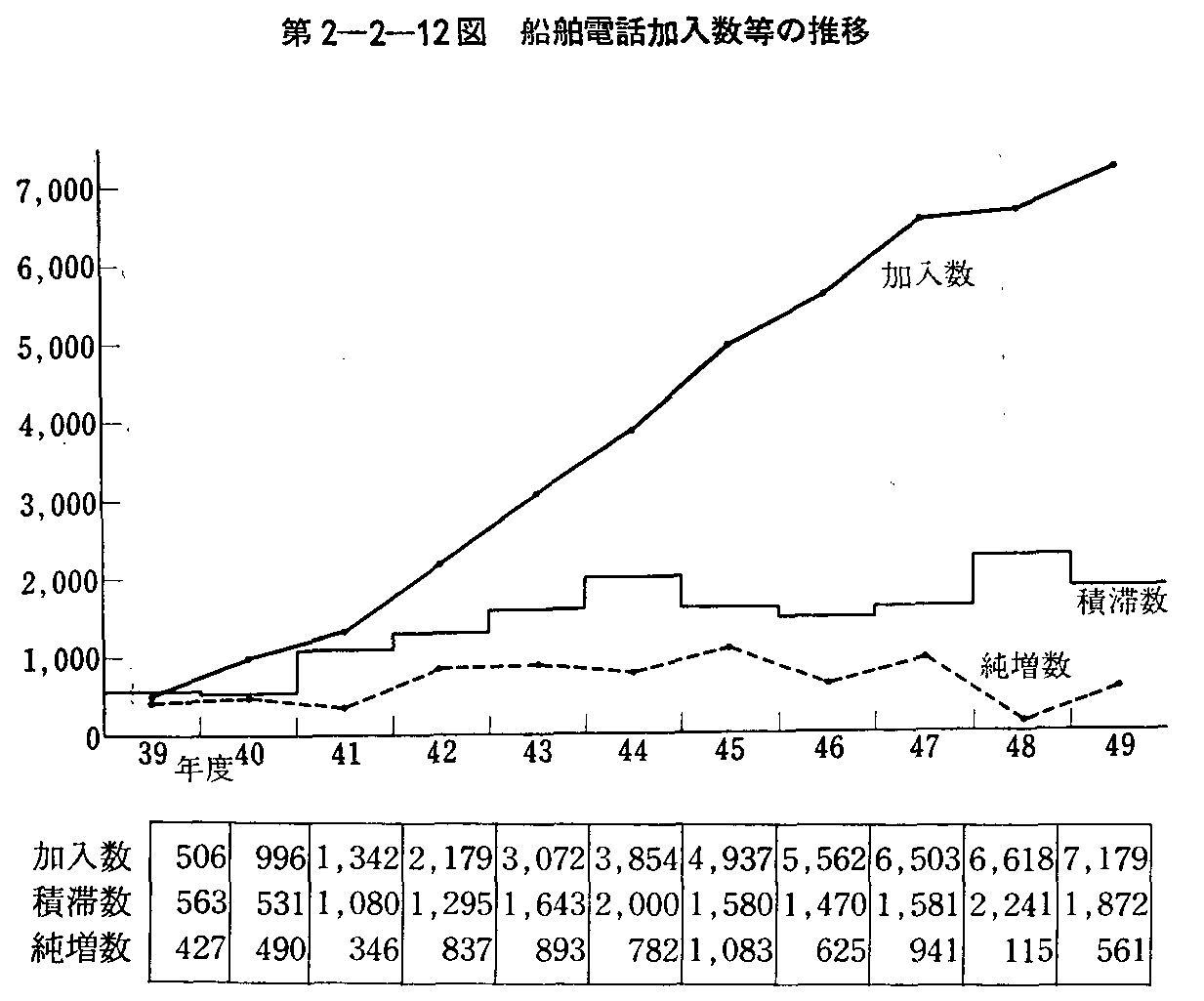
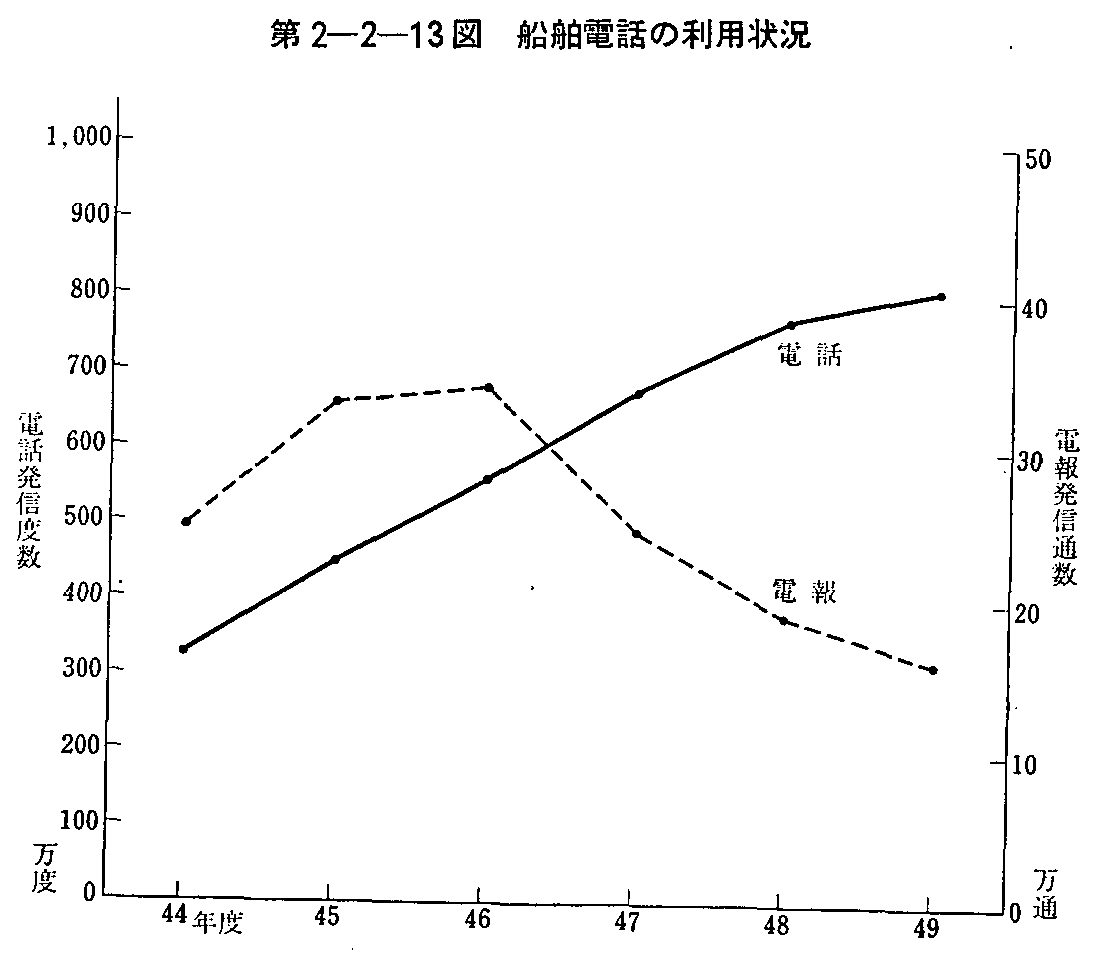
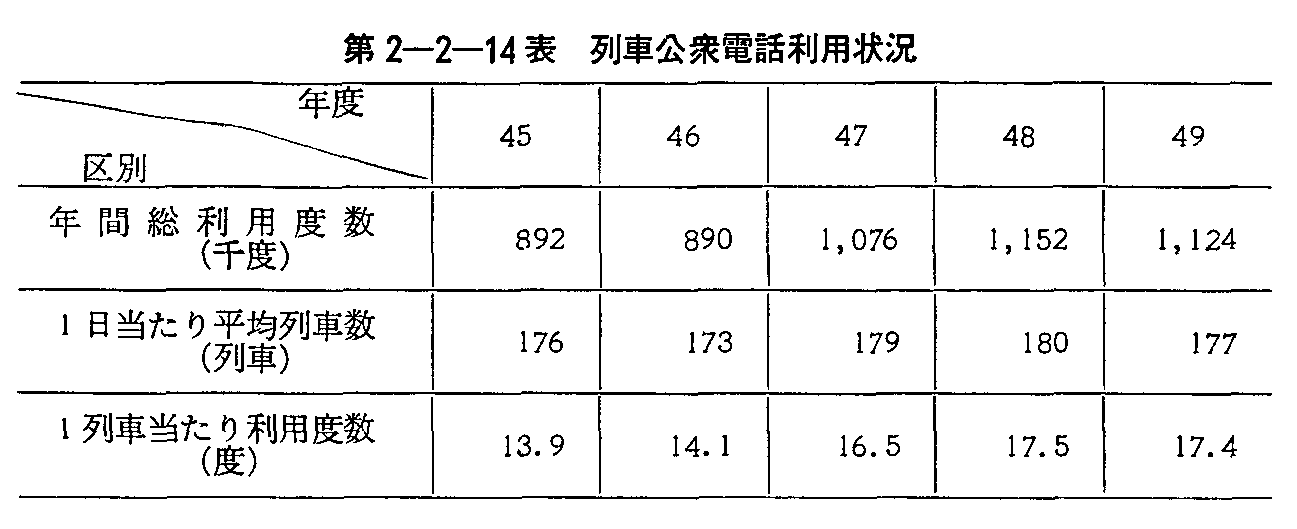
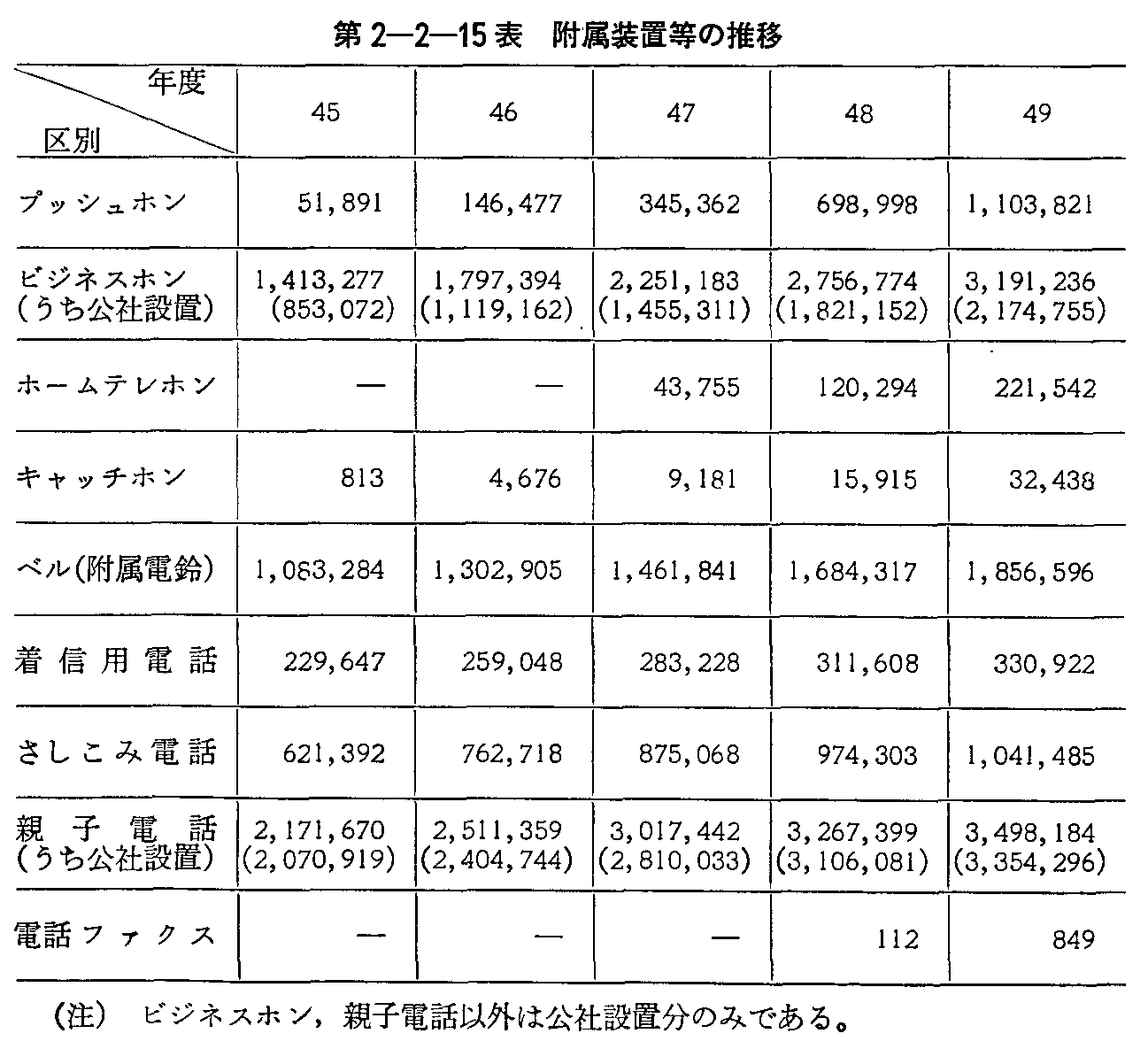
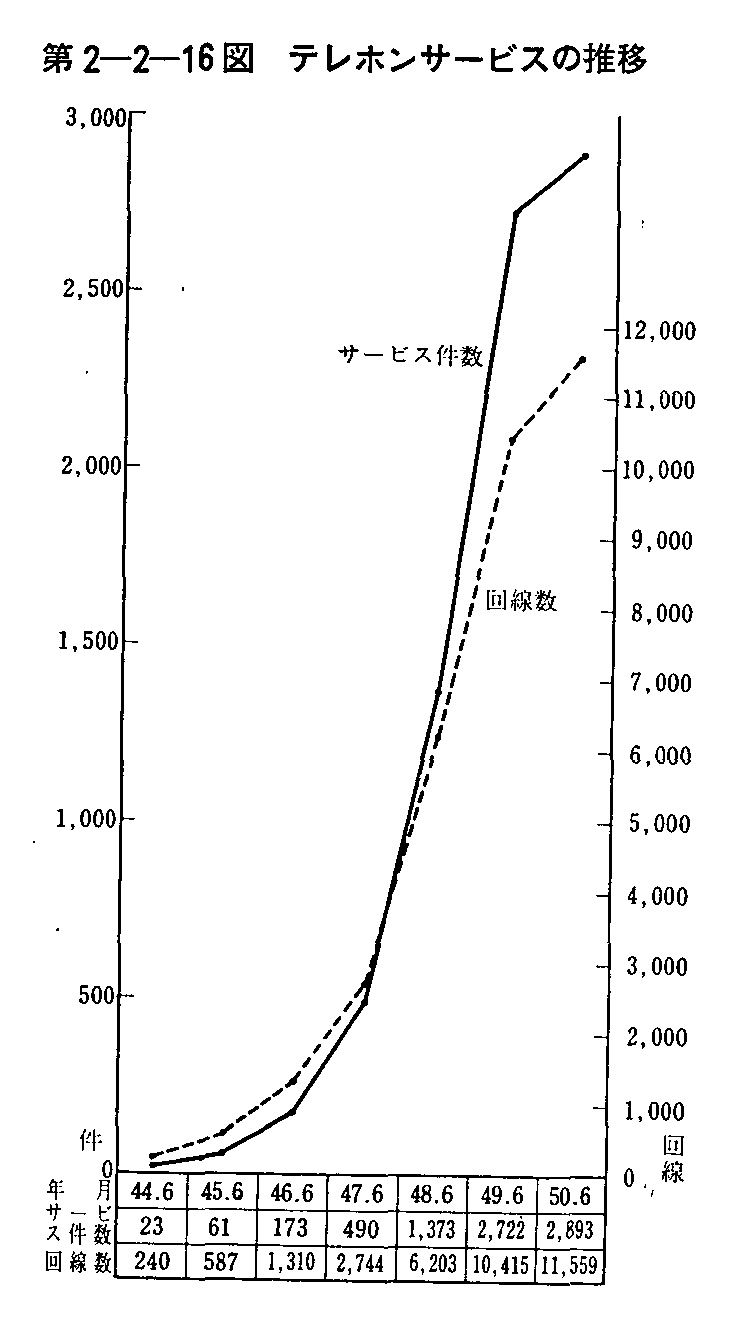
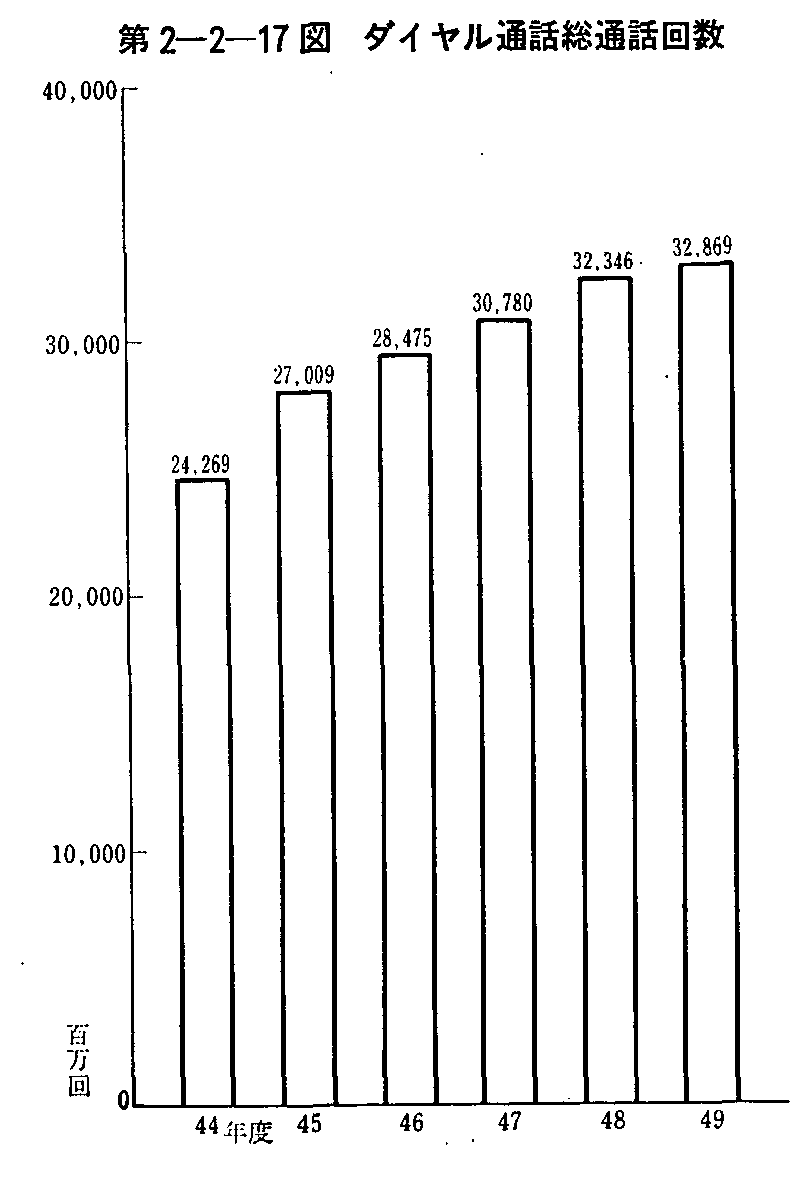
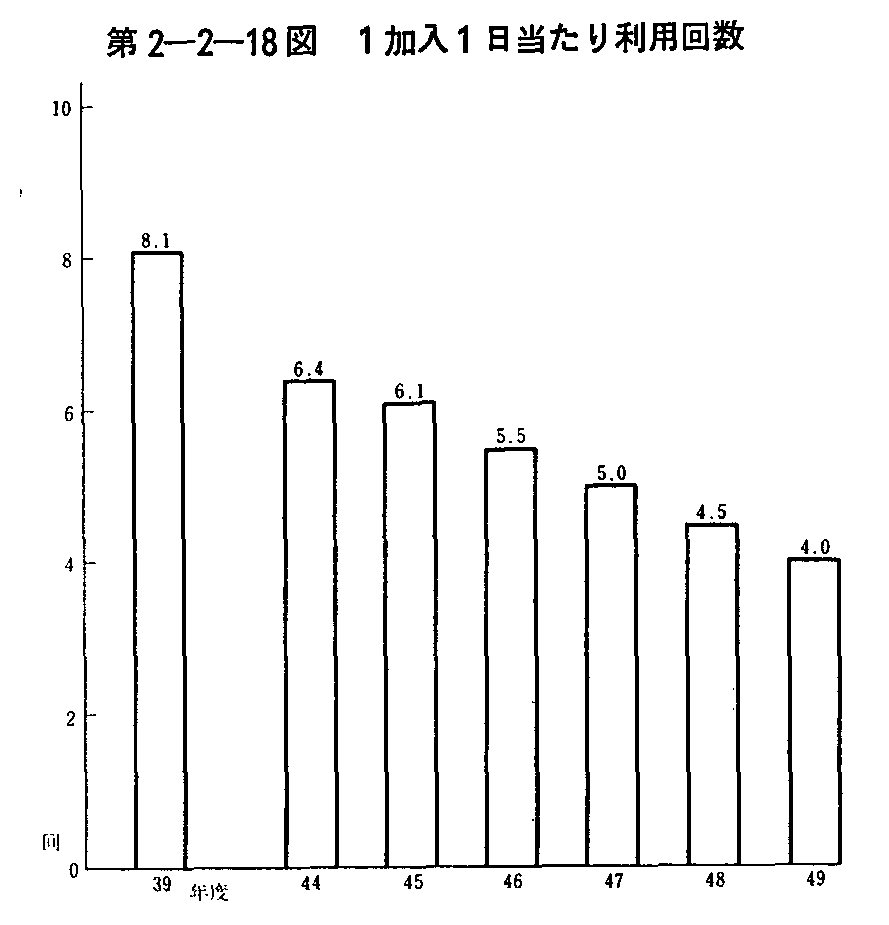
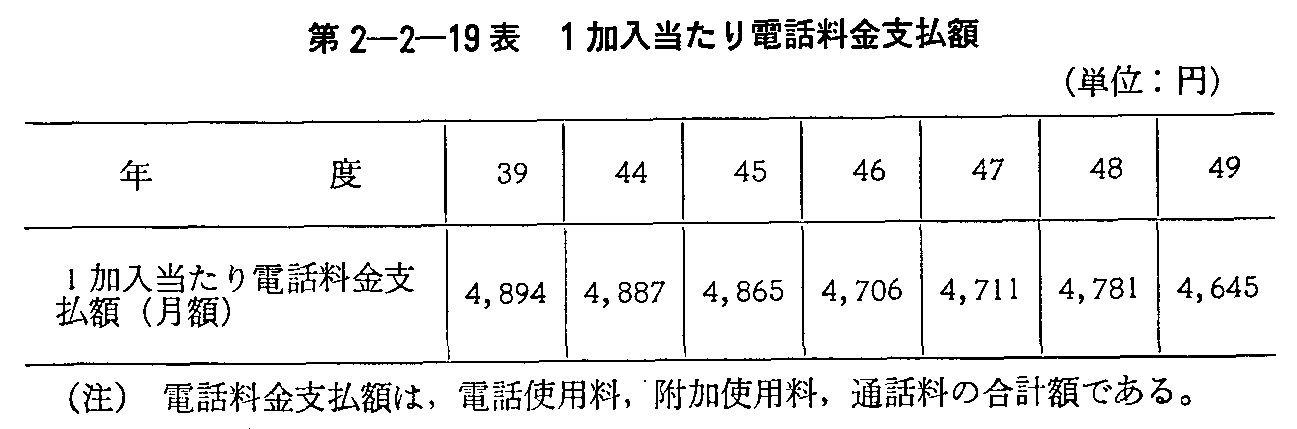
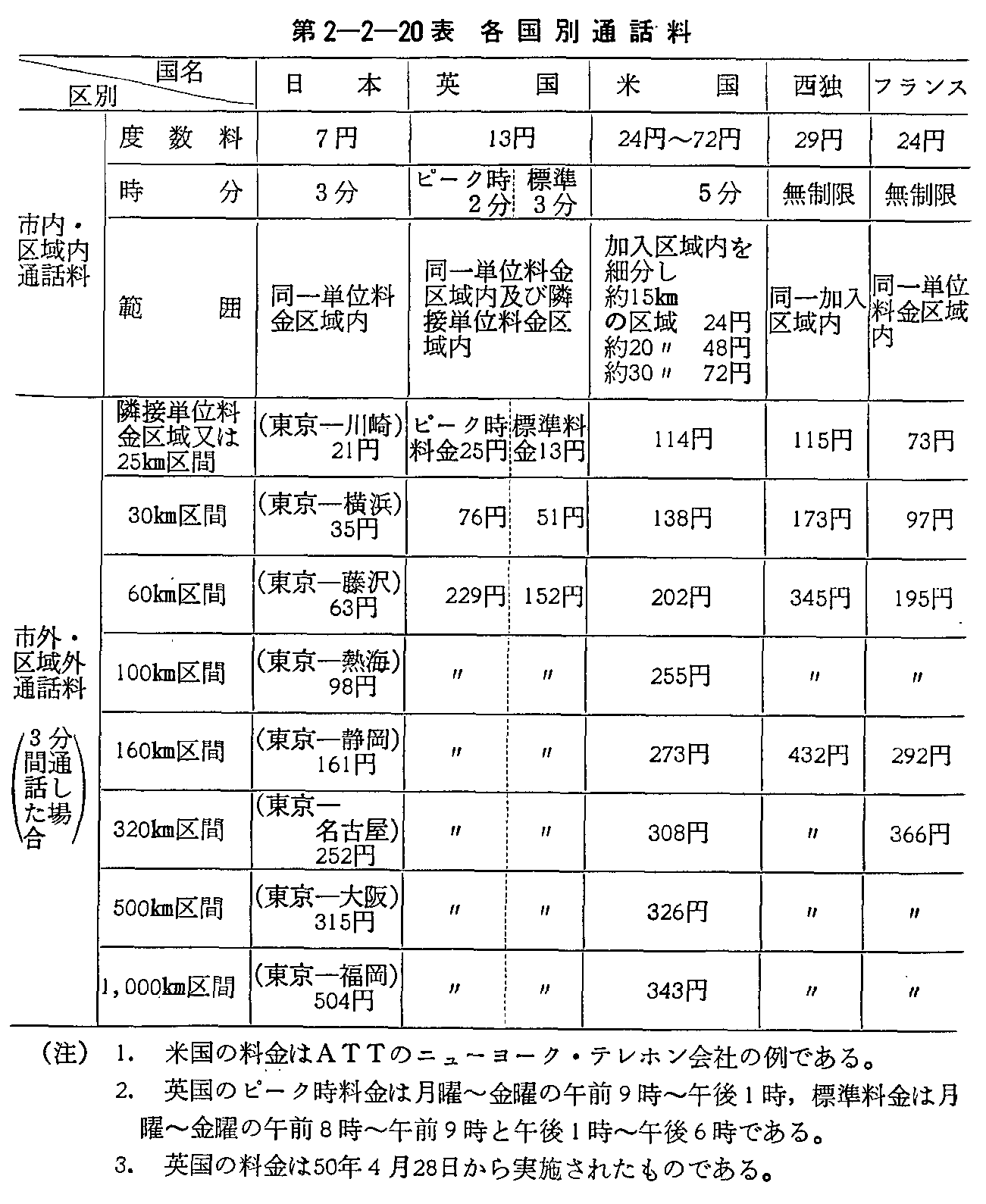
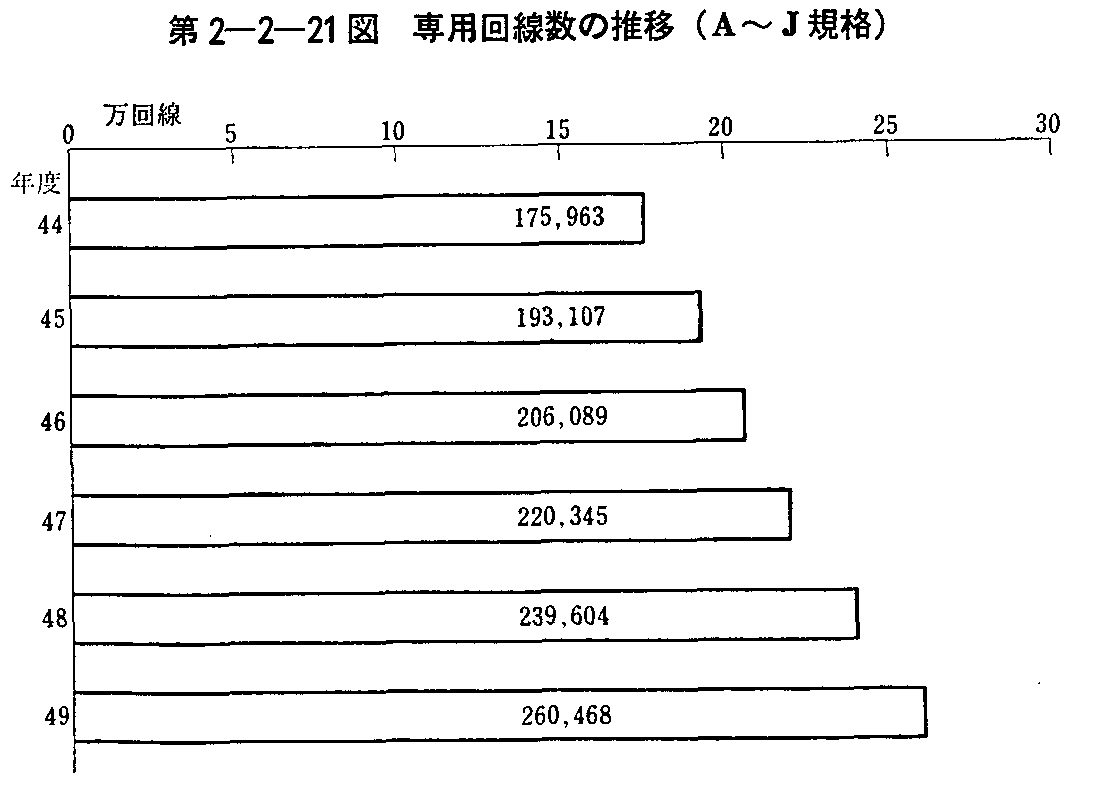
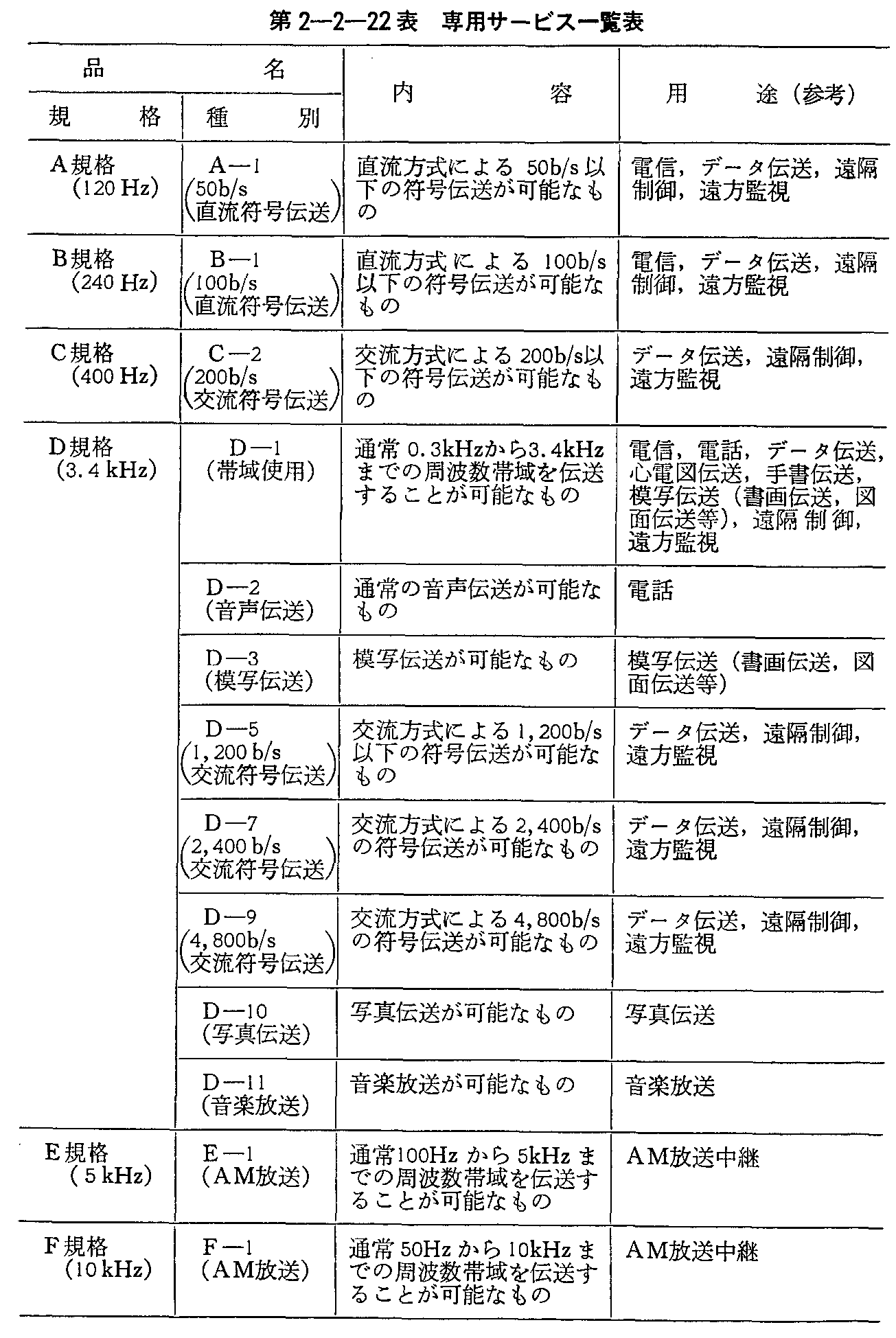
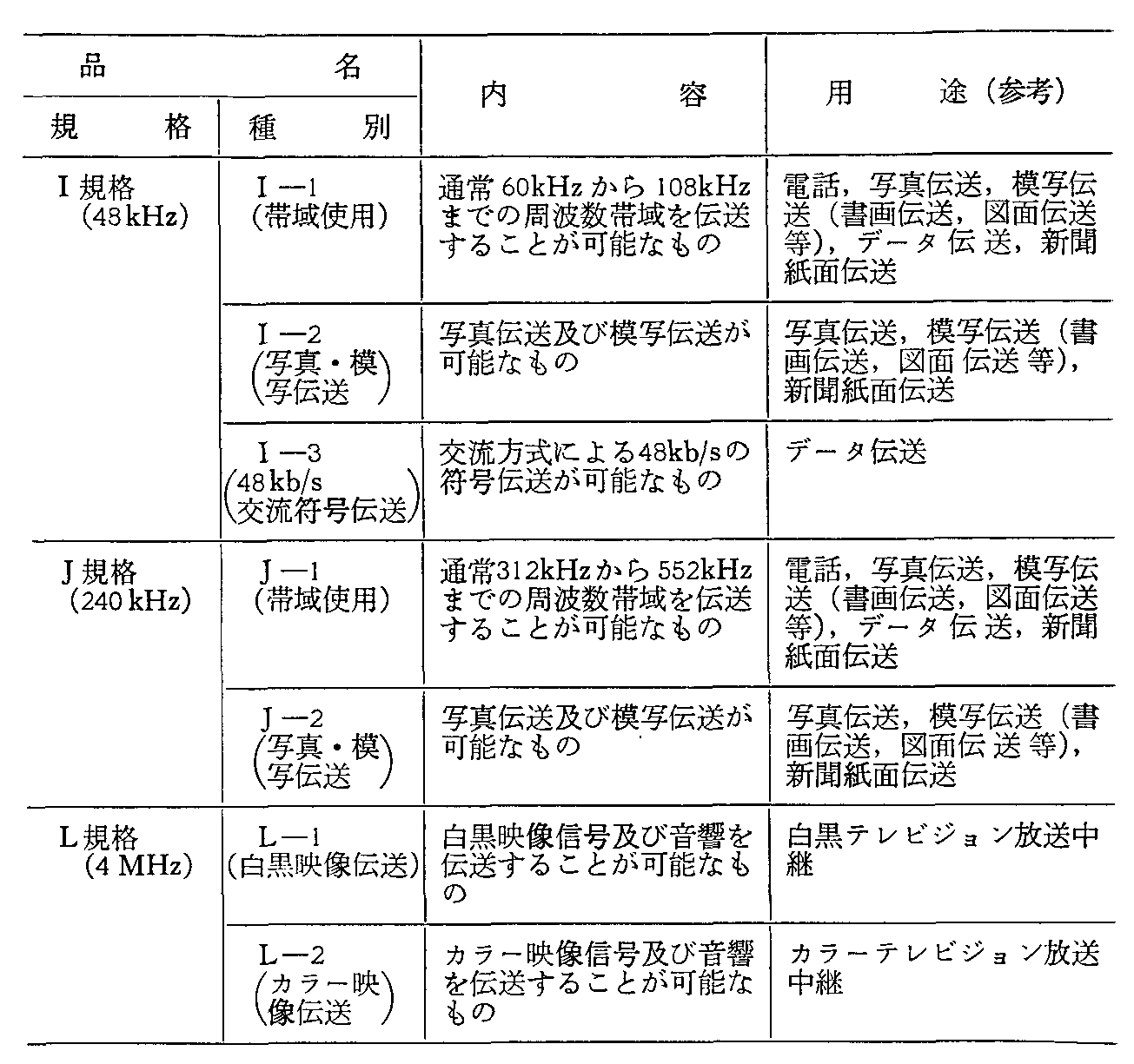
|