 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
3 老人及び身体障害者世帯における電話普及の動向
福祉優先の社会を重要な目標とする我が国においては,老人,身体障害者等の福祉対策が急務とされ,国としても重点的に推進を図っている。
郵政省においても,電気通信の分野から積極的に協力することとし,福祉用電話システムに係る機器の開発,普及を図るための基礎資料を収集する目的で,48,49の両年度において「通信サービスの需要動向調査」を実施した。
老人に関する上記調査によれば,公社電話,インターホン,ベル等の通信連絡手段を保有している老人は全体の45.4%であり,そのうち最も多いのは公社電話(34.7%)である。寝たきり及び寝たり起きたりの老人で,通信連絡手段を保有していない者は58.6%である。また,公社電話を持っていない理由は,経済的理由が43.7%,「近所で借りる」が27.8%などであり,無料で電話を架設するとするとき電話の架設を希望する者は62.3%となっている。
また,身体障害者に関する調査によれば,公社電話を保有している者は79.0%,公社電話はないが有線放送電話のある者は4.7%,電話を保有していない者は16.3%である。現在,公社電話を保有していない者のうち,国,地方公共団体が架設する福祉電話の設置を希望する者は89.5%である。なお,1日に1回も電話をかけない者が14.4%いるが,その理由として「自宅に電話がない」,「身体障害のため現在の電話機では取扱いが不便で使えない」という者が各々20.2%,14.6%いること,また,新しい通信手段に対する身体障害者の関心が相当高いことなどが注目される。
以上の調査を集約すれば,今後いかにしてこれらの人々に対して電話を設置し,また,機器の改善を図っていくかが大きな課題となっているが,その動向は次のとおりである。
(1) 機器開発
老人や身体障害者は身体機能が不十分なため,電話の利用に当たっても通常の健康な人と比べてハンディキャップがあるので,老人,身体障害者が利用しやすい機器の開発が強く望まれている。このような要請に対処するため,電電公社では次のような措置を実施している。
目の不自由な人でも電話が利用しやすいように盲人用ダイヤル盤を45年4月に開発し,盲人施設や盲人家庭の希望者に無料で取り付けている。この盲人用ダイヤル盤は直径45mmの円型金属板に3本の突起(ガイドライン)を付けたもので,これを電話機のダイヤル盤に取り付け,指で触れると3,6,9のダイヤル数字の位置が分かるようにしてあり,現在,全国で約7万個が利用されている。
公衆電話についても,身体の不自由な人が便利に利用できるよう,48年9月から身体障害者施設や福祉事務所等に公衆電話の設置を進めるとともに,車いすのままで利用できるように置台やキャビネットの高さを20cm程度低くしたり,盲人用ダイヤル盤を取り付けるなどの改善を行っている。これらは,現在,東京,大阪をはじめ全国で約2,300個設置されているが,今後は施設に限らず街頭等の公衆電話についてもボックス,置台,キャビネット等を改善するよう検討を進めている。
また,一人暮らし老人等に便利な電話機器として現在シルバーホン(あんしん)を開発中であり,本格的なサービスの実施に先立ち,実際に設置した場合の利用実態,利用者への適応性等について調査を行うため,市町村が設置する老人福祉電話及び身体障害者福祉電話を対象として,50年度中に試験的にサービス提供を行う予定である。シルバーホン(あんしん)は,一人暮らし老人等が日常簡単に電話をかけることができるだけでなく,緊急の場合にはボタンを押すだけでヘルパや掛かり付けの医者を呼び出し,あらかじめ吹き込んだ録音テープて自動的に急を告げることができるものであり,この装置の機能は次のとおりである。
[1] 送受話器を上げずに緊急ボタン又はリモートスイッチを押すだけで,特定の連絡先を呼び出し,あらかじめ吹き込んであるカセットテープにより自動的にメッセージを送ることができる。
[2] 日常よく電話をかける相手の電話番号をセットしておき,送受話器を上げてから自動ダイヤルボタンを押せば自動的に呼び出しができる。
[3] 受話音量が通常の電話機の約3倍になっている。
[4] ベルの音量調節ができる。
[5] 電話機だけを持ち運べるように装置と電話機がロングコードで接続されている。
耳の不自由な人のためにシルバーホン(めいりよう)を開発中である。この電話機は,送受話器に音量調節つまみを組み込み,このつまみを操作しながら自分の聴力に合わせて相手の声を聞くことができるもので,難聴度が4級から6級程度の難聴者に有効である。
更に,電話機のベル音が聞き取りにくい人のために,着信がフラッシュ式の表示ランプで分かる閃光式着信表示器や低周波の鳴音を発する電鈴も近く実用化されることになっている。
このほか,難聴者用公衆電話機について本格的検討を進め,試作を行うとともに,今後の福祉対策用機器の充実を図るため,難聴者用の骨伝導電話機等について基礎検討を行うこととしている。
(2) 普及対策
身体の機能が衰えた一人暮らし老人にとって,電話は通信連絡を確保する有力な手段となるものであるが,46年12月国の社会福祉施策の一環として,福岡,豊橋の両市において老人電話相談センタを設置するとともに,低所得の一人暮らし老人等で定期的に安否の確認を行う必要があると認められる老人にいわゆる老人福祉電話を設置して,安否の確認,各種の相談を行う事業が開始された。この事業が毎年積極的に推進されるとともに,国の補助を受けない地方公共団体や社会福祉法人独自の施策も多数みられるようになった。また,48年から身体障害者宅に設置するいわゆる身体障害者福祉電話が一部地方公共団体独自の施策として行われ,50年度から国の施策としても実施される予定である。50年3月末現在老人福祉電話8,800台,身体障害者福祉電話231台が設置されている(第1-2-5表参照)。
これらの福祉電話の架設に当たっては,国,地方公共団体等が設備料,加入料を負担しているが,電電公社においても郵政省の指導の下に,債券の引受を免除するとともに,その加入申込を優先的に承諾することとしている。また,一人暮らし老人等個人からの加入申込についても,48年6月から加入電話優先設置基準を改正して,一人暮らし老人,身体障害者,公害病認定患者,母子家庭等を対象にその加入申込を優先的に承諾することとした。なお,49年度中にこの適用を受けた加入数は,8,027加入である。
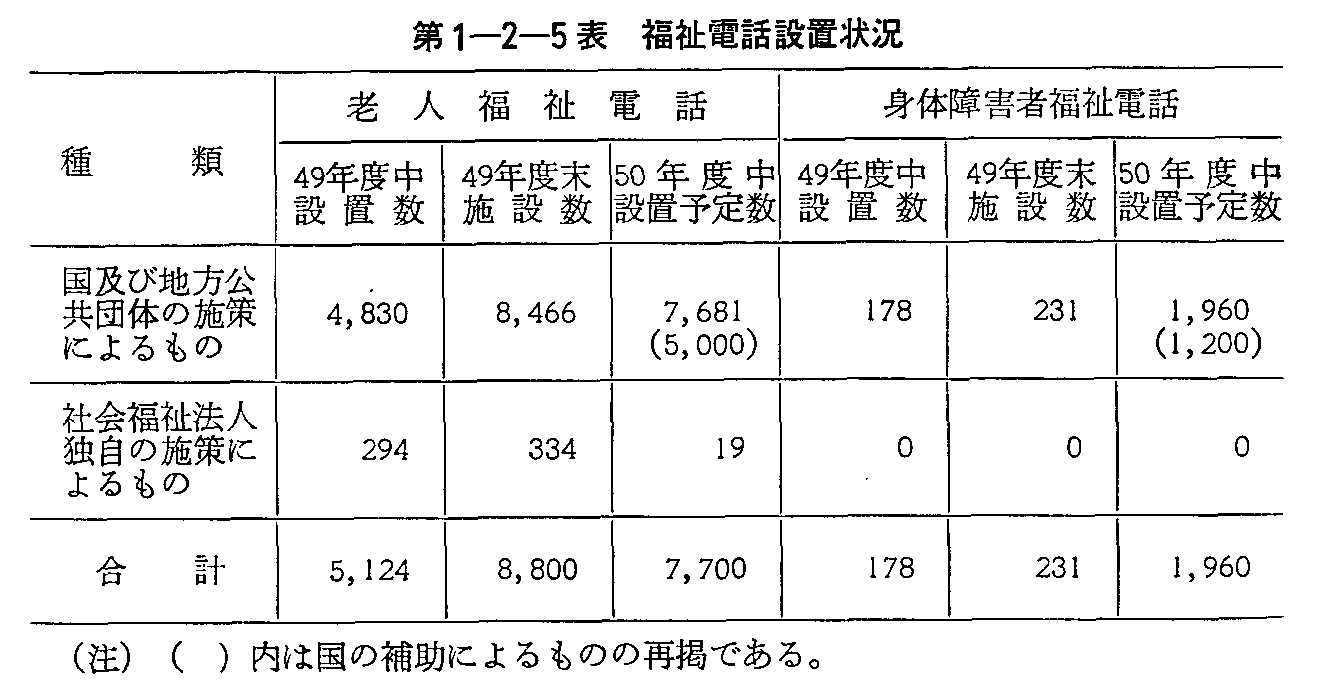
|