 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
9 漁 業 用
我が国は世界屈指の漁業国であり,漁業は毎年発展の一途をたどってきたが,近年漁場環境の悪化と国際的な漁業規制の強化等によって,その前途は誠に厳しいものがある。加うるに,48年の石油危機以降における漁業用資材価格の異常な値上りも漁業経営に深刻な影響を与えている。こうした情勢は,漁業に従事する漁船の船舶局の普及の動向にも影響を及ぼし始めており,特に遠洋漁業に従事する50トンを超える大中型漁船の船舶局は漸減の傾向にあるが,一方10トン未満の小型漁船の船舶局は沿岸漁場の整備と,つくる漁業への転換と相まってむしろ増加の傾向にあると言える。
漁船の船舶局の局数は,49年度末には4万3,175局に達しその普及状況は第2-3-14表のとおりである。
無線電信及び無線電話は海上における唯一の通信手段として,船舶の航行の安全及び人命財産の安全に必要欠くことのできないものであり,特に漁船は船型がおおむね小型であるにもかかわらず,出漁海域が広範にわたっており,かつ,洋上で操業するという特殊性をもっているので,無線通信の果たす役割は極めて大きく,漁場で能率よく操業するためには,漁海況情報の連絡,漁場の秩序維持のための通信及び漁獲物の水揚げ等漁業経営の合理化を図るための通信が極めて大きな比重を占めている。また,乗組員の家族との間の安否に関する電報の取扱いも漁船の運航に欠くことのできない通信の一つである。
その使用する電波は,沿岸及び沖合漁業では27MHz帯又は中短波帯,遠洋漁業では短波帯が主に使用され,海岸局及び船間相互間で通信を行っている。現在,漁船の船舶局が使用する電波は27MHz帯153波,中短波帯102波,短波帯302波,VHF帯26波である。
次に,漁業用海岸局として遠洋漁船との間に短波無線電信による漁業通信を行うことを主目的として,37年4月,千葉県松戸市に開設された中央漁業用海岸局は,沖合漁船向けに漁海況ファックス放送並びに無線電信及び無線電話による漁海況放送を行うとともに漁業通信の合理化を図るため,短波帯における狭帯域直接印刷電信(テレプリンタ)通信をも行っている。
また,全国の主要漁業根拠地には,民間漁業者が構成員となって組織している漁業者団体が開設する漁業用海岸局と,国(水産庁)又は都道府県が漁業の指導監督業務用のため開設する漁業指導監督用海岸局とがあり,漁船の船舶局と常に緊密な連絡を確保し,人命財産の安全と漁業経営の向上を図っている。49年度末現在,漁業用海岸局484局,指導監督用海岸局70局である。これらの海岸のうちには,2,091kHzの遭難信号受信機又は27,524kHzによる注意信号受信機を備えて漁船の安全確保のため聴守を行っているものもある。
(1) 沿岸漁業及び沖合漁業の無線通信
沿岸漁業の漁船特に10トン未満の小型漁船の船舶局は,その漁船総数に比して無線設備を装備する割合いはいまだ9.4%と極めて低いが,主としてこれらの漁船に使用される27MHz帯1W・DSBの設備は,価格の低廉と操作の簡便さから,この種漁船の船舶局は今後とも増加の傾向にあり,その船舶局数は2万7,787局であって,全漁業用船舶局4万3,175局の64.4%を占めている。
また,この周波数帯のみの漁業用海岸局も326局で,全漁業用海岸局554局に対し,58.8%を占めている。
これらの漁船の行う通信は,船間通信では漁海況の交換,投網,揚網の際の連絡が主で,また,同一の漁場に多数の漁船が集まる入会い操業の場合は,この船間通信は操業に欠くことのできないものとなっている。
漁業用海岸局が所属漁船の船舶局との間に行う陸船間通信は,気象,漁海況,操業上の注意及び入港時間等の通報の交換であるが,これらの通報は漁船の操業の安全と漁獲の向上に大いに役立っている。
小型機船底びき網,まき網,さんま棒受け網,いかつりなどの漁業で,沿岸又は近海に出漁する50トン前後の中型漁船は,中短波帯の電信,電話あるいは短波帯の電信,電話によって漁業通信を行っており,その普及率は10トン以上100トン未満の海水動力漁船1万4,854隻のうち1万2,192隻が無線設備を装備しており82.1%となっている。
(2) 遠洋漁業の無線通信
我が国の遠洋漁業はその操業海域が太平洋全域から大西洋,地中海,インド洋と世界の全海域に及んでおり,まぐろ,かつお漁業,底びき網漁業,捕鯨業及びまき網漁業等を行っているが,いずれも操業期間は半年から1年間と長期にわたっているため,無線通信は極めて重要な役割を果たしている。
これらの漁船の船舶局は主として短波帯の電信又は電話を使用しているが,短波帯は世界的に共通に使用されているため混信が多いことと,操業海域によっては電波伝搬の特性から我が国の海岸局と直接通信を行うことが困難な場合も少なくない。49年度末現在,これらの漁業に従事している船舶局は7,442局であり,また,これらの漁船の船舶局を通信の相手方としている漁業用海岸局(12MHz帯以上の電波を装備しているもの)は63局である。
また,これら遠洋漁業に従事する漁船の船舶局の漁業通信の取扱状況を中央漁業用海岸局についてみると第2-3-15表のとおりである。
(3) 母船式漁業の通信
我が国の母船式漁業には,南氷洋捕鯨業と母船式北洋漁業(さけ,ます,かに,底魚,捕鯨)があるが,年々国際的規制も厳しくなっており,漁獲量のわくも減少しているが,無線通信は,出漁船の安全確保と操業の円滑化に役立っている。
母船と独航船又は捕鯨船,独航船相互の船間通信には,27MHz帯,中短波帯及び短波帯が使用されており,母船と我が国漁業用海岸局との間の陸船間通信には短波帯が使用されている。
母船式漁業においては,その通信量が膨大であることと限られた通信可能な時間帯にこれらの通信を迅速にそ通させることが必要であるため,短時間に多量の通信そ通が可能である狭帯域直接印刷電信(テレプリンター)が導入され,漁業通信の省力化と能率化に役立っており,今後の普及が期待されている。
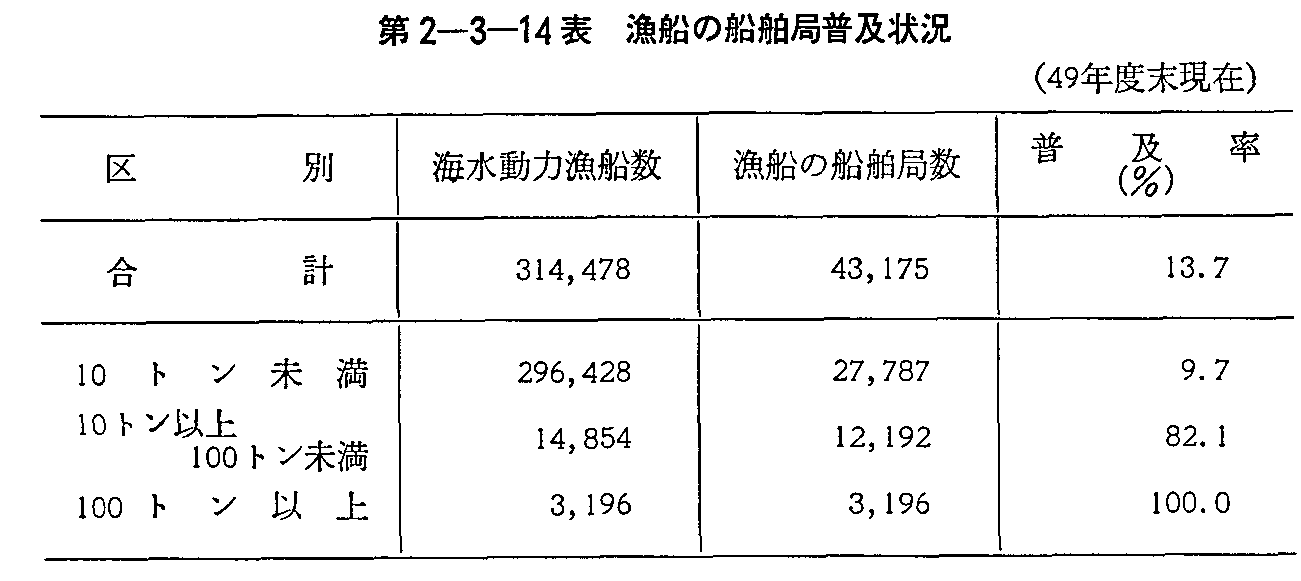
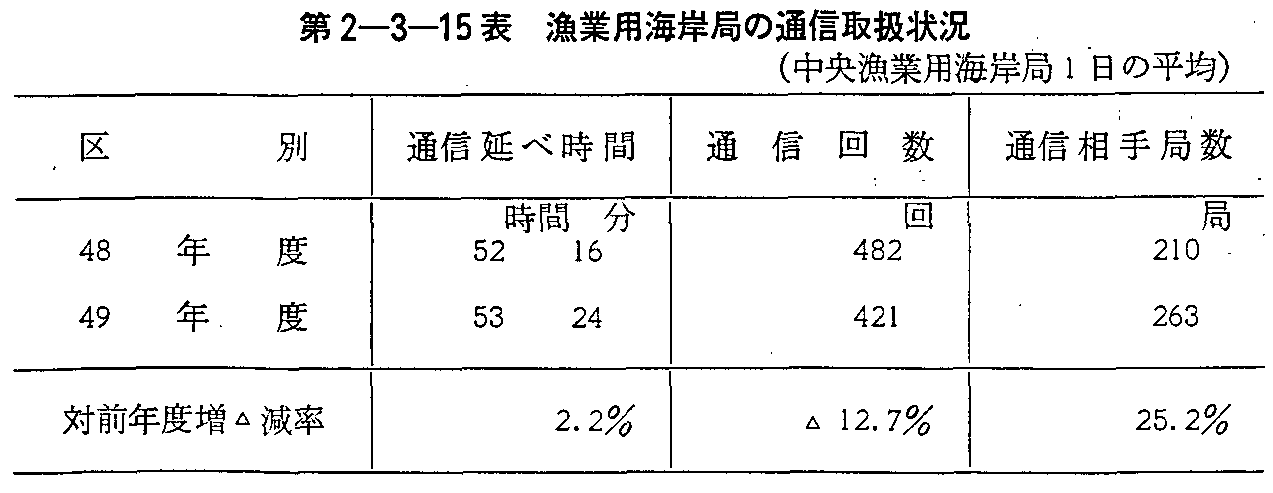
|