 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 農林漁業地域における電話
戦後における急速な経済成長は,国民に豊かな経済生活をもたらしたが,一方では人口の大都市への集中により,都会においては過密や公害をもたらし,また,農村等においては過疎や荒廃を生ずることとなった。このような事態に対処して,地域住民の福祉向上,国土の均衡的発展を図るため,各分野から地域開発計画,過疎対策が実施されているが,電話の分野においてもこれに応じて次のような種々の施策が行われてきた。
(1) 農林漁業地域に適合したサービスの実施
農林漁業地域の電話を都市の電話と比較した場合,利用面においては通話回数が少なく,また,その通話は地域共同体内の通話が多いなどの特性があり,設備面においては電話局から加入者までの線路距離が長く,1加入当たりの設置費や保守費が高いなどの特徴があげられる。戦後における経済成長の過程で農林漁業地域においては過疎化が進展したが,一方では地域住民の生活も年々豊かになり,その電話需要も増加の一途をたどっていたので,電電公社では限られた資金でこのような需要をできるだけ充足するため,農林漁業地域の特性に適合した電話サービスを開発し,その普及を図ってきた。
25年ごろ我が国における電話需給の不均衡を打開する方策の一つとして,米国において普及発達していた農村電話に倣い,多数共同電話を実施した。多数共同電話は,一つの加入回線を3加入から10加入の加入者が共同して使用するもので,単独電話と比較した場合,設置費や保守費の節減が図れるという長所があり,農林漁業地域における電話の普及に貢献した。
多数共同電話は,「農山漁村電話普及特別対策」(31〜37年度)における施策項目の一つとして取り上げられるなど農林漁業地域の電話普及に重用される一方,都市部を含め当時のひっ迫した我が国の電話需給状況を緩和するために活用された。更に,32年8月農林漁業地域専用の電話として,地域団体加入電話制度が実施された。この電話は,普通加入区域外の電話による連絡が不便な地域等一定の条件を満たす地域の住民が,電電公社から公衆電気通信役務の提供を受けることを目的とする組合契約を締結して加入組合を設立し,その組合と公社との契約により設置されるもので,組合加入回線,組合交換設備,組合内線及び組合本電話機から構成される多数共同方式の電話である。地域団体加入電話は,サービス開始以来順調に普及し,40年度には847箇所,組合本電話機数11万個に達したが,農村集団自動電話の開発,普及に伴い漸次減少し,現在では北海道等一部の地域に残置されているのみである。
39年7月から農村集団自動電話が試行されたが,これは,地域団体加入電話は加入組合が交換事務を行うオペレータを配置する必要があり,その改善が望まれていたこと,また,39年1月有線放送電話接続通話制度実施の際,国会において,政府及び電電公社は農山漁村地域における本来の通話手段である公社電話設備の拡充,サービスの改善に更に努力すべきであるとの附帯決議がなされたことなどが推進力となり実現されたものである。その後,44年10月公衆電気通信法の改正により集団電話が法制化されたことに伴い,農村集団自動電話は地域集団電話として本格的に実施されることとなった。地域集団電話は,農林漁業地域で低トラフィックの電話需要が大量に発生している地域内の適当な場所に設置された簡易な無人自動交換機と加入者宅内に設置された多数共同電話方式による電話機とから構成されており,線路設置費や附加使用料の支払は不要とされている。
地域集団電話は,農林漁業地域における共同利用電話として急速に普及したが,電話加入区域が拡大されたこともあって43年度以降需要が漸減しつつある。49年度中の新設数は1万3千加入であり,年度末加入数は124万4千加入となっている。
このほか,31年度以来普通加入区域外に所在する無電話集落や電話の少ない集落における電話の普及を図るため,農村公衆電話の設置が積極的に推進されてきた。その49年度末における施設数は1万6千個となっている。
(2) 有線放送電話の活用
27,8年ごろ電話の普及が遅れていた農林漁業地域の通信連絡手段として,ラジオの共同聴取設備に送受話器のついた設備が現われた。この通話兼用の有線放送設備は,その後の改良によって通話機能も向上し,31年度から始まった農林省の新農山漁村建設計画や自治省(当時は自治庁)の新市町村建設計画においてこれを補助の対象に含めることとしたため,この通話兼用有線放送設備は急速に発展した。
このような情勢にかんがみ,32年に有線放送電話業務の適正な運営を図ることによって,有線電気通信に関する秩序の確立に資することを目的として「有線放送電話に関する法律」が制定された。本法律においては,有線放送電話の業務区域を社会的経済的につながりが深く,電話の連絡が不便な一の市町村の区域内に限定しており,有線放送電話を地域共同社会内の通信手段として位置付けている。
法制定以後における有線放送電話の普及は目覚ましく,法制定当時は施設数750,加入世帯数30万であったものが,37年度末には施設数2,600,加入世帯数200万に達し,設備の設置地域は全国郡部地域の半分近い割合を占めるようになった。また,超多数共同電話方式が有線放送電話の特色であったが,この1回線当たりの共同加入数も徐々に減少し,更に,秘話装置,個別呼出装置等の開発利用が行われるなど有線放送電話設備の技術水準は格段の向上を見せるようになった。このような背景の下で,38年に公衆電気通信法が改正され,有線放送電話設備と公社電話設備との接続通話制度が39年1月から実施された。なお,接続通話のできる範囲は,有線放送電話の地域性,設備の質等を考慮して,同一都道府県(北海遣は5分した地域)の区域内で無中継又は1中継により接続される範囲とされた。
更に,44年には公衆電気通信法が改正されて,県外であっても社会的経済的につながりの深い隣接市町村については接続通話ができるようになるとともに,「有線放送電話に関する法律」が改正されて,その業務区域を社会的経済的につながりの深い隣接市町村の一部まで広げることができることとなるなど有線放送電話の制度も時代の変化に対応して徐々に改められてきている(第1-2-3図参照)。
有線放送電話については,上記のような施策のほか,国(農林,郵政,自治の各省)が過疎対策,地域格差是正策の一環として,有線放送電話業者,日本有線放送電話協会に対して各種の補助金等を交付し,その健全な育成に貢献している。
(3) 電話加入区域の拡大
現在の公衆電気通信法制は,電電公社に対して,加入電話による公衆電気通信役務の提供について独占的地位を認めている反面,その役務を全国にわたってあまねく提供すべき義務を負わせているが,加入電話を設置することができる地域は資金的にも技術的にも限られているので,公衆電気通信法は電電公社に対しあらかじめその地域を電話加入区域として指定することを義務付けている。電話加入区域には普通加入区域と特別加入区域があり,普通加入区域は加入電話の設置時に設備料等通常負担すべき費用のほかには特別な費用の支払を要しない区域であり,特別加入区域は通常の負担のほかに線路設置費の支払を要する地域である。また,電話加入区域外に加入電話を設置する場合は,通常の負担のほかに線路設置費とその線路に係る附加使用料の支払が必要とされている(第1-2-4表参照)。
このような電話加入区域制度の内容から,普通加入区域の定め方,線路設置費,附加使用料の料金額等は,普通加入区域外に居住する加入者の料金負担面に重要な影響を与えるものといえよう。
電話加入区域については,従来,電話局の加入数に応じてその範囲を定めており,普通加入区域については,電話局からの平均半径は2〜3kmであり,また,特別加入区域については,普通加入区域の外側に,普通加入区域に準ずる需要が見込まれる場合,原則として3kmの範囲内で設定されてきた。
電電公社は,近年における社会生活圏の拡大に対処するため,「電信電話拡充第5次5カ年計画」において基礎設備の整備を行いながら,逐次段階的に普通加入区域を半径5kmまで拡大することとしている。49年度末現在全国に4,632の普通加入区域が存在するが,50年度においては910区域の拡大が予定されている。
(4) 施策の動向
このように農林漁業地域の電話は,地域の特性に応じた電話サービスの実施,地域共同体電話としての有線放送電話の活用,電話加入区域の拡大策により利便の確保が図られてきたが,今後一層農林漁業地域の国民に電話を普及し電話の利便を確保していくためには,既存の施策の強化を図るとともに,新たな施策の展開が必要である。このため,郵政省では「地域通信調査会」を設け,農林漁業地域における電気通信サービスの在り方について広く意見を求め,49年9月報告書が郵政大臣に提出された。
本報告書は,農林漁業地域における電気通信サービスの現状と問題点を論じた後,その在り方として次のような提言を行っている。
第一に,有線放送電話の在り方を時代の変化に即応させていくことである。本報告書はこれにかかわる問題として業務区域及び公社回線との接続制度について取り上げている。
業務区域については,現在,原則として一の市町村の区域内に限られているが,現行の市町村の区域が住民の生活圏・経済圏に一致しているとは必ずしもいえないものであることを考えると,有線放送電話の業務区域を市町村の区域に制限することは適当でなく,その住民が社会的経済的に相互に緊密な関係を有している地域である限り,業務区域の設定が認められるべきであるとしている。
また,公社回線との接続制度については,現在,その接続範囲が同一都道府県の区域(北海道については5分した区域)内で1中継以内とされているが,農林漁業地域の中でも電話による連絡が特に不便な地域に所在する有線放送電話については,地域の実情に即応する措置として,公社電話なみの技術基準の確保を条件に,暫定的に全国接続通話に準ずる措置を講ずるなど接続範囲の拡大について検討することが必要であるとしている。
これらの提言については,対立意見が付されているが,有線放送電話の性格等を考慮しつつ,積極的な施策の展開を求めている。
第二に,電電公社は数次にわたる電信電話拡充5か年計画の実施の中で,農林漁業地域に対しても電話の普及に努めてきたが,現在同地域における公社電話のサービス水準は都市地域に比較してなお低い状況にあるとして,その向上の必要性を指摘している。本報告書はこれにかかわる問題として,一般加入電話の増設,地域集団電話の組合せ数の緩和・一般加入電話への種類変更,普通加入区域外における電話加入条件の緩和について取り上げている。
これは,農林漁業地域における生活水準の向上に伴って,電話に対する要求も高度化,多様化の傾向をたどっており,今後,電話の普及を更に推進するだけでなく,現在の地域集団電話には提供できるサービスに限りがあることや話中状態が多いことなどから,その改善を図る必要性があることを指摘しているものである。
電電公社は,この指摘に関連する施策として,「電信電話拡充第5次5ヵ年計画」において,地方中小局の普通加入区域を拡大するとともに,地域集団電話についてはすべての申込みに応じられるようにし,更に既設地域集団電話については組合せ数の緩和,一般加入電話への種類変更等サービスの改善を逐次計画的に実施することとしている。また,53年度以降の対策として,普通加入区域をさらに拡大することや集団的な需要がある地域には電話局を建設して普通加入区域を新設することなどを検討中である。
第三に,農林漁業地域には都市地域とは異なる特有の生活情報,生産情報等に対する需要があると思われ,有線放送電話の地域共同社会の通信手段としての特色を生かしていくために,国としてはそのような多目的の情報通信システムについてパイロット施設による実験その他の開発を推進する必要があるとしている。
最後に,農林漁業地域の中でも都市地域から離れた過疎的地域に対しては,地域の実情に即して次のような施策の展開が必要であるとしている。
すなわち,有線放送電話の地域共同体電話としての存在意義にかんがみ,有線放送電話及び有線放送の新設,改修等に対する助成の拡大について考慮するほか,電話加入区域外に設置する公社電話については,設置に必要な費用の一部を加入者に対して補助することを検討する必要がある。また,公社電話については,今後の電話に対する要望を考慮し,農村公衆電話の増設を図るほか,地域の特性を考慮した技術開発を促進し,更に一般加入電話の普及を図ることが必要であるとしている。
電電公社は,この指摘に関連する施策として,31年以来農村公衆電話を積極的に設置してきたが,「電信電話拡充第5次5カ年計画」においても1,600個増設の予定であるとともに,比較的遠隔地にあるいわゆる過疎的地域における小規模な需要集団に対してより経済的に電話サービスを提供するため,各糧の通信方式を検討している。
このように,農林漁業地域の電話サービスを向上させるためには,技術開発,普通加入区域の拡大等電電公社の一層の経営努力が必要とされるが,過疎的地域における電話の設置が事業運営上極めて効率が悪いことを考えるとき,独立採算制を標ぼうする電電公社が独力で全国をカバーするには限界があるので,これら地域における電話の普及をどのように進めるか国の施策として検討していく必要があろう。
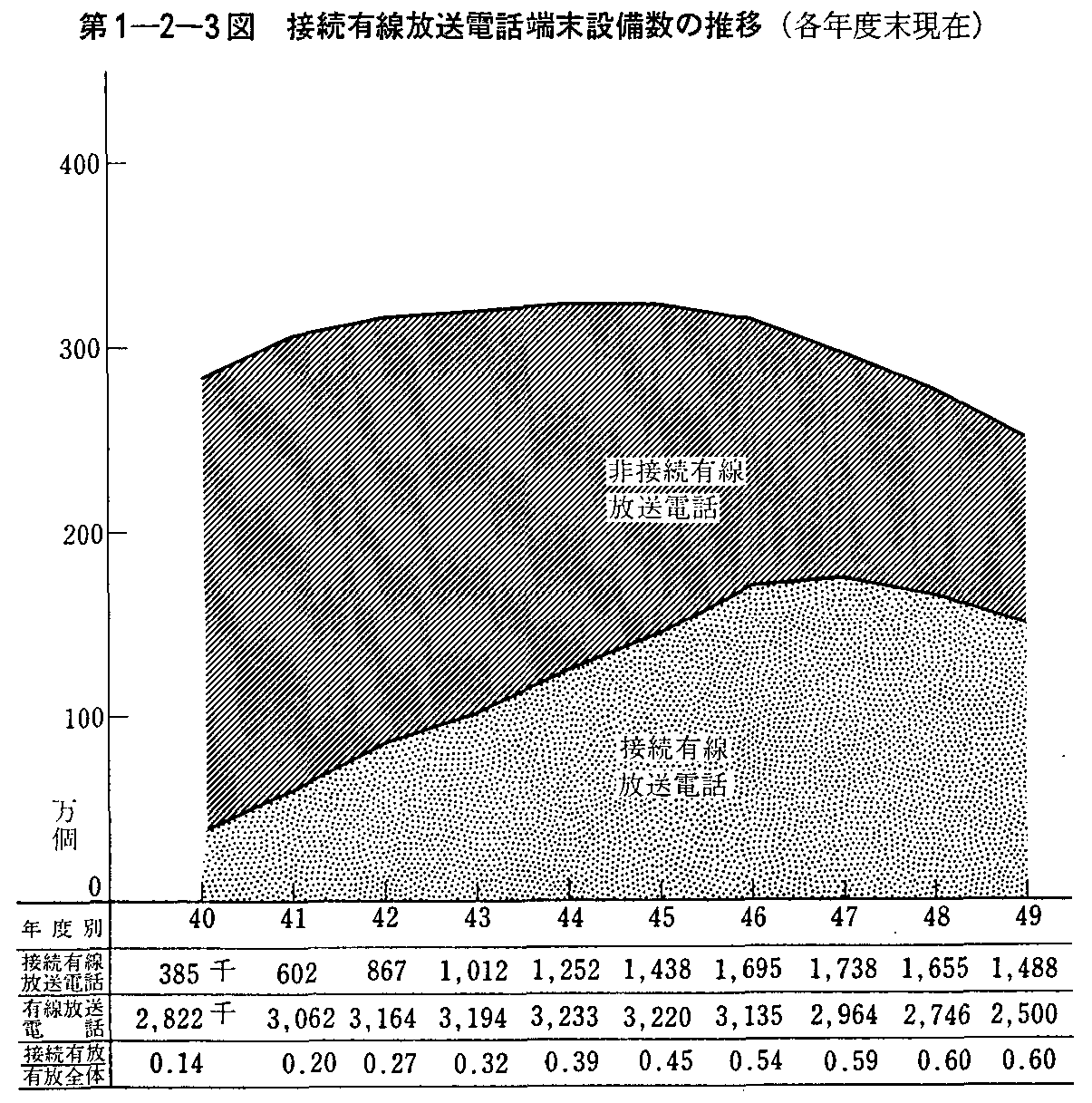
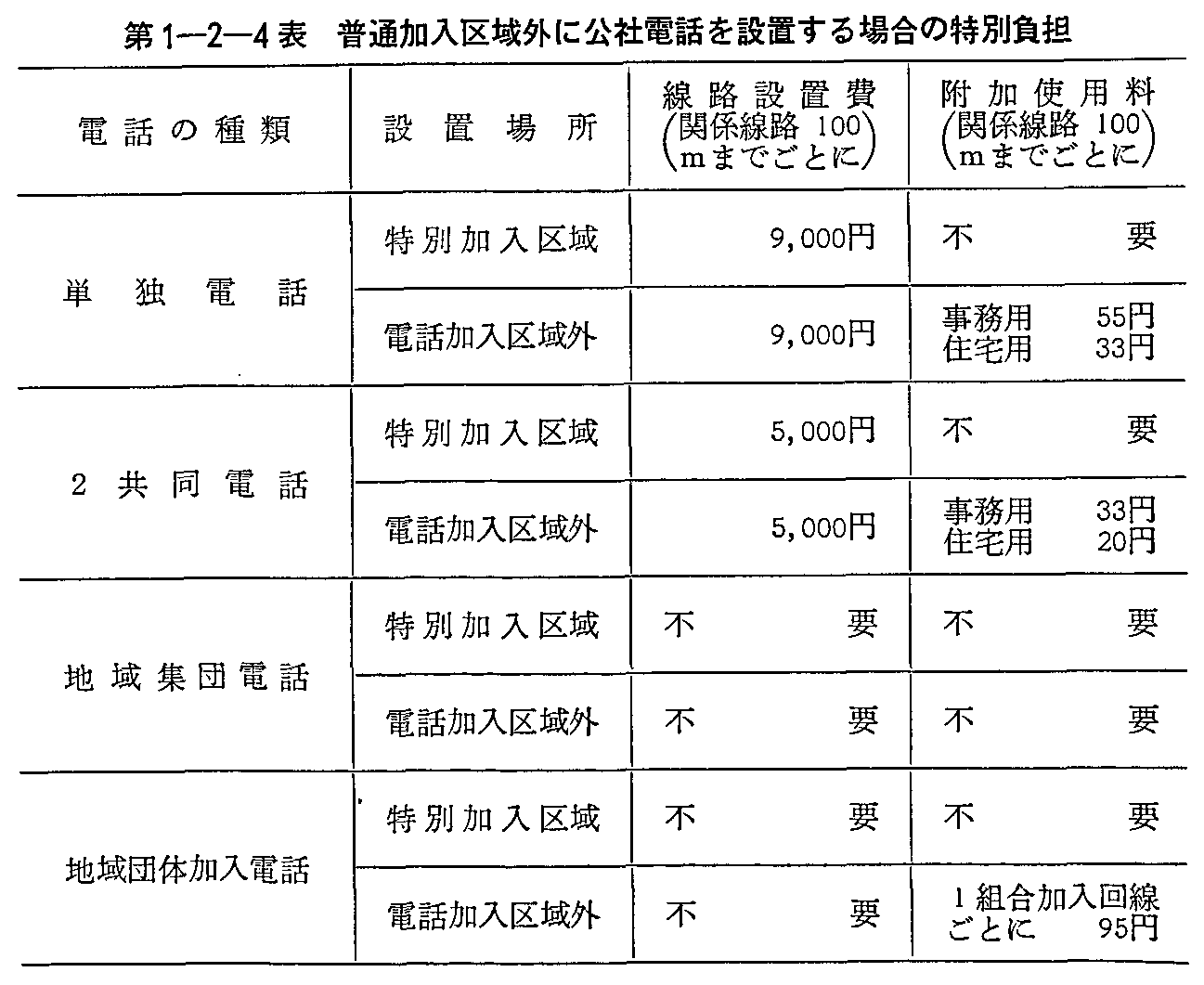
|