 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第2節 電話の完全普及
1 電話の未普及世帯
公社電話は,全国的なネットワークを形成し,国民にとって身近な通信手段として,我が国の情報流通において基幹的な役割を果たしている。また,有線放送電話は,最近は漸減の傾向にあるが,30年ごろから急速に成長し,農林漁業地域の通信手段として大きな役割を果たしてきた。49年度末における我が国の電話機数は4,190万個に達しており,1964年以来その規模は米国に次いで世界第2位を維持している(第1-2-1図参照)。
戦後における電話の普及は,30年代に入って急ピッチで上昇し,特に住宅用電話は40年代に驚異的に普及しているが,全国世帯における電話(住宅用電話,地域集団電話,地域団体加入電話,有線放送電話)の普及状況は,100世帯当たり62.9個(49年度末現在)となっており,一層の普及が期待されている(第1-2-2図参照)。電電公社の「電信電話拡充第5次5カ年計画」(48年度〜52年度)によれば,52年度末までに電話の積滞を解消することとしているが,今後における電話の普及を展望するとき,電話積滞解消後に残る農林漁業地域に多い普通加入区域外に居住する住民,一人暮らし老人,重度の身体障害者等の潜在的需要にいかにして対処するかが重要な課題となっている。
(1) 農林漁業地域における電話の普及状況
我が国における第一次産業就業者数は,552万人(50年3月現在)であり,就業者総数の11%を占めている。農林漁業地域における公社電話の普及は,従来都市地域に比較して遅れていたが,近年かなりの進展をみるに至っている。ちなみに,都市地域と農林漁業地域の比較を市部,郡部の観点から行ってみると,人口100人当たり開通電話数(公衆電話等を含む。)が,37年度末で市部が6.5,郡部が2.7であったものが,47年度末では市部が23.6,郡部が15.7となっている。
このような公社電話の普及は,農林漁業地域における生活水準の向上等により公社電話に対する需要が強くなる一方,公社においても一般加入電話(単独電話,共同電話等)の増設,手動式局の自動化,普通加入区域の拡大と併せ,農山漁村特別対策として地域集団電話(以前の農村集団自動電話),農村公衆電話を設置するなどの方策を講じてきたことによるものである。
また,有線放送電話は,49年度末現在,施設数で1,373,端末設備数で250万であり,いずれも年々減少している。これは,新設が少なくなったこと,施設の統合が進められていること及び公社電話の普及等に伴い施設が廃止されたことによるものである。
(2) 老人,身体障害者世帯の電話の普及状況
近年,平均寿命の著しい伸長に伴い,我が国の総人口に占める老年人口の割合が着実に増加しており,老齢化社会の到来が予想されている。その上,戦後における扶養意識の変化,核家族化の進行に伴い,一人暮らし老人や老人を含む核家族世帯が多く見られるようになっており,48年度において一人暮らし老人84万人,老人を含む核家族世帯284万世帯が存在する。また,身体障害者も40年度115万人に対し,45年度は141万人となっており,最近増加の傾向にある。
これらの老人や身体障害者は,身体機能上のハンディキャップや対人接触の機会が少ないことなどの問題に悩んでいるだけでなく,経済的不安に直面している者も多く,生活保護世帯の75%を占めているのが実態である。
このような人々の福祉の充実を図るため,通信の分野においても電話を活用した各種の一人暮らし老人対策,身体障害者対策が進められているが,その電話普及状況を見ると,一人暮らし老人35%(48年度),身体障害者84%(49年度)となっている。
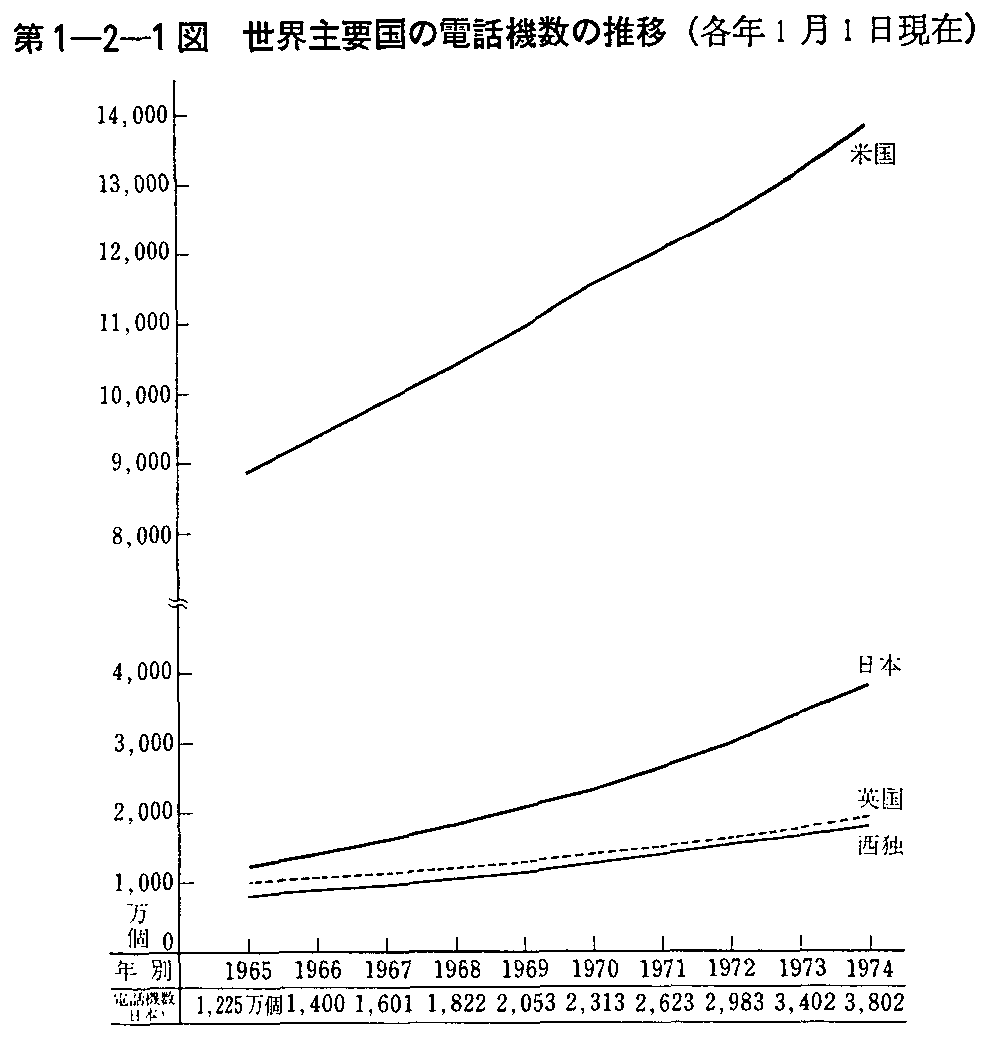
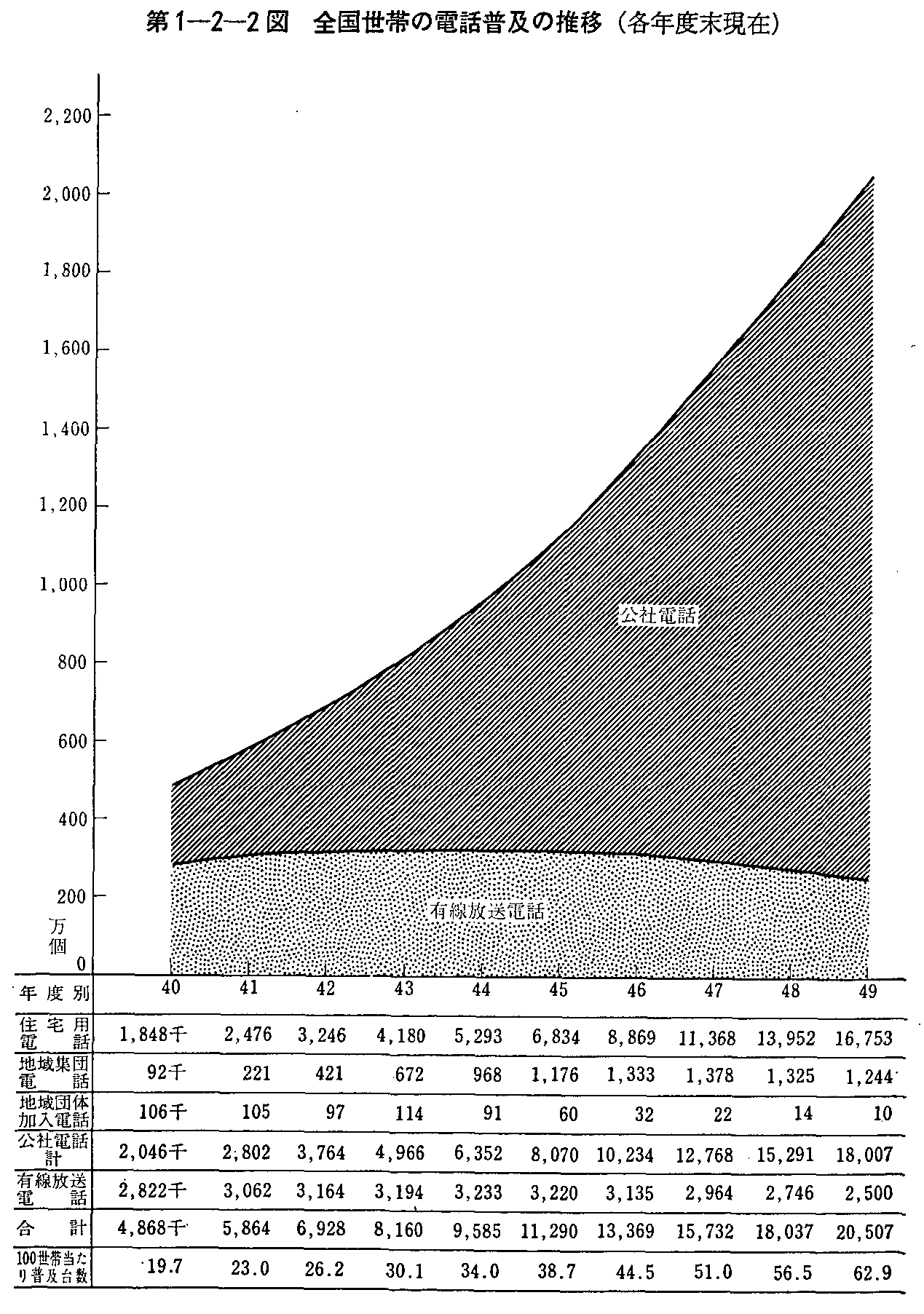
|