 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 郵便集配サービスと郵便集配施設
(1) 取集サービス
ポストの設置数は,49年度末で13万5,271本となっているが,大都市やその近郊など,人口が集中しているところを中心に,同年度中に1,720本増設した。この普及状況の推移は,第2-1-9表のとおり逐年向上しているが,一方ポスト1本当たりの投入郵便物は,窓口引受郵便物の比率が高くなっているため,減少の傾向にある。
また,都市内に設置されているポストについては,最近の交通規制に伴い取集作業に困難を来たしており,移設を必要とするポストが増加している。
ポストからの取集度数は,郵便物の多少により,1日1度から5度までの間に設定されているが,最近,都市では交通難のために取集作業時間がかなり延伸し,定められた運送便への接続が困難になりつつある。
一方,49年に行ったポスト別,取集便別差出物数調査によれば,1便当たり差出物数がわずか20通にも満たないポストが全体の約6割も占めている現状にあり,1日最大5便の取集度数は効率的でなくなってきている。そこで取集度数を減らして取集便を再編成することによって,安定的な取集サービスを確保し,運送便へ確実に接続するよう検討する必要が生じている。
(2) 配達サービス
ア.配達度数
配達区(1日,1人が配達を分担する区画)は,49年度末現在,4万8,889区あり,同年度中において,発展する大都市及びその周辺を中心に総体で670区増加した。なお,過疎過密化現像の進行に即して,過疎地の配達区を併合するなどして再編成し,それによって減じた区を過密地に増区する努力も引き続き行っている。
また,49年度末現在の1日に配達する度数別の配達区画の現状は,第2-1-10表のとおりである。これを諸外国と比較すると第2-1-11図のとおり,配達2度以上の区が諸外国の場合はごく限られた地域であるのに比べ,日本の場合は,全配達区の半数近く,世帯数の約6割,配達物数の約7割をカバーしており,著しく比率が高くなっている。
1日2度以上の配達については,1度配達に比べて多量の労働力を必要とすることから,48年12月の郵政審議会の答申にも,「郵便が確実に,かつ,安定した送達速度で1日1度配達されるならば,おおかたの利用者の意向に沿うものと思慮され・・・・・・・・・・・・労働力の効率的活用を図り,経済的な業務運行を維持するためにも,配達度数を1日1度とすることについて具体的に取り組むべきである」と書かれており,今後検討を進めるべき大きな問題である。
イ.速達配達
速達配達区域は郵便局から陸路4km以内の地域及び4kmを超え8kmまでにあり,かつ,速達郵便の配達物数の多い地域とされている。49年度末現在では,全国の世帯数の91%に相当する2,900万世帯が速達配達区域に含まれている。
(3) 辺地集配
郵便の集配サービスについては,辺地に至るまで原則として毎日各戸配達のサービスを行っているが,特に過疎地域(過疎地域対策緊急措置法に基づき公示された約1千の過疎地域市町村で,国土総面積の41.8%を占めている。)においては,人口密度がこれら地域以外の地域に比べて極めて小さく(過疎地域以外の地域が440人/km2であるのに対し過疎地域は58人/km2である。),かつ,道路の整備も十分でない状況にあるため,郵便物の1通当たりの配達コストは極めて割高となっている。例えば,北海道で過疎地域対策緊急措置法の適用をうけている地域に所在する集配特定郵便局は312局あるが,このうち受持世帯数が300世帯以下の局は142局あって,1局平均の受持世帯数138世帯,受持配達区数2.3区,1区当たりの1日平均配達物数139通ときん少であり,集配作業の効率は著しく低い。
そこで経営の合理化等の観点から,郵政省は配達物数がきん少であり,交通が困難な地域については,郵便規則第85条を適用して,年間を通じ,又は期間を限って郵便局の窓口において交付し,あるいは郵便局長の指定する場所に設置された集合郵便受箱に配達する方法を採っている。この対象世帯は約1万世帯で全国の世帯数の0.03%となっている。
また,それに準じた地域についても,実情に応じて配達度数を減じ,1日おきに配達するなどの方法を採っている。この対象世帯は約1万2千世帯で全国の世帯数の0.04%となっている。
最近においても,これらの地域を含めて過疎地域における過疎化が更に進行し,35年から40年,40年から45年の各5年間において,人口がそれぞれ13.1%,13.3%と著しく減少しており,その結果,郵便の取扱通数が減少しているため,各戸配達がますます非効率的なものとなっている。
一方,郵便局から遠く離れた丘陵地や山の斜面等にまで,住宅,別荘団地等が建設される事例も多く,各戸配達が著しく困難なものになってきている。そこで,郵政審議会は,48年12月,「地域の出入口の幹線道路沿いに集合受箱の設置を義務づけるなどの措置を検討すべきである」と答申し,各戸配達についての再検討を示唆している。
(4) 集配作業環境の改善
集配サービスの作業環境は,特に都市部において,高層ビルディングの増加,交通難の激化,急激な都市化による地番の混乱等により,次第に悪化している。したがって,円滑な集配サービスを提供するには,郵政省の経営努力とともに,利用者の協力を得て作業環境の改善を図る必要がますます大きくなっている。これまでの施策の状況は次のとおりである。
ア.高層ビルディング配達
都市における建築物の大型化,高層化により,これらあての郵便物の物数及び重量がますます増加し,配達作業が困難になってきている。これに対処するため,36年6月の郵便規則の改正により,3階以上のエレベータのない建築物については,郵便受箱の設置を郵便の配達を受けるための条件とした。
一方,エレベータのある建築物についても,集合受箱の設置,一括配達の勧奨を推進し,43年7月からは,勧奨の効果を高めるため協力者に謝礼金を交付している。しかし,49年度末現在,上記エレベータのある建築物のうち全棟数の2.8%に当たる約600棟(配達箇所約2万4千箇所)に集合受箱が設置されておらず,また,エレベータのある高層ビルディングが毎年約3千棟(同約11万箇所)建設されているので,今後とも上記各施策を強力に進めていく必要がある。
そのほか,超高層ビルディングについては,43年から,そこに設置された無集配局等に郵便私書箱を設置し,居住者全員に無料で貸与する方法も採っており,49年度末現在9局で実施している。
イ.郵便受箱及び表札
配達郵便物の安全保護及び配達作業の能率化を図るため,44年から48年までの5か年計画で,全戸に郵便受箱を設置する勧奨運動を行ってきたが,設置率は77%にとどまったので,引き続き勧奨を行い,49年度末現在では80%となっている。この点についても,48年12月に郵政審議会は,配達作業の能率化を図るために,「2階以上の建物,集合住宅について,集合受箱設置の義務化を検討すべきである」と答申している。
なお,配達箇所が2箇所以上ある2階建の建物は,全国で約41万棟あり,その配達箇所数は約260万箇所で,全国の配達箇所数約3,010万箇所の約9%に相当する。
また,最近,都市及び周辺の地域においては,人口の移動が激しく,各配達局で区内の居住者をは握することが困難になりつつあるので,正確な配達を期するため,受箱の設置勧奨に並行して,表札の掲出を勧奨してきたところであるが,49年度末現在での掲出率は91%にとどまっている。
ウ.住居表示
地番等の混乱による作業難を解消するため,37年5月,「住居表示に関する法律」が施行されて以来,今日まで,郵政省は関係機関に働き掛けて新住居表示の実施促進を図るとともに,住居表示制度実施地域に対して,住居番号表示板を寄贈するなどのバックアップをしてきたところである。しかし,49年9月末の進ちょく率は,地方自治体の実施計画数1,464万世帯に対して,実施済世帯数は1,026万世帯で,実施率は70%にすぎず,かつ,最近の実施率の伸びは小さい。
実施困難な理由の一つに,地方自治体の財政事情があると思われ,郵政省では46年度から簡易保険積立金による短期融資のみちを開いている。
エ.交通安全対策
最近における道路交通事情の悪化等から郵便外務員の交通事故が増加し,49年度では4,736件にも上っているので,外務員に対し安全運転意識を徹底させるとともに,運転技術の向上を図り,交通事故を防止するため,安全運転技術講習会等の各種講習会,車両の点検整備の強化等交通事故防止対策に力を入れている(第2-1-12表参照)。
(5) 郵便集配作業用機動車
外務員の労力の軽減と作業の能率化のため,集配作業に軽四輪車,自動二輪車の導入を進めてきたが,49年度末現在で,全国の配備両数は軽四輪車が3,438両,自動二輪車が4万5,676両,計4万9,114両となっている。これら車両類の配備状況は,第2-1-13表のとおりである。
(6) 集配作業の外部委託
ア.取集関係
大都市を中心に,中都市以上に所在する郵便局の取集作業の効率化を図るため,49年度末で全国の集配郵便局5,754局のうち232局において郵便専用自動車による通常(小包)郵便物の取集作業を運送業者に委託している。
イ.小包配達関係
都市における労働力の確保難に対処するため,45年に小包配達の外部委託を試行し,その後逐次拡大してきているが,49年度末現在180局で行っている。
ウ.辺地,離島の集配関係
辺地,離島においては,取扱物数がきん少であり,地況,交通等の関係で,職員が郵便局から直接集配することが困難な場合があるので集配作業を外部に委託している。これらの委託区は,49年度末で1,542区となっている。
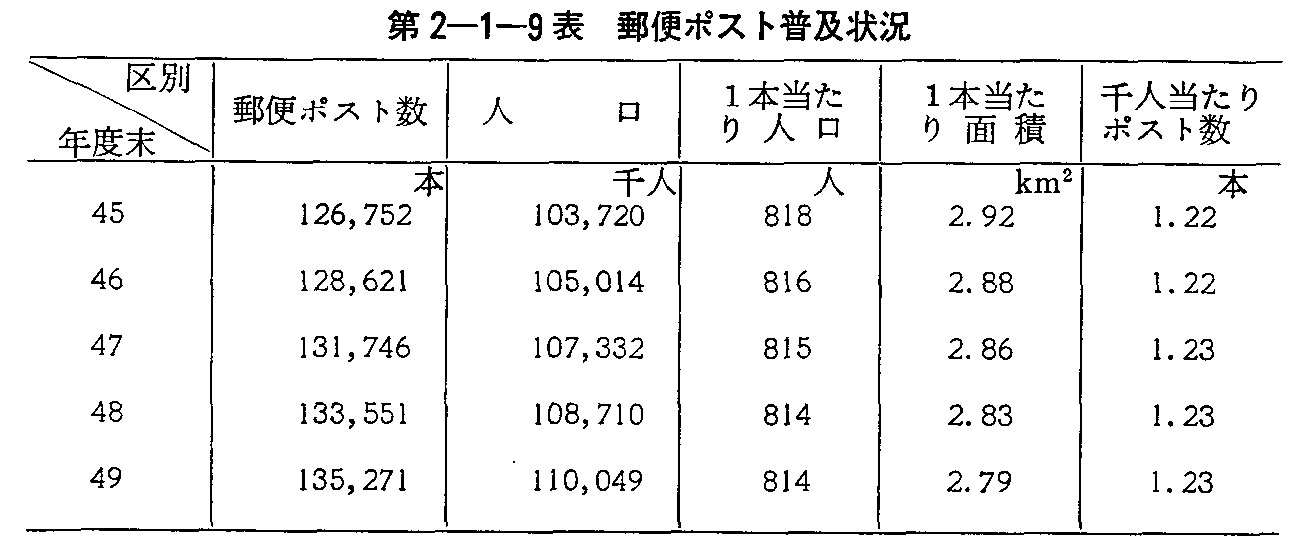
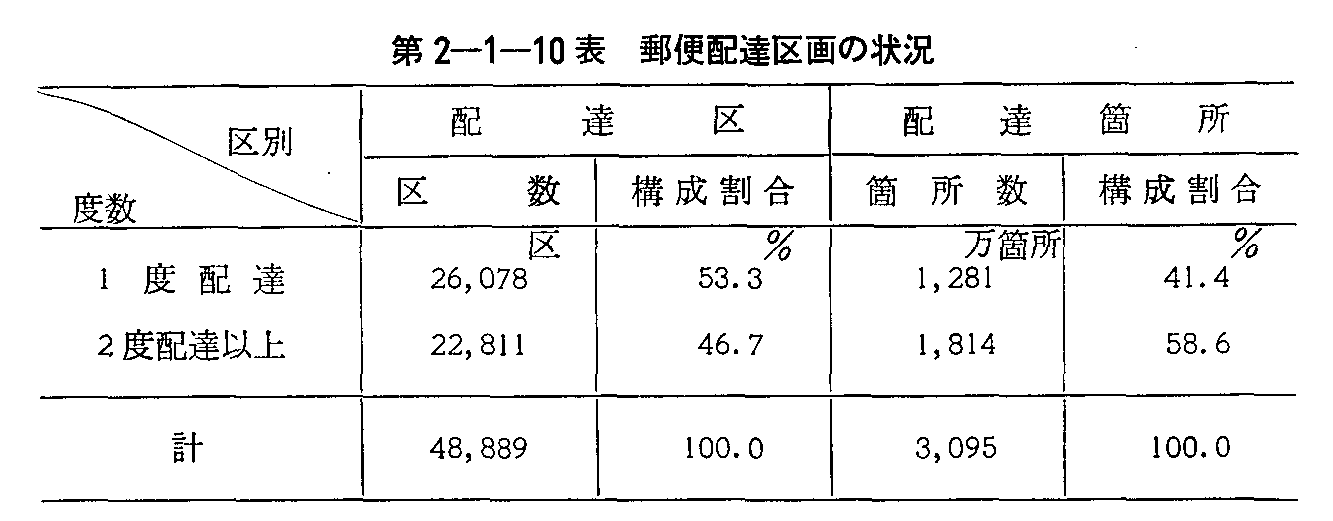
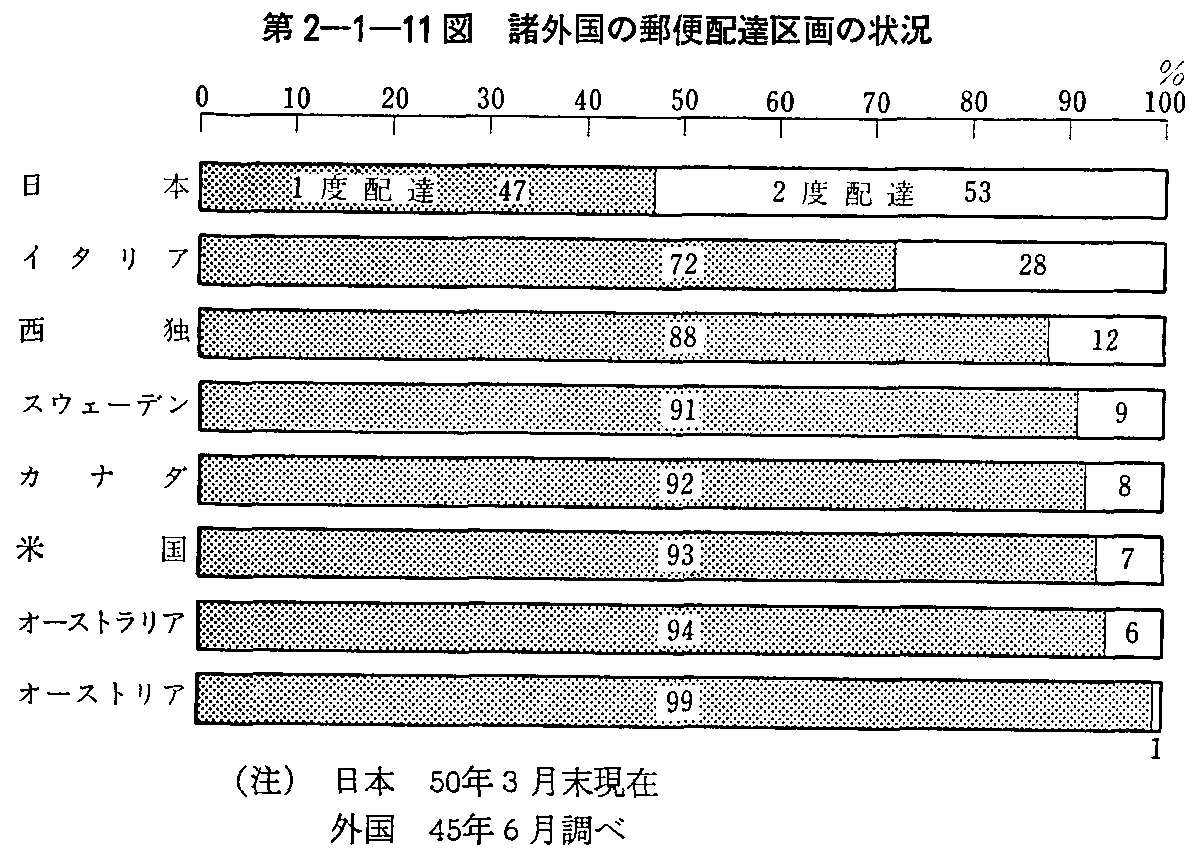
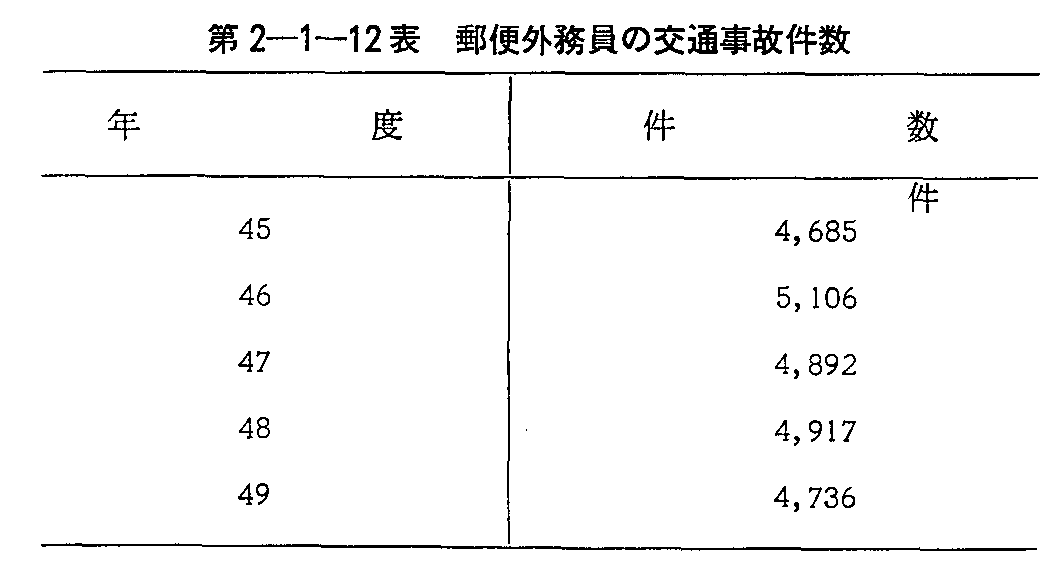
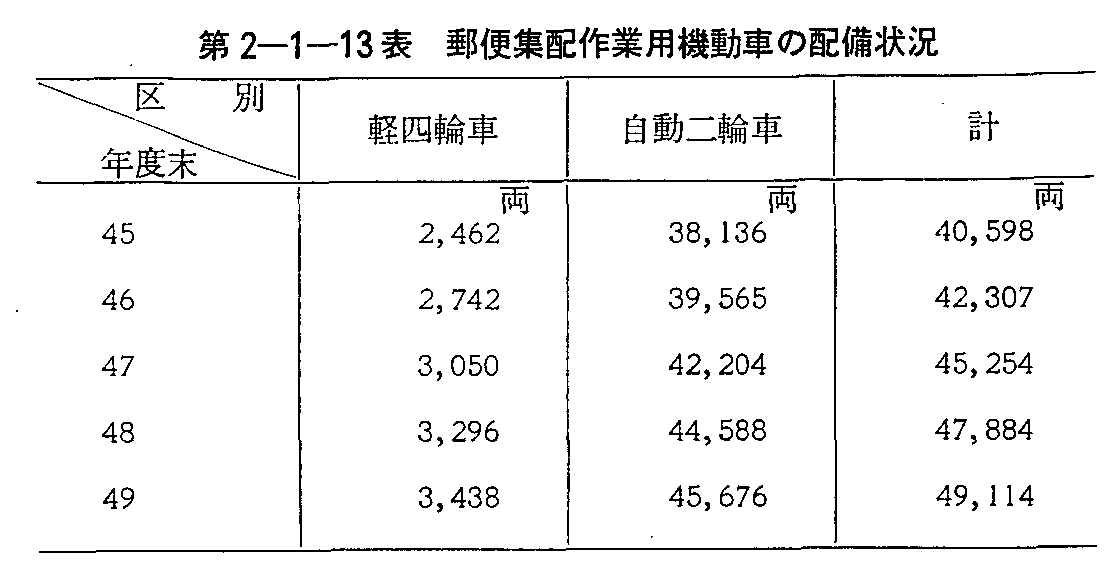
|