 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 辺地難視聴
辺地難視聴については,従来,放送事業者が実情に応じて中継局又は共同受信施設を設置して解消に努めている。国はテレビジョン放送の重要性にかんがみ,辺地難視聴を解消するよう放送事業者を指導してきた。
また,地方公共団体の一部においても中継局の建設や共同受信施設の設置に対し補助を行っているところがある。
しかしながら,依然として辺地難視聴は残されており,情報の地域格差解消,過疎対策等の見地からこの早期解消が望まれている。
(1) 中継局の設置
NHK及び民間放送におけるテレビジョン放送局の設置状況は,第1-2-8表のとおりである。
中継局の設置は,おおむね難視聴世帯数の多い地域から順次行われているが,最近では難視聴地域が山間へき地に散在しているため,置局による解消効率が低下している。
NHKは放送法により,放送を全国に普及する義務を課されている立場から,年間約200地区,400局前後の中継局を設置している。
また,民間放送においても,毎年200局近い中継局を設置しているが,辺地難視聴の解消が事業収入の増加に結び付かないこともあって,NHKに比べて設置が遅れている。
郵政省では,従来,放送事業者に対し中継局の設置による難視聴の解消を指導してきたが,特に,48年11月の放送局の再免許時においては,民間放送各社から個別に難視聴解消計画を提出させるとともに,積極的に難視聴の解消に努めるよう指導を行った。また,国が民間放送の難視聴解消費用を助成する初めてのケースとして,国土庁は奄美群島振興開発計画の一環として,50年度から奄美群島にテレビジョン放送用中継局を建設する民間放送2社に対し,その費用の一部を補助することとしており,4か年計画で実施される予定である。
一方,都道府県の中には,民間放送の中継局の建設に対する補助事業として,市町村に対して中継局建設関連の道路整備事業費の一部を補助するとともに民間放送に対して直接,中継局建設費用の一部補助,借入金の全部又は一部についての利子補給,資金融資等を行っているところもある。
また,日本開発銀行及び北海道東北開発公庫は,地域開発に効果のある民間の事業計画に融資を行っており,41年度からは民間放送に対しても中継局建設資金の融資を行っている。
(2) 共同受信施設の設置
比較的規模の小さい難視聴地域については,テレビジョン放送の良質な電波が受信できる山頂等に共同の高いアンテナを立て,受信した電波を増幅してケーブルで各家庭に送る共同受信施設を設置して難視聴の解消が行われている。
NHKは,テレビジョン放送の全国普及の一環として,辺地難視聴解消のための共同受信施設の設置を積極的に推進している。35年度から43年度までは経費の一部を助成しており,この期間中約6,700施設に対し助成した。また,44年度以降は,更に積極的に難視聴解消を推進するとともに,視聴者の負担を軽減するため,共同受信施設のうち,NHKのテレビジョン放送受信用アンテナ設備及び幹線設備の部分をNHKが所有し,分配線,引込線等残りの設備の部分は地元住民が所有して,これらの施設を共同で設置し,運用することとなった。44年度以降,NHKが地元住民と共同して設置した施設の設置状況は,第1-2-9表のとおりである。49年度末における運用施設数は5,361で,これにより総計約40万7千の難視聴世帯が解消されている。
また,住民が難視聴を自力で解消するため,共同して受信施設を設置しているところがある。このような施設は,48年度末現在,全国で約3千施設あり,約20万の世帯がこれに加入している。
(3) 技術的解消方策
辺地難視聴の解消に対しては,地域の実情,条件等に応じてそれぞれの解消策が講じられてきたが,現在残されている難視聴地域は,山間へき地の小規模なものに限られてきている。したがって,中継局あるいは共同受信施設1施設当たりの解消効率は極めて悪いものとなってきており,低廉で効率の良い技術的な解消方策が求められている。
NHKでは,送信電力100mW程度の無線設備いわゆるミニサテの研究開発を行っており,現在28箇所に実験局を開設している。このミニサテは,建設・保守両面にわたり経済性と簡易性を追求したもので,1km2程度の地域をカバーすることが可能であり,過疎的地域の難視聴解消に有効であると考えられる。
また,郵政省では,現在放送衛星の開発を進めており,52年度には,実験用中型放送衛星の打上げが予定されているが,将来,実用衛星が開発された場合には,難視聴解消にもその効果が期待されている。
(4) 施策の動向
辺地難視聴については,これまで主として放送事業者によって解消が図られてきたが,49年度末においてなおNHKの難視聴世帯が約91万,民間放送の難視聴世帯が約230万残されていることは前述のとおりである。
これらの残された難視聴地域をみると,既に述べたように,そのほとんどが山間へき地であり,今後,辺地における難視聴地域の散在,狭域化の傾向がますます強まるとともに,難視聴解消施設の解消効率が悪化し,施設設置に要する地元住民及び放送事業者の負担が増大するものと考えられる。
放送事業者についてみると,NHKは,難視聴解消の財源にもなっている受信料収入の伸びが近年鈍化してきている上,収支率は年々悪化し,47年度以降経常事業収支が赤字となっている。民間放送については,残存の難視聴世帯を解消することが収入に結びつかないこと,また,今後は民間放送の営業収入もこれまでのような高い伸びが期待できず,収支率は悪化するものと考えられることなどから自力による難視聴の解消にはおのずから限界があろう。
一方,今日,テレビジョン放送は国民の日常生活に不可欠な存在となっているため,これら地域へのテレビジョン放送の普及が重要視され,地方公共団体,関係住民等各方面から抜本的な辺地難視聴の解消方策を求める声が強まっている。このため,郵政省では,48年6月テレビジョン放送難視聴対策調査会を設置して,都市受信障害の問題と併せて,辺地難視聴の抜本的解消策について検討を重ねてきた。調査会は,2年余にわたる調査検討の結果を取りまとめ,50年8月報告書を郵政大臣に提出した。報告書は,辺地難視聴解消を促進する方策の在り方として,放送事業者の自力による難視聴解消には限度があることにかんがみ,国,放送事業者等関係者が協力して,速やかに難視聴解消を促進するための適切な施策を講ずることによって,国民の強い要望と期待にこたえるべきであるとしている。その際,基本的にはNHK,民間放送いずれのテレビジョン放送についても難視聴解消を促進すべきであるが,民間放送による中継局の設置が,全国的にみると,NHKに比較して大幅に遅れており,しかも,NHKと民間放送の置局格差は拡大する一方であること,民間放送の難視聴解消に対する関係住民の要望は極めて強いものがあることなどにかんがみ,民間放送の難視聴解消を促進する施策を検討することが緊要であるとしている。
そして,その具体的方策として,国は民間放送が自ら難視聴を解消することが期待される範囲を設定すること,放送事業者以外の者による中継局の設置を認めること,放送用周波数割当計画等で,親局・中継局一括免許方式を導入することなどを提言している。
NHKについては,難視聴世帯数約91万(49年度末現在)のうち,約30万は数十ないし300世帯程度がまとまって集落を形成しているので,当面,NHKが中継局又は辺地共同受信施設の設置等により自主的に解消を図ることが適当であるが,民間放送の難視聴解消促進方策のうち,適用可能なものを採用することによって,難視聴世帯の早期解消を更に推進することが必要であるとしている。なお,現在,NHKが実験中のミニサテは,辺地難視聴の解消を進める上で,有効な手段と考えられるので,その早期実用化を促進すべきであるとしている。更に,NHKが新たに行う難視聴解消施設の設置等については,経費効率及び地元住民の要望等を考慮して,民間放送との協力体制を確立することが望ましいと指摘している。
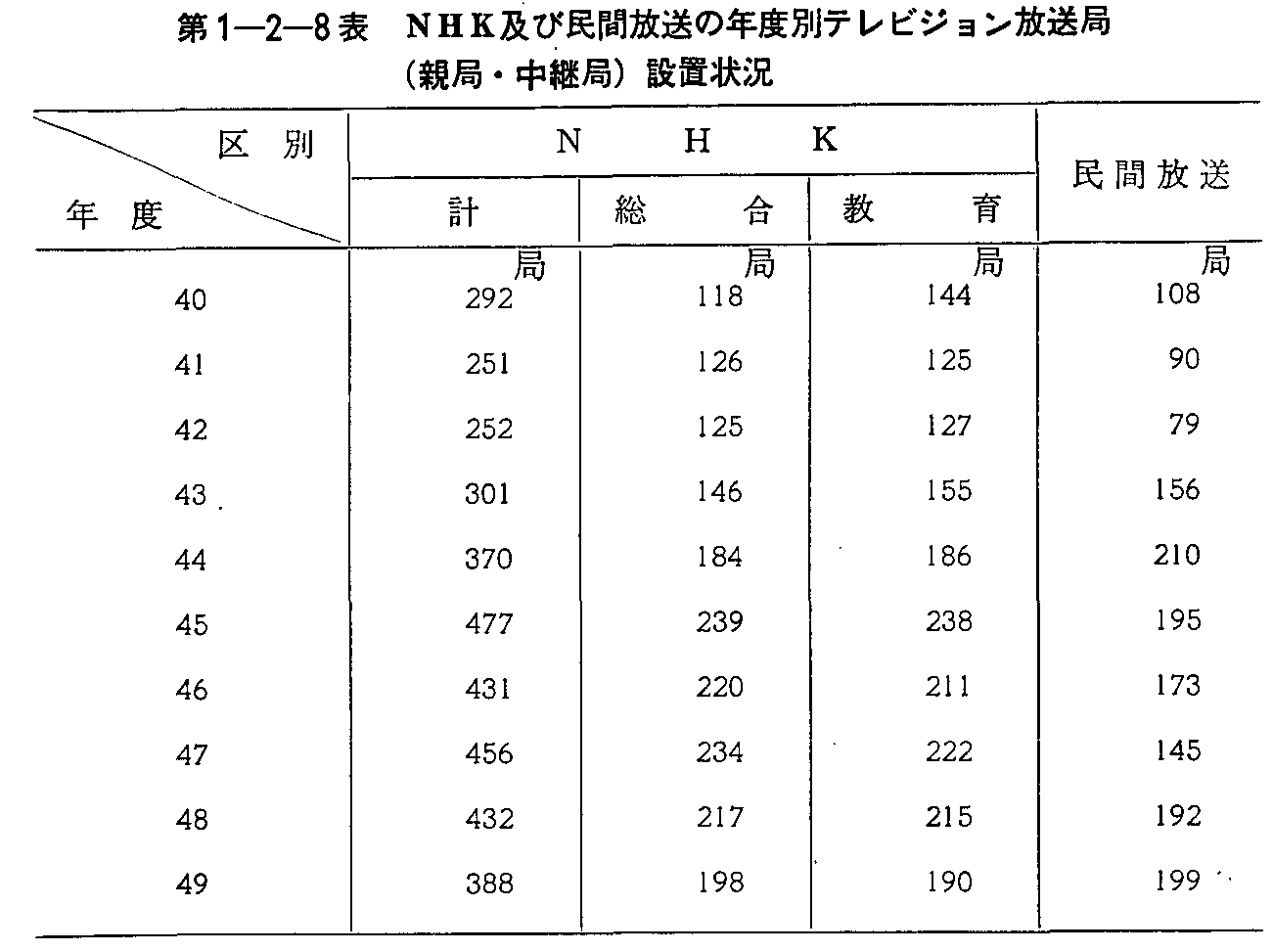
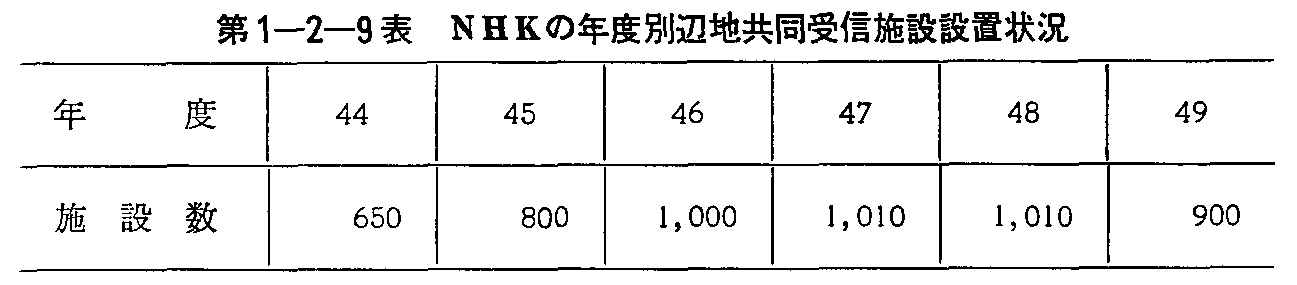
|