 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第4節 事業財政の現状
最近における郵便事業の収支状況は第2-1-17表のとおりである。
事業経営に必要な経費の中で人件費関係経費の占める割合が極めて高いため,近年における人件費の高騰は,郵便事業財政を著しく圧迫している。46年度14.7%,47年度13.5%,48年度17.5%と,高率の賃金上昇が引き続いたことなどにより,49年度においては当初から,696億円の赤字予算を編成せざるを得ない事態となり,これについては,借入金の充当により対処することとした。更に,49年度における賃金上昇が29.7%とかってない大幅なものになったことによって年度決算において1,247億円の赤字となり,財政事情は一層ひっ迫の度を加え,事業経営は極めて憂慮すべき事態となった(第2-1-18表参照)。
なお,郵便物数,郵便業務収入及び郵便業務費の推移(40〜49年度)は第2-1-19図のとおりである。
このような事業財政悪化の推移を踏まえ,48年10月,郵政大臣から郵政審議会に対し,「郵便事業の健全な経営を維持する方策について」諮問が行われ,同年12月,同審議会から大臣へ答申がなされた。その答申においては,「近年の賃金高騰などにより事業財政がひっ迫の度を加え,このまま推移すると,事業経営は危機にひんする状況にあると認め,また,事業収支の不足額は,郵便事業にとって少なからざるものであり,かつ,労働集約的な郵便事業の特質もあって,各種の合理化施策によっても,短時日に効果的にその不足額を償う方策はないと認めた。一方,利用者負担の原則を離れた事業収支改善の方途は,一時的な糊塗策にすぎず,また,企業の利用が圧倒的部分を占める最近の郵便利用の実態などからみても,適切なものではないと判断した。加えて,今日の諸情勢の下においては,現行料金のまますえ置くならば,近い将来において大幅な値上げを余儀なくされるなど,かえって国民に大きな迷惑をかけ,その措置いかんでは,健全な経営を維持することを一層困難にするものと思われる。以上総合的に勘案した結果,事業収支の改善を図るためには,この際,郵便料金を改正することが適当である。」として具体的な料金改定案が提起されたが,たまたま,石油危機に端を発した資源不足や物価高騰等を背景とした政府の公共料金抑制策の一環として,小包料金は10月1日から改定されたが,その他の郵便料金の改定は見送られた。
このため,郵便事業財政は,ますます窮迫の度を加え,49年11月,郵政大臣から再度郵政審議会に対し諮問が行われ,同年12月,同審議会から,「このような財政をたてなおすため,第一種50円,第二種30円を骨子とする料金案で,50年4月から料金改正を実施すること。」として答申がなされたが,なお公共料金を極力抑制するという政府の方針の下に,料金改定実施の時期を6か月延期して50年10月からとするほか,第二種について,その改定幅を圧縮して20円とすることとして,50年1月31日「郵便法の一部を改正する法律」案が第75通常国会に提出された。しかし,この法律案は同年7月4日,同国会において審議未了となった。
郵便事業は郵便法第三条の規定により,事業運営上必要な費用は受益者負担としての料金収入で賄うのが原則であるが,上述のように現下の経済情勢の中にあって,物価抑制が最大の政治課題であるとの判断から料金改定幅等を圧縮したために生ずる収入不足は,当面の措置として借入金をもって充てることとしている。しかしながら,独立採算制を建前として経営する郵便事業としては更に一層,事業の近代化合理化施策を推進するとともに,やはり事業の置かれているこうした厳しい実情について,国民の深い理解と協力を得て,今後できる限り早期に財政基盤の改善を図る必要に迫られている。
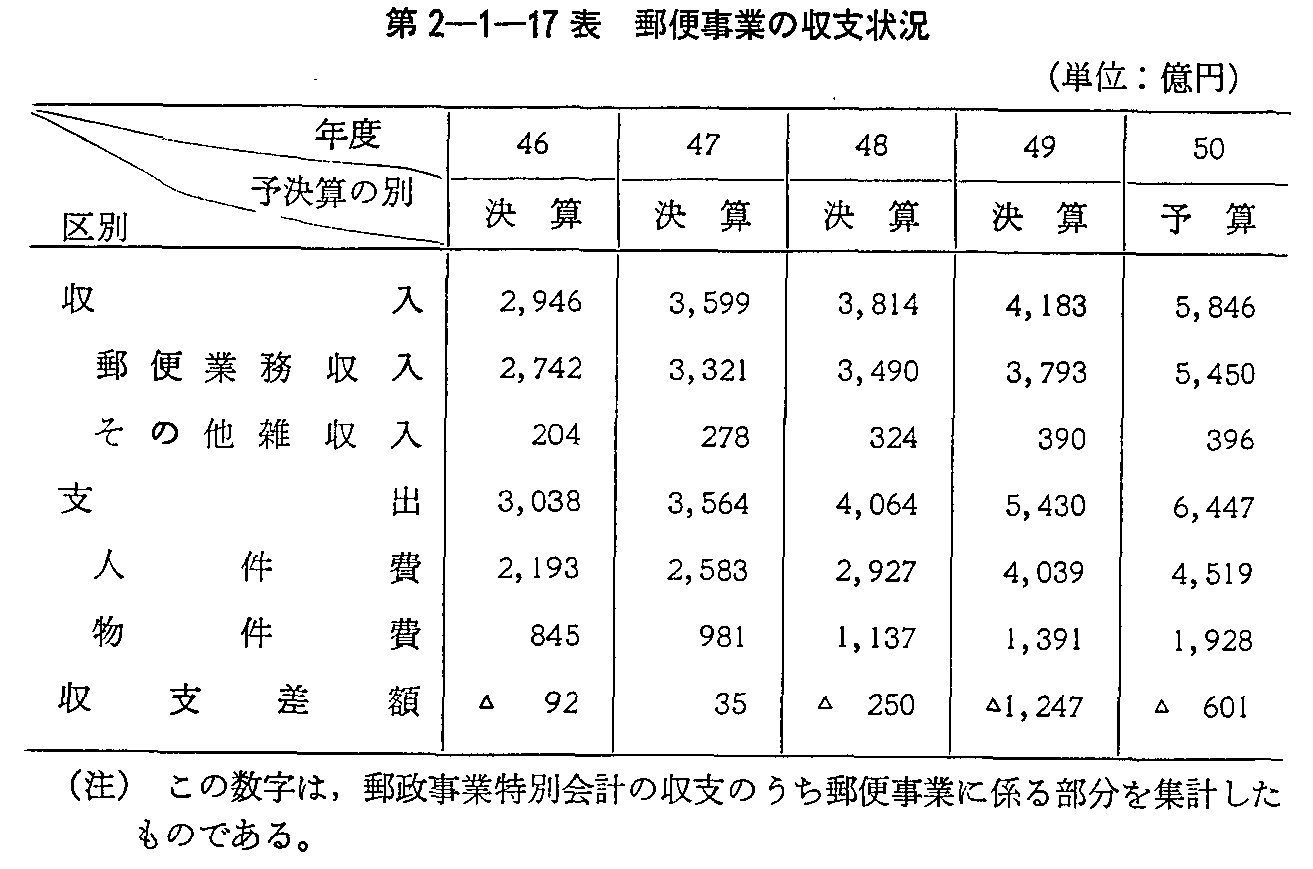
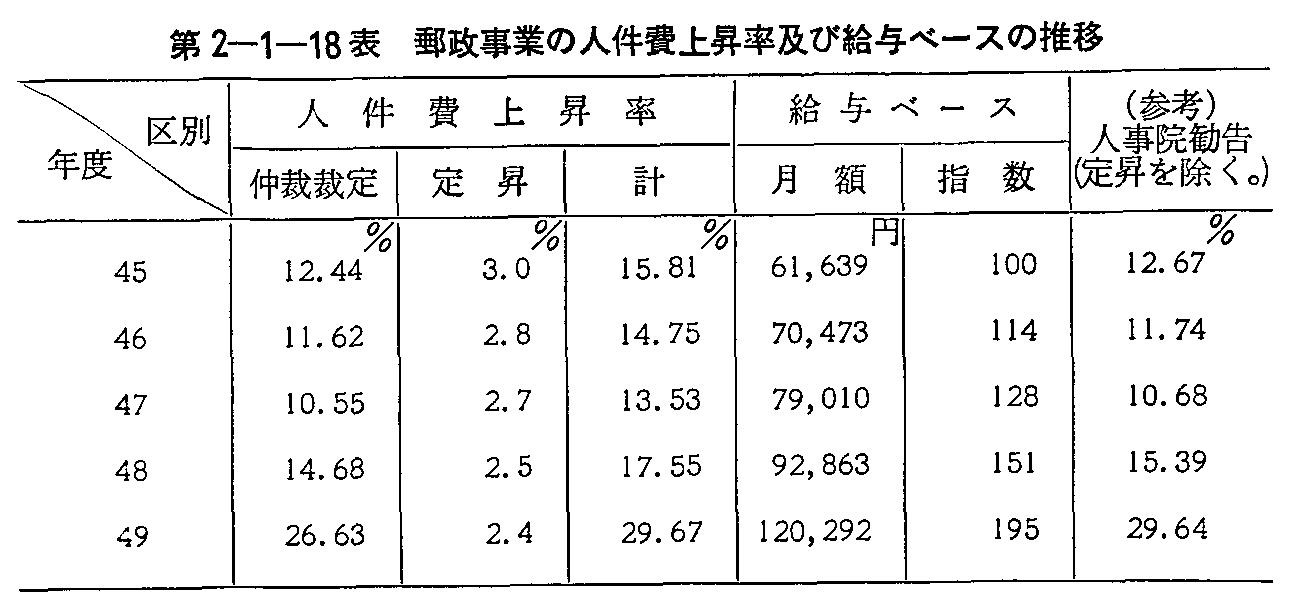
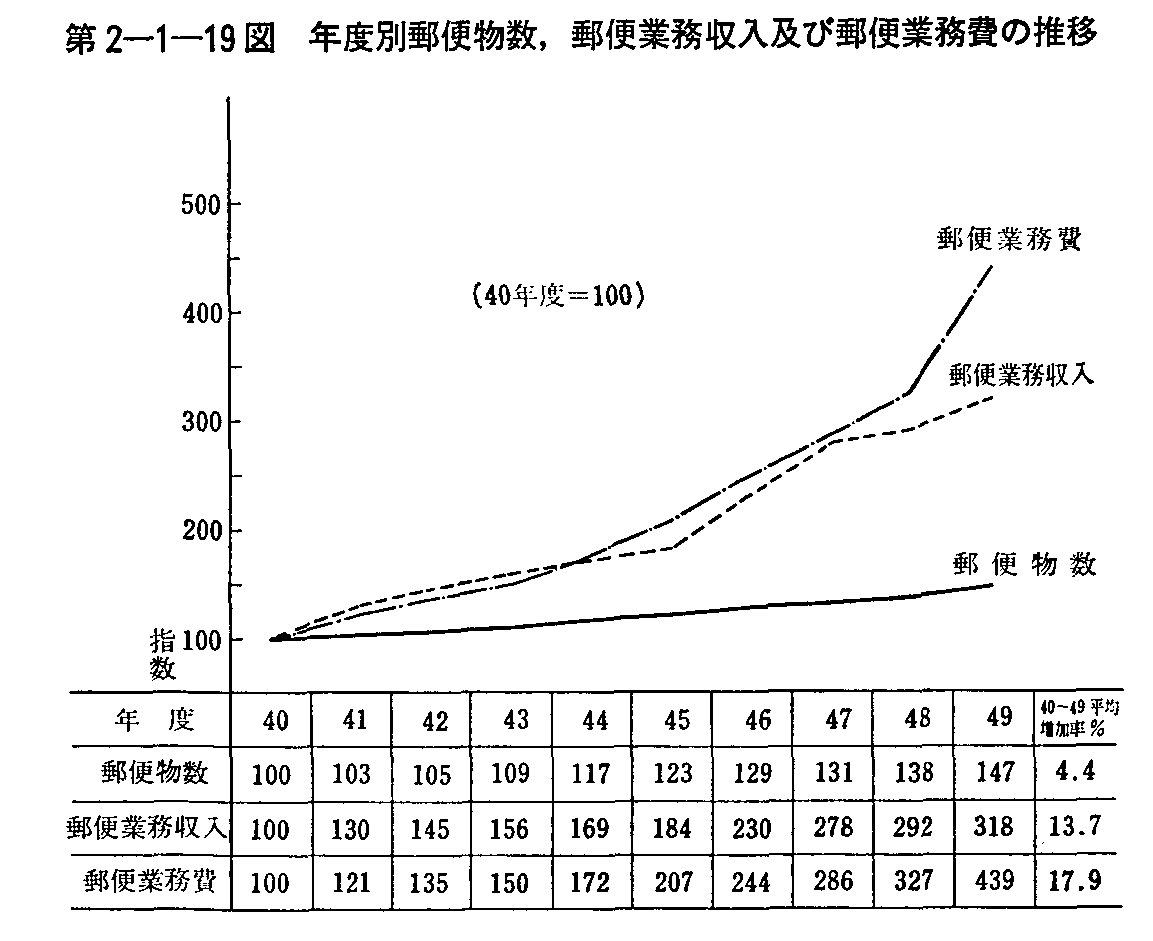
|