 第1部 総論
 第1節 昭和49年度の通信の動向
 第2章 今後における基幹メディアの普及
 第1節 基幹メディア普及の現状と将来  第2節 電話の完全普及  第3節 ラジオ放送の国際的混信の解消  第4節 テレビジョン放送の難視聴解消
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第3節 データ通信回線の利用状況  第4節 データ通信システム  第5節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
5 日本経済における通信事業
(1) 通信事業の規模
郵便,公衆電気通信及び放送を合わせた我が国通信事業の規模を,そのサービス生産額(事業収入又は営業収益),設備投資額及び従業員数でみると第1-1-9表のとおりである。
通信事業のサービス生産額は49年度において約2兆9千億円(対前年度比10.2%増)に達したが,これは名目国民総生産の約2%を占める。48年度においては通信事業の生産額は,通信とともに社会経済活動の基盤となっている運輸・倉庫業の生産額の約4分の1の規模である。
通信事業の設備投資額は,49年度約1兆5千億円であり,住宅を除く国内総固定資本形成の約4%を占めている。また,通信事業のうち郵便事業及び電電公社の投資額は,住宅を除く政府固定資本形成の約12%に達する。通信事業の生産額に対する設備投資額の比率は,各年度とも50%前後に達し,全産業中では電気・ガス・水道業に次いで高率であるが,これは投資額の92%が労働装備率の高い電電公社によって占められていることによる。
通信事業の従業員数は,49年度末において約49万人であり,運輸・通信業就業者数の約15%を占める。また,全産業就業者数及び第三次産業就業者数に対する割合は,それぞれ約1%,約2%である。
我が国通信事業の規模を欧米先進諸国のそれと比較すると,第1-1-10図のとおりである。これによると,各国通信事業の規模はほぼ経済全体の規模に比例しているが,両指数の比率によって通信事業の相対規模を比較すると,我が国を100とした場合,米国138,英国110,西独99及びフランス69となる。
次に,各国通信事業の事業部門別生産額構成をみると(第1-1-11表参照),我が国の場合,郵便の比率が小さく,放送の比率が大きいのに比べ,欧米諸国ではこれとほぼ逆の構成となっている。
最後に,産業別国民所得からみた通信事業の規模及び水準についてみると(第1-1-12表及び第1-1-13図参照),通信事業の国内純生産(純付加価値額)は49年度において約1兆4千億円に達した。48年度における他産業との比較では通信事業の国内純生産は,通信事業と同じく労働装備率の高い電気・ガス・水道業の国内純生産の約1.5倍の規模である。通信事業の国内純生産を従業員数で除した従業員1人当たり国内純生産は,49年度279万円に達し,産業別比較(48年度)では金融・保険・不動産業に次いで高い。47年度までは電気・ガス・水道業が通信事業より上位であったが,48年度にはオイルショックによる原油価格の高騰が影響して両者の水準は逆転した。なお,通信事業の従業員1人当たり国内純生産は,付加価値率に労働装備率及び有形固定資産回転率を乗じたものに等しいが,通信事業の場合,従業員1人当たり国内純生産を増大させてきた要因は労働装備率である(第1-1-14表参照)。
(2) 景気変動と通信事業生産額
戦後数度にわたる景気後退を経ながらも驚異的な高度成長を達成してきた我が国経済は,48年度末のオイルショックを契機に不況に突入し,49年度はついに戦後初めてのマイナス成長を記録することになった。通信事業の経営もこのような景気の下降局面に直面して悪化の状況にあるが,事業部門別生産額をみると不況の影響は必ずしも一様ではない。過去15年間における経済成長率と各通信事業体収入増加率との比較により,景気変動と通信事業生産額との関係をみれば,第1-1-15図のとおりである。
電電公社及び国際電電による公衆電気通信事業は,国内外の経済活動との関係が密接であるため,事業収入及び営業収益はマクロ経済の変動と符合した動きを示している。今回の不況における両収入の対前年同月比を景気動向指数と対比すると(第1-1-16図参照),オイルショック後の景気後退に数か月遅れて両収入の増加率も減少している。減少の度合いは,国際電電の営業収益の方が急激であるが,これは前年度における両収入の成長率の差異によるとともに,公社収入において電話収入の約30%を占める住宅用電話の利用が比較的景気に鈍感であることや今回の不況が世界貿易の低迷と呼応していることなどによるものである。
民間放送事業の営業収益の伸びは,第1-1-15図に示されているとおり,好況期と不況期との落差が通信事業中最も大きく,景気変動に対して敏感に反応している。これは,営業収益の大部分がラジオ及びテレビジョンの広告料収入であることによるものである。特にテレビジョン広告の場合,好況時にスポットCMが大きく伸び,不況時には収益の約6割を占める番組CMが減少するため,収益の変動幅が大きくなる傾向にある。
郵便事業については過去に郵便料金の改定が行われたこともあり,収入の伸びは経済の動きと符合していない。
NHKの収入については,その大部分が受信料であるため,収入の動きは景気変動とは対応していない。48年度及び49年度の受信料収入の伸びの低下は,不況の影響というよりはカラー契約の普及率の上昇とともに,カラー契約数の伸びが鈍化してきたためと考えられる。
(3) 家計と通信費
49年(1月〜12月)の家計消費支出は,総理府「家計調査報告」によれば,1世帯当たり1か月平均13万6,024円で,前年に比べ21.3%の増加となった。
通信関係支出(郵便,電報・電話,放送)の1か月平均は,2,088円で前年に比べ16.9%の増加となった。その内訳は,郵便費で157円(対前年比15.4%増),電報・電話費で1,614円(同20.4%増),放送受信費で317円(同2.6%増)となっている。
電報・電話費の伸びが著しいが,第1-1-18図に示すとおりこれは住宅用電話の普及によるものである。
家計消費支出に占める通信関係支出の割合は,合計でも1.5%と比較的低い。その内訳は郵便費が0.1%,電報・電話費が1.2%,放送受信費が0.2%で,これを前年と比べると,郵便費と電報・電話費は同率であるが,放送受信費は低くなっている。
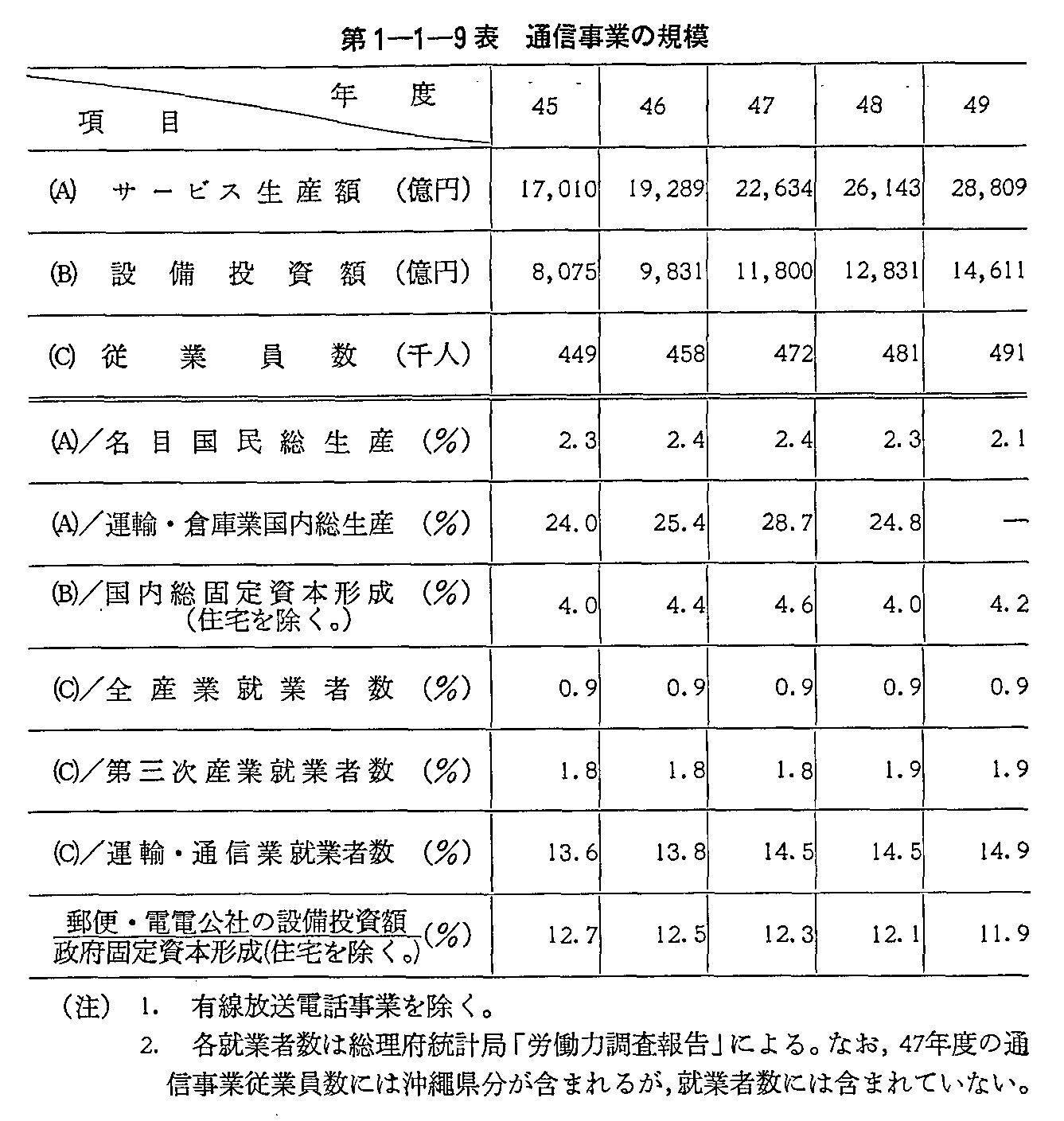
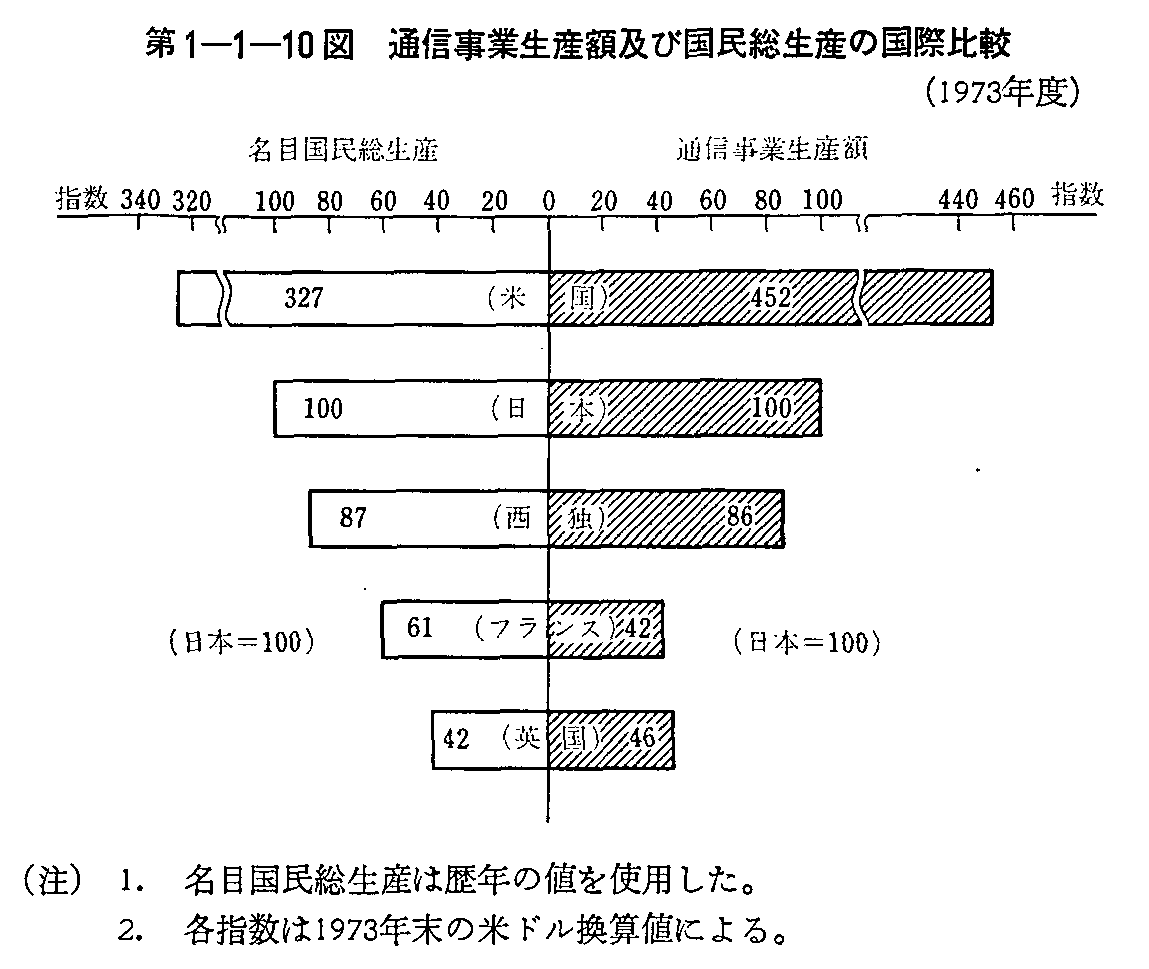
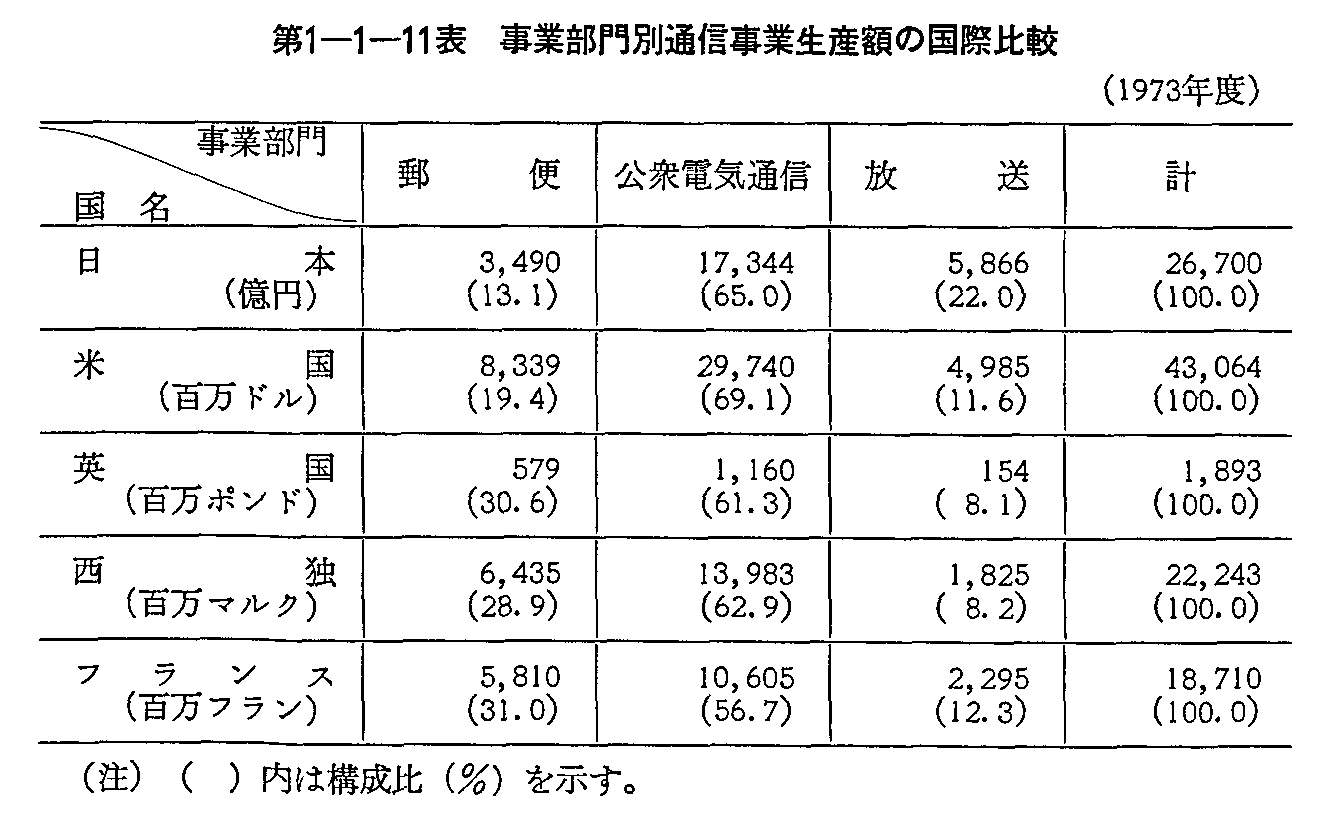
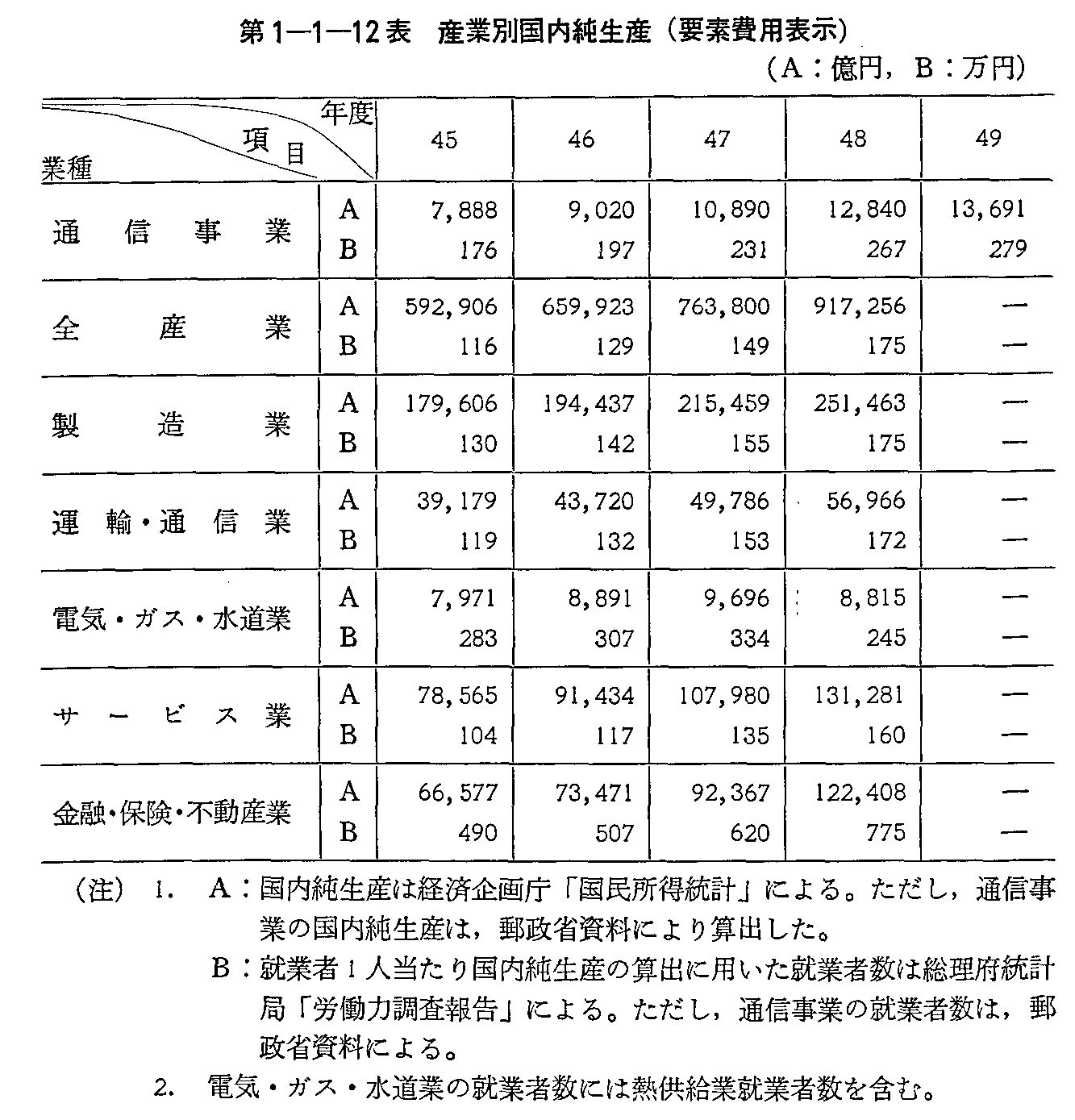
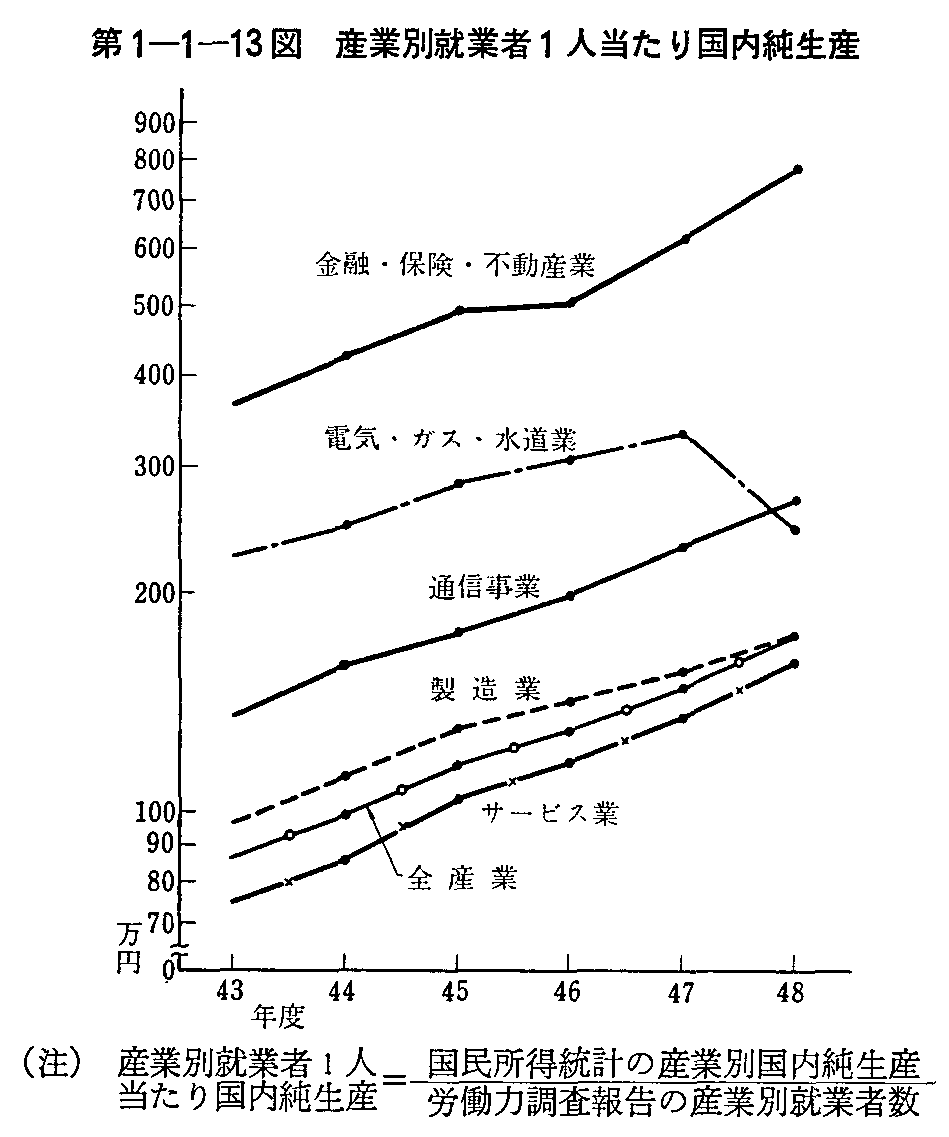
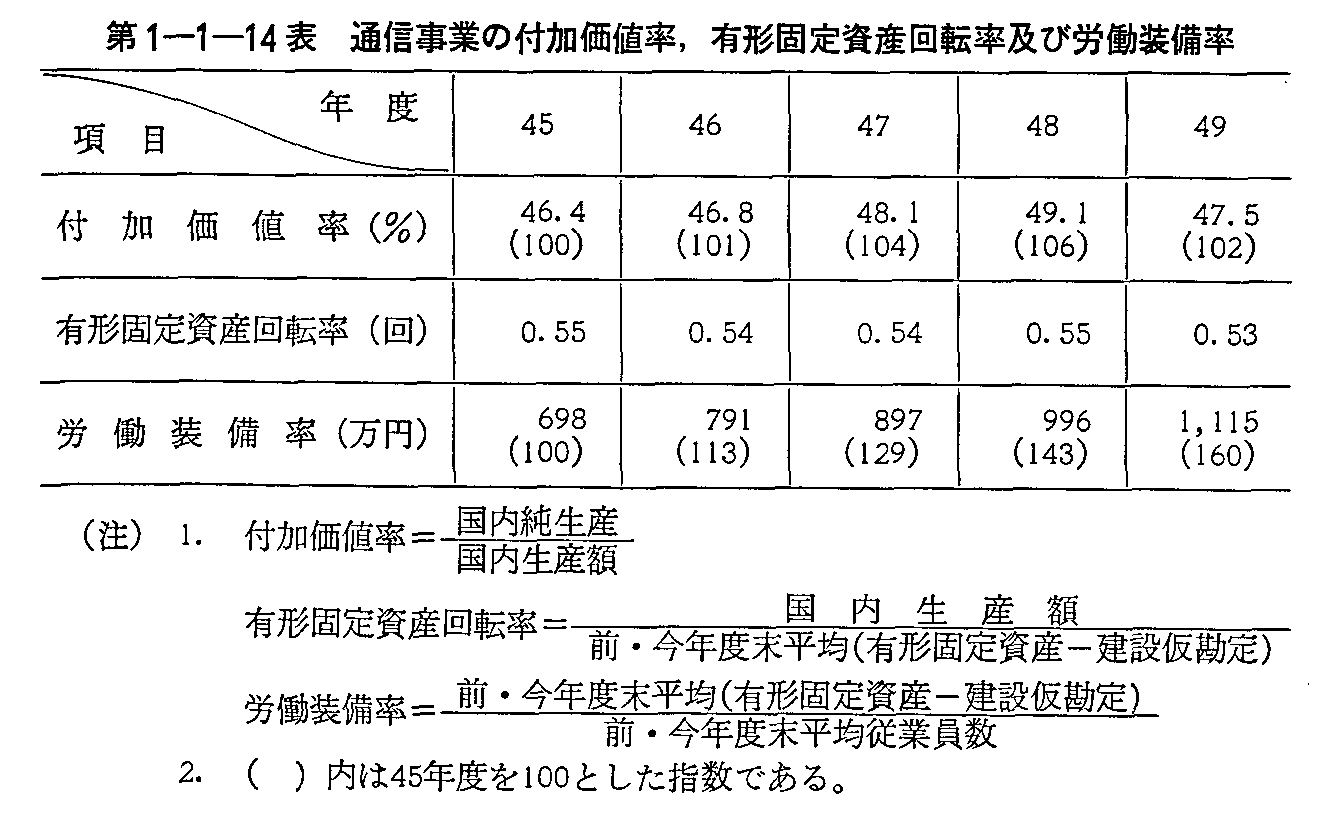
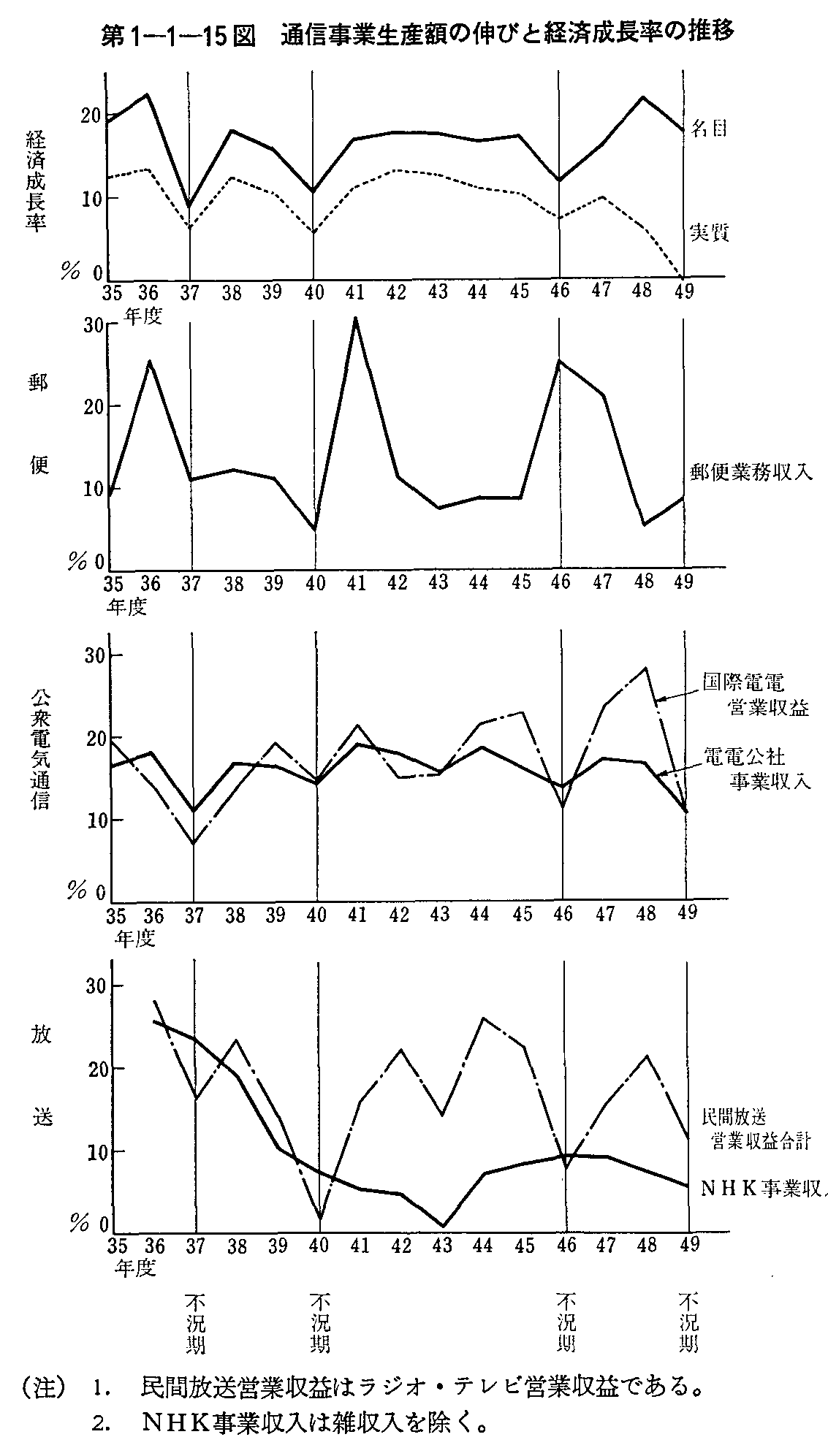
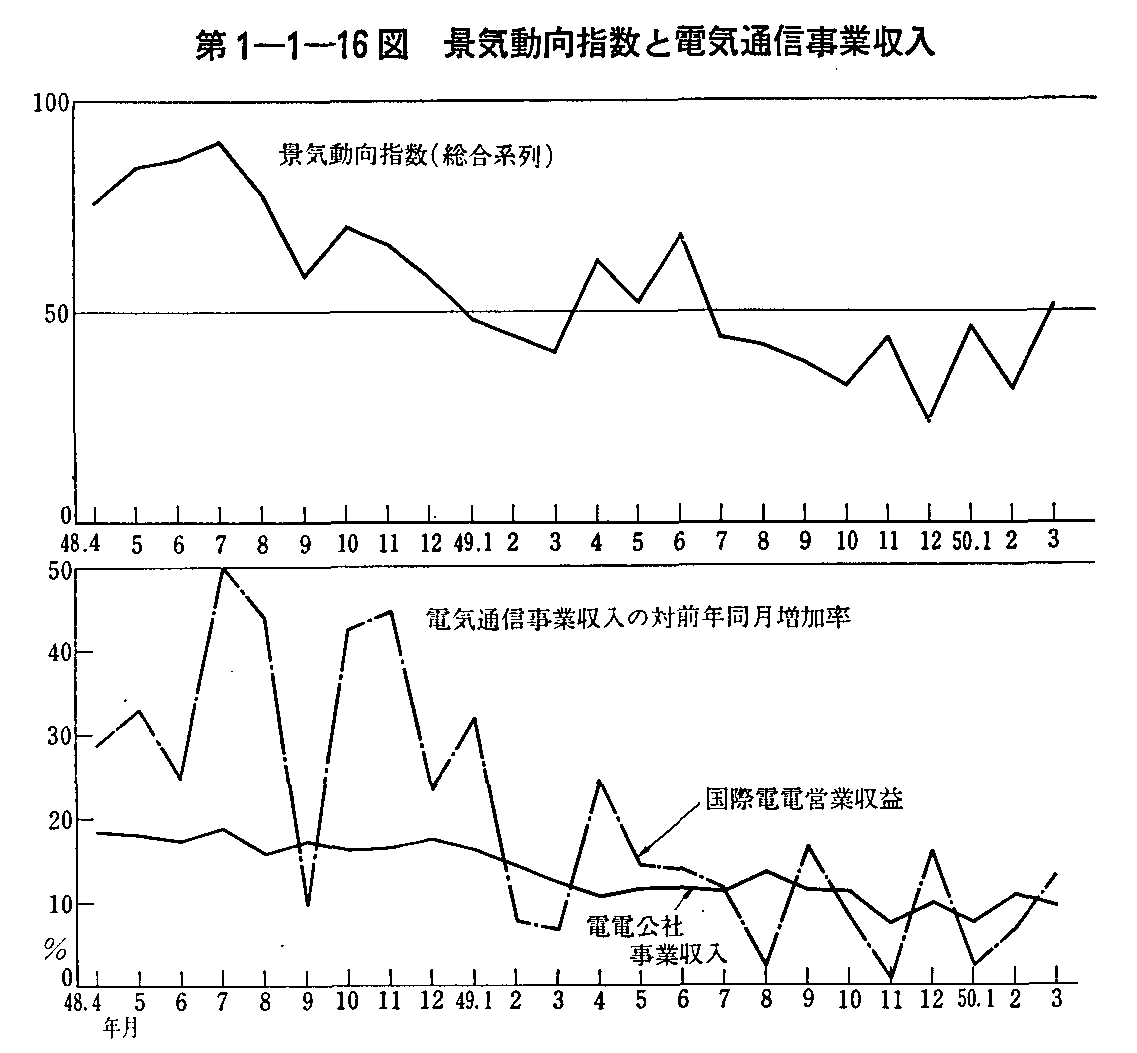
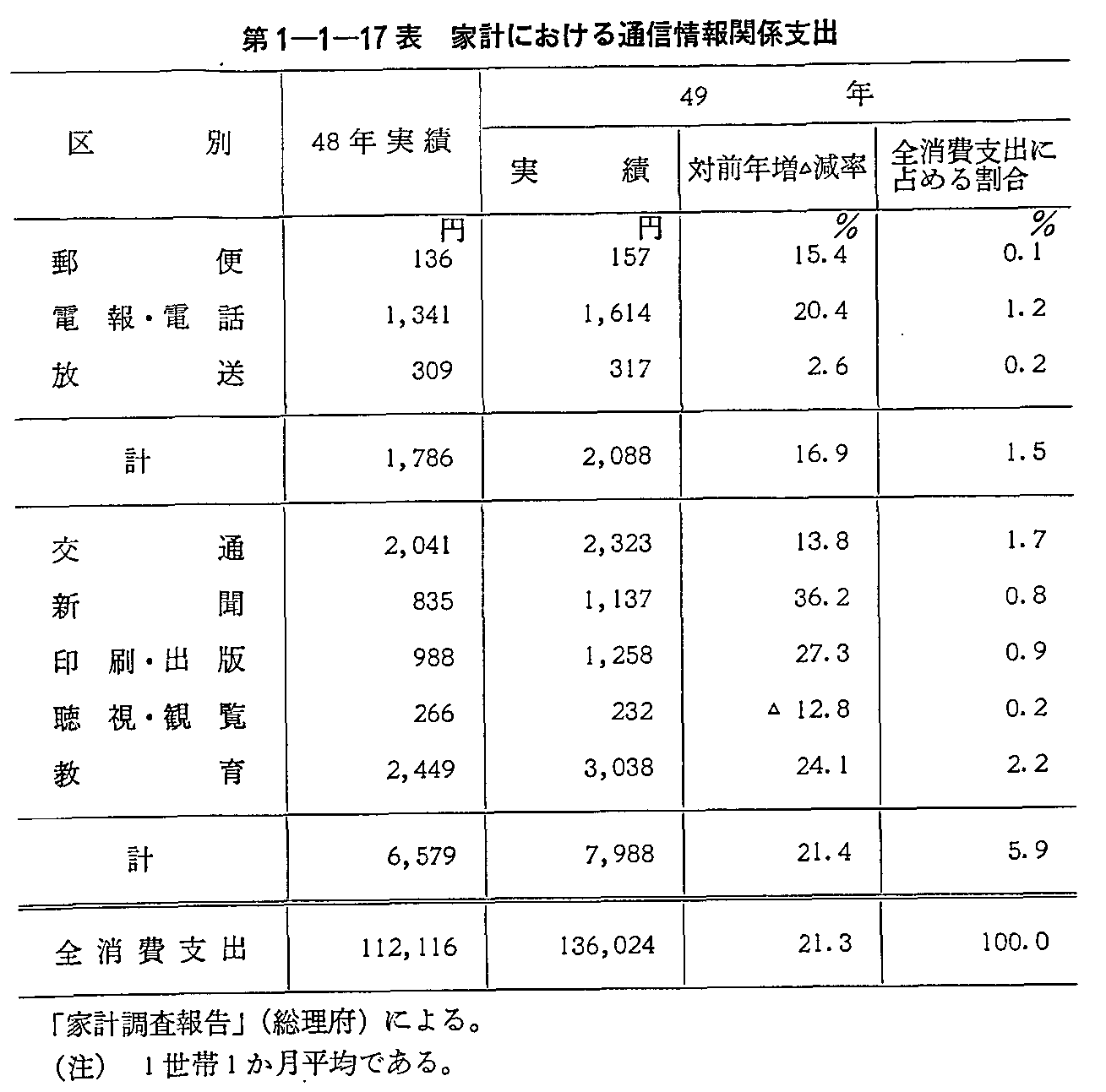
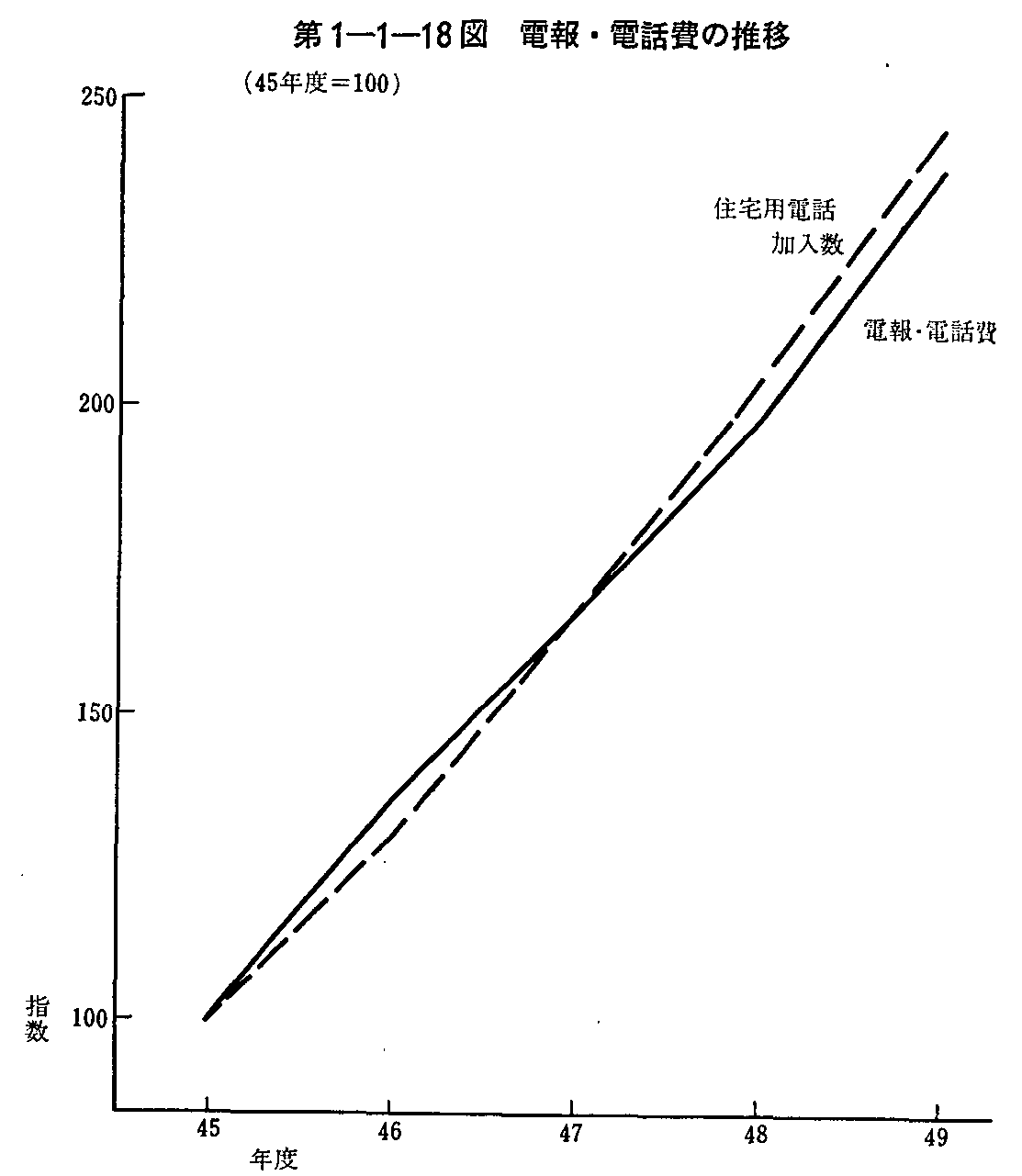
|