 第1部 総論
 第1節 昭和53年度の通信の動向
 第3節 通信と現代文化の今後の潮流
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第6節 データ通信システム  第8節 その他の技術
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第1節 昭和53年度の通信の動向
1 通信の動向
(1) 概 況
ア.国内通信の動向
最近の国内通信の動向は,第1-1-1図のとおりである。
郵便サービスについてみると,53年度の内国郵便物数は142億通(個)で,対前年度比4.3%の増加となり,51年の料金改定前の水準を上回る結果となった。
年賀及び選挙郵便物を除いた平常信の動きをみると,116億通(個)となり,対前年度比5.0%の伸びを示している。
これを郵便サービスの生産額でみると,対前年度比2.5%増の7,503億円となった。
なお,利用状況を諸外国と比較すると,52年度の国民1人当たりの差出通数は,120.6通と,米国の428.7通,英国の172.7通,西独の190.9通と比べてなお相当のへだたりがある。
電信サービスについてみると,電報の発信通数は,38年度の9,461万通をピークに毎年減少を続けてきたが,53年度においては,3,919万通と対前年度比0.8%の微増となった。また,利用内容をみると慶弔電報の全体に占める割合が年々増加し,53年度では70.0%となった。その反面,「チチキトク」といった緊急内容の電報はわずか0.5%を占めるにすぎなくなっている。
また,国民1人当たりの利用通数は年間0.3通と少ないが,英国,西独等の0.1通に比べると高い値を示している。これは慶弔電報の利用が多いことなどによるものとみられる。
加入電信加入数は,51年度末の7万6千加入をピークに減少傾向となり,53年度末は6万7千加入と,対前年度比7.5%の減少となった。これは,新規需要の伸び悩みに加え,51年の料金改定の影響により,契約解除が依然として続いており,データ通信やファクシミリ等の他の通信メディアへの移行があったためとみられる。
53年度のこれら電信サービスの生産額は,加入電信加入数の減少のため,702億円と対前年度比3.8%の減少となった。
53年度末の加入電話等加入数は, 3,640万加入に達した。このうち一般加入電話については,増設予定数160万加入に対し,27万加入減と前年度並の133万加入が増設されるにとどまったが,事務用電話の増設数が25万加入と対前年度比44.5%の伸びを示した。また,地域集団電話については,22万3千加入が一般加入電話に変更された。
電話の普及状況についてみると,人口100人当たりの加入電話普及率は,31.5加入,住宅電話世帯普及率(100世帯当たり)は69.4加入となった。
また,電話機数では,米国に次いで世界第2位,人口100人当たり電話機数では,米国,スウェーデン,スイス,カナダ,ニュー・ジーランド,デンマークに次いで第7位に位置している。一般加入電話に占める住宅用電話の割合は66.8%に達した。このような住宅用電話の普及が進行している中で,電話に対する国民のニーズは高度化,多様化の傾向を強め,各種の附属装置等においても全体的に着実に増加している。電電公社が提供している附属装置等のうち,親子電話は468万個にも及び,プッシュホン244万個,ホームテレホン64万セット,ビジネスホン355万個,電話ファクス1万1千台となっている。また,従来からのサービスに加え「普及形ホームテレホン」,「プッシュ式スピーカホン」,「クロスバー式小容量構内交換設備」等が,新たに提供されるようになった。
電話サービスの生産額については,対前年度比5.1%増の3兆2,225億円となった。
なお,農林漁業地域の通信手段として利用されている有線放送電話の端末設備は,前年度に比べて5.8%減少し187万台となった。
また,53年度の有線放送電話の生産額は,前年度に比べ4.7%減の182億円となった。
専用サービスは,企業の情報流通量の増加傾向に伴い,電話のほか,データ伝送,模写伝送等多様な用途に利用されている。
その利用動向を回線数(L規格を除く。)でみると,53年度末現在,対前年度比3.9%増加し28万9千回線(高速模写伝送サービスからG規格への移行分を含む。)となった。これを規格別にみると,主として通常の音声伝送に利用されているD規格が,21万3千回線と,全体の73.7%を占めている。専用サービスについては,53年4月,料金改定と符号品目の新設等が行われた。53年度の専用サービスの生産額は,料金改定の影響もあって対前年度比29.1%増の778億円となった。
飛躍的な発展を遂げてきたデータ通信は,53年度も順調に推移し,データ通信システム数は,前年度に比べ26.2%増加し,3,468システム(私設システムを除く。)となった。
データ通信回線のうち,特定通信回線は6万7千回線と前年度に比べて14.3%増加しており,公衆通信回線も1万6千回線と対前年度比33.8%の堅実な伸びを示している。
このような状況の下で,電電公社のデータ通信サービスの生産額は,前年度比で25.5%増加し1,163億円となった。
放送関係では,テレビジョン放送は国民の間に広く普及しており,日本放送協会(以下「NHK」という。)の受信契約総数は,53年度末において対前年度比2.2%増の2,839万件となった。このうち,カラー契約は,2,529万件となり,契約総数の89.1%となったが,普及の進展とともに年度増加数の伸びは鈍化している。
一方,ラジオ放送は,カーラジオ及びラジオ・カセット等,若い世代を中心とした需要に支えられて地道な発展を続けている。
放送サービスの生産額については,NHKでは対前年度比2.4%増の2,092億円となった。また,民間放送では,スポット収入を中心とする広告料収入の伸びに支えられて対前年度比12.9%増の8,279億円となっている。
イ.国際通信の動向
最近の国際通信の動向は,第1-1-2図のとおりである。
外国郵便物数(差立及び到着)は,対前年度比2.4%増の2億2,155万通(個)であった。通常郵便物の地域別交流状況をみると,差立では,アジア州が最も多く29.9%を占め,到着では北アメリカ州が35.7%と最も多い。また,航空便の占める割合は,年々上昇しており,差立及び到着を含めた外国郵便物数全体で,53年度は78.1%となった。
国際電信サービスについてみると,国際電報は国際加入電信の普及等により,近年停滞の傾向にあり,53年度における取扱数は412万通と前年度に引き続き7.8%の減少となった。地域別にみると,アジア州が最も多く55.7%を占めている。
国際加入電信取扱数は活発な貿易活動に支えられ,対前年度比18.8%増の2,786万度となった。また,53年度末の国際加入電信加入数は6,474加入,電電公社の加入電信加入者で国際利用登録をしている者の数は,1万7,329加入で,それぞれ順調な伸びを示している。
なお,国際電信サービスの生産額は,対前年度比12.9%増の498億円となった。
国際電話サービスについてみると,その通話度数は対前年度比29.5%増の1,569万度となり,これを生産額でみると対前年度比20.7%増の566億円となった。対地別ではアジア州が最も多く,37.3%を占めている。なお,48年3月に開始された国際ダイヤル通話は,全発信度数の20.6%を占め,52年度に比べ約102.3%増の急成長を遂げており,今後国内利用可能地域の拡大とともに増加することが予想される。
貿易商社や銀行等で利用されている国際専用回線等のサービスは,53年度末現在で音声級回線171回線,電信級回線571回線となり,前年度に比べ各々10.3%,9.8%の増加となった。これをサービスの生産額でみると対前年度比0.5%増の95億円となっている。
(2) 主な動き
ア.ひっ迫する郵便事業財政と年末年始郵便業務の混乱
郵便事業財政は,48年のオイルショックに端を発した経済情勢の変動及び料金改定の遅れにより,50年度末には2,475億円の借入金を抱えるに至ったが,51年1月の料金改定により,51年度及び52年度においてはそれぞれ単年度で601億円と183億円の黒字を計上し借入金を減少させることができた。しかし,53年度には人件費等の経常費増などの影響もあって再び239億円の赤字を生ずることとなった。このため,53年度末における累積赤字は1,900億円を上回ることとなり郵便事業財政は再び悪化することとなった。
一方,53年度の年末年始郵便業務は全逓労組の業務規制闘争が長期にわたって行われたため,全国的に郵便物の滞留が生じ,また,年賀郵便物も配達が大幅に混乱した。
イ.ふみの日の設定
郵政省は,毎月23日を「ふみの日」と定め,手紙を書く運動を全国的に展開することとし,54年3月から積極的にキャンペーンを推進していくこととした。この「ふみの日」は電話の普及等により,いわゆる手紙離れ・文字離れが個人的通信の分野にみられることから,広く国民に手紙を書いてもらうことにより,生活の中にものを書く習慣を取り戻していくとともに,人と人との心の触れ合いを盛んにしたいという趣旨から設けられたものである。この運動を通じ,『手紙』の良さを多くの国民に再評価してもらい,それによって手紙文化・文字文化の見直し気運を醸成していこうとするものである。
ウ.ダイヤル自動化の完了
電電公社は,28年度以降数次にわたる電信電話拡充5か年計画により,電話のダイヤル自動化を進めてきたが,54年3月14日,東京都利島並びに沖縄県南大東島・北大東島における自動化を最後に,全国のダイヤル自動化を完了した。電話のダイヤル自動化は,関東大震災による通信設備の壊滅的な打撃の復興を契機に,それまでの交換手が接続する「手動交換」に替え,大正15年1月に東京中央電話局京橋分局で自動交換機とダイヤル式電話機による「自動交換」を行ったのが最初であるが,明治23年の電話事業創業以来89年目,ダイヤル自動化を開始してから54年目にして,長年の悲願であった「全国どこへでもすぐかかる電話」が実現した。
エ.海事衛星通信システムの進展
大洋を航行する船舶と陸地を結ぶ通信は,80年前に長距離無線通信方式が人命と船舶の安全確保の見地から導入されて以来,短波や中波による無線通信方式が旧態依然として続いていた。しかし,通信の安定維持の困難性等短波通信システムの宿命的限界を解決するため,衛星通信技術を利用したシステムが必要と考えられてきた。この観点から実現したものが海事衛星通信で,現在,米国のマリサット・システムを利用して行われている。このマリサット・システムのインド洋衛星向け海岸地球局が,国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)の山口衛星通信所に完成し,53年11月18日からインド洋海域などの船舶を対象とした電話・テレックス通信の送受信業務を開始した。既に太平洋海域をカバーするサンタポーラ海岸地球局と大西洋海域をカバーするサウスベリー海岸地球局により,両海域上の船舶への業務は開始されており,山口局の開局で三大洋をカバーする世界的規模の海事衛星通信サービスの提供が可能となった。
一方,恒久的国際機関として海事通信を改善するために必要な宇宙部分を提供することを目的としている国際海事衛星機構(インマルサット)の設立に関しては,1976年9月3日にロンドンにおいて「国際海事衛星機構に関する条約」が署名のために開放され,1979年7月16日に発効してインマルサットが発足した。
オ.海底ケーブル建設計画の進展
増加する通信需要に対処するとともに,通信の安定的確保をはかるため,日本・韓国間海底ケーブル建設に関して両国間で協議がなされてきたが,郵政省は53年6月16日,国際電電が韓国逓信部と共同で,このケーブル建設に参加するための日本・韓国間海底ケーブル建設保守協定を締結することに関して認可を行った。この海底ケーブルの全長は280kmで,電話換算2,700回線の容量を持つものであり,55年末に完成する予定である。
一方,東南アジア諸国連合(ASEAN)5か国は,各国を相互に結ぶ海底ケーブル網を1983年ごろまでに完成する計画を進めているが,53年8月に完成したフィリピン・シンガポール間海底ケーブルに続き,計画実施の第二段階としてインドネシア・シンガポール間海底ケーブルが建設されることとなった。郵政省は,54年4月24日,国際電電に対して同社がこの建設に参加するため,インドネシア・シンガポール間海底ケーブル建設保守協定を締結することに関しての認可を行った。同ケーブルは,長さ約1,100km,電話換算480回線の容量を有し,55年6月に完成する予定である。
カ.テレビジョン多重放送時代の到来
53年9月28日のNHK及び日本テレビ放送網株式会社を皮切りに,54年3月までに民放10社が実用化試験局として免許を受け,ステレオホニック放送・2か国語放送のテレビジョン音声多重放送を開始した。また,53年12月25日郵政大臣の諮問機関である電波技術審議会は,テレビジョン放送と同時に文字や図形を流す文字多重放送の方式の基本について答申した。この音声多重放送及び文字多重放送は,既存のテレビジョン放送の電波にその放送とは別の信号を重畳して送信する新しい放送形態であって,電波の利用上極めて効率的である上,設備面においても経済的なものである。
なお,電電公社では,54年8月から放送事業者の要望にこたえて,専用線として提供しているテレビジョン放送中継回線の音声多重化を行った。
キ.民間放送の超短波放送局(FM放送局)及びテレビジョン放送局の新たな周波数の割当て
郵政省は,53年12月15日,放送の多様化を図るねらいで,民間放送の超短波放送局を札幌・仙台・静岡・広島の各地域に,民間放送のUHFテレビジョン放送局を静岡・熊本・鹿児島の各地域に,それぞれ新たに1局開設できるようチャンネルプランを修正した。
民間放送の超短波放送に関しては,43年11月の超短波放送用周波数割当計画によって,中波放送の再編成に伴い必要となる周波数の割当ては留保し,東京・名古屋・大阪・福岡の各地域においてのみ超短波放送の特質を生かした放送が実施されてきた。しかし,その後,中波放送の国際的調整問題の帰すうについてその見通しを得るに至ったため,民間放送事業者による超短波放送が,全国的にできる限り早期に実現できるよう,外国の電波による混信対策を要しないと認められる地域のうちから,放送需要の態様を勘案して周波数割当てを進めることとしたものであり,この周波数の追加割当ては10年ぶりのことである。
また,テレビジョン放送に関しては,放送事業の存立の基盤をなす各地域の経済力が着実に向上しており,地域住民の放送番組の多様化に対する要望も高まっている。このため,経済力・人口等から現在以上の民間放送の存立が可能な地域については,テレビジョン放送の数を拡大することとしたものであり,民間放送のテレビジョン放送局に関しては,48年10月以来5年ぶりで周波数の追加割当てがなされたものである。
ク.中波放送局の周波数変更
53年11月23日,中波放送局の周波数が新周波数に変更された。これは50年にジュネーブで開催された「長・中波放送に関する地域主管庁会議」において取り決められた,従来10kHz間隔であった周波数を9kHz間隔に置きかえるという協定が,同日発効したことに伴うものである。
ケ.宇宙通信実用化体制の進展
近年,通信・放送分野等における衛星利用は世界各国において盛んになってきており,我が国においても衛星利用本格化に向けて各種実験が進められている。例えば,電離層観測衛星「うめ2号」は53年4月24日に,実験用中容量静止通信衛星(CS)「さくら」は5月15日に,また,4月8日に打ち上げられた実験用中型放送衛星(BS)「ゆり」も7月20日にそれぞれ定常段階の運用に移行し,郵政省が中心となって実験中である。また,54年2月6日に打ち上げられ一部装置の不具合から静止軌道投入に失敗し所期の実験が不可能となった実験用静止通信衛星(ECS)「あやめ」は,55年初めにその予備機を打ち上げることになっている。このほか,航空海上技術衛星,電磁環境観測衛星,通信技術衛星の研究開発を推進していくこととしている。
これらの実験の成果を踏まえ,我が国においても,実用の通信衛星及び放送衛星が打ち上げられることとなるが,これらの衛星の管理体制を確立する必要があるため,「通信・放送衛星機構」が,54年8月,通信・放送衛星機構法に基づき郵政大臣の認可を得て設立された。
なお,通信衛星については,通信衛星に関する技術の開発を進めるとともに,利用機関における通信需要に応じることを目的として,57年度に通信衛星2号-a(CS-2a)を,58年度に通信衛星2号-b(CS-2b)を打ち上げることが宇宙開発計画(53年度決定)において決定されており,また,放送衛星については,人工衛星によるテレビジョン難視聴の解消等を図るとともに,放送衛星に関する技術の開発に資することを目的として,58年度に放送衛星2号-a(BS-2a)を,60年度に放送衛星2号-b(BS-2b)を打ち上げることを目途に,関係機関との間で,目下,検討が進められているところである。
コ.キャプテンシステム実験準備の進展
郵政省は,53年4月にキャプテンシステムの実験構想を発表して以来,電電公社と共同で実験準備を進めてきたが,54年2月28日,その実験業務を推進する「財団法人キャプテンシステム開発研究所」の設立を許可した。また,実験サービス用情報素材については,新聞・放送・出版・広告など関係各方面からの提供協力の申出がなされており,これらの提供者により構成される「キャプテンシステム実験サービス用情報素材提供協カ会」が発足し,本格的な活動を開始している。実験は,東京23区内の電話加入者1,000名を対象に,約1年間の予定で実施されることとなっている。
サ.新しい技術の進展
53年度における通信技術の発展状況としては,次のようなものがある。
(ア) 多摩CCIS
郵政省は,同軸ケーブルによる生活情報システムの開発実験を,51年1月から53年3月まで,財団法人生活映像情報システム開発協会生活情報システム開発本部に委託して行ってきたが,53年8月10日に同システムの普及基盤の整備を図るため,55年度までの予定で同システムの運用を再開した。この第二段階の実験は,第一段階の実験調査の成果を踏まえて,モニターに好評で費用・便益比のすぐれたフラッシュ・インフォメーション等のサービスに重点をしぼって運用されている。
(イ) VRS
電電公社は,プッシュホンや簡易キーボードからセンタを呼び出し,テレビ受像機を利用して教養・娯楽・各種案内情報をカラーの静止画又は動画でサービスし,音声の同時サービス及び画像情報のコピーも可能なVRS(画像応答システム)の開発実験に成功した。
(ウ) 光ファイバ
電電公社は,53年9月,心線換算総延長約910km,中継器総数115台を使用した本格的な「光ファイバケーブル伝送方式」の総合的な伝送試験に成功した。これにより,高品質で経済的な伝送方式として有望視されている同方式の実用化に大きく近づくものと期待されている。
(エ) 超LSI
電電公社は,53年4月,世界に先駆けて128Kビット/チップの電子ビーム直接描画による読出し専用超LSI(大規模集積回路)メモリの開発に成功した。読出し専用メモリは固定的な情報の記憶用として,各種電子通信システムの端末機器等へ幅広い適用が進められており,その適用領域の一層の拡大と経済化を図るため,更に集積度の大きなLSIの開発が望まれていたものである。
(オ) 新海底同軸ケーブル
郵政省は,増大する国際通信需要に対応して,将来の銅に代えてアルミニウムを外部導体として使用するとともに,ケーブルシステム全体について経済化を指向した「新海底同軸ケーブルシステム」の開発を終え,その結果を54年3月29日に発表した。
(カ) テレメーターシステム
郵政省は,53年7月25日,総合テレメーターシステム開発会議を設け,加入電話回線を利用して電気・ガス・水道のメーターの計量値を一体的に自動検針する総合テレメーターシステムの実用化を検討してきたが,54年4月12日に開発調査の中間報告をまとめた。
シ.マスメディア宣言の採択
1978年11月28日,パリで開催された第20回ユネスコ総会でマスメディア及びコミュニケーションの役割に言及している「平和及び国際理解の強化,人権の促進並びに人種差別主義,アパルトヘイト及び戦争の扇動への対抗に関するマスメディアの貢献についての基本的原則に関する宣言」が採択された。この宣言の第1条では,「平和及び国際理解の強化等のためには報道の自由な流れ及び一層広いかつ一層均衡のとれた情報の伝播が必要であり,このためにマスメディアは指導的な貢献を果たす。」と,うたっている。なお,本件については,東欧諸国等によって第16回ユネスコ総会(1970年)で提起されて以降,毎回のユネスコ総会で審議されてきた経緯がある。
ス.アジア・太平洋電気通信共同体の創立
54年5月にタイのバンコックでアジア・太平洋電気通信共同体(APT)の創立総会及び管理委員会の創立会合が開催され,54年7月1日より活動を開始した。
APTは,国連経済社会理事会(ECOSOC)の監督下にある国際連合アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において,ESCAP地域の電気通信業務に関する均衡のとれた発達を促進するためにその設立が検討されていたものである。その後,APT設立のためのアジア・太平洋電気通信共同体憲章が51年3月の第32回ESCAP会合において採択され,効力発生条件が備わった54年2月25日に発効してAPTが発足することとなった。
このAPTは,アジア・太平洋地域において伸張著しい通信需要に対処して,地域的及び国際的電気通信網の完成を推進し,同地域における電気通信の発達を助長し,援助することを目的としている。
なお,我が国は電気通信に関する先進国という立場にかんがみ,同地域の安定的国際通信の確保のため並びに国際的連帯の観点から,積極的役割・援助を果たす必要性を認識して,APT創立に寄与してきた。今後はAPTを通じ,同地域内の国際協力に努めることとしている。
セ.国際無線通信諮問委員会総会の開催
53年6月7日から国際無線通信諮問委員会(CCIR)の第14回総会が京都で開かれた。このCCIRは,国連の専門機関で電気通信に関する国際的調整等を行っている国際電気通信連合(ITU)の常設機関の一つで,無線通信に関する技術上及び運用上の問題を研究し,勧告を行う諮問機関である。
この第14回総会では,スペクトラム拡散方式等多くの勧告・報告が承認され,また,54年秋に20年振りに開かれる予定のWARC-79(無線通信規則及び追加無線通信規則の全般的改正のための世界無線通信主管庁会議)での関係規約改正のための技術的基礎をまとめた。
ソ.ガット東京ラウンド政府調達問題
48年9月,東京においてガット閣僚会議が開催され,その東京宣言により,ガットの枠内における包括的な多角的貿易交渉の正式の開始が宣言され,その後,日本,米国,EC等の交渉参加国の間において,工業製品関税引下げ,非関税障壁緩和のための協定類等について所要の交渉が行われてきたが,54年4月12日にはジュネーブにおいて,これら交渉成果の実質内容を確認するための署名(いわゆる仮調印)が行われた。しかし,非関税措置に関する協定類中の一つである政府調達に関する協定については,その協定の適用対象機関(調達体)に関し,日米間においては引き続き交渉が進められてきているところである。
この政府調達問題は,基本的には他の交渉参加国とのバランスを勘案しつつ,我が国がこの協定の適用対象機関をいかなる範囲で定めるかの問題であるが,米国との間においては,日米貿易不均衡を背景とする対日批判,日本市場の開放要求とも関連して大きな問題となり,とりわけ,電電公社への協定の適用問題に関しては,その適用内容の質的・量的拡大をめぐって,日米間において幾度となく交渉が重ねられた。この結果,54年6月2日,政府調達問題を含む貿易経済関係問題について日米間に合意が成立し,共同発表として公表された。この共同発表では,政府調達問題に関し今後の交渉の枠組みと手順について合意している。すなわち,相互主義を電気通信市場開放の基本原則として掲げるとともに,政府調達に関する協定に係る電気通信分野における調達体の範囲については,55年12月31日までに日米間において合意に達するべく努力していくこととしているところである。
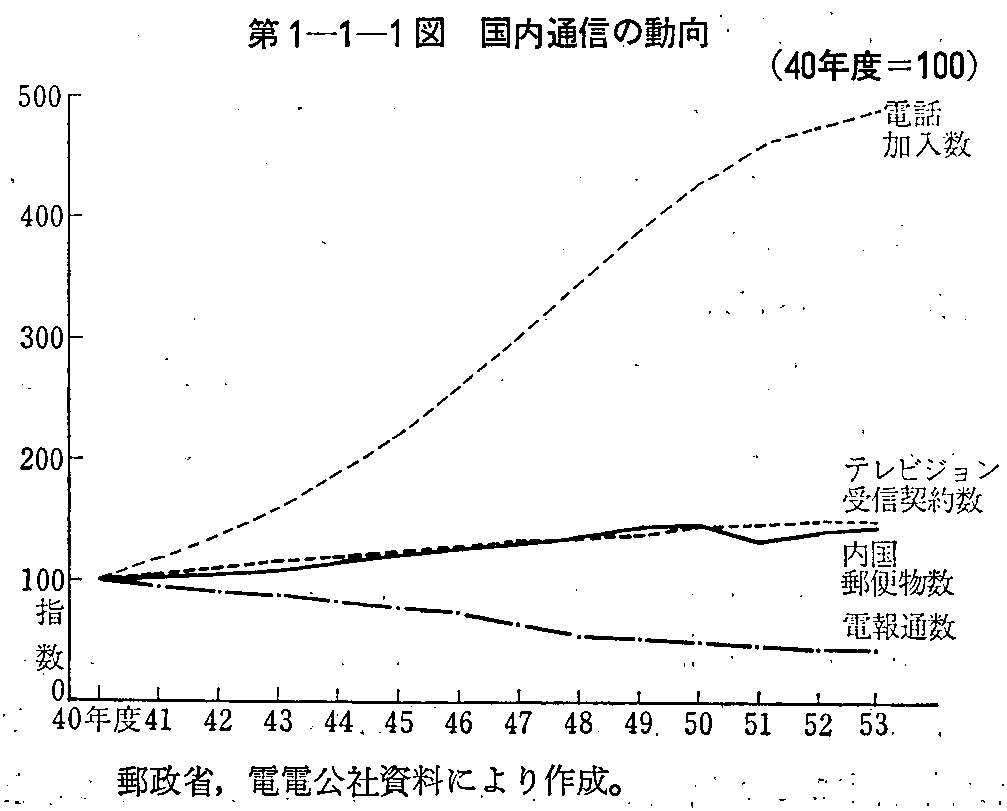
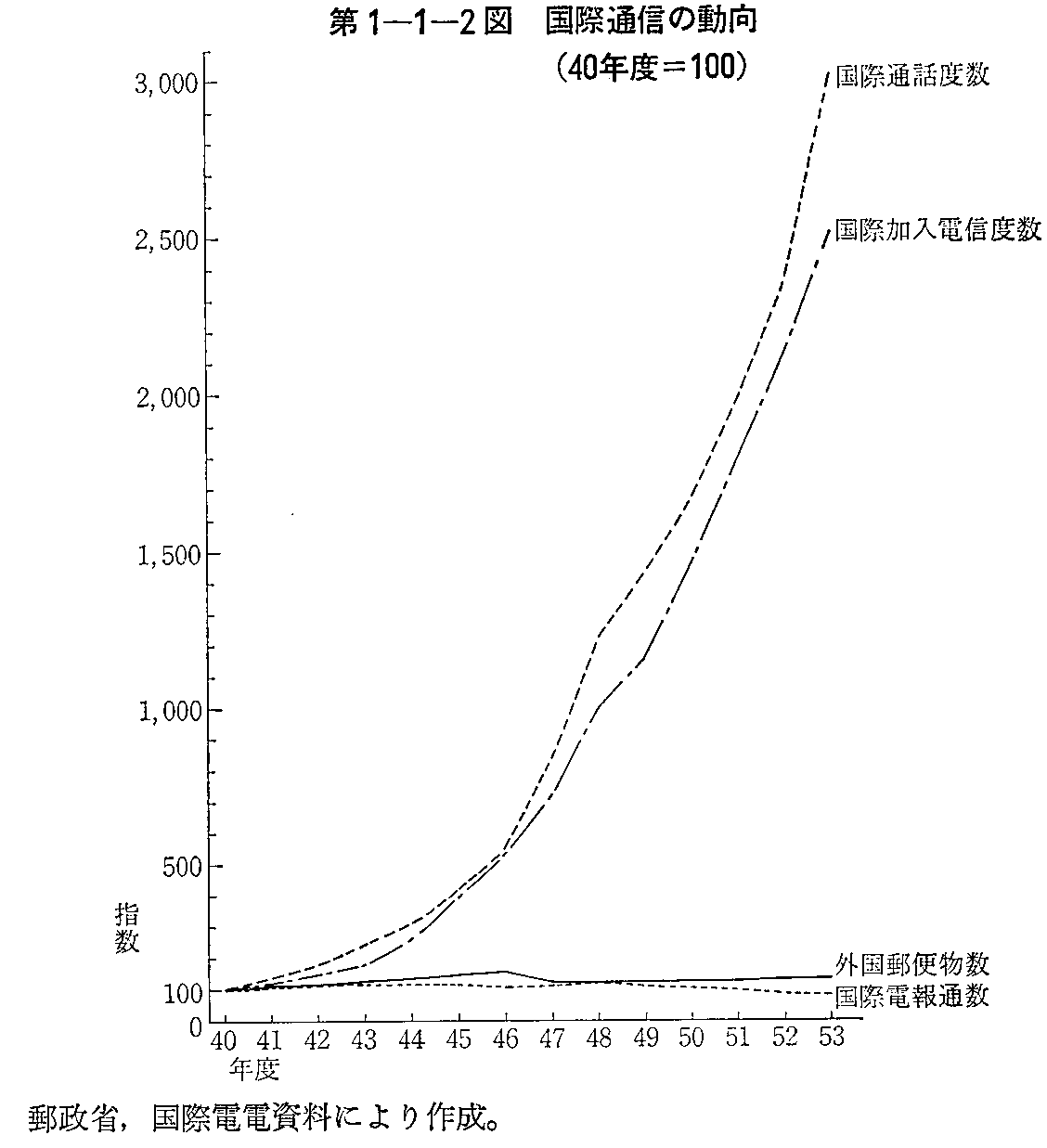
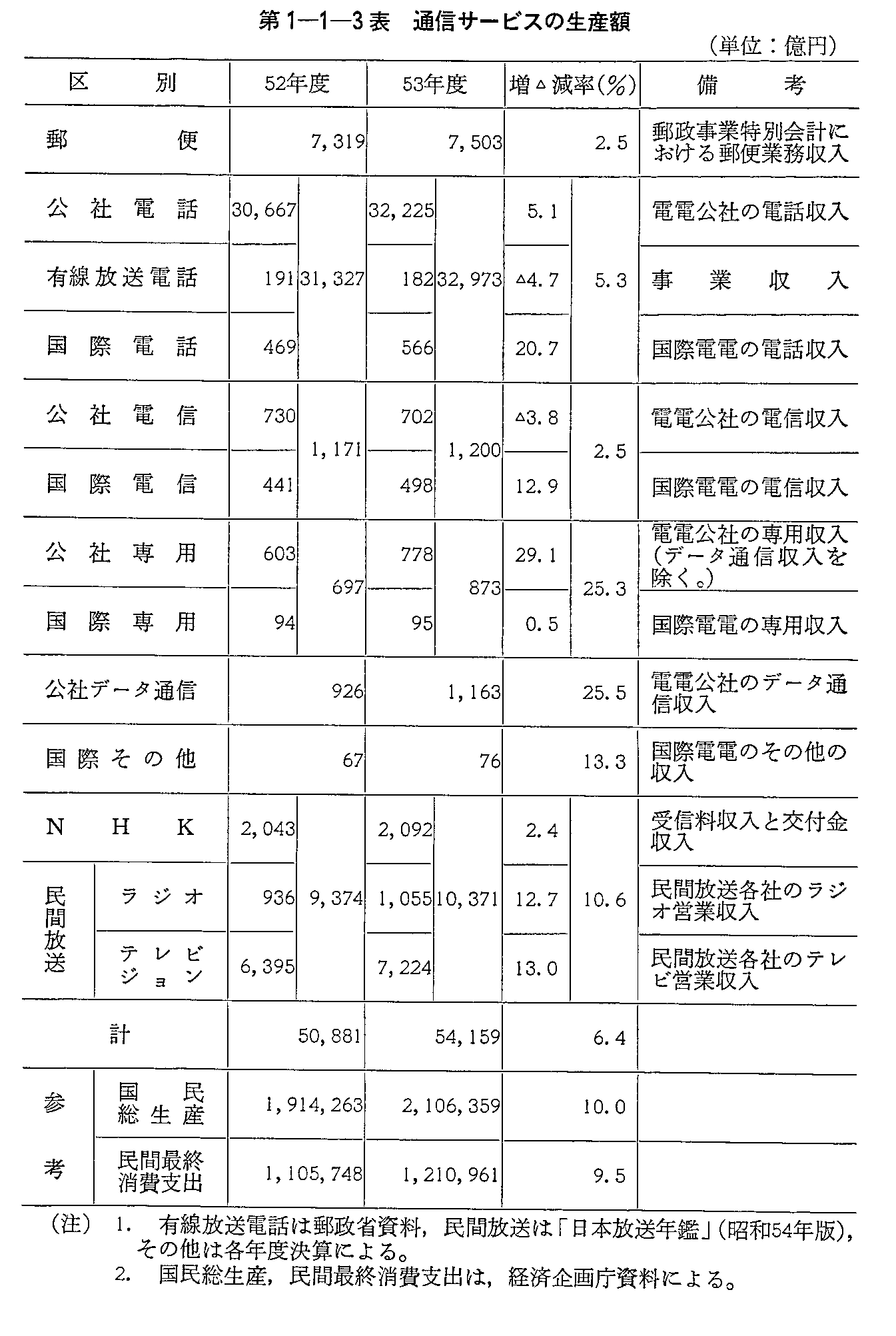
|