|
第1章 特集 インターネット第5節 課題と展望
1 利用環境整備 (1)プライバシー保護 個人情報の本人の予期しない形での利用、漏洩、窃用が懸念 インターネット等で流通し電子化された個人情報は、ペーパー上の個人情報に比べコピーや加工が容易であり、ネットワークなどを通じた個人情報の流出事件等が問題となっている。また、9年9月、一般消費者を対象に行われたアンケート調査(高度情報通信社会に向けた環境整備に関する研究会報告書)によると、個人情報に対する国民の意識は高く、個人情報の保護を強化すべきとの意見が72.8%となっている(図表2))。 そこで、郵政省では、電気通信サービスにおけるプライバシー保護の在り方等を検討するため「電気通信サービスにおけるプライバシー保護に関する研究会」を開催し、10年10月にその報告書を取りまとめ、同年12月に「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(http://www.mpt.go.jp/whatsnew/guideline_privacy_1.html)を告示した(3-5-1(3)参照)。 また、(財)日本データ通信協会(http://www.dekyo.or.jp/)は、10年4月より、個人情報保護登録センター(http://www.dekyo.or.jp/hogo/kojin.htm)を開設し、適正な個人情報保護措置を講じている事業者の登録を行い、その旨をマーク表示(図表3))することにより、事業者及び利用者の個人情報保護意識の向上を図っている。マーク表示は、個人情報の保護についての積極的な企業姿勢を利用者が確認することができ、事業者を選択する際の一つの目安となる。 電子商取引における個人情報の取扱については、9年12月に、電子商取引の実証実験を推進する民間団体であるサイバービジネス協議会(http://www.fmmc.or.jp/associations/cba/)が「サイバービジネスに係る個人情報の保護に関するガイドライン」を制定し、1)アクセス・ログ等の情報収集の事実、利用の可能性について本人に明確にしておくこと、2)個人情報の取扱方法についてはホームページ上で情報提供を行うなどの周知措置を講ずることなど、電子商取引にかかわる事業者がインターネットの特質を踏まえた自主的な保護ルールを整備することを促している。 郵政省では、消費者の不安感を除去するため、民間部門による自主的な取組を積極的に支援するとともに、今後、電子商取引における個人情報の実態等を勘案し、ネットワーク環境に応じた法的対応の必要性を検討する予定である。 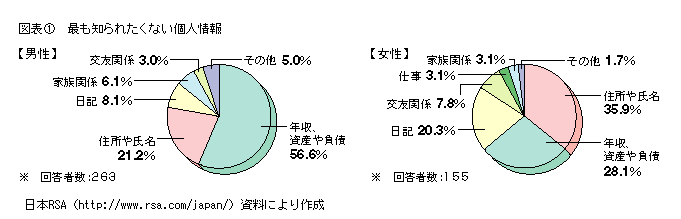 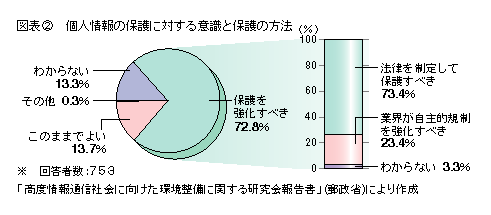 
|