|
第2章 情報通信の現況3 電気通信料金低下の効果
昭和60年から9年にかけての電気通信料金低下率は20.4% 「企業向けサービス価格指数」(日本銀行)によれば、昭和60年から9年にかけて電気通信料金は20.4%低下した(注16)。 電気通信料金の低下が、我が国の各産業の価格をどの程度引き下げ、実質消費額をどの程度増大させたかを分析(注17)すると以下のとおりである。 1)電気通信料金の低下による各産業の価格低下率 電気通信料金の低下は、電気通信を使用する各産業のコスト低減を通じて、各産業の価格を低下させる要因となり得る。 昭和60年から9年における電気通信料金の低下によってもたらされた、価格低下率の大きな上位10産業は放送、卸売、研究等であった(図表)。 この結果から電気通信料金の低下は各産業の価格低下に貢献しており、非情報通信関連部門に対しても大きな効果を及ぼしたことがうかがえる。 2)各産業の価格低下による実質消費額の増大効果 各産業における価格低下の結果もたらされる、実質消費の増大効果(注18)を計測すると、昭和60年から9年までの間に9,300億円の実質消費額の増大がもたらされた。 これを実質国内総支出の成長にどれだけ寄与したかという観点から計測すると、昭和60年から9年までの実質国内総支出の成長率2.64%のうち、価格低下によってもたらされた部分は0.02%であった。 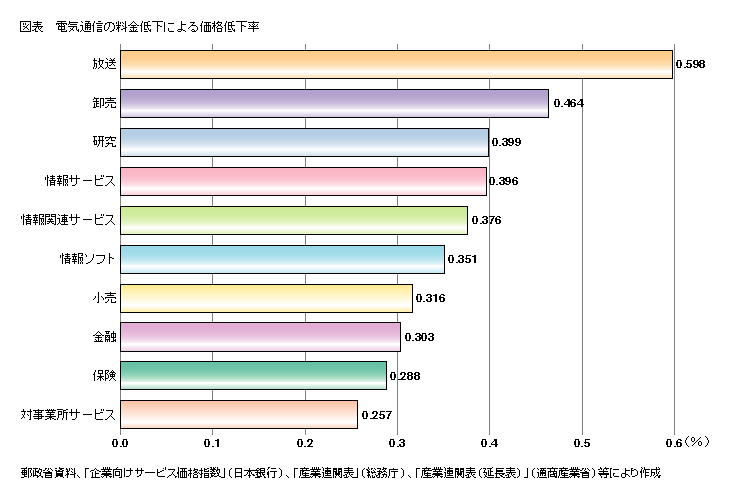
|