第1章 平成4年情報通信の現況
(2) 地域の情報流通の動向
ア 地域別情報流通状況
郵政省では全国を対象とした「情報流通センサス」と並行して、昭和62年度から都道府県別の情報流通量を把握するため、「地域別情報流通センサス」の計量を行っている。ここでは4年度に実施した3年度分の調査結果に基づき、都道府県別の情報化の現状を概観する。
(ア) 発信情報量
3年度において各県内の情報発信者から県内外に発信された計量対象31メディアの合計である地域別発信情報量の地域別のシェアをみると、東京が19.8%と突出して大きく、第2位の大阪(シェア 7.4%)を大きく引き離している。東京の発信情報量が高いシェアを占めているのは、新聞、雑誌等が多く出版されており、輸送系メディアによる情報発信が他の地域と比べて突出して大きい(シェア28.2%)ためである。第3位以降は神奈川(同 5.8%)、愛知(同 5.2%)と続いており、上位7都道府県でシェアの過半数(50.6%)を占めている(第1―3―6図参照)。
また、発信情報量の地域的偏在の推移を変動係数で示したものが第1-3-7図であり、これによると3年度には地域間格差が若干拡大する傾向を示している。
第1-3-8図により、発信情報量に大きな影響を与える電気通信系メディア、輸送系メディアの地域間格差をみると輸送系メディアの方が格差が大きく、また過去10年間の推移をみると、近年電気通信系メディアの拡大傾向は顕著であり、変動係数は昭和63年度の 1.194から3年度には 1.320となっている。
(イ)
選択可能情報量( 供給情報量)
3年度において各県内の情報の受け手に対して県内外から提供された計量対象31メディアの情報量の合計である地域別選択可能情報量について、県民一人当たりでみると、東京(全県平均の1.58倍)が最も高い水準にある。第2位以降は、神奈川(1.51倍)、長野(1.46倍)、山梨(1.46倍)、千葉(1.42倍)、埼玉(1.36倍)、大阪(1.30倍)、群馬(1.26倍)の順となっている。関東地方とケーブルテレビの普及が進展している地域の水準が高くなっている(第1―3―9図参照)。
昭和56年度との比較で大きな伸びを示した地域としては、山梨(3.94倍)、長野(3.24倍)、長崎(3.21倍)、佐賀(3.00倍)、岩手(2.61倍)等が挙げられ、近年新たに民間テレビジョン放送局が開局した県(長野、長崎、岩手)若しくはケーブルテレビの普及の著しい地域(山梨、長野)となっている。これは、一人当たりの選択可能情報量を比較した場合、テレビジョン放送局の開局数、ケーブルテレビの普及状況等に左右されるためである。
また、選択可能情報量の地域的偏在の推移を変動係数でみると、3年度には2年度に引き続き格差が縮小する傾向を示している(第1-3-7図参照)。
(ウ)
消費情報量
3年度において各県内で実際に消費された計量対象31メディアの情報量の合計である地域別消費情報量について、県民一人当たりでみると、最も高い水準にあるのは栃木・北海道(全県平均の各1.06倍)であり、次いで東京・茨城(同各1.05倍)、富山・山梨・山口・新潟(同各1.04倍)の順となっている。消費情報量については、県民一人当たりでみると、地域的な違いはほとんど見られない状況になっている。
(エ)
地域ブロック間の情報流通格差
情報流通量の地域的単位での特徴を明らかにするため、全国を北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の10の地域ブロックに分け、ブロック単位での情報流通量の比較を試みた(付表8参照)。
このうち発信情報量と選択可能情報量について抽出、図示したものが第1-3-10図である。
これによると、発信情報量、選択可能情報量ともに関東地方が全ブロックの平均の1.34倍、1.39倍と、いずれも10ブロックの中で最も大きくなっており、情報の発信と供給において関東地方の水準が高くなっている状況がうかがわれる。
図に見るとおり選択可能情報量では、関東に次いで近畿(同1.17倍)、信越(同1.13倍) 、東海( 同1.13倍)の水準が比較的に高くなっている一方、東北、九州・沖縄は各々全ブロックの平均の0 .74 倍、0 .77 倍となっており、一人当たり情報量の大きい地方と小さい地方とが比較的はっきりと分かれている。それに対して、発信情報量では、関東(同1.34倍)に次いで近畿が同1.07倍とわずかに全ブロックの平均を上回っている程度であり、関東地方だけが突出し、他の地域にはあまり格差はみられない構造となっている。
このように、地域間ブロック間でみても、一人当たり情報流通量には地域的な違いがある。この地域格差の推移を、発信情報量について各年度の全ブロックの平均を 100とした指標によりみたものが第1-3-11図である。過去10年間の推移でみると、発信情報量の地域間格差はほぼ横這いであり、大きな変動はみられない結果となっている。
(オ)
情報流通量と経済指標との関係
一人当たり選択可能情報量と一人当たり県民所得により、各都道府県の散布状況をブロックごとにみたものが第1-3-12図である。
これによると、関東、近畿、東海の各地域が、比較的に図の中央上部から右上部に位置しており、特に東京は一人当たり選択可能情報量、一人当たり県民所得ともに全国で最も大きく、突出している。
一方、九州・沖縄及び東北の各地域の一人当たり選択可能情報量、一人当たり県民所得は相対的に小さく、両地域の分布は図の左下方部に位置しており、東京と両極を成す結果となっている。
イ 地域間の情報交流状況
電気通信事業報告規則による報告に基づき作成したものによると、3年度の国内加入電話トラヒックにみる全通話回数は 769億回となっており、対前年度比 2.4%の増加である。
(ア)
MA内通話終始率
各MAから発信される総通話回数のうち、同一MA内に向けられる通話回数の比率(MA内通話終始率)は、全国平均で66.1%、また隣接MAに向けられる通話回数の比率は同じく13.4%であり、我が国の通話の大半は、市内通話を中心とする近距離との通話である(第1-3-13図参照)。
地域ブロック別にみると、関東、東海、近畿のMA内通話終始率は低く、北海道、四国、九州、沖縄は高い。特に、沖縄は90%を超える高い比率になっている。関東、東海、近畿におけるMA内通話終始率が低いのは、東京特別区、名古屋市、大阪市といった大都市から受ける影響が強く、大都市MAとの通話交流が頻繁に行われているためと考えられる。一方、北海道、四国、九州、沖縄のMA内通話終始率が高いのは、強い影響を受ける大都市が近隣になく、通話交流が比較的狭い範囲に限られるためと考えられる。
(イ)
都道府県内通話終始率
同一都道府県内に終始する通話の比率をみると、全国平均で81.6%となっており、首都圏、近畿圏では、70%台前半の県が多い。これらの地域では、東京都や大阪府の影響を強く受け、都道府県境を越える通話が頻繁に行われているためと考えられる(第1-3ー15図参照)。
なお、対象を地域ブロックにまで広げると同一の地域ブロック内に終始する通話の比率は92.7%となり、ほとんどの通話が近隣の都道府県まで含めた地域ブロック内で完結している(第1-3-16図参照)。ここで示した都道府県内通話終始率及び地域ブロック内通話終始率の値は、いずれも漸減しており、より遠方との通話交流の比率が徐々に高まり、通話圏が徐々に拡大していることがうかがえる。
(ウ) 都道府県間トラヒック交流状況
地域間のトラヒックの交流状況を都道府県単位でみると、各県とも通話対地として近隣県が上位を占めるとともに、東京都又は大阪府が上位に現れている。特に、東京都は鳥取県を除き、他のすべての道府県において通話対地として上位5位以内に入っており、その影響力が全国に及んでいる。大阪府は、近畿、中国、四国の各県との関係では東京都よりも上位にきているが、九州地方になると、逆に東京都の方が上位になっている。(第1―3―17表参照)
地域ブロック別にみると、上記と同様の傾向がみられ、各ブロックとも自ブロックから外にでていく通話の対地としては関東又は近畿が上位となっている。(第1―3―18図参照)
このように、通話交流においては関東(東京都)と近畿(大阪府)の影響力が強いが、特に、関東の影響力が強く、情報面からの首都圏への一極集中の状況がうかがえる。
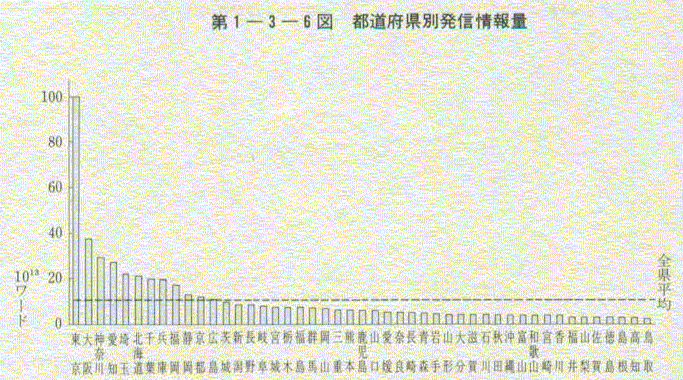
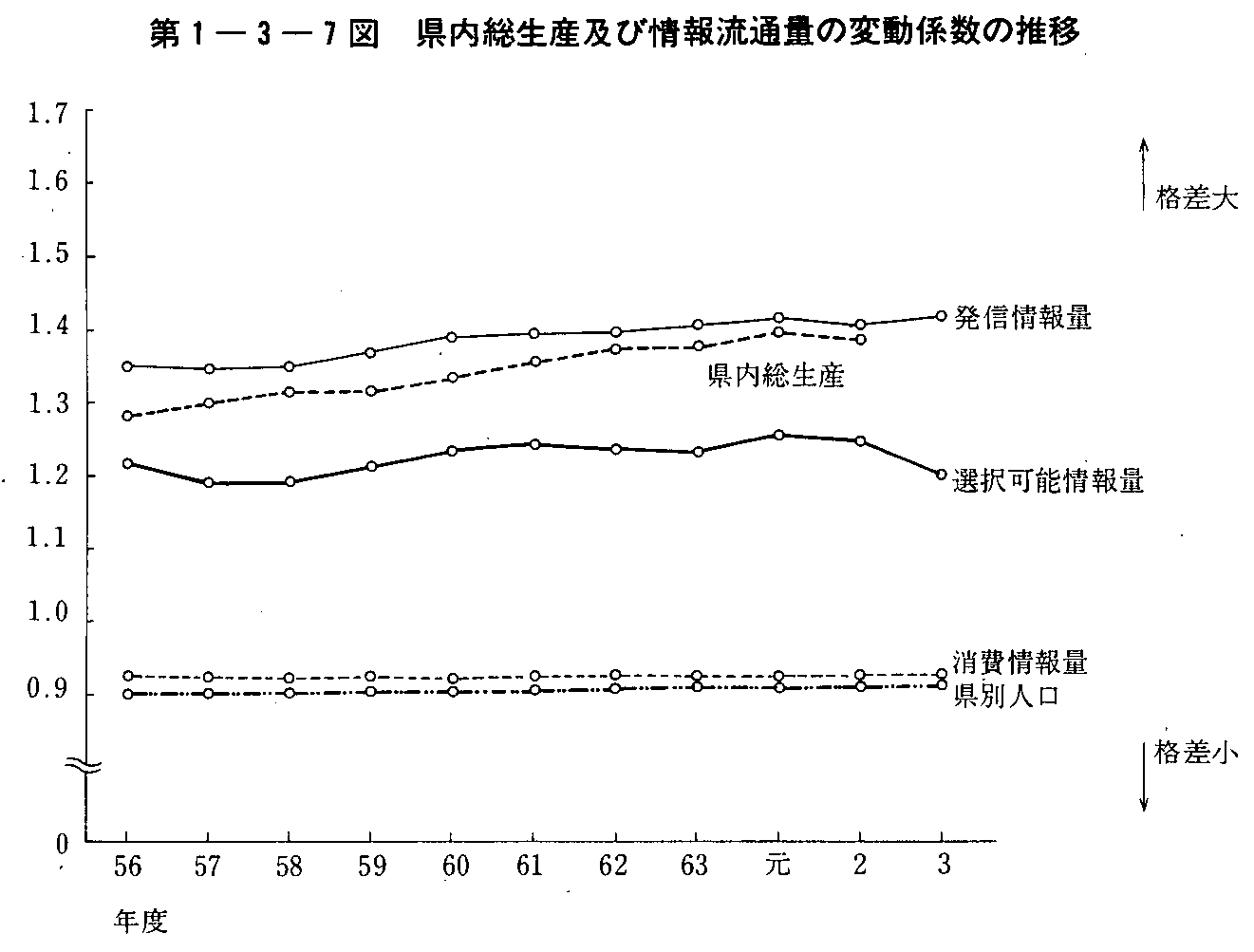
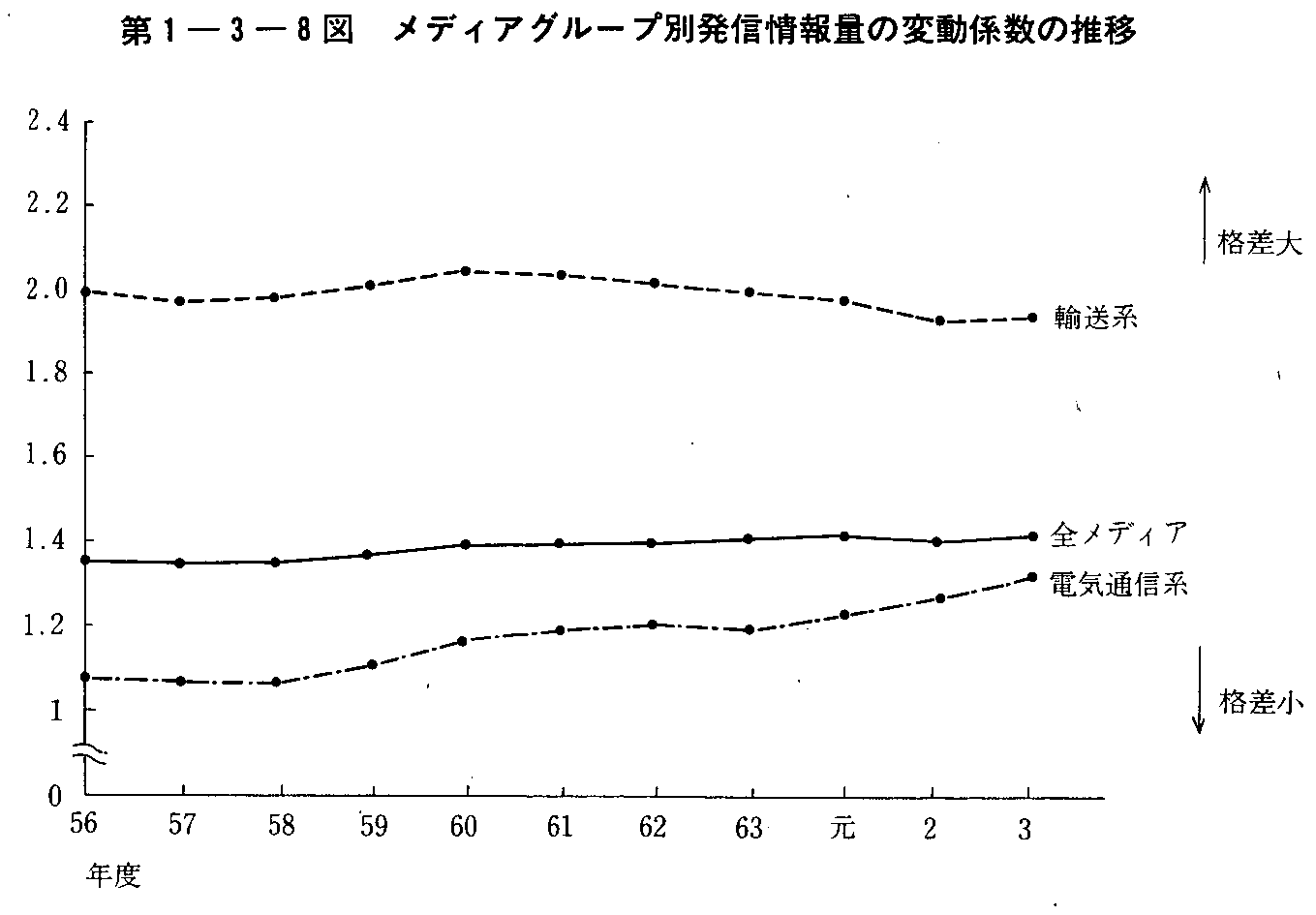
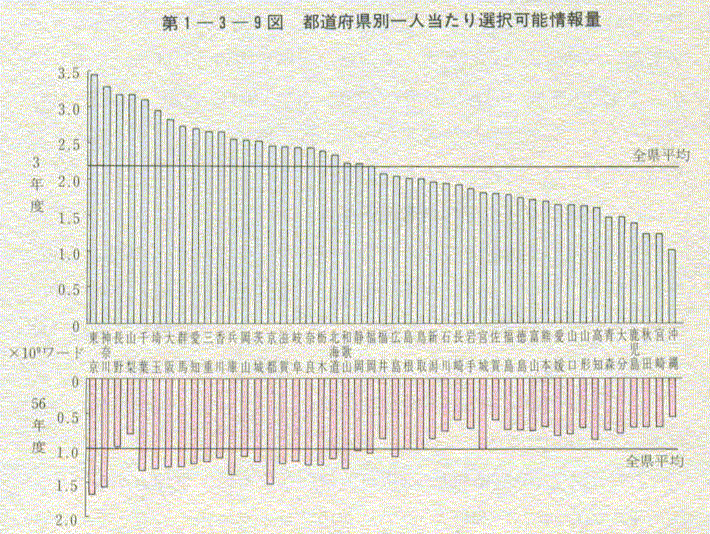
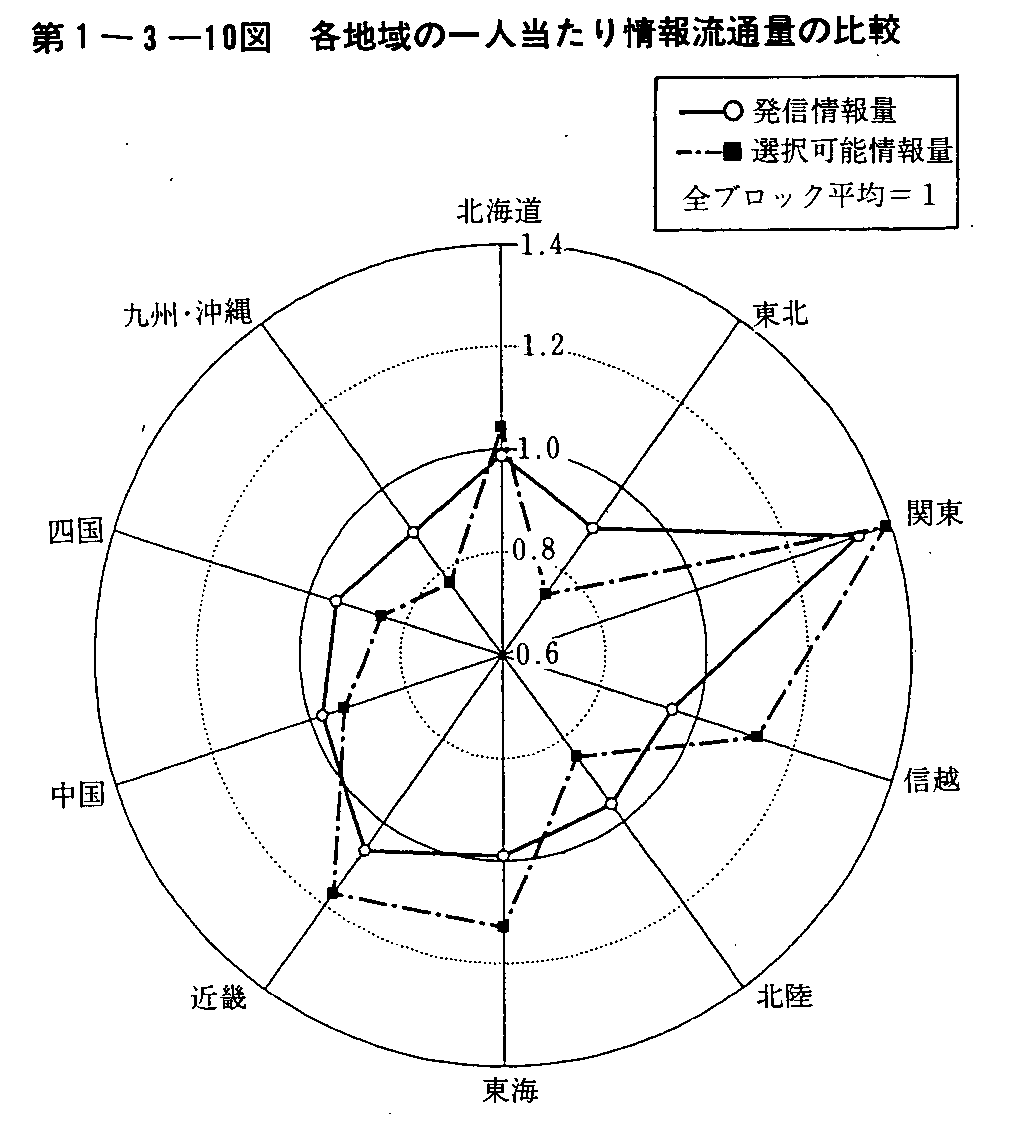
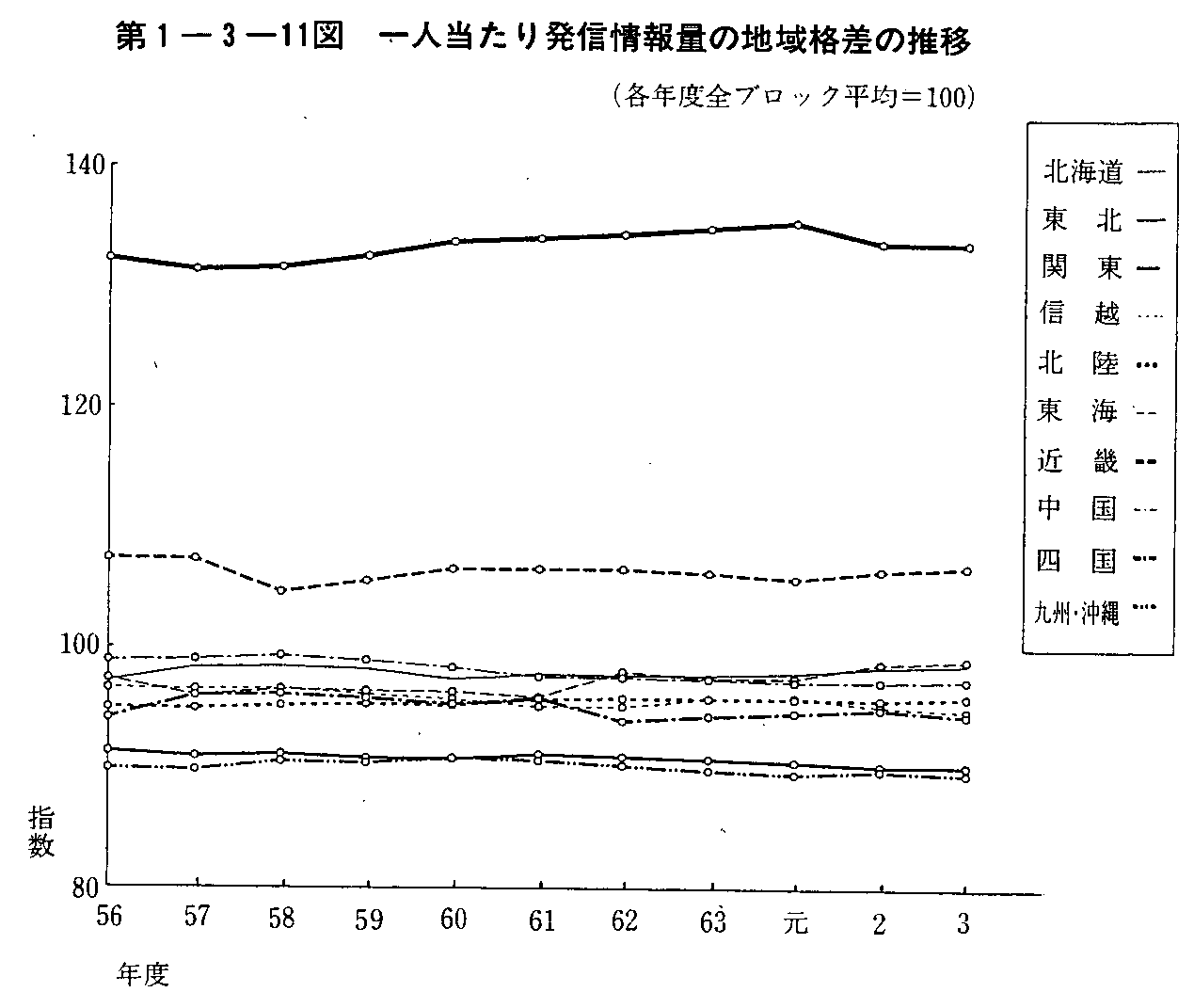
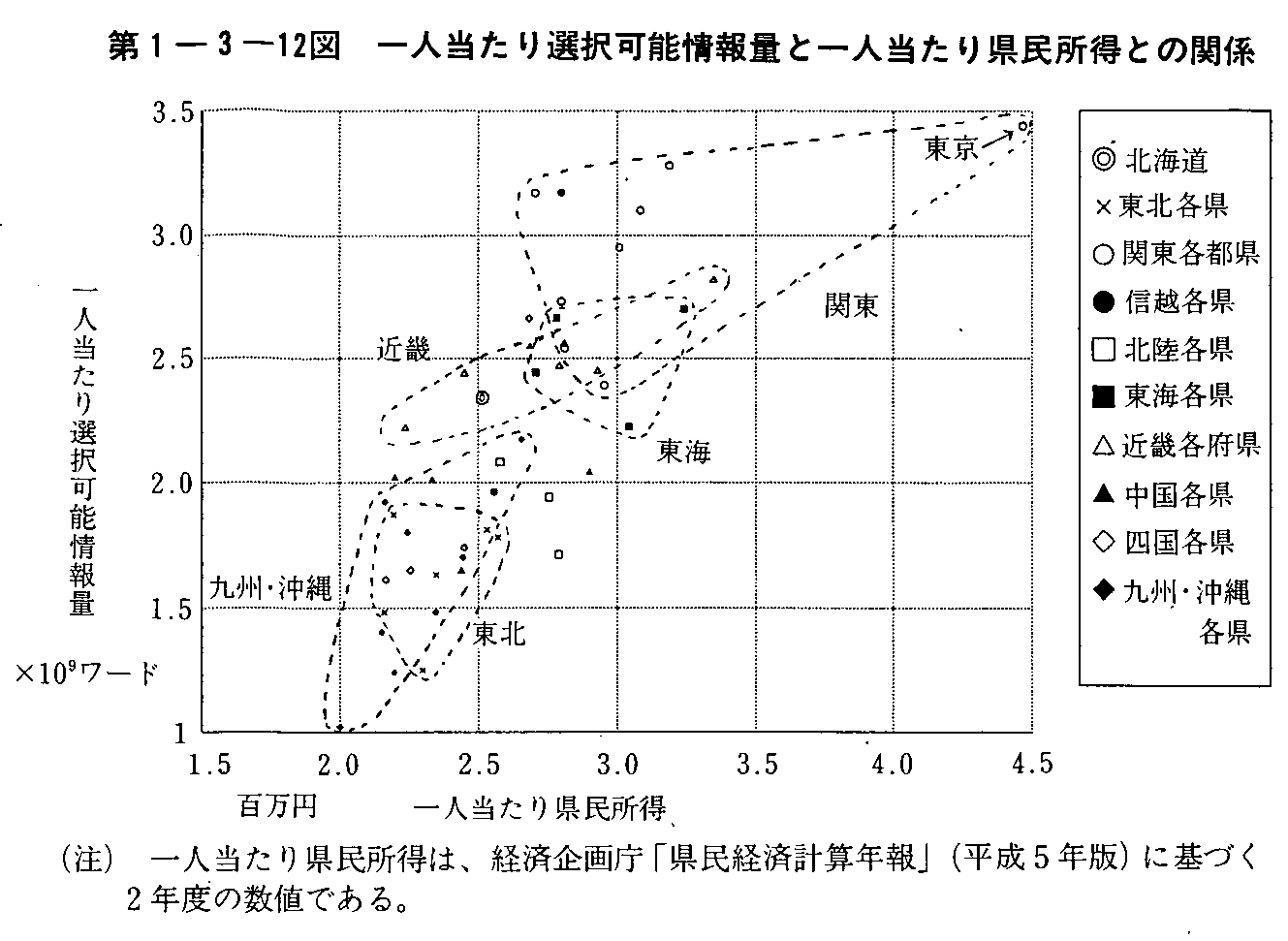
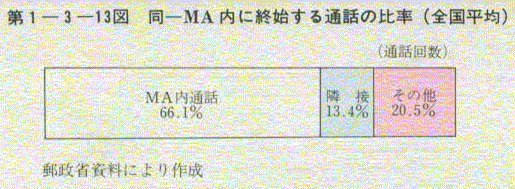
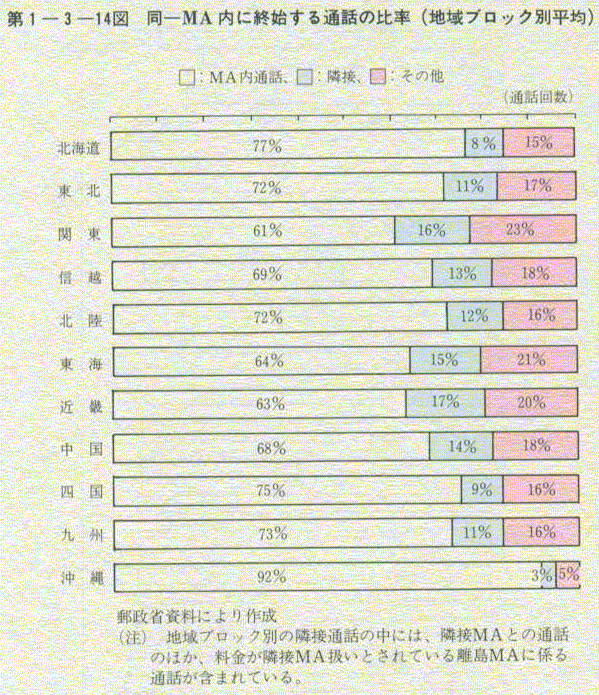
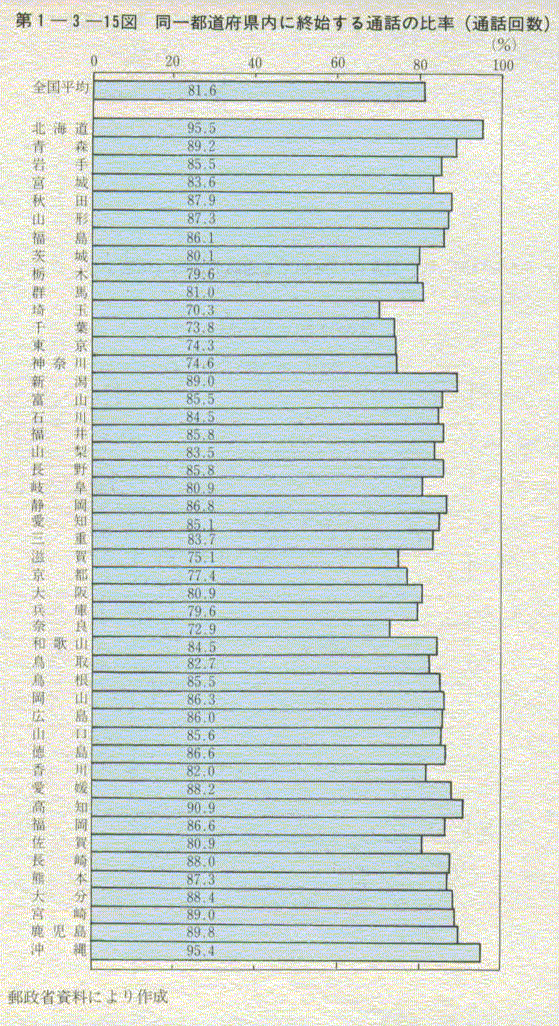
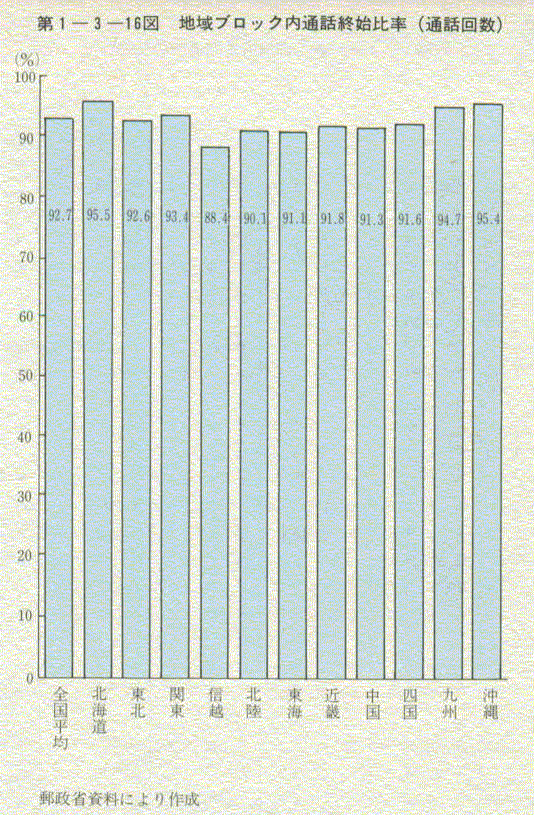
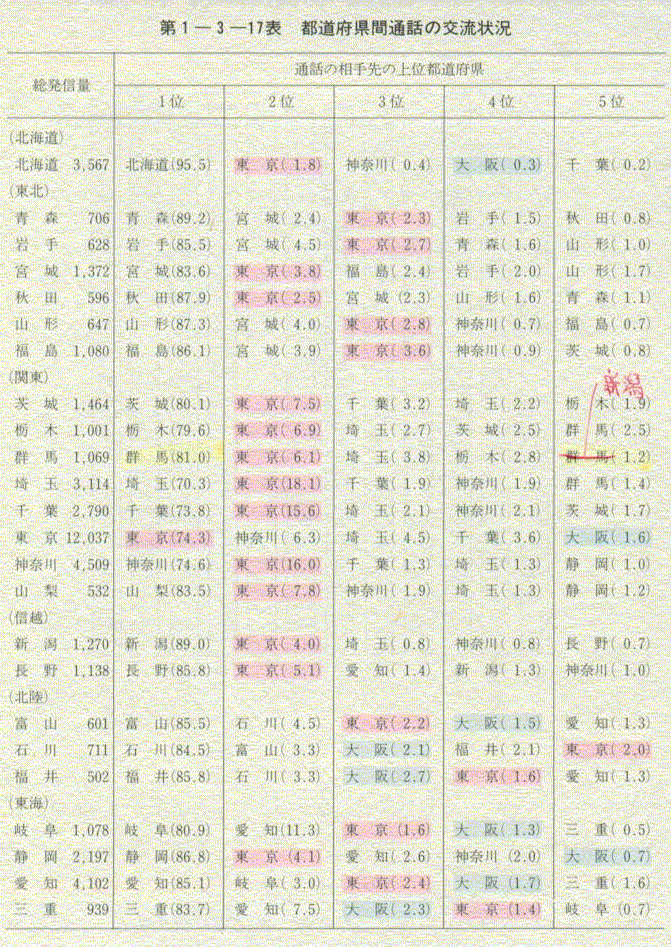
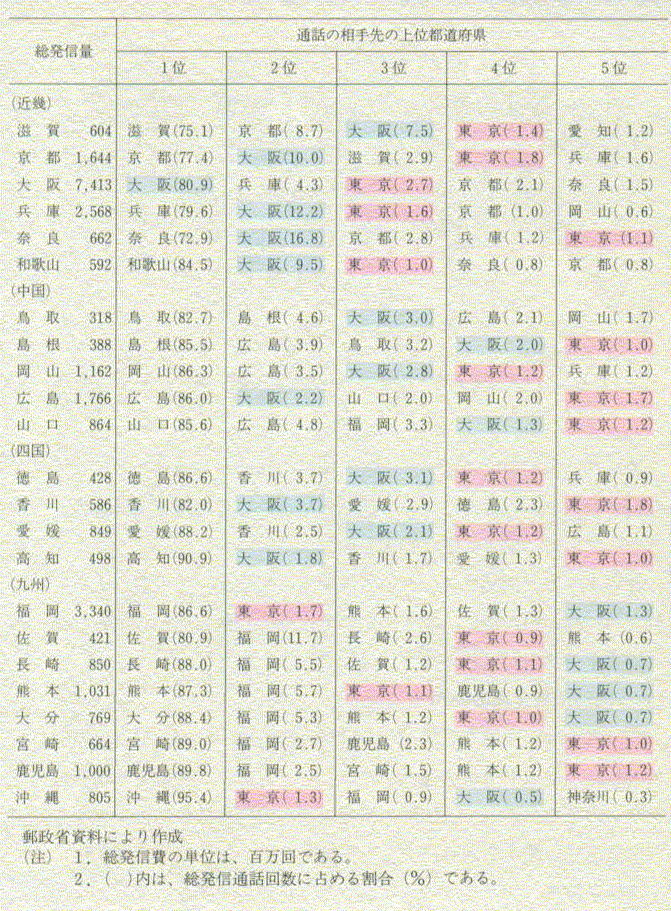
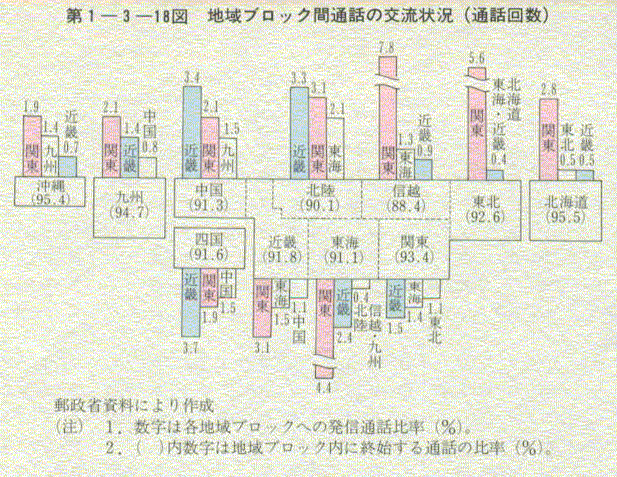
|