 第1節 情報通信サービスの動向  第2節 情報通信経済の動向
 2 情報通信経済の状況
 1 情報流通の動向  2 情報化の進展状況
 第1節 情報通信政策の展開
 3 情報通信による豊かさとゆとりのある生活環境の整備  4 情報通信による環境問題への対応  5 情報通信による国上の均衡ある発展  6 地域情報化の推進  7 電気通信産業振興のための環境整備
 第2節 電気通信の健全な発展
 1 電気通信事業政策の着実な推進  2 電波利用の促進
 第3節 放送政策の新たな展開
 1 放送メディアの多様化に向けて  2 放送ソフトの充実のために  3 放送の利用格差の是正に向けて
 第4節 郵便事業・郵便局ネットワークの新たな展開
 1 郵便事業運営基盤の整備・充実  2 豊かな暮らしづくりに向けた郵便サービスの提供
 第5節 情報通信に関する国際政策の充実
 2 国際協力の推進
 第6節 技術開発・標準化の一層の推進
 1 次世代を支える技術開発の促進  2 重要性を増す標準化の推進
 第1節 映像メディアの発展と現代社会
 1 映像系情報通信の利用動向  2 映像市場等の動向
 1 総合的な政策の推進  2 情報通信インフラ整備の推進  5 利用機会均等化等の推進  6 環境及び生活環境への貢献  8 技術開発の推進
 第4節 映像新時代の発展とマルチメディアの推進
 1 今後の展望  2 21世紀に向けた課題
|
第1章 平成4年情報通信の現況
(3) 社会の情報化
我が国においては、企業・産業界、家庭等における情報化の進展とともに、地域社会においても情報化への様々な取組が行われており、社会全体としてバランスのとれた情報社会を実現させていくためには、より豊かで充実した社会生活の実現に向けた情報化の推進が必要である。
ここでは、総合情報提供、生涯学習、医療・福祉、交通等の分野における情報化の動向について、主な先進事例をもとに社会の情報化を概観する(第1―3―36表参照)。
ア 行政情報提供分野
行政情報の提供については、市民の生活やサービス等の向上を図るとともに、地域住民に対して、地域社会の活性化及び情報化を図ることを目的として、一元的、総合的、最新の地域サービスの情報が様々に提供されている。長野県飯田市では、加入電話回線の空き時間を利用するオフトーク通信網を介して、通信センターとオフトーク通信網に加入している各家庭が電話回線で接続され、地域の総合的な情報が効果的に家庭に提供されている(第1―3―37図参照)。
提供情報としては、次のようなものがある。
[1] 市政情報(市政に関する情報、イベント・催し物の案内、市議会の生中継等)
[2] くらしのための情報(市役所等への届出、健康に関する情報、ボランティア等に係る福祉情報等)
[3] 余暇情報(地域サークル活動や地区市民センター等で開催されている講座・教室についての案内等)
[4] 地域の歴史
[5] 災害、火災時の緊急通報
さらに、各家庭では、オフトークスピーカーから音声で、各種情報を入手する以外に、ケーブルテレビでオフトーク通信で提供されている情報の背景映像や市議会の生中継が視聴できる。
このように、地域社会に密着した総合的な情報提供については、電気通信サービスや放送サービスを組み合わせて、文字や音声、映像等の情報が提供される動きがある。このような動向は、今後の社会における情報化の進展を先導していくものとして期待されるところである。
また、郵政省は、5年1月よりパソコン通信サービス及びビデオテックスサービスを利用して、「郵政省オンライン広報システム」により、報道発表に供した郵政行政情報を提供している(第1―3―38図)。参照このシステムは、情報提供網の拡大・強化を図り、多くの国民や企業等が、郵政行政の各種情報を簡便に入手できるように、その機会を拡大することを目的としている。
イ 教育・学習分野
労働時間の短縮、週休2日制、長寿化等から個人の自由時間が拡大し、国民生活においては、これまでの物質的な豊かさに加え、精神的な豊かさの充実が求められており、余暇の過ごし方が問われている中、生涯学習への関心が高まっている。
このような状況において、既存の文化情報や学習情報を素早く確実に入手して、市民等が自主的に気軽に学習活動に参加できる体制を整備することを目的として、生涯学習情報提供に係るネットワークシステムが構築、利用されている例がみられる(第1―3―39図参照)。
生涯学習情報ネットワークシステムでは、公民館や図書館、体育館、地区市民センター、保健センター等に設置されているパソコン端末から、学習情報データベースにアクセスすることにより、例えば次のような情報が入手できる。
[1] 講座教室情報(今学びたい講座や講習会が、いつ、どこで行われているかなどに係る情報)
[2] 団体・サークル情報(どこに、どのような目的でどんな活動をしている団体があるのかなどに係る情報)
[3] 講師・指導者情報(どこに、どのようなことを指導できる人がいるのかなどに係る情報)
[4] 施設情報(どこに、どのような施設があり、その場所への交通機関は何かなどに係る情報)
[5] 図書情報(県立図書館等における蔵書の種類、貸出し及び返却に係る情報)
[6] 施設予約情報(公民館や体育館等の公共施設の予約状況に係る情報)
このようなシステムの活用より、生涯学習関係の情報が体系化され、学習を行おうとする市民等は講座・教室等の情報を得ることができ、学習意欲や参加意欲が高まるなど、地域社会の学習活動の推進及びより一層の市民サービスの向上につながっている。
今後は、一般家庭のパソコン等の端末からの自由なアクセスが可能となるなど、生涯学習に係る総合的なネットワークシステムの構築が望まれる。
ウ 医療・福祉分野
(ア)
保険・医療支援
高齢化社会における地域住民の健康づくりや健康意識の高揚等を目的として、医療情報を記憶したICカードを媒体として、保健医療カードシステムに登録された総合病院と病院や診療所、健康福祉総合センター等を結ぶシステムがテレトピア指定地域等で導入されている例がある。
このシステムを利用することにより、次のような効果がある。
[1] 医療機関は、ICカードを介して、すべての検査、投薬情報等を即座に知ることができ、診療に役立てることが可能となり、効率的な医療を迅速に患者に提供できる。
[2] ICカードには救急情報が入力されており、カード保有者が不慮の事故等に遭遇した場合、直ちに姓名、住所、年齢等身元が判明するとともに、特異体質の有無、既往歴等の入力情報により、迅速かつ有効な医療を受けることが可能である。
[3] 住民は、ICカードを保有することにより、自分の生涯の保健、医療情報を自分で所有することとなり、有効な医療を受けることができるという大きな安心感を持つことができる。
なお、個人のプライバシー保護対策としては、本人の申出による感染症等の病歴情報のICカードへの入力拒否が可能であり、さらに、患者の情報入手に際してはセキュリティカードを用いるなどのセキュリティの確保も配慮されている特長がある。
また、患者宅と病院や診療所、健康福祉総合センターを、双方向ケーブルテレビ伝送路を介して結び、医師は患者の訴えを直接聞き、看護婦や患者に適切な指示を与えるシステムの導入が検討されている。
患者から緊急連絡を受けた看護婦や保健婦は、携帯用カメラとマイクを持って患者宅を訪問し、患者の表情や外傷患部の映像、血圧、体温等の基礎データを伝送し、適切な処置方法についての指示を受けるものである。
これにより、短時間に患者の状態を把握し、適切な医療を施せるとともに、医療過疎問題の克服にもつながることが期待される。
(イ) 在宅福祉支援
高齢者を対象とした在宅福祉支援としては、微弱電波の利用により、痴呆による徘徊行動がある在宅老人に痴呆性老人徘徊感知機器(小型送信機)をつけ、老人が屋内受信機のループセンサーを通ると、即座に送信機が作動し、ランプと警報音で家族に外出を知らせるシステムの利用の例がある。
また、大分県大分市では、ひとり暮らしの老人向けに、在宅老人コミュニケーションシステムが構築されている(第1―3―40図参照)。屋内の電話機の本体やコードレスのペンダント型発信機には、緊急ボタンがついており、日常生活に合わせて使い分けが可能となっている。
急病や事故等の緊急事態が発生した場合、老人が緊急ボタンを押すと、老人ホームの緊急通報センターのパソコンシステムが作動し、まず、老人宅に自動的に電話がかかる。老人宅の応答がない場合は、パソコンに登録されている近隣のボランティアの連絡協力員に自動発信で電話がつながり、老人宅に様子を見にいってもらい、報告によっては、救急車や医師が手配されるなど、高齢化社会において、生活に根ざした情報化が進展している。
エ 交通分野
現代社会において、違法駐車や都市部における駐車場不足、慢性的な交通渋滞、交通事故の多発、都市環境の悪化等、車社会がもたらす弊害が問題となっている。このような交通社会において、交通渋滞、交通混雑、交通規則の実施等各種の道路交通情報に対して、標識や表示板、路側通信設備等の整備等により、情報収集及び情報提供に係るシステムの拡充、高度化が推進されており、一般道路利用者に対して迅速かつ的確な道路交通情報が提供されている。例えば、既存の民間駐車場等を含めた駐車場の効率的な利用を体系的に図ることなどを目的として、愛知県豊田市では、都心に向かう市内主要道路沿いに設置された案内板に、駐車場の位置や満車・空車・閉鎖等の利用状況とともに、駐車場に至る道路の渋滞状況が表示されている。また、漏洩同軸ケーブルを使った路側通信やテレホンサービスによる道路情報も併せて提供されており、違法な路上駐車の抑止や空き駐車場探しの徘徊車両の削減、ドライバーに対する駐車意識の啓発等につながっている。
オ その他の分野
佐賀県伊万里市では、田や畑に出て働く留守がちな家庭向けに、プリンタを内蔵した安価な端末と電話回線との組み合わせによる電子メールサービスと自動遠隔検針等のサービスからなるテレメータVANが利用されている例がある。
電子メールサービスの利用は、緊急を要する連絡時に効果があり、農業協同組合や市役所からの連絡用として利用されているほかに、住民の声を直接聞くことができるアンケートにも盛んに利用されている。
また、テレメータVANにより、水道とガスにおいて自動遠隔検針サービスも行われており、市の水道局とガス会社からのリモコン操作で検針されている。例えば、ガス漏れの場合は、センサーが感知しガスの供給をストップし、同時にガス会社からその家庭に連絡をとり、状況を確認するようになっている。
地域社会における情報化は、各々の地域が主体となり、ビデオテックスやパソコン、多機能電話等メディアのもつ特性を生かしながら、最適な情報通信システムの構築や普及が進められている。
また、最近の動向としては、双方向機能を有するケーブルテレビの導入が顕著であり、新しいメディアとしてのオフトーク通信の導入も進められているなど、ニューメディアの定着やその特性を生かした活用の普及発展が期待される状況にある。
今後は、様々な通信・放送メディア等を利用することにより、豊かでゆとりある生活の実現、地域社会の振興、医療・福祉の向上等が図られるような情報化の進展が必要であると考えられる。
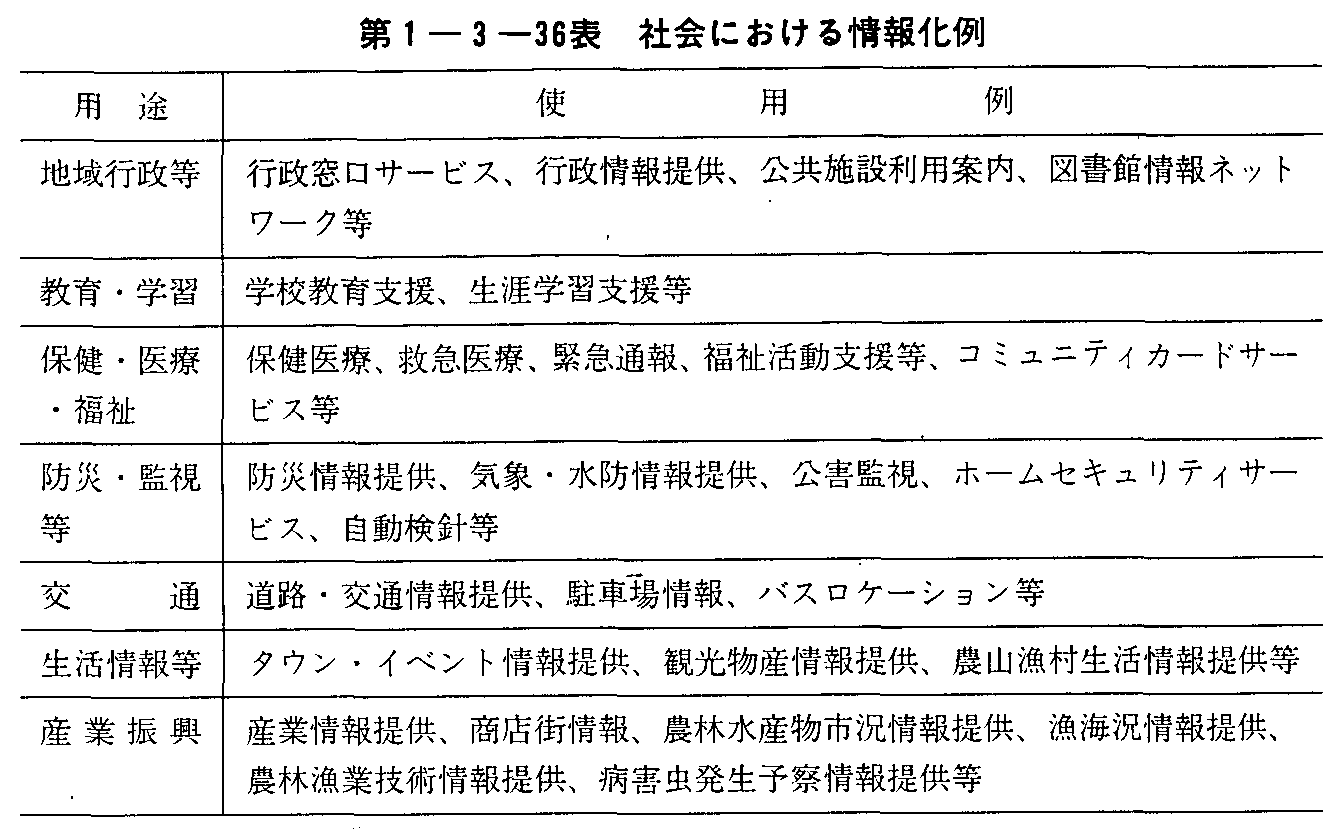
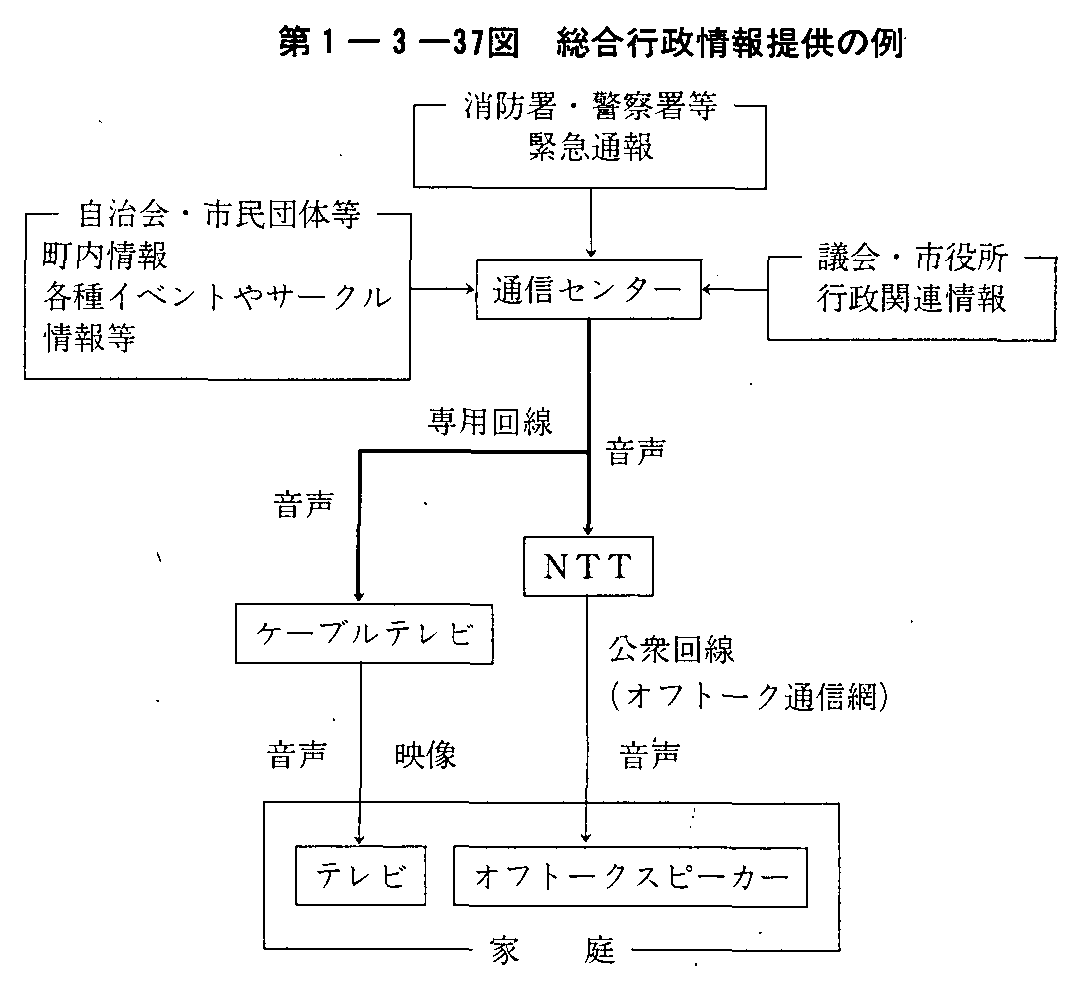
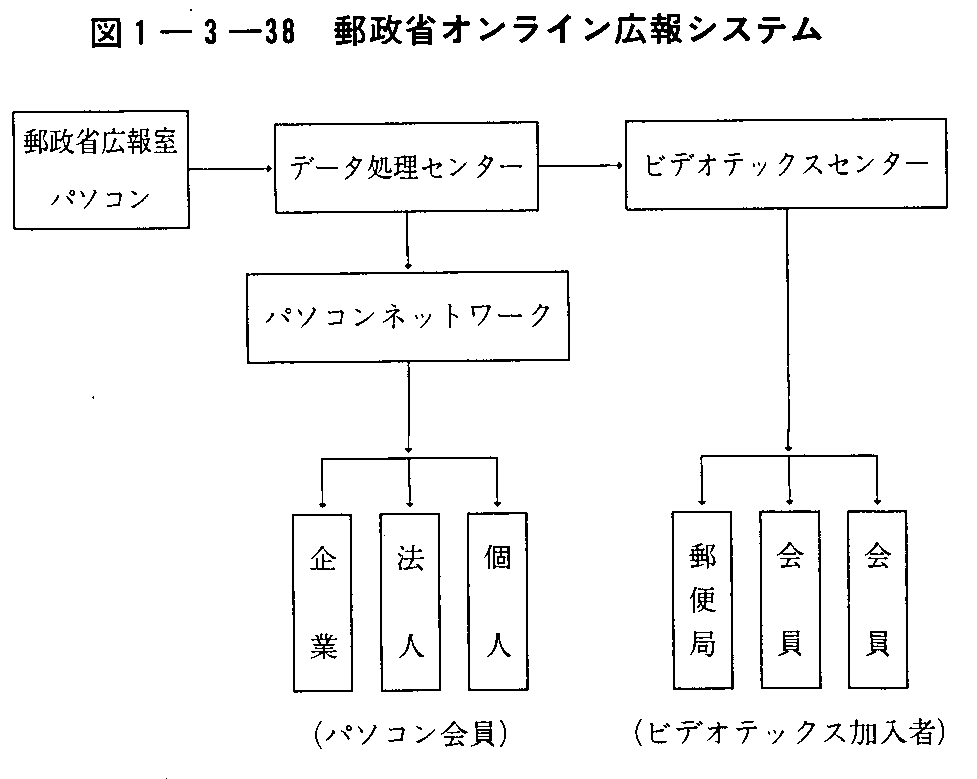
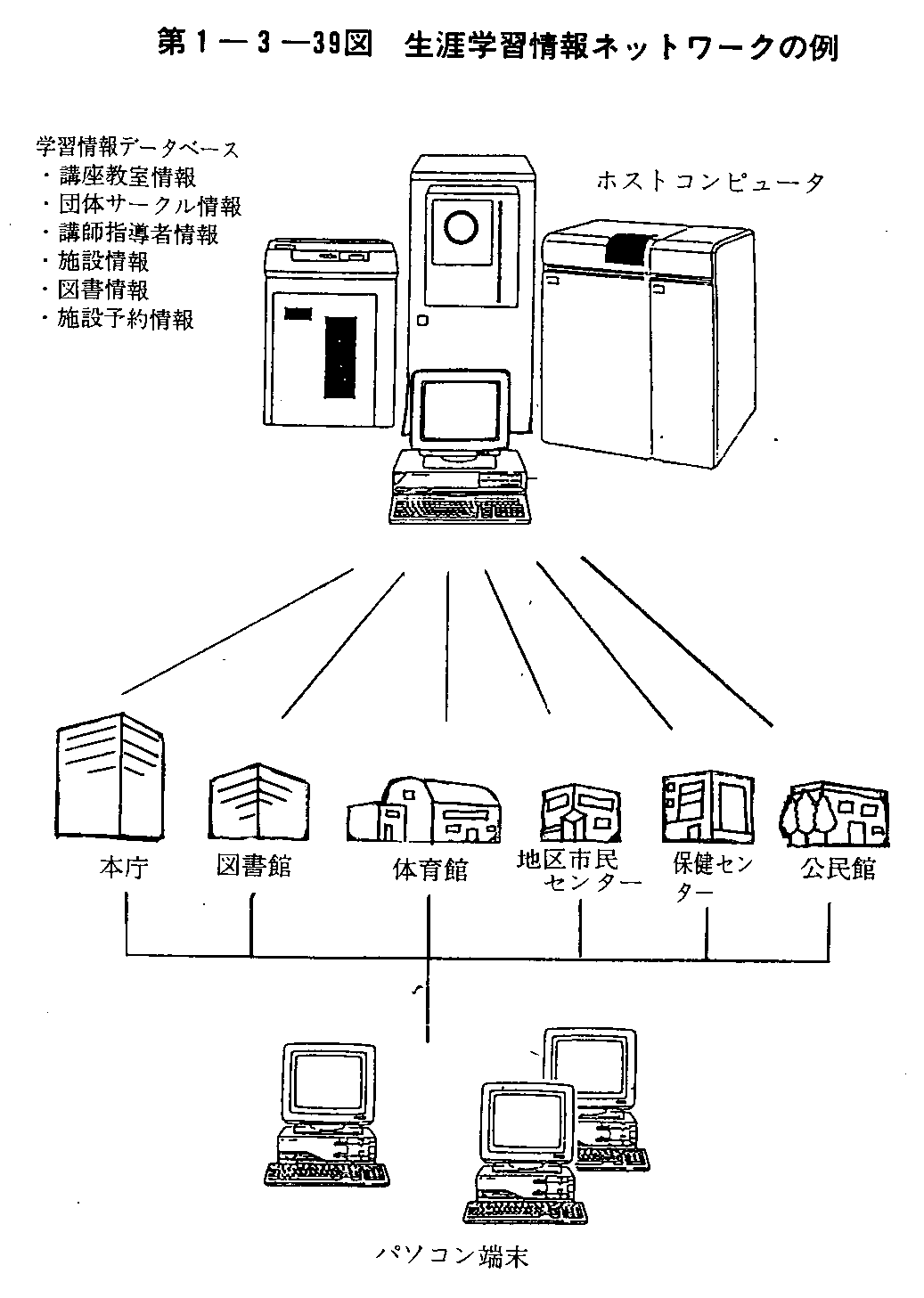
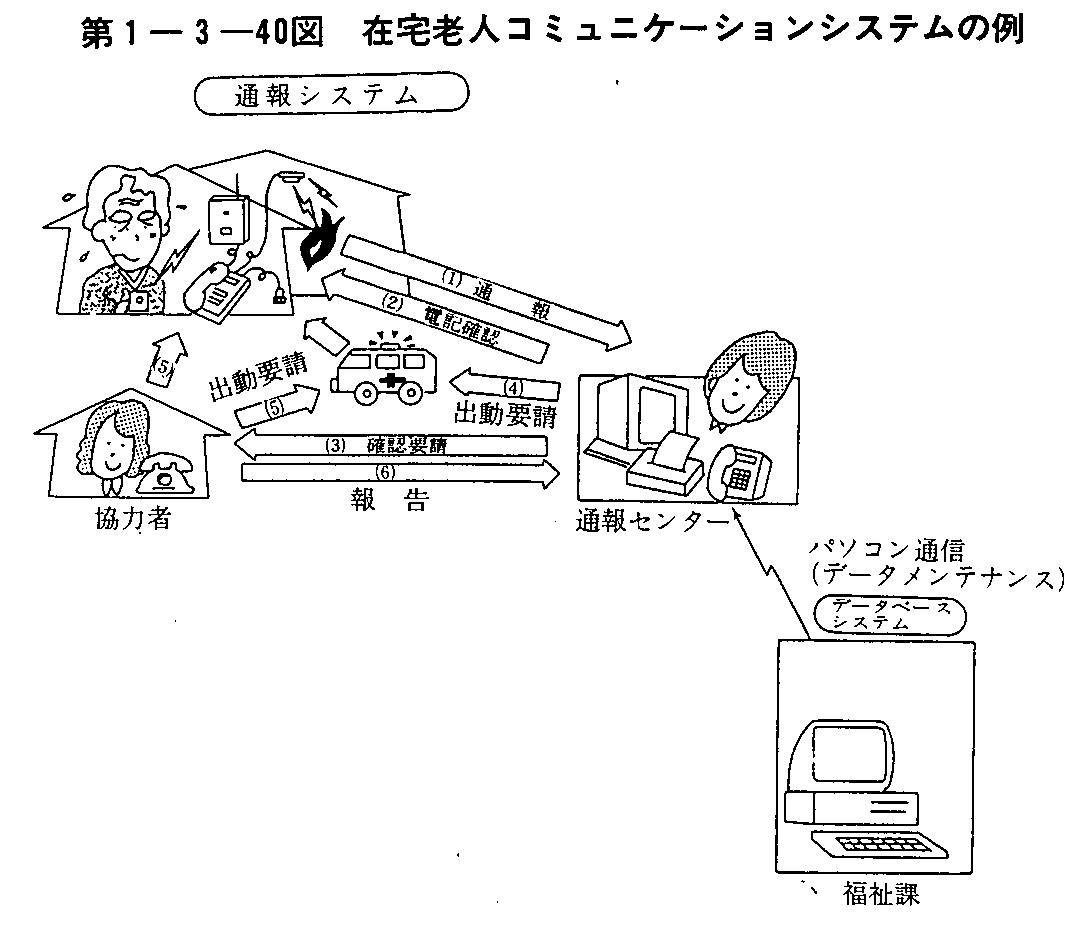

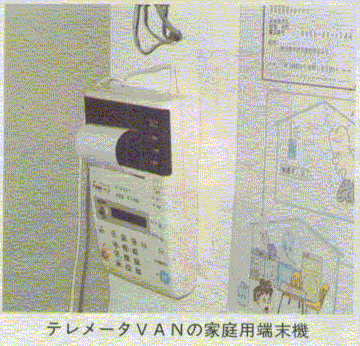
|