 第1節 情報通信サービスの動向  第2節 情報通信経済の動向
 2 情報通信経済の状況
 1 情報流通の動向  2 情報化の進展状況
 第1節 情報通信政策の展開
 3 情報通信による豊かさとゆとりのある生活環境の整備  4 情報通信による環境問題への対応  5 情報通信による国上の均衡ある発展  6 地域情報化の推進  7 電気通信産業振興のための環境整備
 第2節 電気通信の健全な発展
 1 電気通信事業政策の着実な推進  2 電波利用の促進
 第3節 放送政策の新たな展開
 1 放送メディアの多様化に向けて  2 放送ソフトの充実のために  3 放送の利用格差の是正に向けて
 第4節 郵便事業・郵便局ネットワークの新たな展開
 1 郵便事業運営基盤の整備・充実  2 豊かな暮らしづくりに向けた郵便サービスの提供
 第5節 情報通信に関する国際政策の充実
 2 国際協力の推進
 第6節 技術開発・標準化の一層の推進
 1 次世代を支える技術開発の促進  2 重要性を増す標準化の推進
 第1節 映像メディアの発展と現代社会
 1 映像系情報通信の利用動向  2 映像市場等の動向
 1 総合的な政策の推進  2 情報通信インフラ整備の推進  5 利用機会均等化等の推進  6 環境及び生活環境への貢献  8 技術開発の推進
 第4節 映像新時代の発展とマルチメディアの推進
 1 今後の展望  2 21世紀に向けた課題
|
第3章 映像新時代を迎える情報通信
(3) 社会(公共分野・文化)における利用動向
教育や医療、防災、監視、美術館・博物館等様々な分野において、積極的に映像情報を活用して、生活サービスの向上や地域社会の振興、医療・福祉等の向上等が図られている。
以下に、各分野における主な映像利用の事例をもとに、社会における映像の利用動向について概観する(第3―2―7表参照)。
ア 教育分野
生涯学習の時代に即応し、放送等を効果的に活用した新しい教育システムの大学教育を推進することにより、レベルの高い、教育・学習の機会を広く国民に提供することを目的とする放送大学が昭和58年4月に設置された。昭和60年4月から学生の受入れ及び放送授業を開始しており、4年度第2学期現在、約4万 3,000人の学生が学んでいる。
放送大学は、東京タワー及び群馬県域送信所から送信された電波の届く関東地域においてテレビ・ラジオによる放送を行っており、また、長野県諏訪地区及び山梨県甲府地区等関東近郊においては、ケーブルテレビによる同時再送信放送が行われている。さらに、学生の学習の場として、関東地域の7か所、甲府及び諏訪の2か所に学習センターが設置されており、ビデオテープやオーディオテープで番組を再視聴することができるようになっている。
また、放送電波の届かない地域に対しては、ビデオ学習センターを設置(4年度末現在14か所)し、放送授業に使用されているビデオテープ及びオーディオテープを利用し、広く社会人等に大学教育の機会を提供している。
イ 医療・福祉分野
(ア)
立体ハイビジョンの利用
社団法人ハイビジョン推進協会は、5年2月に開催された日本眼科手術学会において、眼内手術の模様をハイビジョンを利用して立体に映し出す、立体ハイビジョンによる生中継を世界で初めて実施した(第3―2―8図参照)。これは、病院において行われる眼内の硝子体手術の模様を、手術顕微鏡に取り付けた2台のハイビジョンカメラで撮影し、光ファイバーケーブル2回線を使って 600Mb/s で学会会場にデジタル伝送し、 220インチのハイビジョンスクリーンに立体で映し出したものである。
ハイビジョンは、従来のテレビの5倍の情報量を持ち、鮮明な画像が得られることから医療の現場や学会等でも注目を集めているが、それを一歩進めて立体で映し出すことにより、二次元映像では表現できない、眼内の病的組織、眼底の血管に富んだ網膜上の増殖膜の切除の様子や硝子体と網膜の立体的位置関係、眼球内での器具操作の立体的位置関係等を明確に伝えることを可能とした。
学会会場では、手術現場から送られてくる立体ハイビジョンによるリアルな映像に加え、手術の状況解説や会場との質疑応答をおりまぜることにより、より多くの情報を提供することが可能となり、効果的な勉強の機会が提供された。
このように、鮮明で高精細なハイビジョンを利用して、最先端手術の模様を光ファイバーケーブルや通信衛星を介して伝送する例が複数みられ、立体ハイビジョンの医療分野での活用効果とそれをリアルタイムで結ぶ情報通信ネットワークの有効性が注目されている。
(イ)
病理診断支援システム
宮城県では、国立大学附属病院と病理医が不在の市立病院間で、顕微鏡標本を、光ファイバーケーブルを介して伝送し、種々の病理診断支援が実験的に行われている。
この実験では、全自動顕微鏡にのせた顕微鏡標本が、病院間を結ぶ光ファイバーケーブルにより市立病院から送信され、受信側病院のハイビジョンモニターに映し出される。遠隔操作装置を使用することにより、顕微鏡の倍率の変更、標本の移動が可能となり、両病院の医師は、同じ標本をモニターで見ながらテレビ電話を通じて病理診断支援を瞬時に行うことができる。遠隔地にいながら病理診断支援を行うことができるため、病理医の派遣が不要となるほか、診断の即時性及び同時性が得られるとともに、顕微鏡画像をハイビジョンモニターで見ることができるため、目の疲れが少なく、大人数で映像情報の共有化が図れるなどの効果がある。
このように、医療映像情報は、映像の中でも特に高度の解像度及び階調を要求される情報であることからも、今後ますます高精細で、臨場感に満ちたハイビジョン映像が医療映像データとして活用される可能性は極めて高いものと考えられる。
ウ 監視分野
郵政省では、地球環境モニタリングシステムの実現に向けて、航空機搭載の高分解能・三次元マイクロ波映像レーダの開発を行っている。これは、森林破壊や砂漠化、海洋汚染、地球温暖化等の地球環境問題及び火山噴火や地震、洪水等の自然災害への迅速かつ機動的な対処を行うとともに、その影響の大きさや広がり、それによる環境の変化を効果的に予測することを目的とするものである。
本システムでは、平面的な映像しか得られない従来の映像レーダとは異なり、地表面の高分解能映像を三次元立体映像で得られるため、海洋油汚染や海流・海洋波浪の観測、海水分布、氷河の消長、森林破壊、砂漠化の進行、火山噴火等の様々な地球環境状況を監視することが可能となる。
エ 防災・防犯分野
(ア)
防災システム
地震や台風、火災等の自然災害及び人為的災害が発生した際には、正確な災害状況把握、応急対策や避難誘導の検討や迅速な意思決定が必要となることから、防災分野においても映像情報を利用したシステムによる対応が図られている例がある。
東京都においては、[1]データ端末や電話、ファクシミリ等の端末から、公衆回線を介して防災センターに送信された各区市町村の災害情報と、[2]消防ヘリコプターや警視庁ヘリコプター、警視庁飛行船等に搭載されたカラービデオカメラで撮影された映像情報及び[3]都庁ビルの屋上に設置されたパノラマカメラで撮影された映像情報をもとに、人的被害、建物被害、避難状況等の項目ごとに災害・被害情報を集計し、大型スクリーンや地図表示盤、状況表示盤にリアルタイムで表示している(第3―2―9図参照)。
また、災害情報のみならず、火災時の延焼予測や降雨量・浸水被害予測にも映像情報が活用されるなど、映像情報が的確かつ迅速な災害対策の検討及び意思決定に有効に利用されている。
(イ)
防犯・安全システム
防犯分野においては、派出所に管轄警察署と直接対話できるテレビ電話を設置し、パトロール等で派出所員が不在の場合でも、管轄警察署が来訪者に対応できるシステムの導入が進められている。このシステムで代表的なものにおいては、マイクとビデオカメラを組み込んだテレビ電話が派出所内に設置され、派出所と管轄警察署が電話回線で結ばれている。来訪者が無人の派出所を訪れるとセンサーが作動し、派出所の画面には管轄警察署の担当署員の顔が、また、管轄署の画面には来訪者等の派出所内の様子が自動的に映し出され、相互対話ができる。また、テレビ電話には、緊急出動要請用の「非常ボタン」も備えられ、ボタンを押すと、テレビ電話に備えられたビデオカメラが動き、警察官が駆けつけるまでに派出所内で起きたことがすべて録画される。
このように、テレビ電話システムにより、派出所勤務員が不在の時間帯がカバーされ、事件発生時の即応体制の強化につながる効果が期待されるところである。
オ 芸術・文化分野
(ア)
放送ライブラリー
放送法による指定を受けた財団法人放送番組センターは、3年10月に横浜市のみなとみらい21横浜館に、放送ライブラリーを開設して、同センターに保存されている放送番組を一般公開している。放送ライブラリーでは、我が国の放送の向上を目指すとともに、貴重な文化財としての放送番組を収集、保存、公開することを目的として、芸術作品賞など国内外18賞の受賞番組、テレビ放送開始の昭和28年から現在までに国内で制作・放送された各年の代表的な番組が保存、公開されている。
同ライブラリーでは、1人用、2人用、3人用の計30台の視聴ブースで、同時に約60人が視聴できるほか、 170インチのスクリーンを備えた映像ホールで収集・保存した番組や資料を活用した公開セミナー等が開催されている。
今後は、放送番組の各種資料や放送日、内容、反響等の情報を収集してデータベース化し、それらを様々な項目から検索、利用できるシステムを構築することが検討されている。
(イ)
ハイビジョンギャラリー
ハイビジョン・シティモデル都市等では、ハイビジョンの高精細な映像と臨場感を活用して、美術館の所蔵品や国内外美術館作品を映像データベース化するとともに、来館者が自由に収録番組を選択、鑑賞できるハイビジョンギャラリーを設置している美術館がある。館内のブースにおいて、利用者は国内外作家、作品種別、製作年代等の項目で作品の画像及び文字情報をデータベースにより検索でき、さらに、検索結果をハイビジョンギャラリーの大画面に映し出し、多人数で鑑賞できる例もみられる。
また、美術館のほかに、博物館や図書館、生涯学習センター等全国約40の施設で、ハイビジョンによる美術鑑賞システムが導入されており、美術に親しみ、楽しめる機会の拡大が図られている。
カ 行政事務分野等
行政事務分野等における映像利用の例として、郵政省による通信衛星を利用した郵便局衛星通信ネットワーク(P-SAT)がある。衛星通信の即時性・広域性・広帯域性等の特徴を活用して、映像により地域の特産物・地場産業・観光情報等全国各地のふるさと情報、最新の経済・生活情報、郵便局の商品・サービス情報等を郵便局のモニターで提供するとともに、職員向けの情報連絡や各種業務講習会・訓練研修・会議の内容を会議室のモニターにより伝送している。
また、郵政省は、本省と郵政局相互間(全国13地点間)で適時適切な効率的な会議等を行うとともに、環境にやさしい情報通信基盤の充実策の一環として、5年度におけるテレビ会議システムの導入を積極的に推進している。
以上のように、社会の様々な分野において、近年、テレビ電話や双方向機能を有するケーブルテレビ、ハイビジョン等のニューメディアが導入され、光ファイバーケーブル等を利用した高度な映像系情報通信が可能となっている。
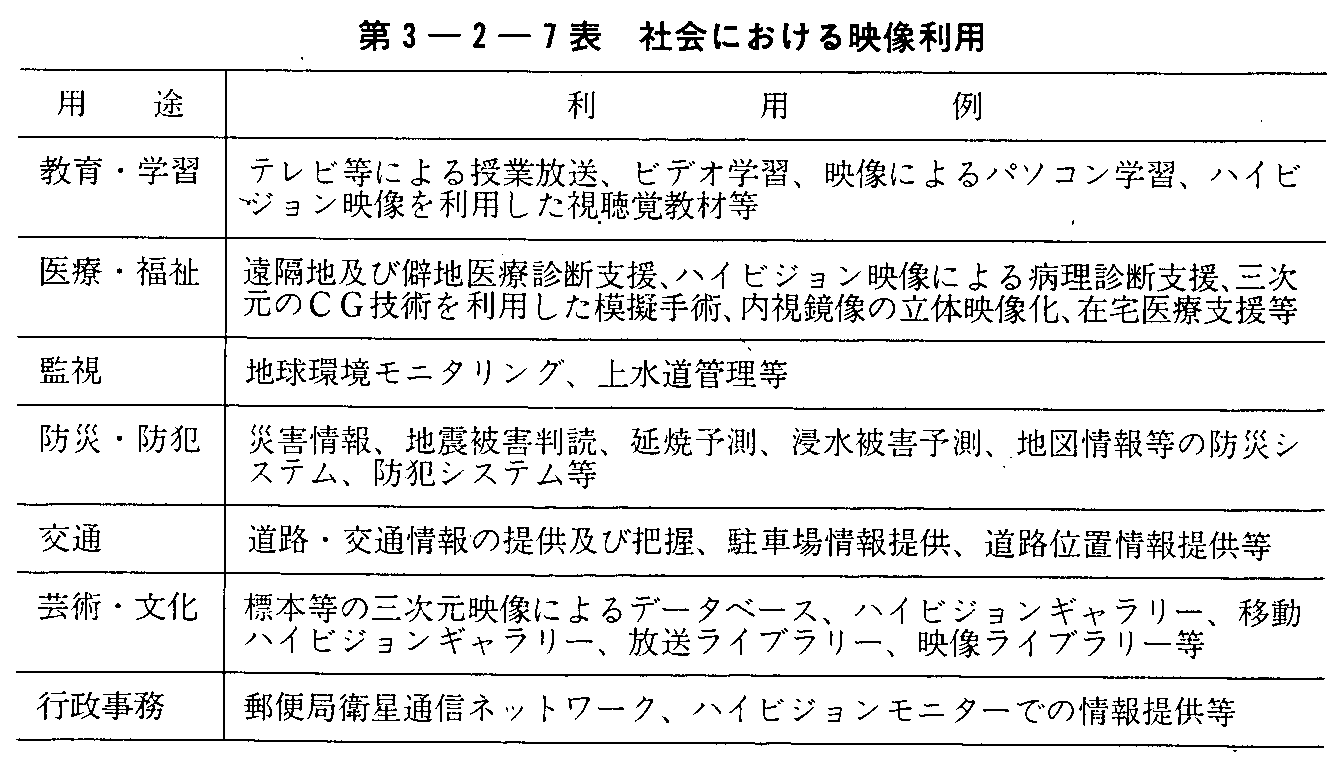
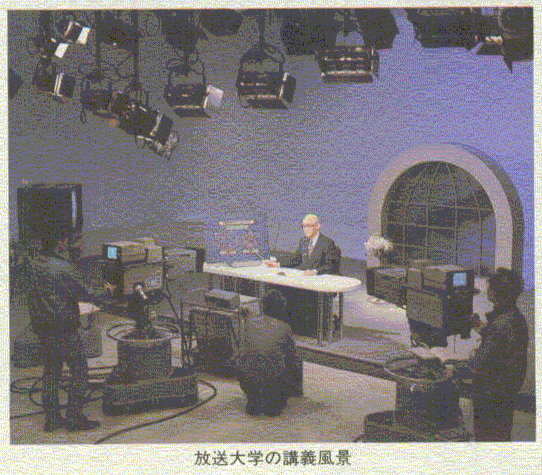
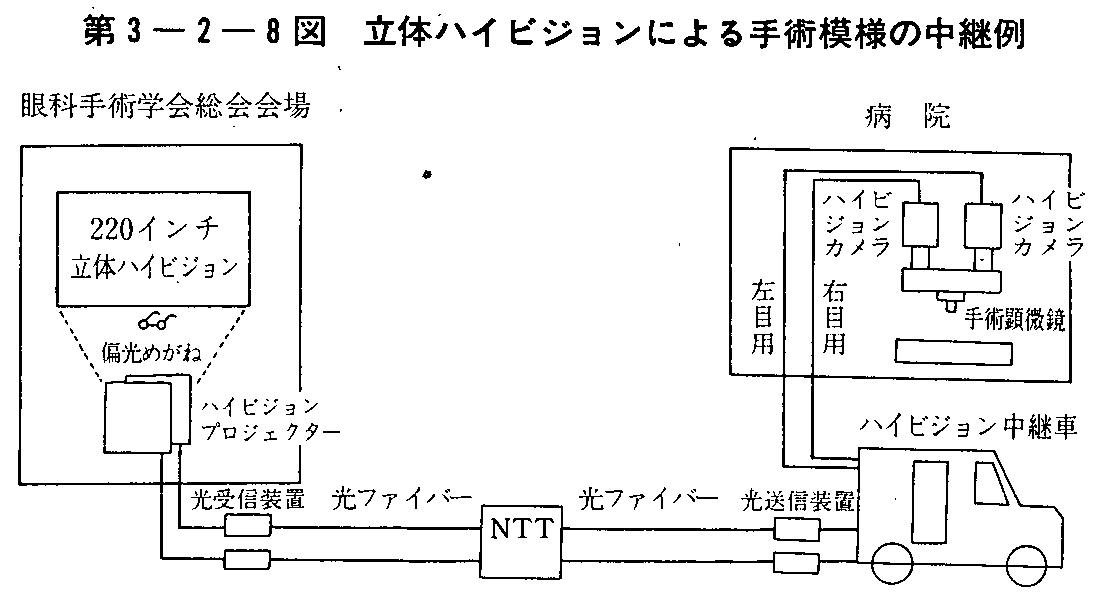
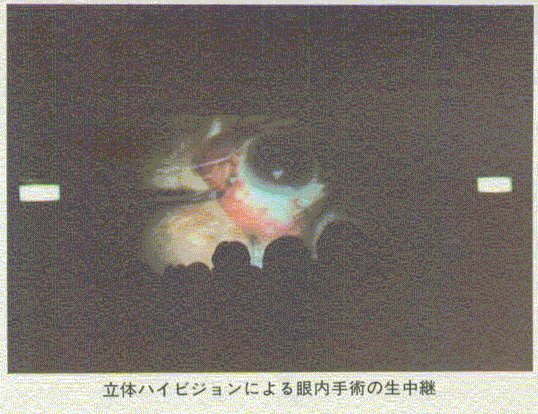
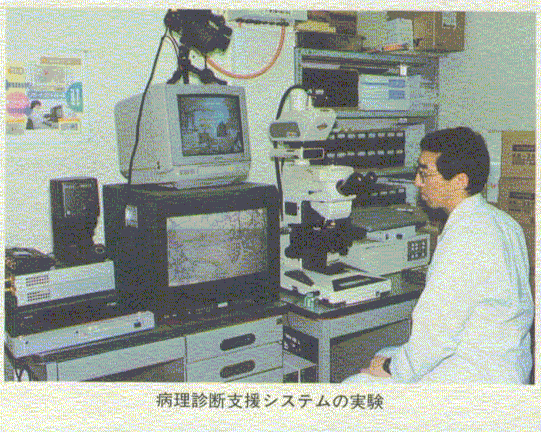
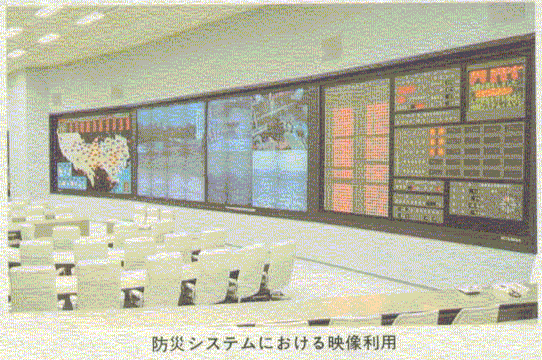
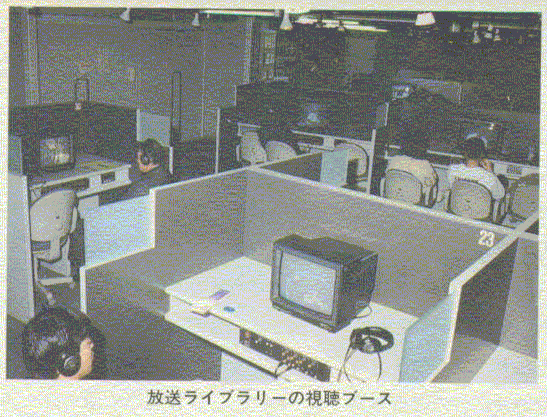

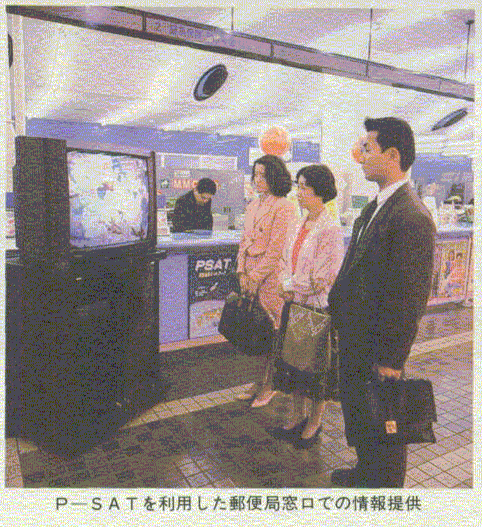
|