注記
(注1)
オープンネットワーク協議会は、NTTネットワークの網機能・網情報に対する第二種電気通信事業者の意見をNTTのネットワーク構築に反映することを目的に、3年7月に設立された。
(注2)
SPC(StoredProgramControl)は、デジタル交換機で採用される制御である。交換動作に必要な手順や方法が記述されたソフトウェアやデータをあらかじめ記憶装置に入れておき、このプログラムを1ステップづつ読み出して交換処理を行う方式である。
(注3)
地域とは、国際電気通信サービスの料金区分上の区分けであり、国又は州等の地域を指す。例えば、米国とは米国本土を指し、アラスカ、ハワイ等とは区分している。
(注4)
複数役務の届出会社があるため、合計は会社数を超える。
(注5)
都市型ケーブルテレビ事業者は、放送法に定める放送事業者ではない。
(注6)
郵政省の所管である通信産業における設備投資等の実態を把握するために、総務庁承認統計調査として年2回(現在は、3月と10月)実施しているものである。
(注7)
通信機械器具及び無線応用装置から無線通信機器(衛星通信装置含む)を除いたもの。
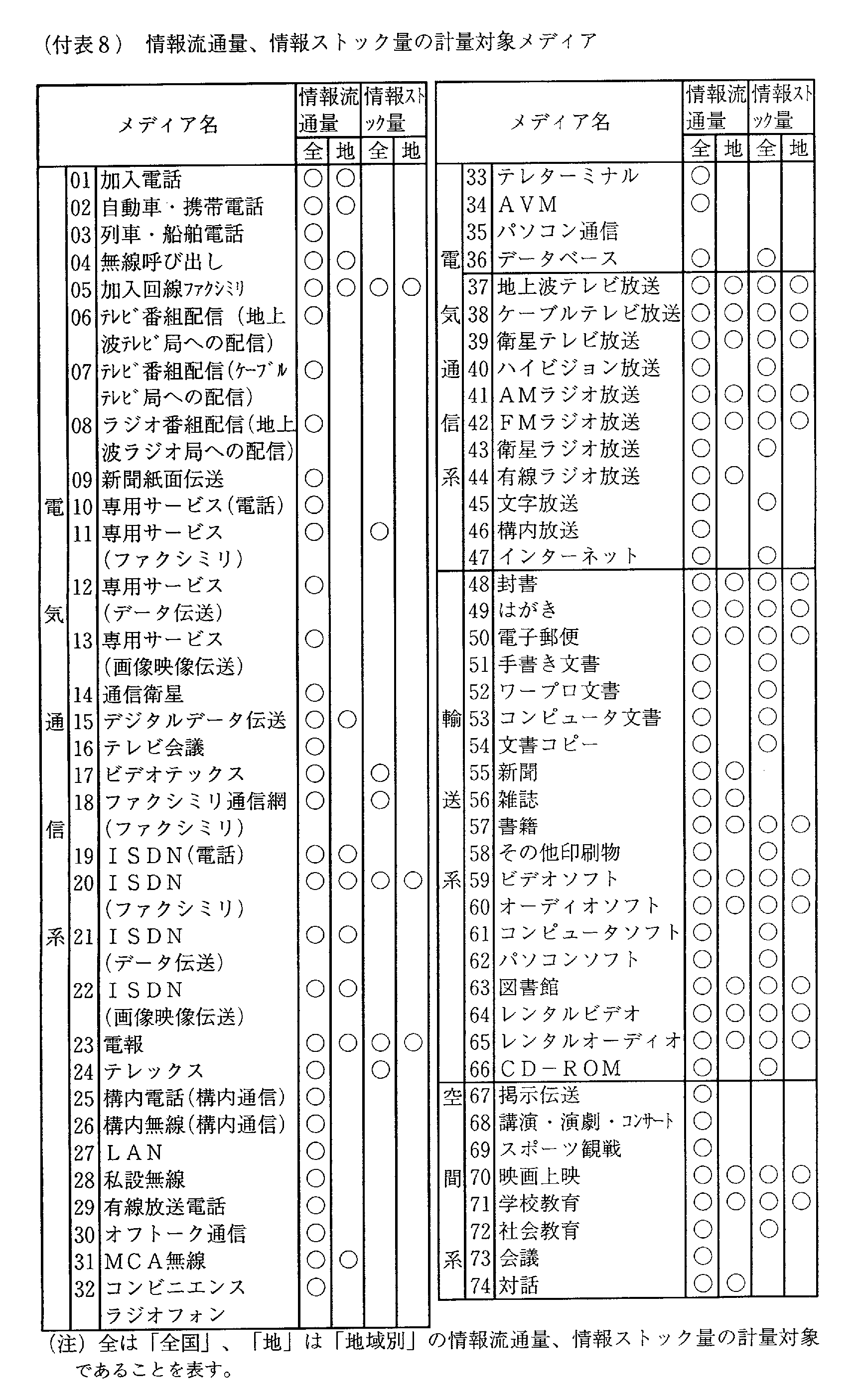
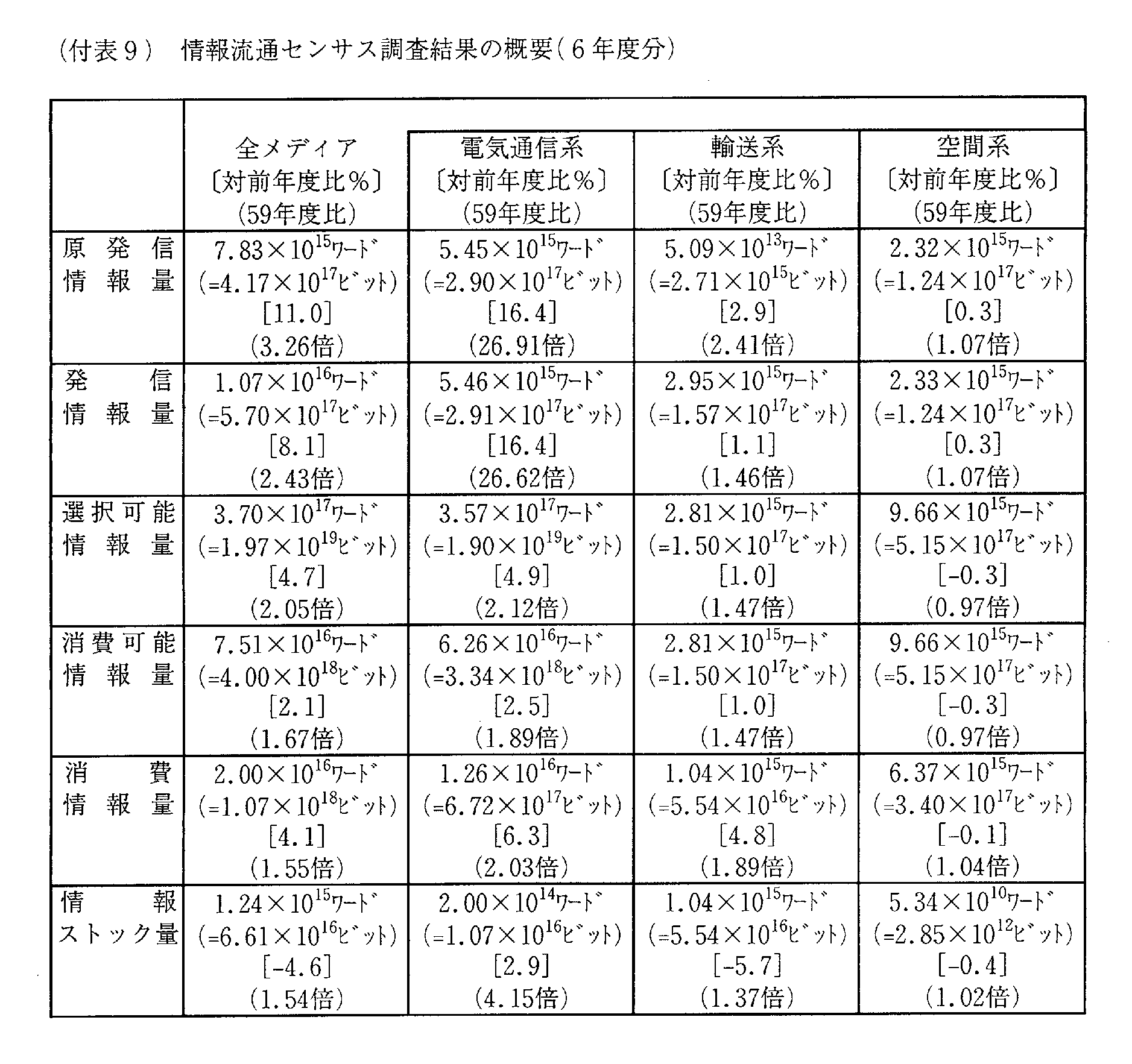
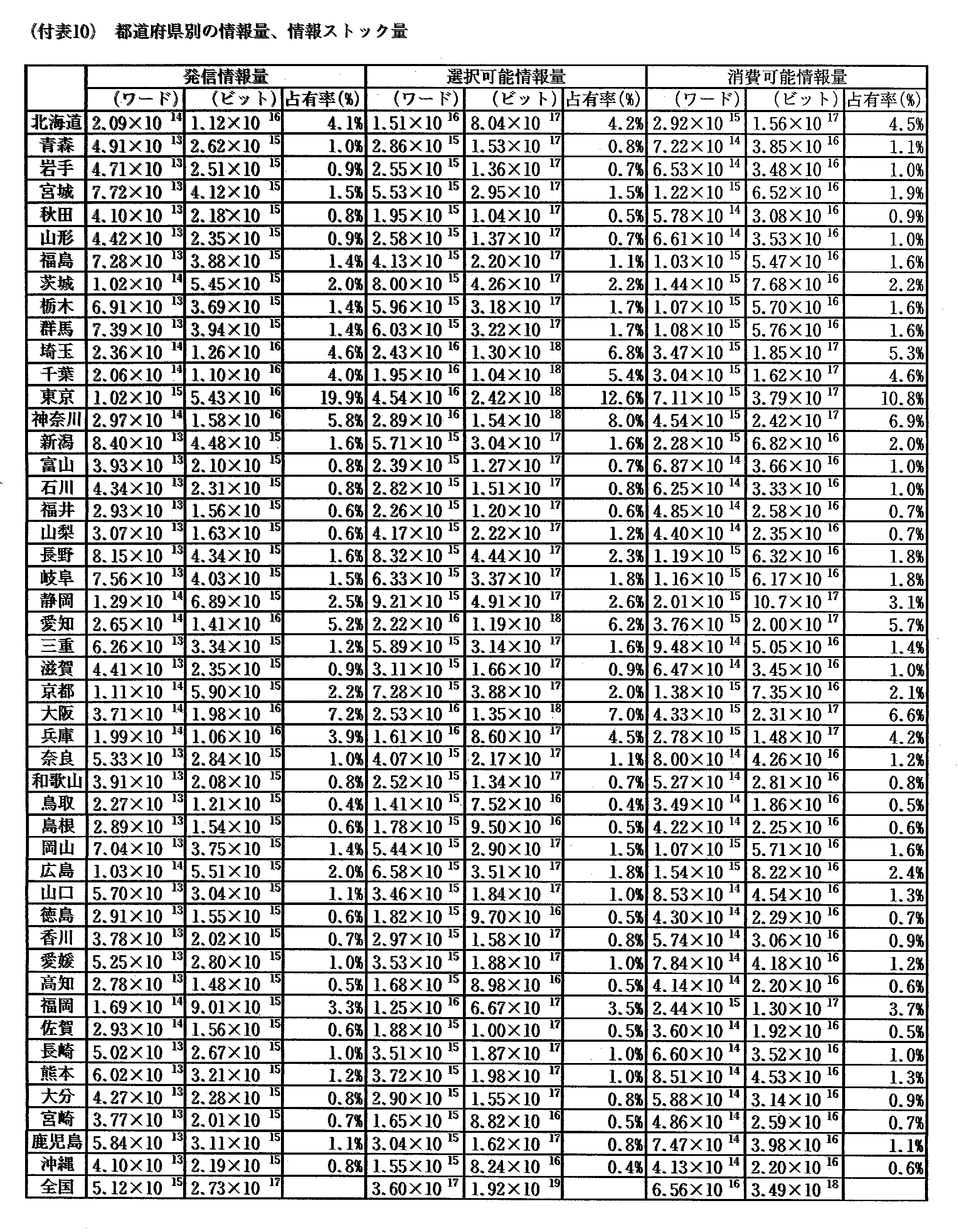
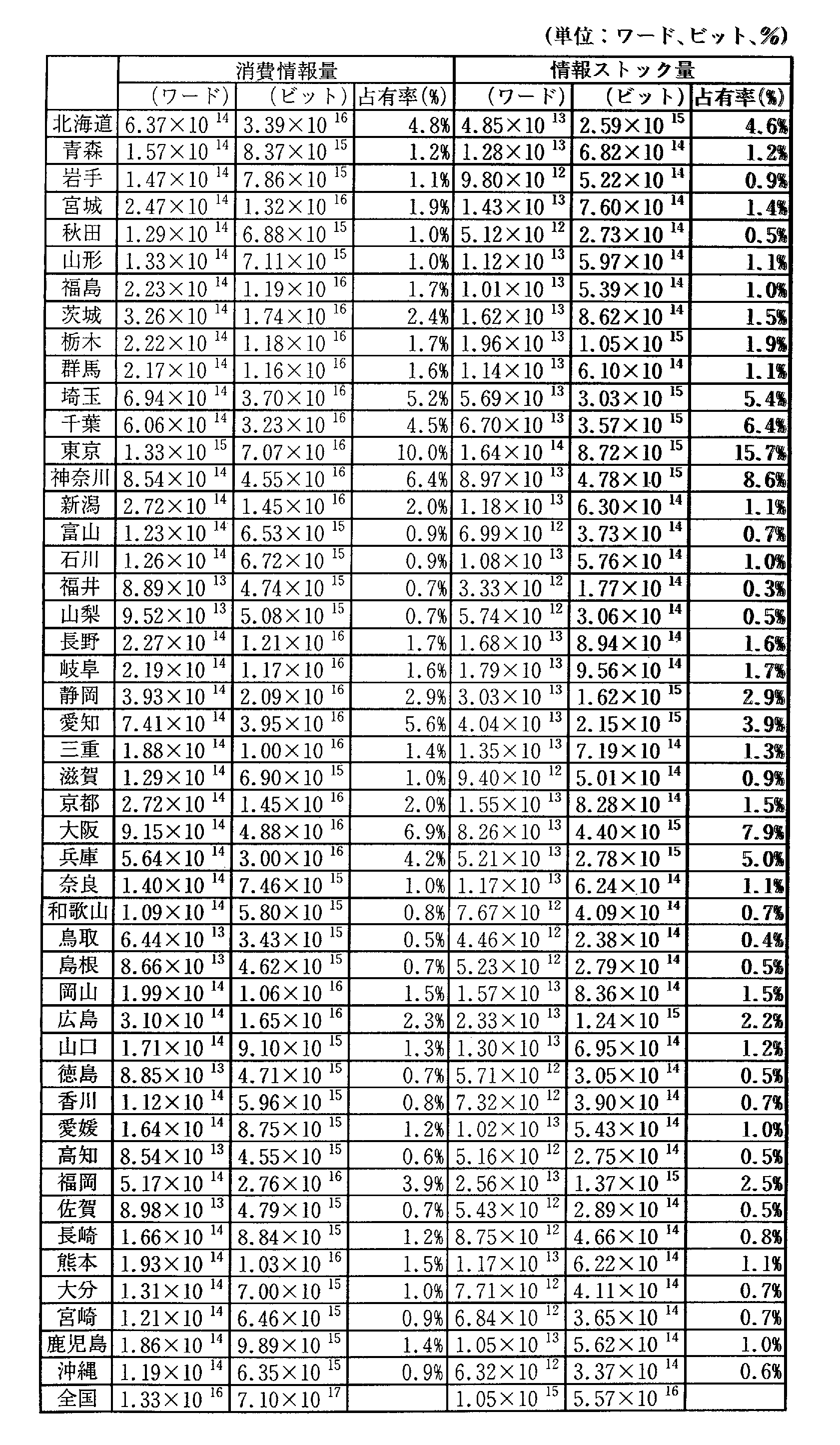
(注11)
変動係数とは、各量の標準偏差を平均値で割ったもので、データの散らばり具合を数値化するための指標である。この値が大きいほど地域間の格差が大きいことを表している。
(注12)
MA(単位料金区域)とは、「その地域の社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画を考慮して通話の交流上おおむね一体と認められる密接な関係にある地域からなるもの」(NTT電話サービス契約約款)であり、全国に567ある。同一MA内の通話は、距離にかかわらず、3分10円の最低通話料金が適用される。
(注13)
情報流通センサスでは、1ワードは、日本語における書き言葉(漢字かな混じり文)3.33文字に相当するとしている。日本語キャラクタは1文字2バイト(=16ビット)であるから、1ワード53.3ビット(=3.33×16)となり、これを使ってビットに換算した。
(注14)
我が国の家計、企業、公共部門の情報通信機器ストック(粗ストックベースの実質価格)は、各主体が保有する情報通信機器の各財ごとに大蔵省令の耐用年数を用いてPI法(恒久棚卸法)を使って計算した。なお、ここでいう情報通信機器は、事務用機械、電気音響機器、ラジオ・テレビ受信機・ビデオ機器、その他の電気音響機器部分品・付属品、電子計算機・同付属装置、有線電気通信機器、無線電気通信機器、その他の電子・通信機器部分品、磁器テープ・磁器ディスク、通信ケーブルである。
本年は、昨年が昭和60年価格基準での実質値を推計したのに対し、平成2年価格基準での実質値を、さらに推計の精度を高めて推計した。
【参考資料】総務省「産業連関表」
通商産業省「産業連関表(延長表)」
日本銀行「物価指数年報」
大蔵省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
郵政省資料
(注15)
我が国の家計部門の耐久消費財ストック(粗ストックベースの実質価格で、住宅は含まない。)は、「国民経済計算年報」の家計の形態別最終消費支出より耐久消費財への実質家計支出額(平成2年基準価格)をベースに推計を行った。推計に当たっては、郵政省資料による財構成比率と大蔵省令の財別耐用年数から算出した平均耐用年数を用いて、PI法(恒久棚卸法)を使ってストックを計算した。
【参考資料】経済企画庁「国民経済計算年報」
大蔵省令「減価償却の耐用年数等に関する省令」
総務庁「産業連関表」
通商産業省「産業連関表(延長表)」
郵政省資料
(注16)
我が国の企業部門の資本ストック(粗ストックベースの実質価格で、住宅は含まない。)は、「民間企業資本ストック年報」による全企業の進ちょくベースのストック額(平成2年基準価格)である。
【参考資料】経済企画庁「民間企業資本ストック年報」
(注17)
我が国の公共部門の資本ストック(粗ストックベースの実質価格で、住宅は含まない。)は、昭和45年の「国富調査」による有形固定資産をベンチマークとした。昭和44年以前の公共投資額は、「国富調査」記載の取得年次別構成比を使って正規分布近似簡略除却法から遡及推計した。昭和46年以降の公共部門の投資額は、「国民経済計算年報」による実質公共投資額(平成2年基準価格、公共住宅を除く)を使っている。公共部門の資本ストック額は、年後都の公共投資額を正規分布近似簡略除却法を使い、PI法(恒久棚卸法)により推計した。
【参考資料】経済企画庁「国民経済計算年報」、「昭和45年国富調査」
(注18)
米国の家計、企業、公共部門の情報通信機器ストック(粗ストックベースの実質価格)は、各主体が保有する情報通信機器の各財ごとに、大蔵省令の耐用年数を用いPI法(恒久棚卸法)を使って計算した。なお、ここでいう情報通信機器は、米国の産業連関表の85部門における、”Office,computing,and accounting machines”、”Radio,TV,and communication equipment”及び”Electronic components and accessaries”である。
【参考資料】米国商務省”Survey of Current Business”
U.S.ElectronicInduststriesAssociation ”ElectronicMarketDataBook”
通商産業省「1990年日本国際産業連関表(速報)」
米国労働省「消費者物価指数」、「卸売物価指数」
(注19)
米国のストック額を日本円に換算するに当たってはまず、米国の1987年基準価格のストック額を米国の卸売物価指数及び消費者物価指数を使って1990年基準に変換し、次いで1990年のOECDの購買力平価を用いて円に換算した。なお、各ストックごとに使った購買力平価は以下の通りである。
・家計部門の耐久消費財ストック
→家計所有耐久消費財の購買力平価:167円/ドル
・企業部門の資本ストック
→総資本形成の購買力平価:172円/ドル
・公共部門の資本ストック
→総資本形成の購買力平価:172円/ドル
・家計、企業及び公共部門の情報通信機器ストック
→電気機器の購買力平価:135円/ドル
【参考資料】OECD”PurchasingPowerParitiesRealExpenditures”(1990)
米国労働省「消費者物価指数」、「卸売物価指数」
(注20)
米国の家計部門の耐久消費財ストック(粗ストックベースの実質価格で、住宅は含まない。)は、下記資料の家計所有耐久消費財である。
【参考資料】米国商務省”Survey of Current Business”(August,1994)
(注21)
米国の企業部門の資本ストック(粗ストックベースの実質価格で、住宅は含まない。)は、下記資料記載の民間企業資本ストック(非住宅)である。
【参考資料】米国商務省”Survey of Current Business”(August,1994)
(注22)
米国の公共部門の資本ストック(粗ストックベースの実質価格で、住宅は含まない。)は、下記資料記載の政府所有固定資本ストックである。
【参考資料】米国商務省”Survey of Current Business”(August,1994)
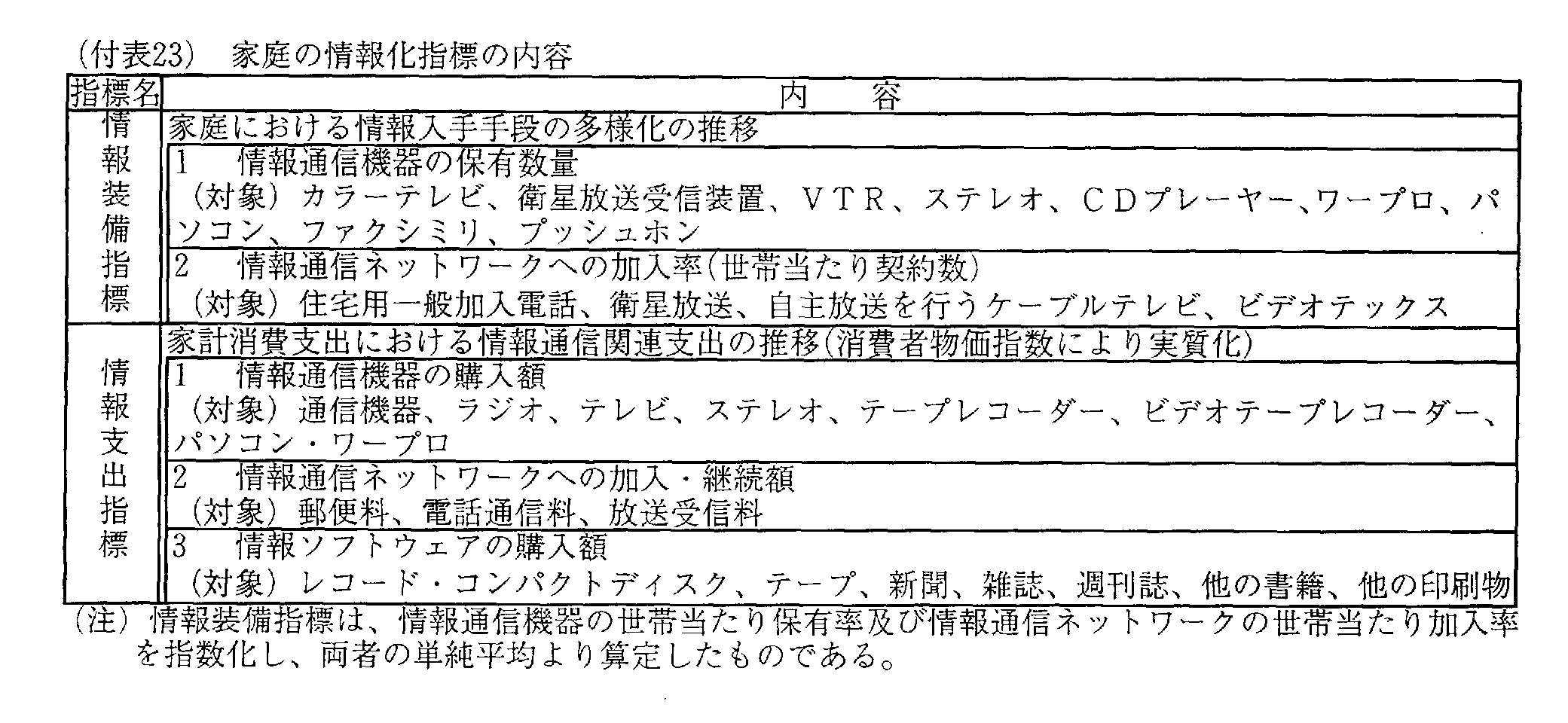
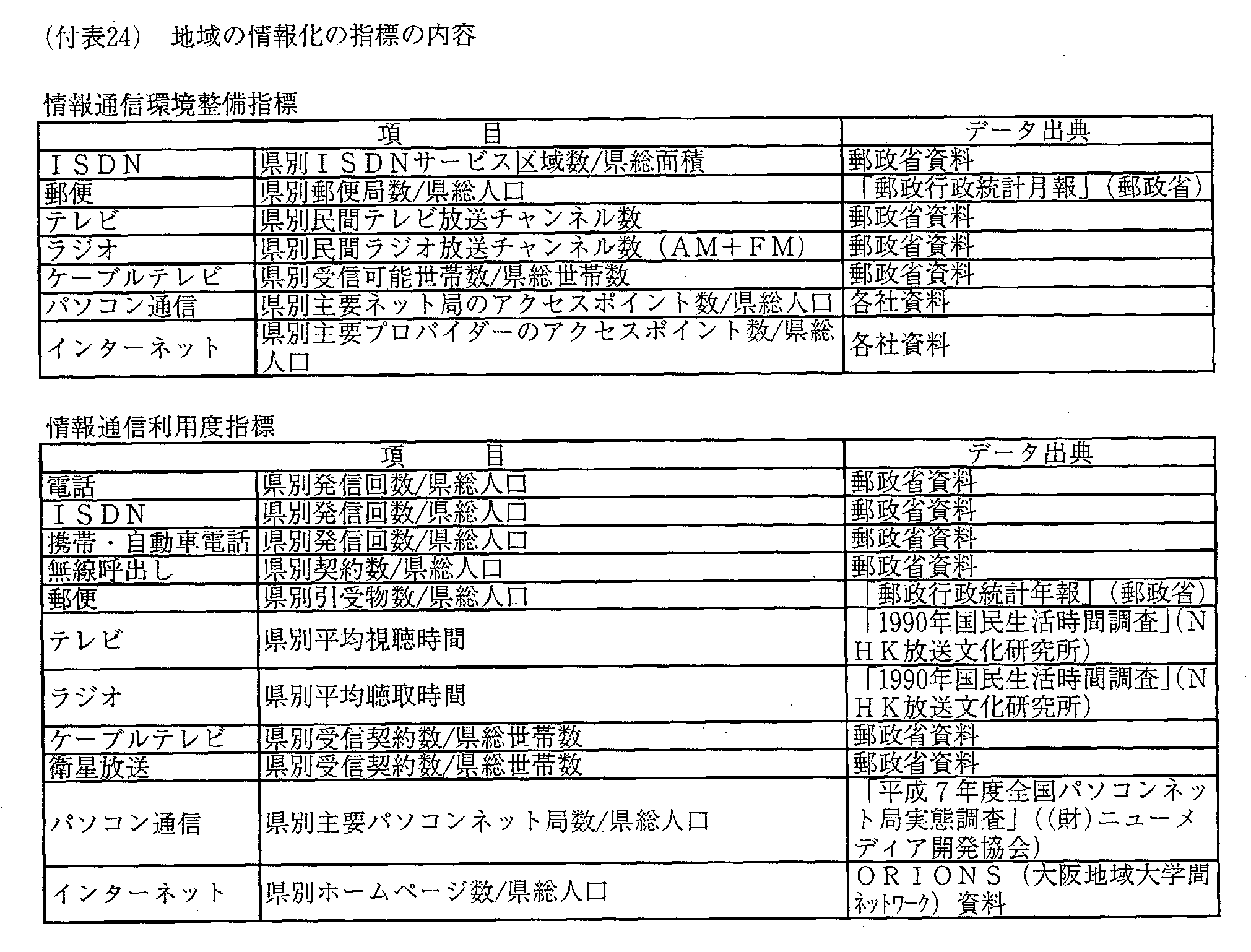
(注25)
本項目において、「(社福)盲人会」は「社会福祉法人日本盲人会連合」を、「(社福)日身連」は「社会福祉法人日本身体障害者団体連合会」を、「(財)聾亞連盟」は「(財)日本聾亞連盟」を、「(社)全難聴」は「(社)日本全難視聴者・中途失聴者団体連合会」をそれぞれ指し、「非特定」のデータは郵政省郵政研究所の「情報メディアの利用実態に関する調査報告書」(6年10月)である。
(注26)
郵政省郵政研究所が委託して行ったアンケートで、(社福)盲人会、(社福)日身連、(財)聾唖連盟、(社)全難聴の協力を得て、全国1都1道8県を対象に、6月12月中旬から7年1月中旬にかけて、各団体に所属する200名の障害者並びに盲人会及び日身連についてはその同居家族に対しても調査を行った。回収率は、障害者56.9%、家族43.3%である。
(注27)
ケーブルテレビ網を利用したPHSサービス
(注28)
米国NetworkWizards社の調査による(http://www.nw.com/)。
この統計のホスト・コンピュータ数はDNS(Domain Name System)を集計したものであり、インターネット・サービス・プロバイダ経由でダイヤルアップ接続されるコンピュータ等は含まれない。
(注29)
ホストコンピュータ1台当たりの利用者は、通例として用いられている10人という仮定を用いた。
(注30)
UUCP(Unix-toーUnix Copy)は、UNIXマシン間でファイルを転送するためのユーティリティの一種で、インターネットへの接続方法の一つとして用いられている。この接続ではインターネットの機能のうち電子メールとニュースのみが利用できる。
(注31)
IP接続は、インターネット接続方法の一つであり、この接続では電子メール、ニュース、ファイル転送(FTP)、リモート・ログイン、WWW等、インターネットのすべての機能を利用できる。
(注32)
WWW(World Wide Web)は1989年にスイスの歐州合同原子核研究機関(CERN)で開発されたハイパーテキストベースの概念に基づく分散型情報システムである。
(注33)
ドメインとは、ネットワークを人間の理解しやすいようにグループ分けした、一部のネットワークグループを指す。インターネットではドメイン全体を国別のドメインに分割して、それを利用主体別(企業、学術機関等)のドメインに分割し、さらに会社別のドメインに分割している。日本ではJPNICがドメイン名の割り当てを管理している。
(注34)
米国Net Genesis社の調査による(http://www.netgen.com/info/groth.html/)。
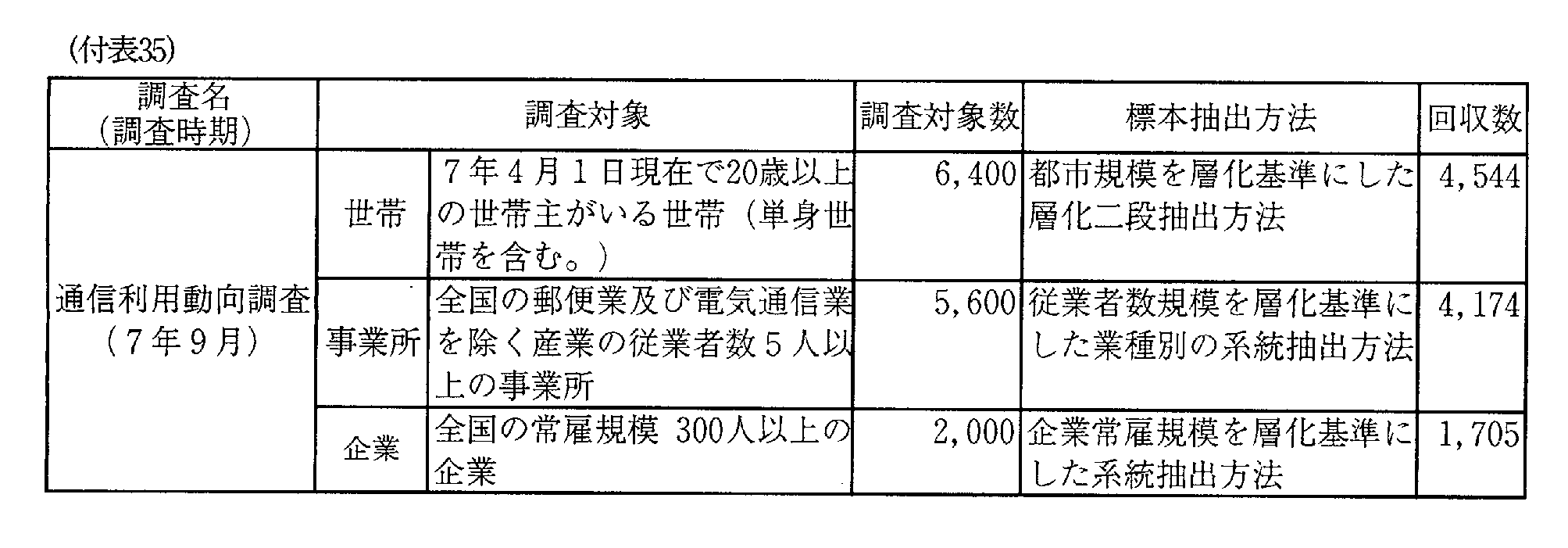
(注36)
1982年修正同意審決により、1984年に旧AT&Tは、長距離及び国際通信を提供するAT&Tと地域通信を提供する7社のRHC(地域持株会社:アメリテック、ベル・アトランティック、ベル・サウス、ナイネックス、パシフィック・テレシス、SBCコミュニケーションズ及びUSウエスト)に分離・分割されている。
(注37)
ここでは、米国、カナダ、メキシコ、チリ及び日本を除くAPEC加盟国及びインド。
(注38)
AT&T・GTE・アメリテック・USウエスト:1994.12現在のデータ、C&W・BT・NTT・KDD:1994.3現在のデータ、ベル・アトランティック・SBCコミュニケーションズ:1995.12現在のデータ
(注39)
BOTとは、外国の民間企業も参画して設立されたプロジェクト実施会社が、施設を建設し、その設備を一定期間運営して、その間の収益により資本投下のを回収し、一定期間経過後は、施設を当該国の国営事業体等に譲渡する方式である。BTOは、当該施設の運用時期と譲渡時期が逆になる。これらの方式には、導入国にとって、巨費を要する施設の建設に外資を含めた民間の資金を活用できること、外国企業の進んだ技術や経営方法が吸収できることなどの利点が、また外国の事業者にとっても料金収入から利益を得ることができるなどの利点がある。しかし、BOTにより十分な外資を導入するためには、商法等の関連法の整備等の環境整備が不可欠である。
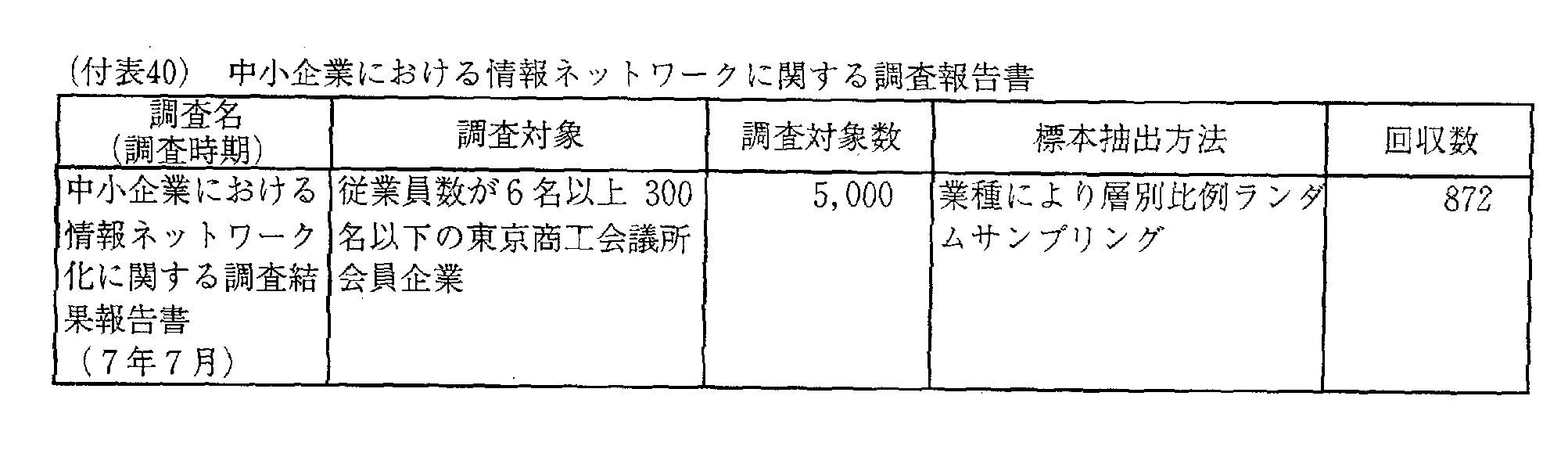
(注41)
CALSの語自体は、統一的な定義はなく、その概念も除々に拡大してきており、特に近年では、「Continuous Acquisition and Life-cycle Support」から、「Commerce At Light Speed]の略語として用いられることが一般的となっている。
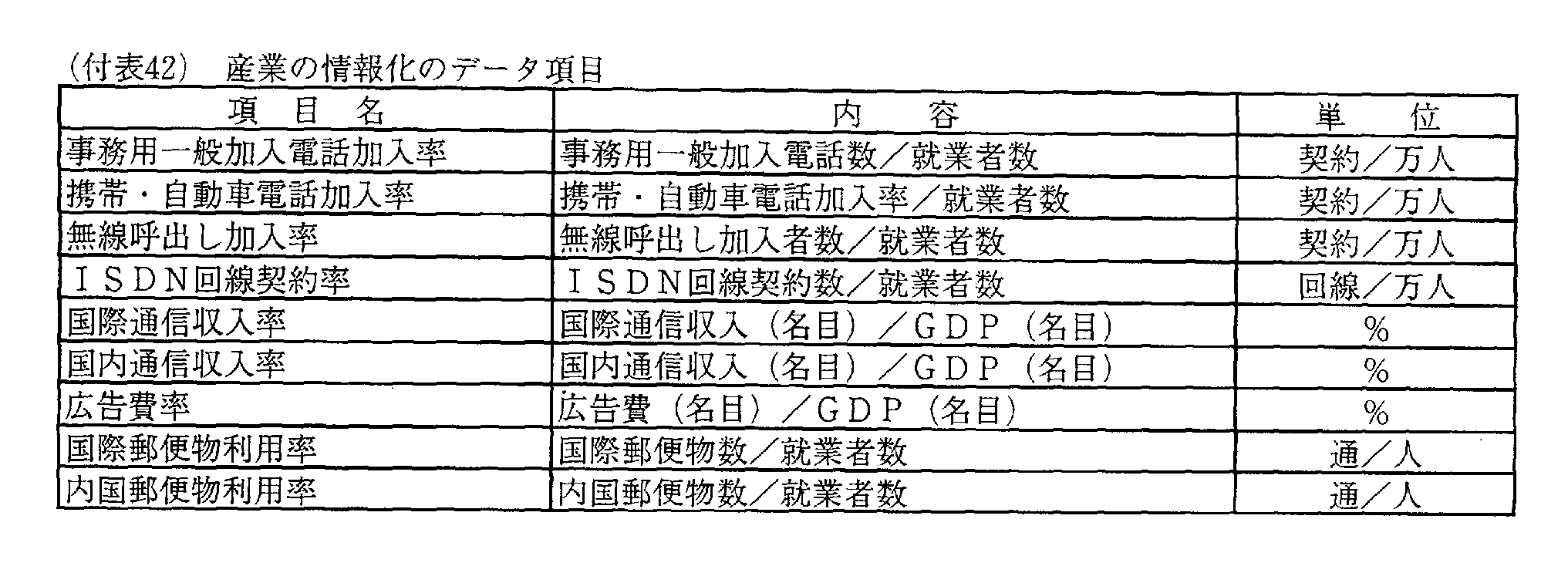
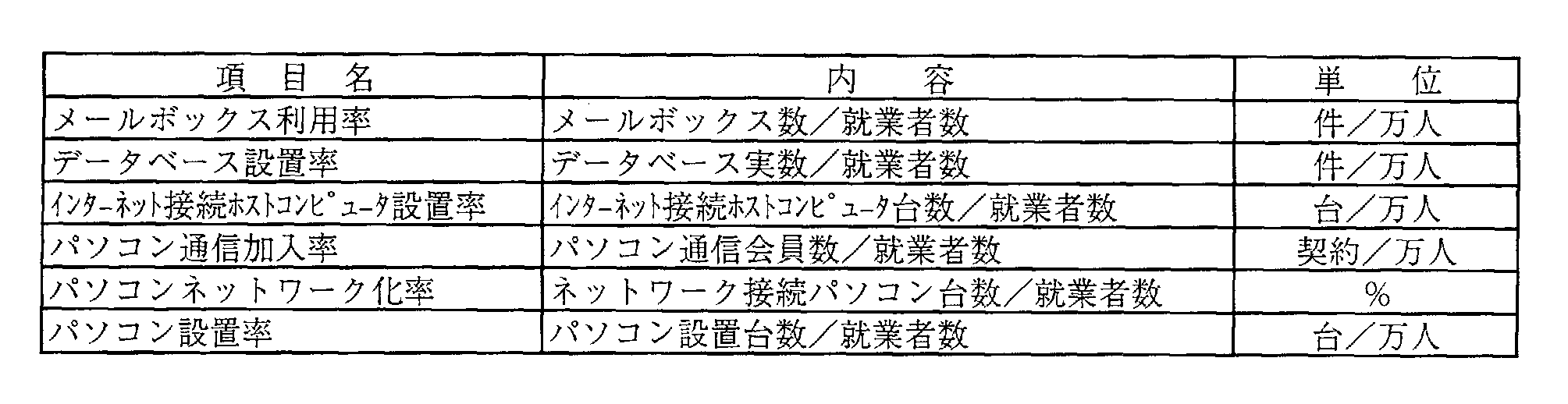
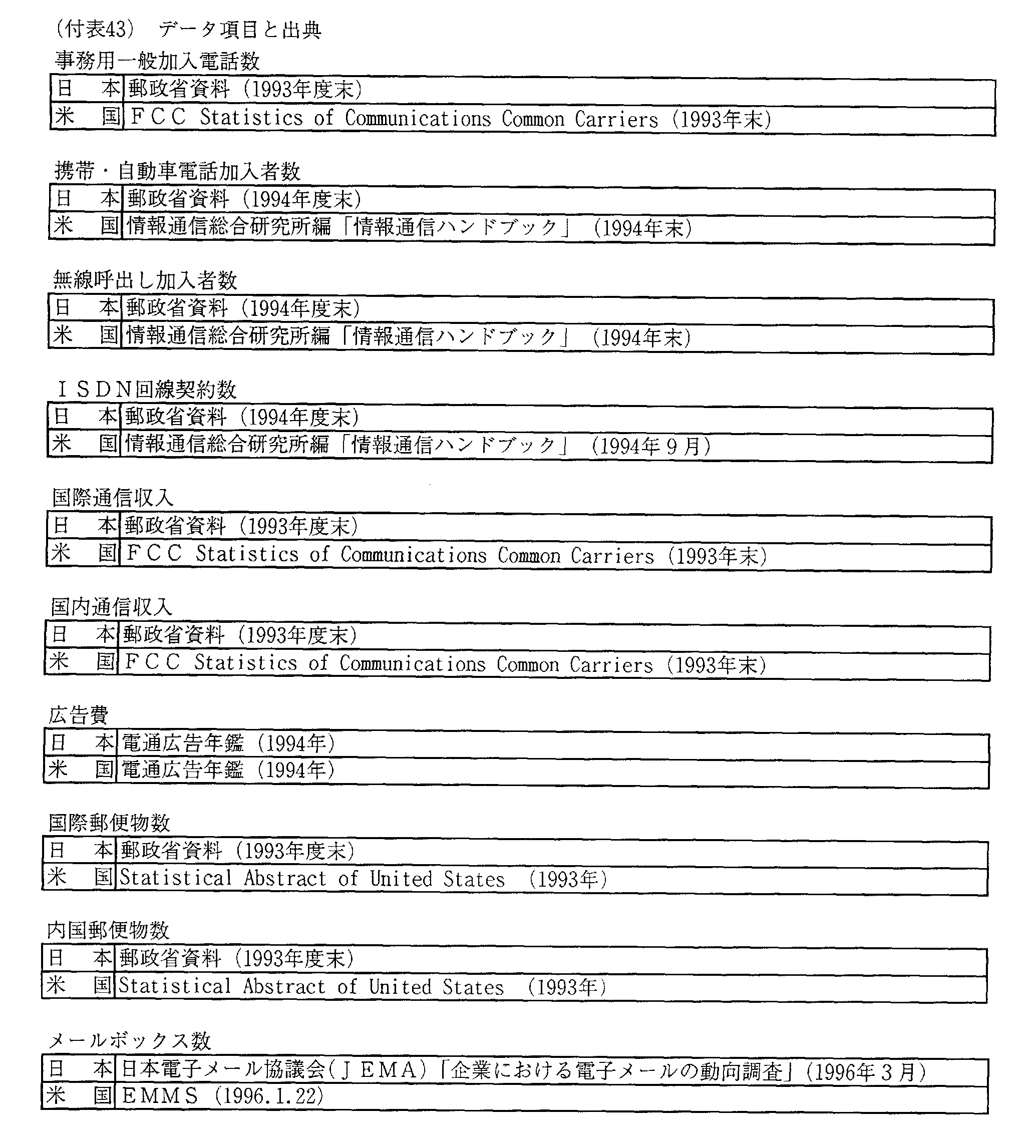
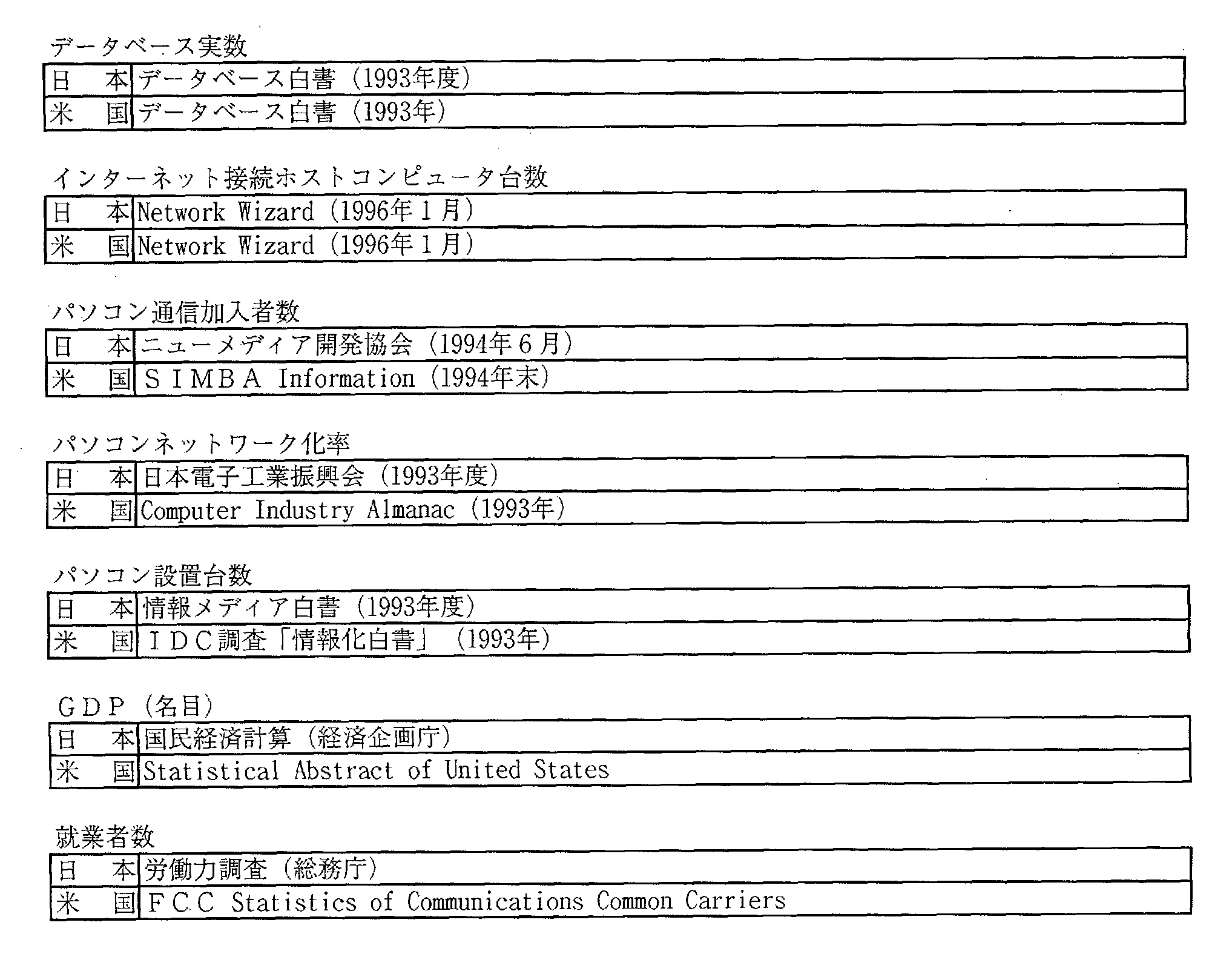
(注44)
日米比較において、日本は1993年4月〜1994年3月の1年間、米国は1993年1月〜1993年12月の1年間の設備投資額を比較した。なお、米国の設備投資額(ドルベース)を円換算するにあたっては、1993年12月末時点の為替レート(1ドル=11.189円)を用いた。
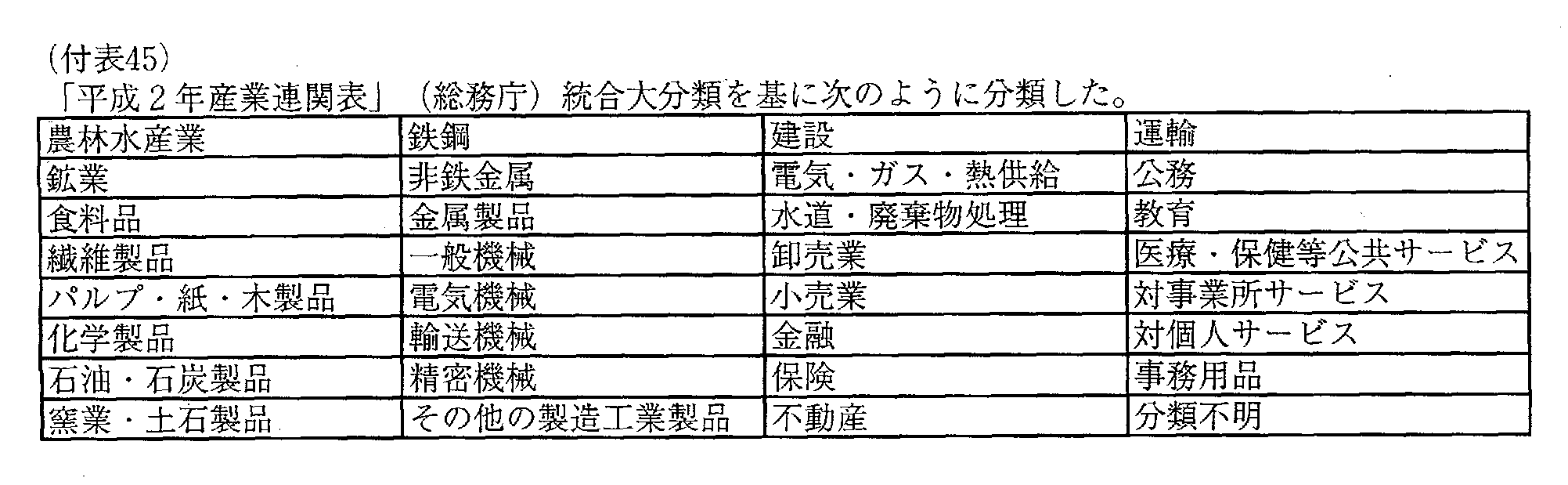
(注46)
実質国内生産額、各目粗付加価値及び雇用者数の推計に当たっては、郵政省資料、産業連関系(総務庁)、接続産業連関表(総務庁)、産業連関表(延長表)(通商産業省)、「国民経済計算年報」(経済企画庁)、「工業統計表」(通商産業省)、「物価指数年報」(日本銀行)、「労働力調査年報」(総務庁)を参考にした。
(注47)
電気通信審議会答申「21世紀の知的社会への変革に向けて一情報通信基盤整備プログラムー」(6年5月)においては、2010年までに光ファイバ網が全国に整備されることを前提として、2010年でのマルチメディア市場の規模を、光ファイバ網関連の新規市場での約56兆円と、既存の市場の成長での約67兆円の合計で約123兆円としている。この場合に既存のマルチメディア市場については、5年の規模を約16兆円と推計している。ここでの情報通信産業と比較すると、同答申においては、マルチメディアに関連するものに限定しているためその範囲は狭く、郵便、新聞、印刷・製版・製本、出版、映画館、劇場・興行場、事務用機械、通信ケーブル、電気通信施設建設、研究等の部門を含んでいない。
(注48)
ここでは、労働生産性を次のように算出している。
労働生産性=実質国内生産額÷雇用者数
(注49)
ここでは、比較のために情報通信産業の範囲を調整し拡大した結果、我が国の情報通信産業の国内生産額は当節前期(1)アでの範囲で推計した場合より約2割大きな額となっている。
(注50)
「1990年日米国際産業連関表」における1990暦年の平均為替レート144.79円/ドルにより換算。
(注51)
情報通信産業の実質GDP(国内総生産)については、産業連関分析により推計した情報通信産業の名目粗付加価値をSNAのGDPデフレータ(1990年基準)をもとに実質化して作成した。
(注52)
情報通信産業の成長による寄与度の、我が国の経済成長率全体に対する比率。但し、ここでの寄与率は年平均ではない。
(注53)
ここで、情報通信資本ストックとは、電気通信事業者の資本ストック及び電気通信事業者以外の民間企業の保有する情報通信関連機器の資本ストックを合わせたもの。
電気通信事業者の資本ストックは、毎年の名目整備投資額を実質化し、耐用年数14年としてPI法(恒久棚卸法)にてストック額を求めた後、さらに、デジタル変換機の導入等の能力の向上を加味して修正を行ったもの。
ここでの電気通信事業者以外の民間企業の保有する情報通信関連機器の資本ストックは、事務用機械、電気音響機器、ラジオ・テレビ受信機・ビデオ機器、その他の電気音響機器部分品・付属品、電子計算機・同付属装置、有線電気通信機器、無線電気通信機器及びその他の電子・通信機器部分品を範囲とし、耐用年数6年としてPI法(恒久棚卸法)によってストック額を求めた。
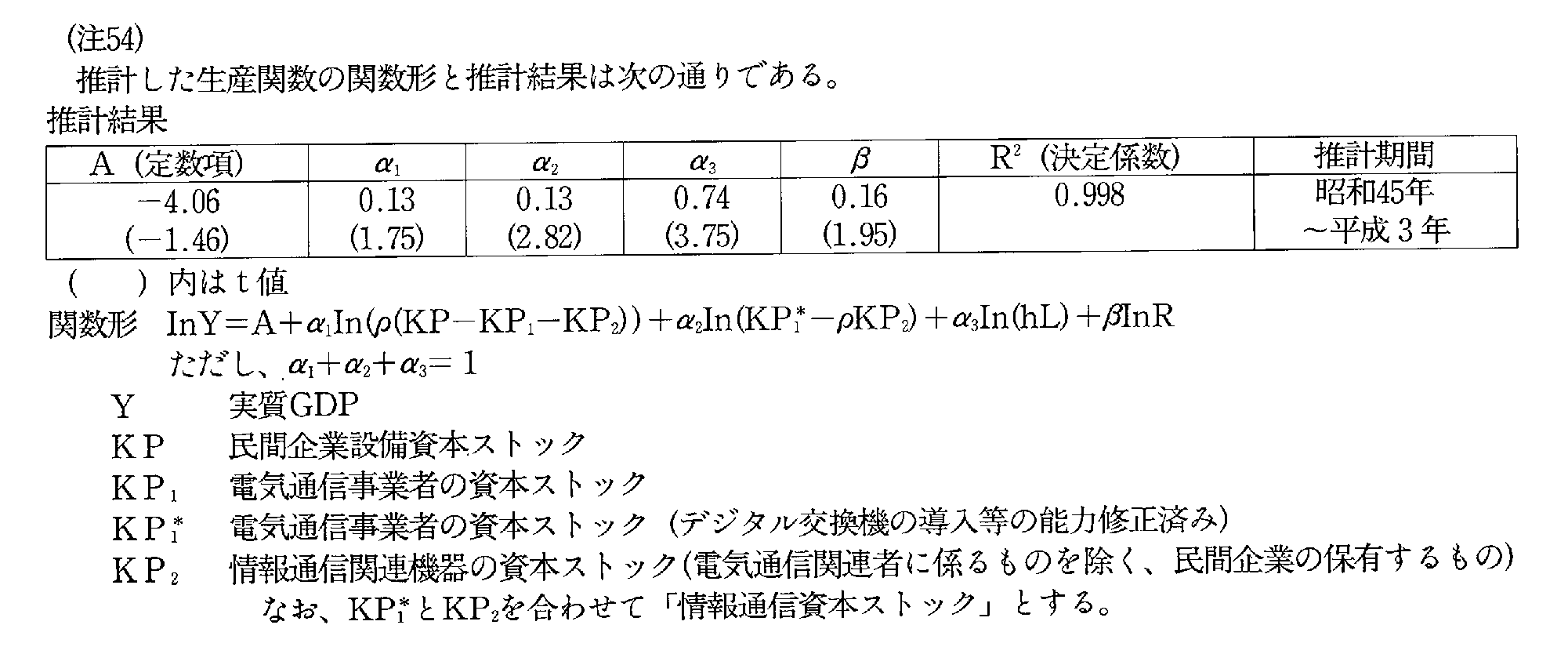
(注55)
国民経済計算の実質民間整備投資から耐用年数を18年とするPI法(恒久棚卸法)によって得られたストック額から、情報通信資本ストックを除いたもの。
(注56)
研究開発投資が一定のタイムラグを経て、投資額に相当する成果(知識)を生み、それらが年間16%の割合で陳腐化していくと仮定した場合における、研究開発についての「知識」のストック。
(注57)
α1、α2、α3及びβはそれぞれ実質GDPの民間企業整備資本ストック弾力性、情報通信資本ストック弾力性、労働力弾力性及び知識ストック弾力性であり、それぞれ各ストック等が1%変化したとき実質GDPが何%変化するかを表す。なお、ここでは昭和60年から2年までの各ストック等の稼働率修正済み年平均増加率とそれぞれの弾力性の積によって、各ストック等の実質GDP成長率に対する寄与度を求めた.
(注58)
情報化傾注度とは、各産業における情報通信産業への中間投入の中間投入全体(内生部門計)に占める割合である。
(注59)
コスト構造の変化に伴う理論的な算出価格。
(注60)
郵政省郵政研究所が委託して行った「阪神大震災発生後における通勤及び仕事環境の変化に関する調査」に基づくもので、この委託調査は神戸市内4区(中央区、東灘区、灘区、長田区)に事業所を持つ企業及びその従業員に対して、7年10月13日から23日までの期間実施した。回答サンプル数は、組織編が33名分、個人編が113名分である。
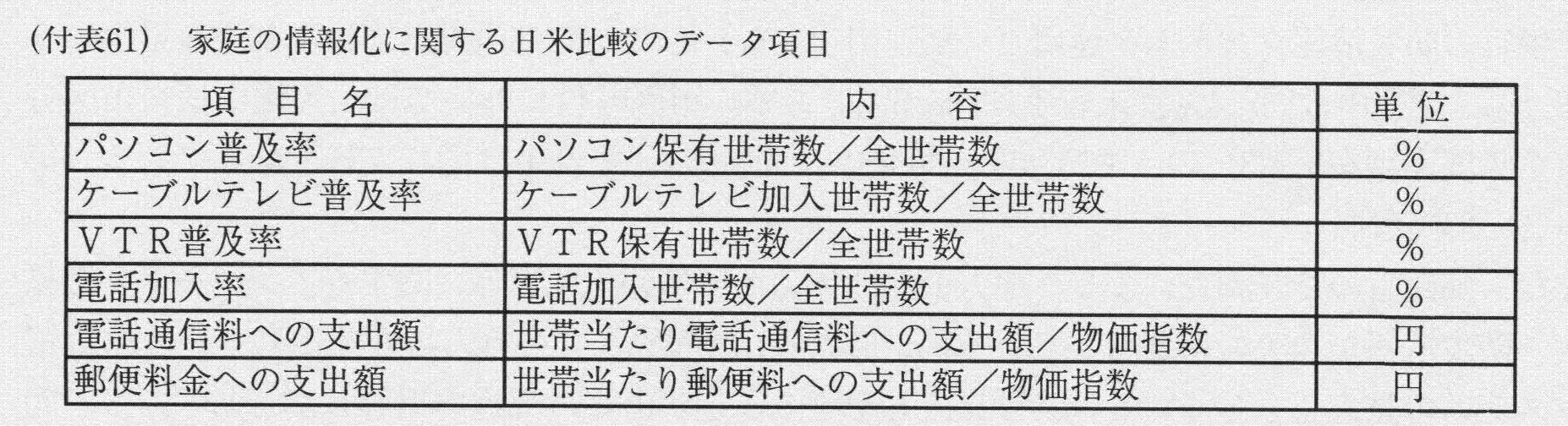

(注63)
郵政省が委託して行ったアンケートで、全地方公共団体を対象に7年12月1日現在における地方公共団体の地域情報化施策等を調査したものである。回答数は、都道府県が47、政令指定都市が12、市区町村が1,166である。
(注64)
(財)過疎地域問題調査会が行ったアンケートであり、人口の社会増が2年続いている過疎市町村54団体から各6名、人口の社会増が2年続いている非過疎市町村48団体から各6名を抽出し、5年9月から10月まで行ったものである。6名の選定基準は1)30歳前で、転入して3年以内の男性2名、2)30歳前で、転入して4年以上の男性2名、3)独身で、転入して3年以内の女性である。有効回答数は、275サンプルである。
(注65)
国土庁が委託して行ったアンケートで、5年12月に東京証券取引所第1部、第2部上場及び店頭登録している企業2,140社を対象とし、1,122社から回答を得ている。
(注66)
郵政省が委託して行ったアンケートで、6年6月に全国の1,000の地方公共団体を対象とし、628団体から回答を得ている。
(注67)
NHK放送文化研究所と大阪、神戸放送局が被災地で行ったアンケートである。調査は、7年2月9日〜12日に神戸市東灘区、兵庫区、中央区、長田区、須磨区、垂水区、芦屋区、西宮区(以上は各50人)及び淡路島北淡町(100人)の9行政区画の17の避難所で、被災した16歳以上の男女500人に対して個人面接法を行ったものである。有効回答数は498人(男性243人、女性255人)である。
(注68)
(財)神戸市問題研究所が行ったアンケートである。調査は、7年3月末から4月末にかけて、区役所、生協、大学等の各種団体を通じて実施されたものである。阪神・淡路地域において大きな被害を受けた神戸市、阪神地域の住民に対して約1,200の調査表を無作為に配布し、5月上旬までに368の回答を得たものである。(男性87人、女性281人)。
(注69)
兵庫ニューメディア推進協議会が、7年3月末に兵庫ニューメディア推進協議会会員(約300名)に対してアンケートを行ったものであり、81の回答を得ている。
|