|
第3章 情報通信が牽引する社会の変革―「世界情報通信革命」の幕開け―(2) インタ-ネットのビジネスへの活用インターネットをビジネス分野で活用しようという動きは、まず米国において、その商用利用への道が開けた1991年に始まり、我が国においてはインターネット・サービス・プロバイダの設立が本格化した1992年末ごろから始まった。インターネットがもたらす情報やそのネットワークの広範性を活用することは、企業にとって大きなビジネスチャンスをもたらすという判断の下、より有利な競争力を獲得しようと、インターネットを自社の情報戦略システムの中に位置付け、ビジネスに活用する企業も現れた。また、インターネットを利用してグローバルに市場を拡大する中小企業や、新しいアイデアをインターネットにより具象化してビジネスを興す個人さえ現れた。こうして、世界中でインターネットへ接続する企業が増加することで、インターネットの情報がさらに豊富に蓄積され、それを求めて、ますます多くの企業がインターネットへ接続するという図式で、企業によるインターネットの利用が急速に拡大している。 ア 企業におけるインターネットの利用状況 企業において、ネットワーク化された情報の戦略的重要性は、十分に認識されているところである。市場動向、競合他社の状況、最新の技術成果、新製品の情報等、戦略的な決定を行う上で新鮮かつ重要な情報源は、社内から得られるよりも、社外から得られる場合の方が多い。企業のインターネットの利用は、情報管理戦略に寄与する資源を社外から得ることを目的に始まったと言えよう。 イ インターネット活用方法の類型化 インターネットのビジネス分野における活用形態を類型化すると第3-1-17図のようになる。即ち電子メール等の「コミュニケーション」機能、電子ニュースやWWW上でのホームページの開設等の「情報公開・情報提供」機能のビジネスへの活用に始まり、現在では、インターネットの環境下で社内業務システムを構築する「イントラネット」という形での活用も盛んになる一方で、インターネットそのものをビジネスあるいはビジネス支援のツールとして活用する電子出版・電子新聞、ディレクトリサービス等の「情報流通サービス」、仮想店舗・仮想商店街、電子取引等の「電子商取引」、電子決済あるいは電子現金等の「電子金融」のような社外に向けた活用へと範囲が拡大している。以下では、こうしたビジネスの活用形態の流れに応じたインターネットの利用状況について事例を挙げて紹介する。(ア) コミュニケーション 社外の人とのコミュニケーション手段として、電子メールを導入する企業が増加しているが、電子メールをやり取りするために採用しているシステムは、現在、自社で設置した独自仕様のLANシステムや外部のパソコン通信ネット等を利用するケースがほとんどである。 しかし、最近では外部とのやり取りを電子メールで行う場合に、外部のパソコン通信ネット等を利用する以外の選択肢として、インターネットを使った電子メールを利用するケースが増えてきている。また現在では、大手のパソコン通信ネットはインターネットとも相互接続され、インターネット利用者とのメールの交換、さらにはインターネットを介して他のパソコン通信ネットの利用者同士でもメール交換が可能になるなど利便性が向上している。 (イ) 情報公開・情報提供 現在、企業にとってインターネットの利用が魅力的なのは、インターネット上にホームページを開設し、企業の外部への情報公開・情報提供ができるところにある。インターネットを利用している企業の中には、自社のホームページを開設し、自らの企業の紹介、商品情報の提供、経営情報の開示を積極的に行っているところもある。現在のところ、我が国の企業においては、こういった情報公開・情報提供にインターネットを利用する場合が多い。例えば、自社の製品情報等を多くの利用者に提供したり、あるいは完成度の高いホームページを提供して自社のインターネット関連技術の優位性を訴えるための自社の広告としたり、CI情報発信の手段として利用している企業もある。 (情報公開・情報提供の利用事例) ここでは、インターネット上にホームページを開設して情報公開・情報提供を行っている、東京都のある食品会社の事例を紹介する。この会社のホームページのメニューは、リクルート情報、協賛しているF1レースの情報、自社商品の紹介等である。特に、F1レースの情報は国内外で人気を得ており、多くのアクセスを得ている。F1レースの開催に合わせてアクセス数は増加傾向を示し、数か月の間に月間アクセス数は十数万件に急増しており、その半数は海外からのものである(第3-1-18図参照)。 大量のアクセスがあることによって、インターネットは、新たな広告媒体としての有効性を示しており、また、アクセスの中には、電子メールによるユーザーの意見等も含まれていることから、インターネットのインタラクティブ性は、ユーザーの反応を商品企画へ活用できるという意味で注目されている。 さらに、企業による情報公開・情報提供だけでなく、国や地方公共団体あるいは非営利組織も積極的にインターネットを通じて情報を提供している。郵政省では、6年9月にホームページを開設し、インターネットにより通信白書、郵政省の施策、電気通信審議会答申等の情報を広く提供してきたが、インターネットの利用者の拡大等を背景にアクセス回数は増加する傾向にある(第3-1-19図参照)。 (ウ) イントラネット インターネットが企業に導入されるためには、インターネットの電子メール、電子会議、電子掲示板等のサービスやインターネット上で動く業務アプリケーションが魅力あるものであることが不可欠である。 これまでは、社内での情報共有、ペーパーレスの手段としては、数多くのベンダーによる独自規格のLANを企業ごとに構築する形態が主流であり、企業内に限定したシステムとしてインターネットが導入されることは少なかった。しかし、異なる企業間でオープンな業務環境を求める機会が増えており、最初からシームレスな企業間のネットワーク構築環境を作るために、企業内の情報システムを構築する際にもオープンネットワークを前提とするシステムを構築する機会が増えてくるものと考えられる。 このように、インターネットで利用されている環境と同じクライアント・サーバ型の社内LANを構築し、WWWサーバとブラウザソフトを使って社内コミュニケーション、社内情報の共有・提供、各種業務システムを実現する仕組みをイントラネットと呼んでいる。 (イントラネットの利用事例) ここでは、先行的にイントラネットの形態で社内情報システムを構築し、利用を推進している、大阪府のあるガス会社の事例を紹介する。この会社では、情報の効率的な共有により生産性や質そのものを向上させることが重要な課題となっていた。これまでのクライアント・サーバ型のシステムでは、パーソナルコンピュータ個々にソフトウェアを配布する必要があり、その操作方法もそれぞれ異なっていた。その解決策の一つとしてWWWをベースとするイントラネットを構築し、各個人のパソコン上のブラウザソフトにより社内の業務システムも利用できる仕組みを構築した。この会社では、高速全文検索専用エンジンとWWWサーバをゲイトウェイ接続し、過去20年以上にわたる技術データをクライアント・サーバ型からイントラネット型に再構築して利用を始めた。これに要した開発費は従来の1割程度で、開発期間は1か月程度であった。利用者は通常のブラウザを用いて、社内のどこからでも社外のWWWへのアクセスと同様の操作で利用でき、図表やプログラム等も含めて瞬時に検索結果を得ることができる。さらに、異音同意語検索等も可能である。 この会社では、同様の仕組みを適用できる業務としては他にも様々なものを検討している。例えば、これまで紙でファイルされている書類は、規程類、通達、仕様書等、様々なものがあり、一部の部署の規程類だけでも数万ぺージもある。さらに付随する画像データも膨大であり、これまでのクライアント・サーバ型のシステム等ではこれらを電子化しても、検索が困難であり使い勝手が悪いため、イントラネットの形態が非常に有効である。また、この会社では、書類や画像データだけでなく、社内ニュース(ビデオ情報)のような映像データも試験的にWWWサーバに蓄積・公開している。 今後は、利便性のよいイントラネット環境が実現しつつあるため、定型の文書のかなりの部分を電子化を前提として作成する方向であり、真のペーパーレス化が確実に進み、業務利用における生産性向上が期待されている。 (エ) 情報流通サービス インターネットのビジネスでの活用が拡大してきている大きな分野として、情報公開・情報提供を基盤とした情報流通サービスの分野がある。情報流通サービスには、インターネット上で情報を収集、配信して付加価値を生み出す電子出版・電子新聞、インターネット上の膨大な情報への適切なアクセス手段を提供するディレクトリサービス、アクセス頻度の高いホームページのスペースを広告媒体として売り出す広告サービス等、インターネット上でコンテントを流通、運用するサービスがビジネスとして現われはじめている。 このような情報流通サービスによるビジネスは、インターネット上にバラエティに富んだ情報が行き交い、利用者が多い米国において数多く展開している。例えば、電子出版・電子新聞では、米国のある会社が発行するコンピュータ誌に付加価値を付けた電子版をインターネット上で発刊し、会員制の有料購読サービスを行っている。また、ディレクトリサービスでは、米国のベンチャー企業が、英語を中心とした情報検索を行うサービスを無料で提供しているが、このような会社がディレクトリサービス単独に運営するベンチャーとして存続できるのは、ホームページを訪れる利用者に向けた画面スペースを企業広告スペースとして販売して収入を得ているためである。 一方、我が国においてはビジネス事例はあまり見られず、現在は、将来ビジネス化を図ろうとする企業が、ビジネスで活用できる基本的なサービスメニューを開発して無料で公開することにより、運営のノウハウを蓄積している段階である。例えば、ディレクトリサービスでは、WWWの日本語情報の検索を求める利用者に対して、日本の企業や大学が様々な日本語ディレクトリサービスを無料で提供しているが、現在のところアクセス数の絶対量が少なく、広告収入はほとんど得られないため、単独の事業としては成立していない。むしろ、情報公開・提供の手段の一つとして利用する企業が多い。 (オ) 電子商取引 インターネットが今後のニュービジネスのために活用される分野で、例えば、商取引の分野が注目されている。インターネット上で電子商取引を行う際には、取引情報のやり取りに高い信頼性が求められる。しかし、現状のインターネットは、ネットワーク自身のセキュリティ機能が十分でないため、高い信頼性を確保するための特別な仕組や手段をネットワーク上のソフトウェアで確保するか、あるいはそのような取引情報をファクシミリ等の他の手段を用いてやり取りするかのどちらかの選択をしなければならない。 この分野において、当初は後者の方法によりビジネスが立ち上がったが、最近ではインターネットのようなオープンなネットワークにおいても、ネットワーク上のソフトウェアによるセキュリティを確保するための技術を利用することにより、電子商取引できる範囲は急速に広がってきている。このような技術を活用すれば、例えば、購入の際もその場で直ちにクレジットカードによるオンラインの決済が可能となる。 こうしたインターネット上のオンライン決済の試みについては既に海外で多くの実験が行われており、代表的な取り組みとしては、米国において進められている企業コンソーシアムによるCommerceNetがある。このプロジェクトには、コンピュータ、半導体メーカー、銀行、パソコンの通信販売会社等、約 140社(1996年3月時点)が参加し、インターネットを利用した、商品情報の流通、製品の共同開発や部品メーカー等への発注、資金決済等のデータ交換を行うための技術開発や実証実験が進められている。 また、我が国においても、出版社やシンクタンク等をはじめとする様々な企業が、WWWサーバ上に仮想商店街を相次いで立ち上げ始めている。 (仮想商店街の利用事例) ここでは、仮想商店街のサービスに取り組む東京都のあるシンクタンクの事例を紹介する。この会社では、仮想商店街に出店する参加企業から商品情報を受け取り、ホームページへの登録作業を行っている。システムの保有及び運営はこの会社が行うため、参加企業はシステムを保有する必要はない。この仮想商店街のシステム構成と、買い物の手順は第3-1-20図のとおりである。 インターネットを仮想商店街という形で利用することにより、 [1] 出店企業にとっては、 ・通常の店舗販売と比較して低コストで商品販売ができ、商品情報も頻繁に変えられること ・販売チャンネル、広告チャンネルの制約がないため、中小企業、あるいは個人でも参加できること ・販売対象が限定されず、日本全国、あるいは全世界のマーケットを相手にできること [2] 消費者にとっては、必要な時に欲しい物を注文できるという利便性があること といった利点がある。また、この仮想商店街を運営する会社としては、インターネットを用いた仮想商店街のビジネスでブランドが確立されることが、今後の事業展開で大きな経営資源となっている。 (カ) 電子金融 金融分野においてインターネットを利用する魅力は、家庭に居ながらにして、いつでも、銀行の決済、資金の移動ができるようになることである。また、将来インターネットを介して自由に出し入れできる電子現金の利用が可能になれば、小銭を持ち歩く必要がないといったメリットも大きい。また、インターネットに対する波及効果として、デジタルコンテントの売買、小額取引等の可能性が大きく広がることが考えられる。 (電子現金の利用事例) ここでは、オランダのある会社が提案した電子現金による利用実験の取組を紹介する。この会社の提案する電子現金の最大の特徴は、ICカードを利用せず、ソフトウェアだけで電子現金を実現したことであり、かつ支払いのプライバシーは守られていることである。この会社では、1994年10月からネットワーク上だけで利用できる仮想通貨による電子現金の実験を開始した。この実験では、参加希望者に 100サイバーバックス(サイバーバックスは仮想通貨の単位)を配布し、インターネット上に開設した店舗を通じてデジタル商品を売買できるようになっている。この実験は、1995年末の時点で、約6万人が参加する大規模なものとなっている。 さらに、米ドルとの交換を保証する電子現金の実験も開始された。米国のある銀行では、前述の会社が提案した電子現金方式の技術ライセンスを受け、1995年10月からインターネット上での電子現金による預金の引き出しと預け入れサービスを始めた。このサービスには、1995年12月末時点で、数千人の消費者と20店舗ほどが参加している。 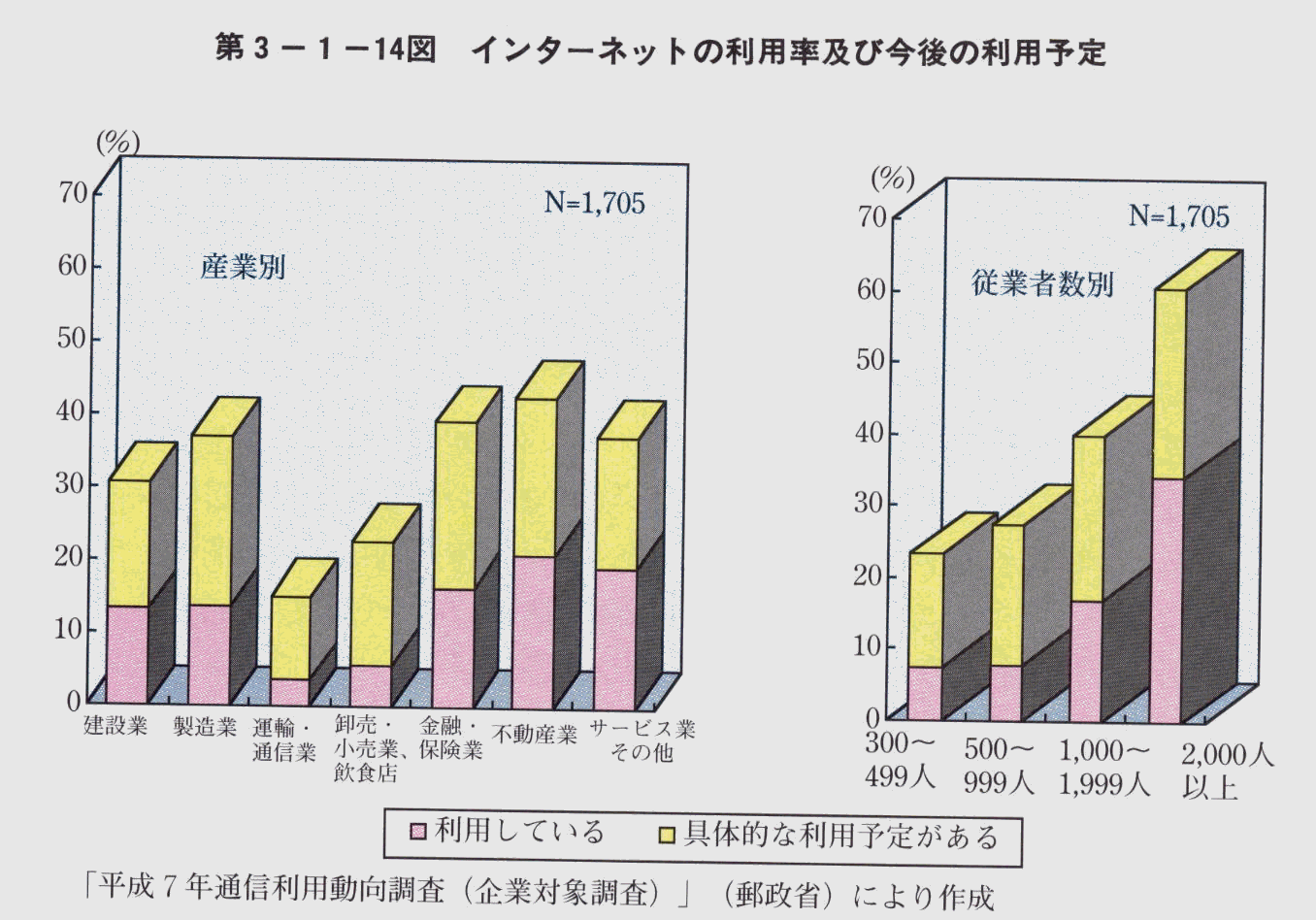
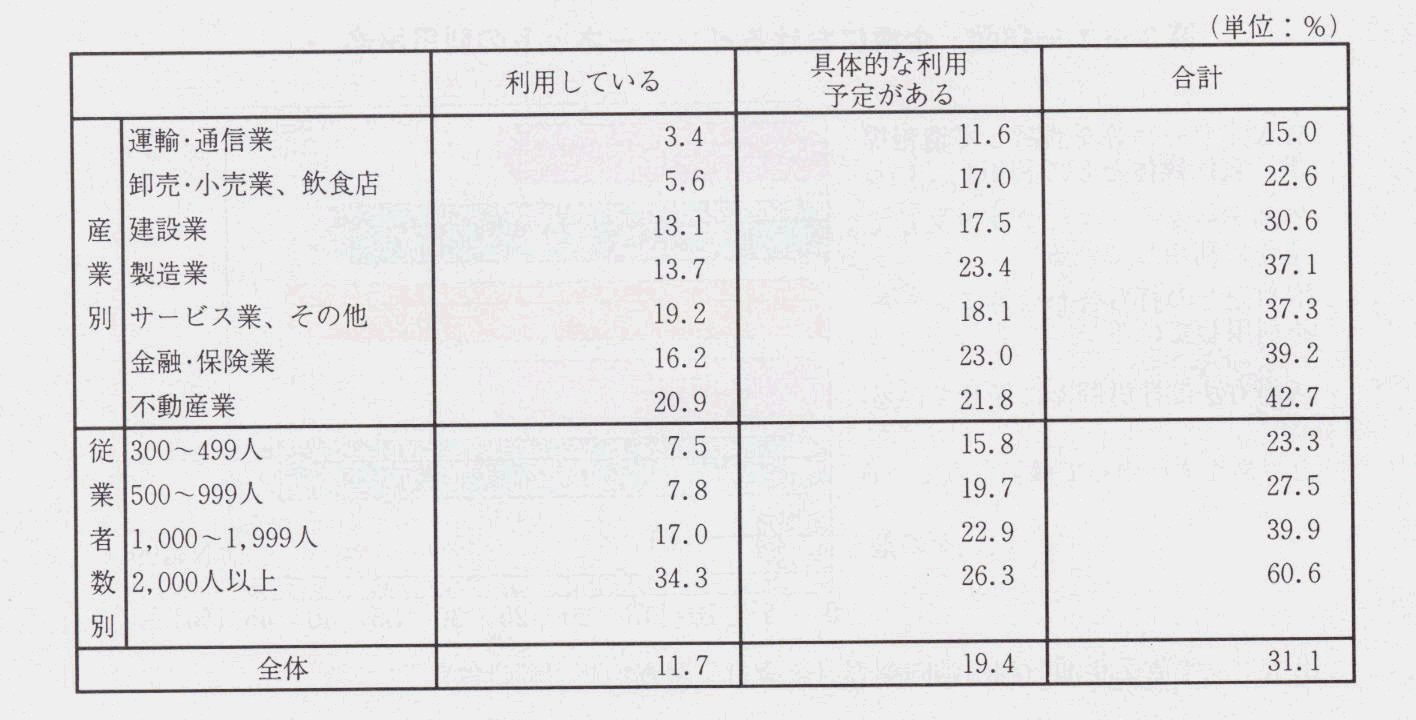
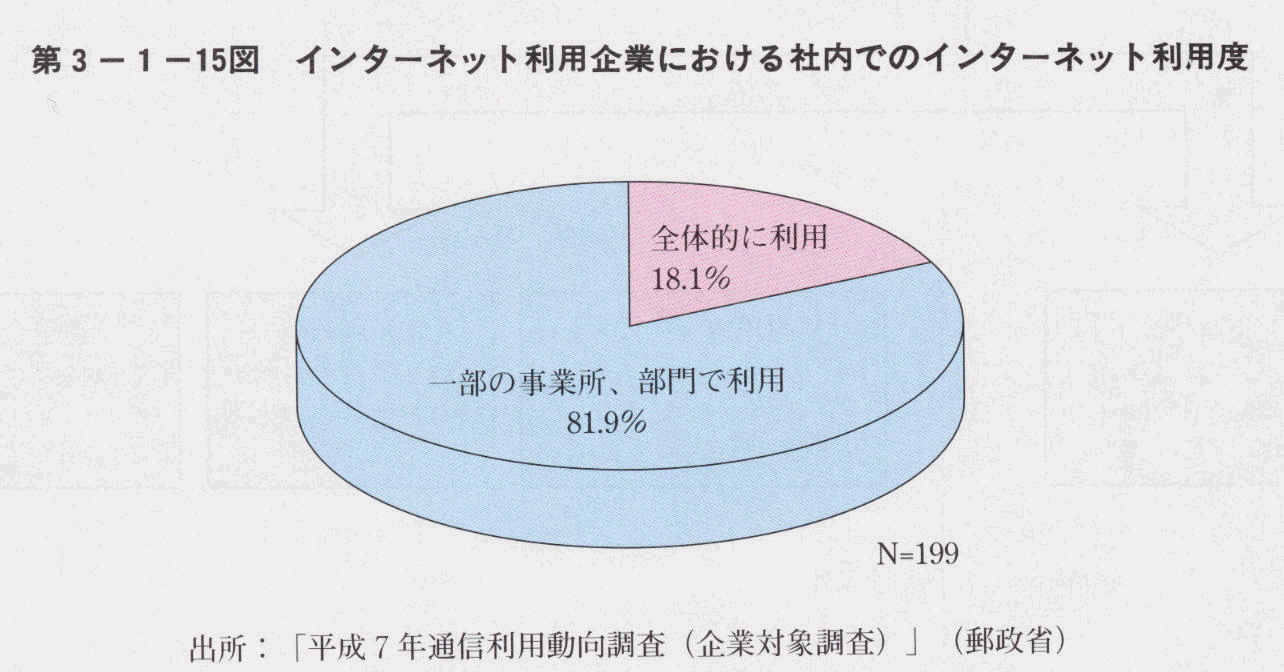
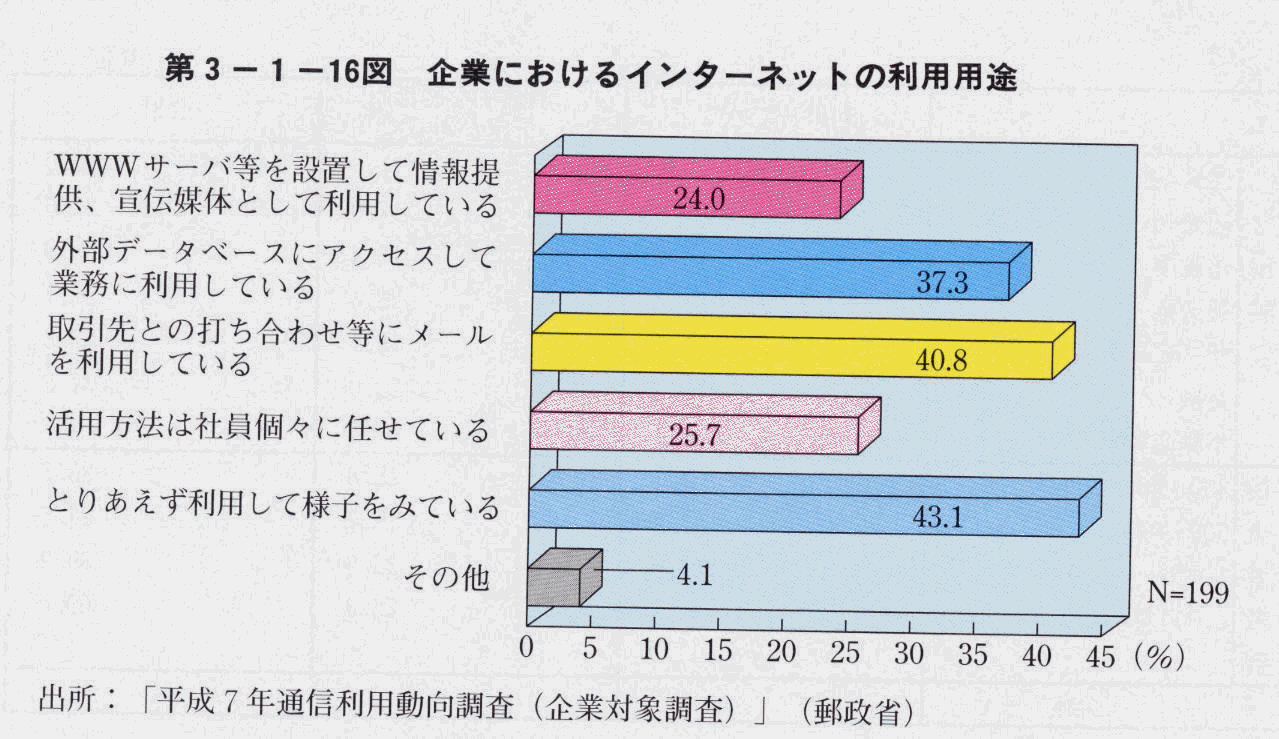
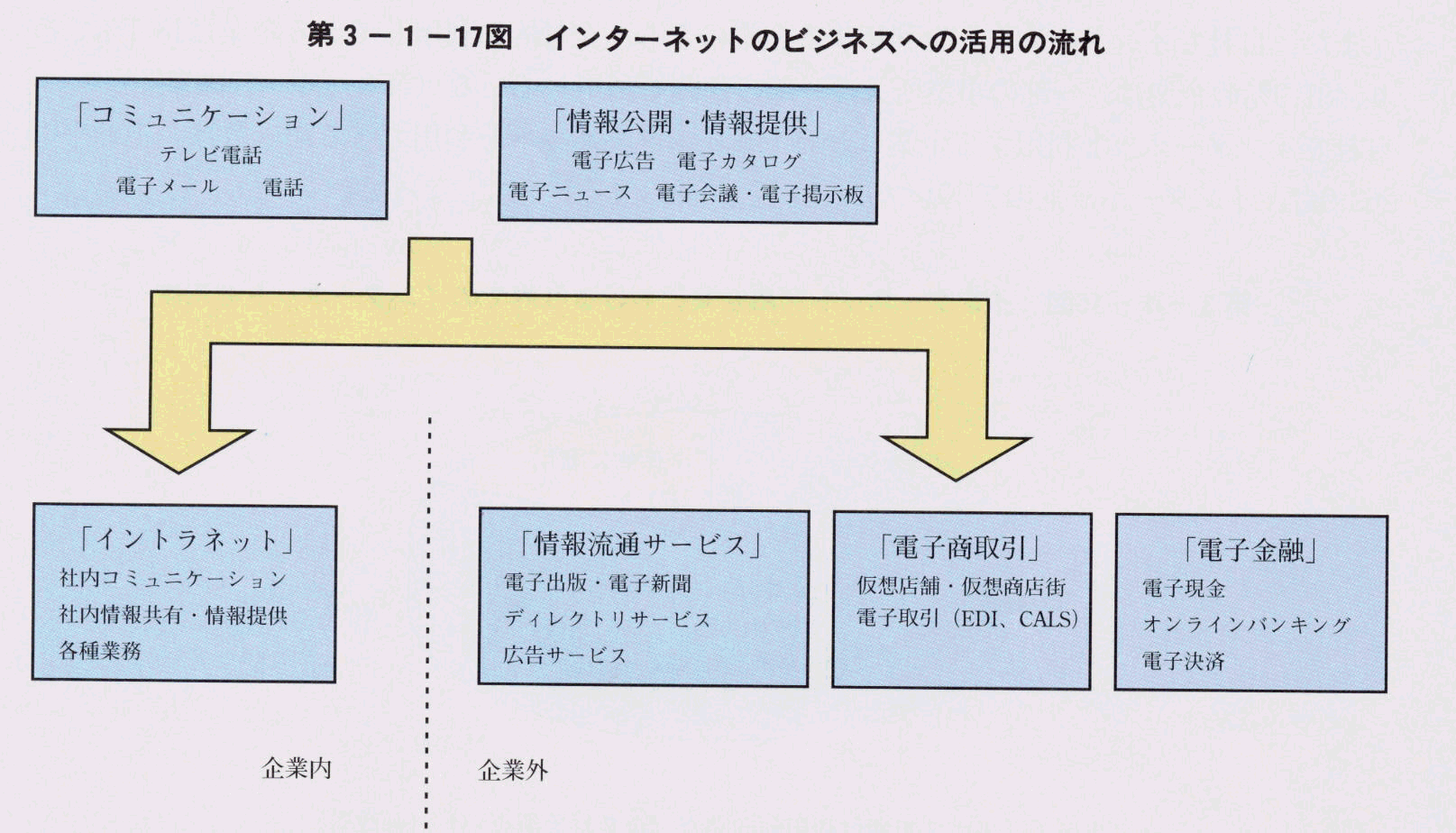
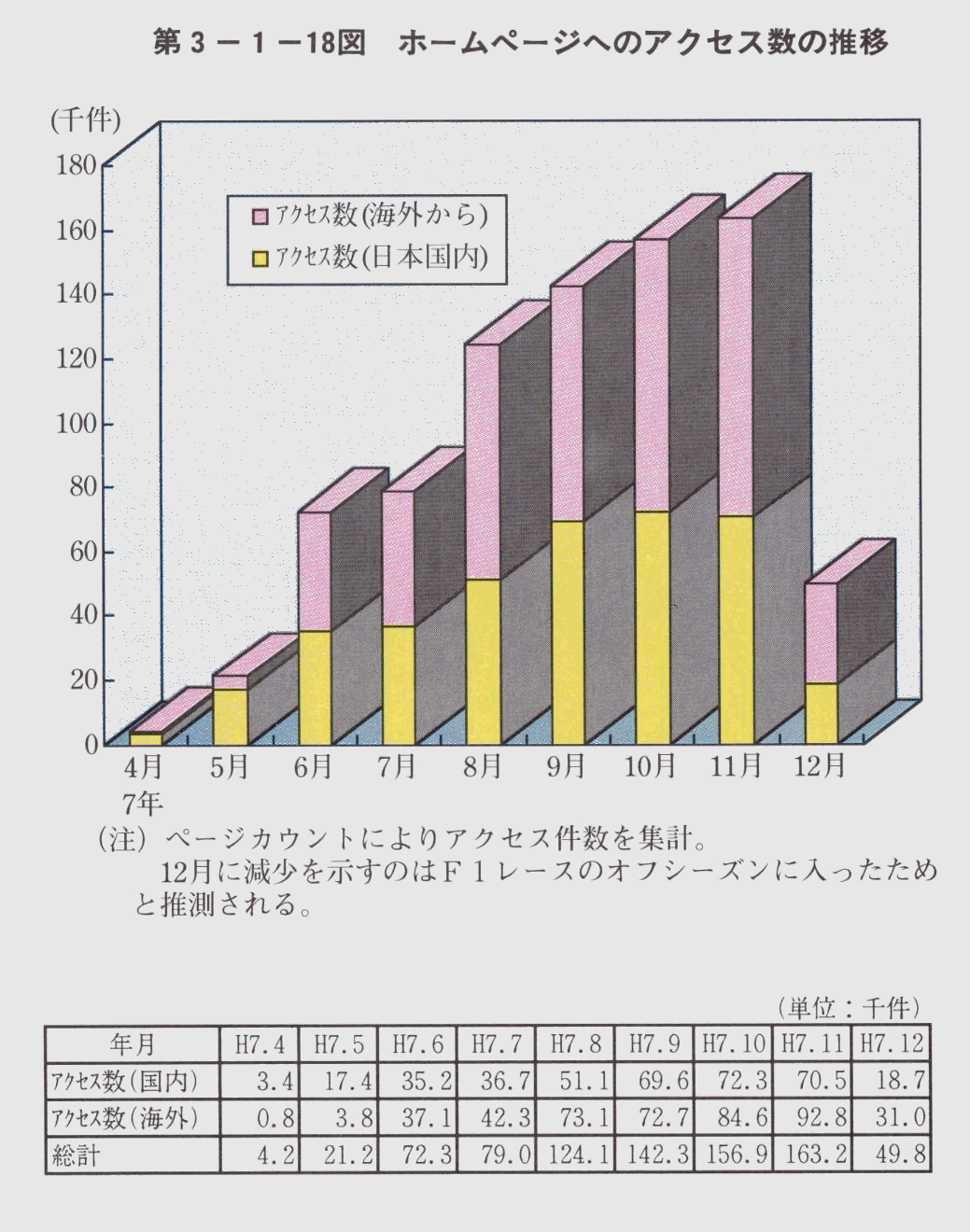
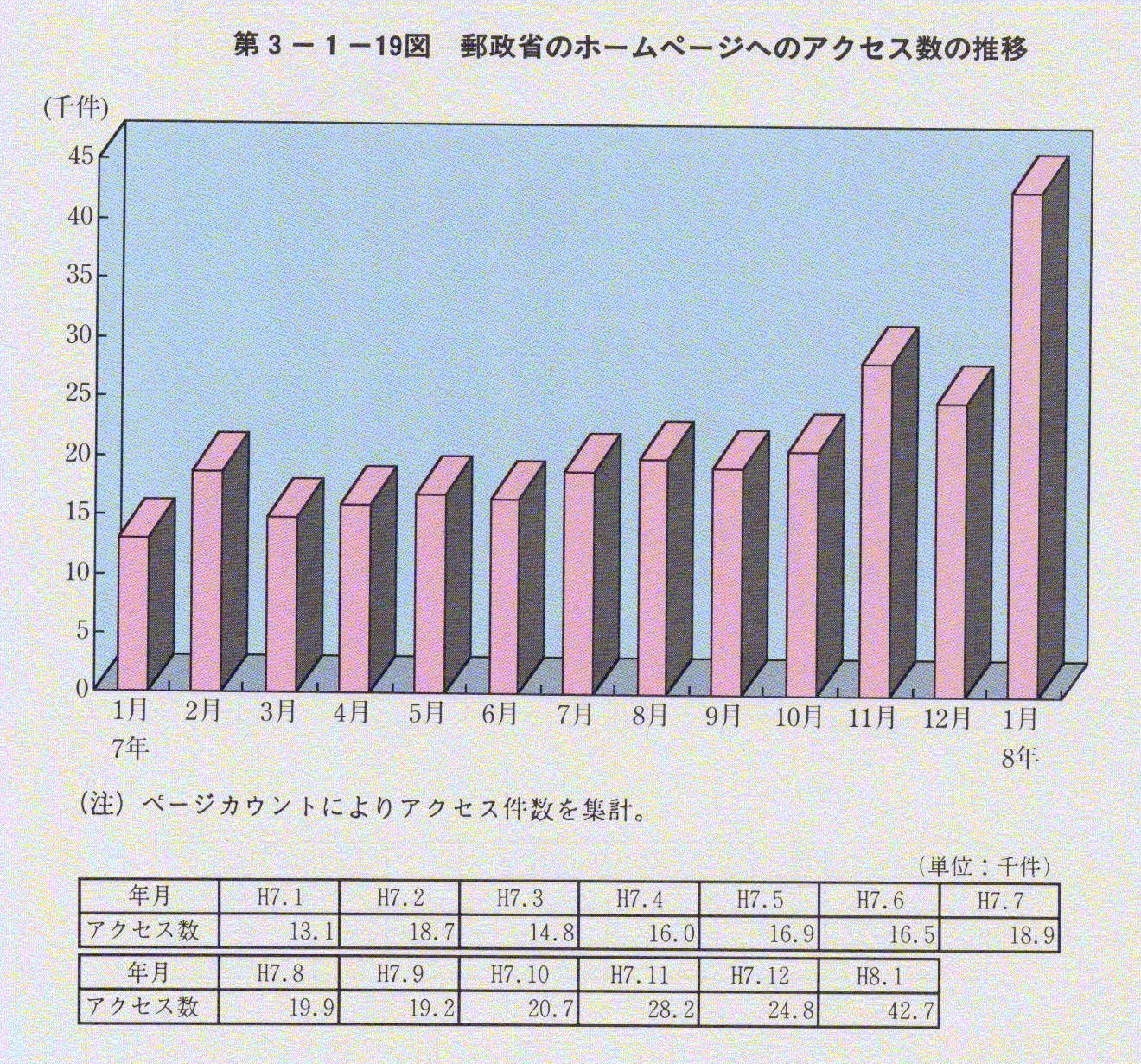
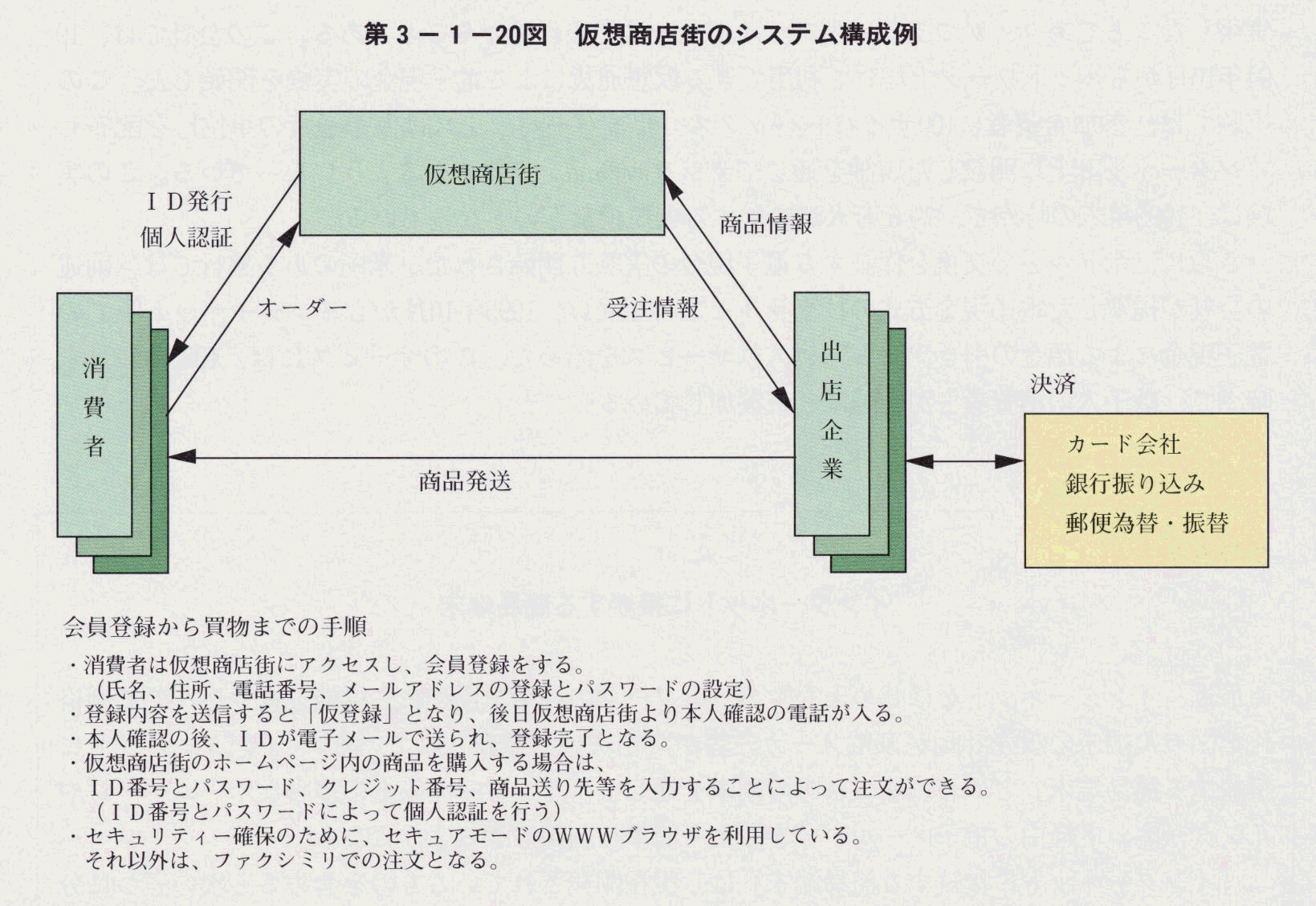
|